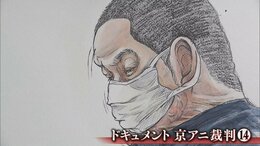祭りに訪れた日本人の声
在日のミャンマーの人々で賑わう中、訪れていた日本人に話を聞きました。
女性客
「会社の同僚がミャンマーの方なので、誘われました。ここに来て、日本にもいっぱいミャンマーの方いるんだなってあらためて思いました」
また、ミャンマーを応援したい人が集まっているグループにも伺いました。
ミャンマーを応援したいグループの方々
「この祭りのことをどなたかが聴きつけて、一緒に行こうかという感じで来ました」
「おばとおじが5年前にミャンマーに旅行に行ってて、それから、ミャンマーに興味が生まれたのですが、その間にいろいろあって、今はちょっと旅行行くのも大変なので、来てみました」


ミャンマー国内では自分の民族の文化を大切にできない
日本の約2倍の面積があるミャンマー。イギリスの植民地だった時期は、ビルマ民族と100以上の少数民族の暮らす地域は別々に統治されていました。独立した1948年以降、自治権の拡大などを求める各少数民族は、70年以上、停戦の時期を挟みながらも、国軍との戦いを続けてきました。
新宿区内で「ゴールデンバガン」という店を開く、シャン民族のモモさんに聞きました。
新宿「ゴールデンバガン」シャン民族のモモさん
「私たちはミャンマー国内では、民族の文化を大切にできる状況ではないのです。海外にいて、私の民族の文化や習慣をいろいろ紹介できて、うれしいです。われわれ少数民族が抱える課題は、70年前から続いてます。日本人に知ってほしいのは、ビルマだけでなく、少数民族があるミャンマーを知ってほしい、そして、各民族を平等に扱ってほしい、自由と民主主義を実現してほしい、ということです」
会場には、長い内戦で隣のタイなどに難民として逃れ、そこで人身売買の被害にあったカチン族の女性たちの自立支援のための小物を売る店などもありました。
クーデター後、民族のコミュニティ間で生まれた変化
ビルマ民族が多い中央政府でも、軍のクーデターや軍政が繰り返されてきたミャンマー。ビルマ民族と他の民族との交流はこれまで、難民として逃れてきた日本でもあまりなかったということです。
「多民族祭り」は去年に続き、2回目。2021年のクーデター以降の変化について、祭りの実行委員会事務局を務めるキンゼッヤーミンさんの話です。
「多民族祭り」実行委員会事務局 キンゼッヤーミンさん
「クーデターの後、基本的人権のこととか、自治権のこととか、少数民族の訴えをあらためて、理解できるようになりました。今回、こういうお祭りをすることで、ビルマ民族と他の民族との交流、そして、ミャンマーに関して、多くの日本人に知ってもらいたいです。ミャンマーでは多様な人たちが共存してますよ、ということを伝えるきっかけになるかな、と思っています」

ミャンマーの状況は変わっていない
ミャンマーの状況は、2021年のクーデター以降、変わっていません。ニュースで大きく取り上げられる時だけでなく、日常の生活や、こういったイベントでのちょっとした関わりからミャンマーの多様性の一端を知り、自分のできる範囲のことで、息長い支援を行う人が少しでも増えてほしいと、キンゼッヤーミンさんたちは希望しています。


担当:TBSラジオ「人権TODAY」崎山敏也