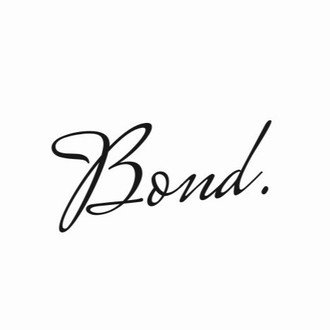「リコリスの森」徹底読解
「リコリスの森」本編を読解していきます。
徹底的にいきます!2万字超えています。考察なのに短編小説くらいあります。
お手元に、覚悟をご用意ください。
初回生産限定盤の冊子があるとなお良いです。
※様々な既出情報が大前提になっていますので最近うたプリ知ったよ〜という方は下記の「リコリスの森資料まとめ」のご一読をオススメします。
それではレッツゴー
【オープニング】
ヴィクター(と黒ずきん)のモノローグから始まります。
「あの子が好きな花が咲く季節が、またやってきた。」p.6
"またやってきた"
→つまりブラッドとランドルフ、そしてアルヴィンが死んだ後、季節が巡り、また秋がやってきた。
ブラッドとランドルフがこのオープニングナレーションに居ないのは当然ですね。もう死んでいますから…。
黒ずきんは人の心の裏(吐露の概念)なので、このオープニングは
「ブラッドの死後、リコリスの花畑を見つめ佇む、ヴィクターの独白」
となります。
ヴィクターは季節が巡ってもなお、ブラッドに惹きつけられており、ランドルフを"悪しき獣"と恨んでいるのが読み取れます。
【赤ずきんと村の人々の会話】
小さな村に、
それはそれは美しい少年が住んでいました p.8
この冒頭のシーンは「美女と野獣」を彷彿とさせます。
美女ベルに対して強引な英雄ガストンは、
ブラッドとヴィクターの関係によく似ています。
この"小さな村"が「広い世界を見に行こう」の理由です。
小さな村に住む人々は"井の中の蛙大海を知らず"。
連帯意識や助け合い精神が強い分、偏見や差別で凝り固まりやすい性質が会話にもよく表れています。
"それはそれは美しい少年"
もちろん見た目もですが、村人やヴィクターのセリフからとにかく心が美しく人を惹きつけているようです。
「心優しく、誰に対しても愛嬌を振りまく」
「母親を早くに亡くしたというのに、
ひねくれることなく明るくまっすぐ育って……。」p.8
ここはブラッドと一十木音也くんの共通点ですね。
役と役者をかすらせる。エモい。
"誰に対しても愛嬌を振りまく"
・音也くんの場合は、頼れる家族が居なくて、とにかく周囲の人間に愛されたいという無意識から。
・ブラッドの場合は、他の兄弟たちのように、父や兄に捨てられたくないという無意識から、来てるのかもしれません。
兄に頼まれ、お使いに出た帰り道
「村長さんにグレアム兄さんからのお手紙を渡したら
たくさん食べ物を貰っちゃった」p.8
→これはヴィクターが言う「奴(グレアム)ができるのは、物乞いすることくらいだろう?」の"手紙での物乞い"ですね。
ヴィクターは血の繋がった弟のように
ブラッドをかわいがっていたのです p.9
逆を言えば、
"血の繋がりはないがブラッドだけを特別扱いしている"ということになります。
皆が美しいと称えるトロフィー(ブラッド)を手に入れたいヴィクター。
あの手この手を使って(毛皮をあげようとしたり、お家に招待してもてなそうとしたりして)手に入れようとしますがうまくかわされています。
ブラッドは自分が愛している兄のことを平然と悪く言うヴィクターに対して嫌いではないが、苦手意識を持っていると語っていました。
「ヴィクターのことは嫌いじゃないけど、
兄さんのことをひどく言うから苦手……」p.21
すごいです。普通、自分の家族対して悪口を言う人なんて秒で嫌いになります…。
心が美しすぎるブラッドから薫る、"常識から逸脱した何か持つ恐ろしさ"を感じます。
あまりにも人々に「美しい」「かわいい」と連呼される光景は、滑稽さを超えて"薄気味悪さ"があります。
ただ"愛されブラッドくん"を描きたくて連呼させたわけではないという筆者の意思が伝わってまいります。
人々をあまりにも魅了するそのおぞましさは魔力ともいえるのではと。
「先日捕った、
シルバーファックスの毛皮をあげよう」
「いい。僕はいらない」p.10
多くの人が思ったのではないでしょうか。
(もらっとけ〜…!要らないなら売ってお金にしなさい…!)
と…。ヴィクターから巻き上げるだけ巻き上げて生活を少しでも豊かにしすれば…ああ〜これが心の醜さか〜…
これは余談ですが
"シルバーフォックス"というと、
もしかして…… (蘭丸は銀髪なので)キツネのトッドの仲間…?
なにかの暗示なの…?みたいな憶測も
発売直後はありましたが、
のちにグッズで出たチャームで
トッド、アカギツネなのー?!
とびっくりした人も多かったのでは…
わたしもそのひとりです笑
「灰色のグレアムがなんだというんだ」p.11
グレアム=グレー="灰色"です。
では"灰色"自体の意味について掘り下げていきます。
一般的に灰色のイメージは
・暗い気持ちで活気がない
・疑惑がある(白黒どっちつかずではっきりしない為)
これだけでもかなり的を射てます。
つまり
・病弱で弱っていて陰気なグレアム
・口減らしに何人もの弟を見送ってきて、さらにブラッドを売ろうとしているグレアム
キリスト教(カトリック)的豆知識
カトリックにおいて「灰」は大きな意味があります。
端的にいえば「灰」=「罪への反省(悔い改める)」「死」を表しています。
「灰の水曜日」というものがあり、
特定の葉を燃やして作った反省の灰で神父様の手によって、おでこに十字を切ってもらう風習があります。
グレアムは祈っていました。
「どうか……罪深き、私をお許しください」p.23
"罪をお許しください"[主の祈り]にも出てくる、クリスチャンがそれはもう幾度となく唱えるフレーズです。
そもそも人は生きているだけで罪と言えます。大元はアダムとイブが禁断の果実をかじり我々人間は天国から地上へ落とされたところにあります。故に、贖罪として生き抜き、人生の最後、死をもってしてたどり着ける天国がゴールです。
これは余談ですが
嶺二の瞳がグレーなのもすごいな…すごい…と感心しました…本当によくできている…
「ここ最近、森にはあぶねぇ奴らが出るって噂だ」
「悪名高き、取り立て屋。キツネのトッドとその一味。森は無法地帯ですから。何があってもおかしくはありません」p.12
"ここ最近"ということはついこの前までは取り立て屋が居なかったということになります。
のちにバーナードが
「ここいらでの仕事はやりつくした感じだし、
これでオサラバかもな」p.28
と話します。
つまり取り立て屋(キツネのトッドとその一味)は不定期に構えを移動しているのが伺えます。
そしてグレアムが取り立て屋からお金を借りたのも"ここ最近"ということです。
"森は無法地帯"
現代よりもまだ発達しておらず、近世まで森自体が正体不明の恐ろしいものでした。人々は気軽に足を踏み入れることはできない。だからこそ、勇敢かつ優秀な猟師ヴィクターが英雄視されます。
「大丈夫、森は僕の庭だから!」p.13
そう言って彼は森へ軽やかにかけて行き、帰宅したとあります。
つまり彼の家は村の中心部から離れ、
村人が簡単には足を踏み入れられない恐ろしい森の中にあるということです。
「はぐれ者」の家族。
ただ貧しいだけでなく、魔術師であるアルヴィンの血縁者ということも少し関係しているのかもしれません。
そんな家族の一員であるのにも関わらず、
ブラッドだけは村の皆から愛され讃えられているのもまたどこか歪んでいて恐ろしさを感じます。
「一番危険なのはオオカミさ!
残虐非道の限りを尽くした半人半獣のワーウルフ。
かわいいお前が1人で出歩こうものなら……ガブリ!
一口でやられてしまうだろうよ」
ヴィクターは脅かすようにオオカミの真似をします。
「……オオカミ!」p.12
「オオカミが悪党なのは決まりきったことだ」p.60
「オオカミ」のイメージは共通して
・悪者
・恐ろしい
です。
よく比喩表現で「男はみんな狼だ」や「送り狼」などの使い方をされており、赤ずきんでも"女子供の敵"の象徴と狼が描かれています。
なぜなのか。
ヨーロッパで狼が人間から恨まれるようになったのは、
羊やヤギなどの家畜を開始したからです。
参考: https://wolfandforest.jimdofree.com/オオカミはなぜ嫌われる/
フランス農村部の口承民話が赤ずきんの源泉と言われており、ブズー(狼憑き男)が悪役で出てきます。その民話から派生したペローやグリム兄弟による「赤ずきん」の童話が世界中に広まり「狼は悪者」というイメージが定着。
本編に話を戻します。
ブラッドはここでオオカミが怖いものだと脅されています。
しかしのちに狼のランドルフと出会ったブラッドは一切怖がったり遠ざけたりしませんでした。
「あの純粋さや輝きに真なる美しさを見た。
生きた奇跡だ」p.72
一切先入観を持たないブラッドの心の美しさにランドルフは惹かれます。
【トッドとグレアムの会話 ブラッドの家にて】※2022.2.28追加あり
トッドというキャラクターについて
先ほど挙げた通り、シルバーフォックスではなくアカギツネ。
一人称:私
丁寧な敬語口調で蘭丸として意外性があります。
そして激昂すると口調も行動も乱暴になるのは普通恐ろしいのですが、「あ、いつもの蘭丸(に近い)…」と安心してしまいました(笑)
トキヤ:今回のプロジェクトでは一般的に皆さんに持たれている印象とは違う配役になっているのも楽しみのひとつかもしれませんね。(プレイボタン)
後に登場する、藍演じるマーリンも、那月演じるバーナードもとても意外性がありました。今までの企画での役柄は基本「当て書き」だったので、今回のプロジェクトの大きな挑戦の一つとも言えます。
プリンスたちが実在のアイドルとして確固たる存在を、歴史を、築き上げた今だからこそできる。素晴らしい。
「父が出稼ぎから帰っていなくて、
お金はおろか、何もありません」p.16
「病気で使い物にならねぇ貴様の体なんて、
売る価値さえもねぇ」p.18
「何人目でしたっけ……人売りに弟を売ったのは?
まあ、今までは父親がやっていたことなのでしょうけど」p.19
改めて情報を整理してみます
・ブラッドが幼い頃、母は他界
・父は子どもを何人も売り、金に換えて生活
・"何人目でしたっけ?「弟」を売ったのは"という台詞からグレアムはおそらく長男
・"お前の「兄弟」は何人消えた?"という台詞からブラッド以外の兄や弟が口減しされた
・長男のグレアムと、ブラッドだけを残し、出稼ぎという名目で捨てる
ここでいくつか疑問が浮かびます
まず
なぜグレアムとブラッドは最後まで売られなかったのか
ここから完全な妄想になりますが、
グレアムが売られなかった理由として考えられるのが
・グレアムが年長だと考えると、"人売りに子どもを売る"ということを認識できてしまっていたため父はグレアム相手には隠せなかった
・グレアムの"病気"のせいで売れなかった
→持病
呼吸器系や心臓が弱いのかもしれない。しかし、その場合、肉体労働させることはできなくても、気絶でもさせて人食趣味のある貴族に人体を売ることは出来るし、働けないならなおのことそうするべきはず。でも父はそれをしなかった。ではなぜか。
→売春させられていて性病にかかった
グレアムが父に命じられて売春していたとしたら納得がいく事が多数ある。
病弱なのに長い間売られなかったのはすでに身体を売って稼ぎがあったから。そして性病にかかってからは売春することも、人食の素材として売ることもできなくなった。
と考えるとやっと合点がいきます。
ブラッドが売られなかった理由は改めてとなりますが、下記になります。
・他の兄弟たちのように、捨てられたくないという無意識から父や兄や村人たちに愛嬌を振りまいていた。
・ブラッドの生来の類稀なる容姿、性格によって村人達から愛され、家族に居れば贔屓してもらえる、金や食べ物を恵んでもらえる、ということで
父が手放したくないと思ったのも要因と考えられる。
本編に話を戻します。
「『仏のトッド』と呼ばれる私でも、
さすがにこれ以上は待てませんよ?」p.17
以前「『仏』というのはキリスト教にも存在する言葉なのでしょうか?」と質問をいただきました。
答えはNOです。
このお話の舞台はフランスやドイツなどのヨーロッパであることは世界観的に間違いないので仏教ではなくキリスト教が根付いていると仮定した上で、この「仏」という単語はあくまで、読者であるわたしたち日本人向けの表現で、見方によっては世界観のブレとして脚本の荒とも取れるかもしれません。
ここで筆者が表現したかったことは「こんなに乱暴で慈悲の無い人が自分で自分のことを「仏のように優しい」と比喩する」ことだと考えます。
「自分は慈悲深い」と表現しながらグレアムのことを暴力でいたぶる。
真逆の事を平然とやってのけているちぐはぐ感が面白いです。
※追記2022.2.28
この記事を書いて少し経ってから気付いたのですが、
ここは"トッド本人の見聞の広さを表現"しているのかもしれません。
キリスト教が根付くヨーロッパに住んでいるが知識としてインドや中国の「仏」のことも知っている聡明さ。
はたまた世界中を転々としながら取り立て屋を生業としていて仏教圏の文化に触れたことがある可能性もあります。
しかしながら学の無いグレアムに「仏の〜」と言ってもさっぱり伝わらないでしょうから、「まあ分からないでしょうけど?笑」というようなトッドの意地悪というか性根の悪さも垣間見えます。
他の可能性として、"トッドが仏教圏(アジア)出身"も調査してみましたが「アカギツネ」自体は昔から世界中に分布している動物で、「トッド」という名も英語圏のキツネの意味を持っているので可能性は低いかもしれないと結論付けしました。
※追記終了
「かわいいかわいいブラッド……。
燃えるように美しい赤い髪。
この世の幸せを、全て集めた恵まれた健康な体。
あいつは上玉だ。きっと今までにないくらい
高く売れるだろうよ」p.19
推しが上玉と評され高く売られる様子はやはり滾るものがあります。
それはさておき、
「赤い髪」が高価値とされるのはかなり珍しいです。
通常赤毛というのは差別対象です。魔女の子であるとか。
アルヴィンの血縁者ということもあり
魔術師や魔女の血族は不思議な力があっても
おかしくないので若返りの作用などを期待した買い手がつく、
ということなのかなと思いました。
そしてこの頃の時代は子供が健康で生まれ育つという事自体がかなり稀有で、なぜかと言えば綺麗な水を手に入れるのが難しかったからです。
子供も大人も水はアルコール濃度の低いぶどう酒などにして飲むのが一般的でした。
「ただいま、兄さん!……あ、お客さん?」p.20
獣人(キツネ)を見ても「あ、お客さん?」程度なところから予想されるのは
①この世界は獣人と普通の人間が共に暮らすのは普通
②獣人は差別対象のため普通の人と暮らせはしないが、ブラッドには差別意識は全くないため
まあ、②で間違いないでしょう。
①になれたらいいのに…。もふもふかわいいのに…。
「自分たちと違う者」は、よくわからないから、恐ろしく、気味悪く、不快だから、袋叩きにし排除しようとするのはどこの世界でも一緒。
理解できないものを理解しようとする前にとにかく「不快だから」「叩く」「排除」
「本当かどうかわからないことを、
悪く言うのは良くないと思う」p.13
こう言うブラッドを美しいと感じて惹かれているのに自分たちはそれをやめない。
集団心理の恐ろしさ。
SNSでよく見る光景が村人たちそのものですね。
村人たちの"この滑稽さ"は「わたしたちの風刺」であり暗喩であると自分は捉えています。
「ううん!僕はね、兄さんがいてくれればそれで十分。
これからも、ずっと一緒にいてね」p.21
普通の環境だったら改めて言わなくてもいいようなことを、
ブラッドはこうして無意識に言葉にして愛嬌を振りまいて捨てられないようにと予防線を張っていたのかなと考えると胸が痛みます。
「……また、私は犯してしまうのか。罪を……」
「罪……。
そう、生きるということは、罪を重ねること……。
何も悩む必要はない。仕方のないことなんだ」
怪しげな声がグレアムの心の中に響きます。p.22
いよいよ黒ずきんの登場です。
セシルはこのシーンに関して下記のように語っています。
セシル:自分の命と弟の命を秤にかけ葛藤しているグレアムの背中を黒ずきんが押すわけですが、
グレアムにはワタシの姿は見えていないという設定なので
なるべく気配を消す努力をしています。(プレイボタン)
あくまで声が心の中に響いた。ということが重要です。
要は自問自答ということです。
黒ずきんはこの後、何度も登場しますが、
表れるには必ず条件があります。
【第一条件】森の中である
・グレアム&ブラッドの家は村から外れた森の中 p.22
※森の中だがあくまで家の中でもあるので姿は見えて居ない
・ブラッドが黒ずきんと会話をしたのは森の中 p.40
・ヴィクターが黒ずきんと会話をしたのは森の中(私有地)p.66
・ランドルフが黒ずきんと会話したのは森の中 p.69
【第二条件】何かを葛藤している
・グレアムは弟を売りに出すことを葛藤
・ブラッドは寄り道しちゃいけないという葛藤(かわいい)
・ヴィクターはブラッドに責められたことにより自分の正義の行いが間違っているのではと葛藤
・ランドルフはブラッドをどうするべきかという葛藤
文明が今ほど発達していなかった時代、 黒ずきんは、人々の欲望を養分として力を溜めていき、最後は誰も抗うことのできない運命に登場人物たちを誘います。
「森」とは人智が及ばぬ恐ろしいところである。
人ならざる力で満ちている。そのひとつが黒ずきん。
「人々の欲望を養分として力を溜めていく」
養分を吸い上げる「森」そのものが黒ずきんである。
だから(黄)緑色のセシルが選ばれた。
緑色は赤色と混ぜると補色同士なので「黒」になります。
姿が見えたり見えなかったりするのは条件下によって変化しますが意味合い的にはそこまで重要ではなく、あくまで「人の心を映し出す鏡のような存在」。
なかなか難しいですが、セシルも
セシル:黒ずきんの存在は「人間の心の闇を表現したもの」だと
自分の中に落しこめるまで役に入り込むことができず苦労しました(プレイボタン)
と言っていたので読み手によってはいつまでもピンとこない…。概念とかいわれても…。という方もいると思います。要は考えるな感じろ的存在ということです…。
セシル:人の心を映し出す鏡のような存在です。
いまもアナタのそばに佇んでいるかもしれません。
(展示:「黒い森」の中にあったコメント)
もしもし、わたしメリーさん。今あなたの後ろにいるの。
そして「Black hood」(黒ずきん)という名前について
Blood(血)とhack(屠る)を入れ替えるとBlack hoodになるという考察は大変面白いです。
・ブラッド(血)を屠ろう(hack)とする存在が黒ずきん。
・ブラッド(血)が(ランドルフやアルヴィンを)屠る(hack)。
どちらとも取れます。素晴らしい。
【取り立て屋の一味の登場】
「そんなに大きな声を出さなくても、聞こえているわよ。」p.24
え!藍くん女の子役!?とびっくりした覚えがあります。
しかしすぐあと
「むさくるしい男達に『お帰りなさ~い』なんて、
かわいらし~く迎えて欲しいわけじゃあるまいしなぁ?」p.24
あ、みんな男だった…。と(笑)
マーリンはかなり面白い役ですね。
声色や喋り方は女性なのに一人称は『俺』なので
心も体も性別は間違いなく男。とても魅力的です。
動物はハヤブサ
なので羽根が生えているのだと思われます。
藍くんにとても似合います。
羽ばたくときに美しい風が起きる。
バーナードはやんちゃで子供っぽいところが可愛い役です。 バーナードはこの中では一番の新入りで、やんちゃな言動から、年も一番下じゃないかとか。もしかしたら、一時的に目的が一致して、お手伝いしているだけなのかなとか。
残虐で単純に何かを傷つけることを楽しむところも
子供特有の無知ゆえの残酷さを感じます。
動物はクマ
なっちゃんのふわふわのブロンドにまあるいお耳が、お尻にまあるいしっぽが生えてるビジュアルなんだなあと嬉しくなってしまいます。
那月くんの役作りは演技によく反映されていました。
「つきあいわりぃ一匹狼だなぁ。
わざわざ住処まで1人だけ遠くにかまえてよ。」p.29
この一言で初聴の自分は(あ…。1人だけ遠く…つまりそこでブラッドと出会うんだな…)と察しました。書き手目線でつい読解してしまう…。
「奴に逆らって、何か得はあるのか?」
揺るぎない事実と絶望が入り混じる言葉。p.30
日々を呪い絶望しながらそれでも生にしがみ付いて生きているランドルフの淡々とした恐ろしさがこの場面には現れています。
「生きていくためには、それしかないだろう」
「死んだような目でそんなこと言わないで。
……あの時からずっと、君は生きているようで、
ただその身を時の流れに任せているだけ……」p.30
マーリンは、ランドルフの過去を知っている友人である。 大事な設定だから明確に伝えることはできないけど、マーリンとランドルフの関係は特に深い。マーリンはランドルフの過去を知ってる人物で、友人でもある。ただ、その想いはランドルフに伝わっていないみたい。
「奴隷として虐げられていた方が良かったと?
ワーウルフとして見世物にされ、鞭で打たれ、
自由も何もない檻の中で生きることの方がマシってこと?」p.31
「貴様と同じで、肉親に金で売られた子だよ」p.53
「わざわざ自分のトラウマをこじ開けるような真似、
しなくてもいいじゃない?」p.30
「その顔の傷……忘れたわけじゃないでしょう?」
右目をかき切るような大きな傷。
「忘れるわけないだろう。捕らわれているのさ、過去に。
体に刻まれた刻印のように、消すことはできない」
今も生々しく横たわる傷に指で触れ、
自分を戒めるかのように顔をゆがめるランドルフ。p.32
ランドルフの気になりすぎる過去の片鱗が見えます。
肉親に売られた後、奴隷となり、"恐ろしい獣"として、それを"人間が屈服させている様子を楽しむ"ために、鞭で打たれ見世物にされていたということ。
顔の傷は売られた時に抵抗してできたものなのか、 そう拗ねないの。設定の話をするとき誰よりも楽しそうだったもんね、トキヤ。設定表を作成して、ボクたちに渡してくれたり。
奴隷にされた時につけられたものなのか、
現在の情報だけでは判別はつきませんがとても気になります。
その設定表見せてほしい~~~!
あとこの日にインタビューで詳しく話していたと思うのでそのインタビュー記事は一体どこで見れるのでしょうか…ツイログ本でしょうか…。今すぐ欲しい…。
もしかしたらマーリンは、
ランドルフが家族と森で暮らしている頃からの仲なのかもしれません。
彼が優しく笑っていた頃を知っているからこそ、
助け出そうとトッドに助力を仰ぎ現在に至るのかも。
自分と同じ境遇の子をまた生み出そうとしているのに関わらず、ランドルフはトッドに逆らいません。
「わざわざ不幸になりにいくようなものよ!
少しくらい自分の幸せを望んだっていいじゃない」
長く付き添ってきたからこそわかる深い心の闇を、
マーリンは少しでも軽くしたいと思っていました。p.33
しかしマーリンの想いはランドルフには届きません。
「俺は罪を犯しすぎた。
救われることなど、あってはならない。
そして、これ以上望むものなどない。」p.32
彼はただの悪逆非道なオオカミなのではなく、
”優しすぎるが故に、罪の意識から、
深い自虐思考に陥ってしまった人”
であるとここで分かります。
「幸せか……。まるで夜空の星を掴むようなものだ」P.33
ランドルフにとってオリオンだったころの温かな記憶は、天に昇った星座のように遠いものになっている。という美しくも切ない描写にぐっときます。
【お使いを頼まれるブラッド】
ここは童話「赤ずきん」の冒頭で見慣れたシーンです。
「焼き立てのレーズンパンにチーズ。
それに真っ赤なラズベリージュース……と。」p.34
なぜレーズンパンとラズベリージュースなのか。
カトリックに置いて「パン」と「ぶどう酒」は「最後の晩餐」にも出てくる大変重要なアイテム。「パン」はイエス様の"身体(肉)"。「ぶどう酒」はイエス様の"血"として食べる風習があります。※詳しくは割愛しますが「イエス・キリスト」は神様ではなく私たちと同じ人間ですので詳しく知りたい方はお調べください
今回リコリスの森だと赤ずきんが子どもということもあり、ぶどう酒はラズベリージュースに。ぶどう要素はレーズンパンに変更してあります。
再度となりますが、電気が無かったころのヨーロッパでは飲料に適した水の入手が困難だった為、当時は子供もアルコール濃度の低いぶどう酒を常飲していました。
なので当時の事情を考えればぶどう酒のままでもいいのですが、現代の文学作品としては倫理上ダメなのでこうなっていると考えています。
普段は行くことが許されていない森に住む、
アルヴィンの元へ行けることに胸を躍らせるブラッド。p.34
大人でも森に分け入ることはかなり勇敢なことで、
子ども一人では普通入らないところです。
童話「赤ずきん」でもかなり不思議な導入ですが、
リコリスの森の場合、
グレアムが病弱の為、どうしても必要な時として
今回ブラッドにお使いを頼んだという意味付けができています。
(本来の意味はブラッドを売るためですが)
「やだな、兄さんったら。
僕はそんなに子供じゃないよ」p.36
さて「ブラッドは何歳くらいなのか問題」に入ります。
そもそも原作の童話「赤ずきん」の少女は何歳なのでしょうか。
子供だとしても、独りで道に迷わず、森を抜けられるので、少なくとも10歳以上の年齢には達しているだろうと考えられます。
ペロー版「赤ずきん」は少女が(無意識にでも)オオカミを性的に誘惑し被害を受けてしまうことに警鐘を鳴らしているので初潮を迎えているとすれば12歳以上。
グリム版「赤ずきん」は単純にオオカミに物理的に食べられてしまうという恐ろしさを描いているので10歳でも問題はありません。
ブラッドの年齢も10歳以上であるとは思います。
ただ、15、16歳の男の子ですと早乙女学園入学時期の音也くんと同じですので
そこまで大きくはないと描写から考えられます。
第二次性徴期を迎えたてな、これからぐんぐん身長伸びて大きくなるよ!という10歳~12歳が妥当かなと。
「いいかい、ブラッド。
決して、このケープを脱いではダメだよ。決してね」
「うん、わかった。じゃあ行ってくるね、兄さん!」
グレアムの注意もそこそこそに
ブラッドは元気よく扉を開けて、出かけて行きました。p.37
ここの音也の演技が最高ですよね!
「うん、わかった。」が全然話聞いてない感じで(笑)
「……太陽のように明るく……輝く瞳……」
「……美しく燃える……炎のような生命力……」
「……ブラッド」p.40
「森」が「養分」としてブラッドを求めているんだ…と感じました。
このころのヨーロッパは土葬です。
死体は土に埋められると考えれば森が彼を死へと導いたのも、この後の黒ずきん(森)の行動にも全て納得がいきます。
「あなたは誰?その黒いケープ。
僕のとよく似ている」p.40
先ほどのグレアムと違い、森の真っただ中にいる為、
黒ずきんの姿が見えています。
甘い囁きで誘い出すシーンは童話「赤ずきん」では悪役のオオカミが担っていましたが、今回のリコリスの森で赤ずきんを"食べたい"と思っていたのは「森」だったのです。
この背景の「森の中の"牙"」。構図的にも"森がブラッドを食べようとしている"のが大変わかりやすいですね。
すっかり日が暮れ、暗くなってしまい帰り道も分からなくなってしまったブラッドに黒ずきんが提案します。
「ほら、あそこに洞窟がある。雨が止むまでそこで休むといい。……それと、その美しい赤い外套。濡れてしまっているよ。大切なものなんでしょう?」
「さあ、脱いで……。その籠の中に入れよう。
ちゃんとしまわないと……」p.42
ランドルフに赤い外套を見られたら連れ去られて貴族の手に渡ってしまうから…。森の養分にならないから…。誘導している…と思うとゾっとします。
「でも、なぜだろう、初めて会った気がしない」p.42
人の心を映し出す鏡のような存在であるので、正しい感じ方です。
またこれは仮説なのですが、
この森にはリコリスの花がたくさん咲いています。
リコリスは死体を野生生物に食い荒らされないように動物避けとして植えられることが多いです。
ブラッドの父は子供たちの臓器を売ってお金にしていたとしたら。その残骸があの森に埋められている可能性があります。あの森にはブラッドの兄弟たちが埋まっていてそれを養分として森は成長した。
すると姿がブラッドと(ずきん姿が)似ているのも、ブラッドを求めるのも、合点がいきます。
また、鏡である黒ずきんの見え方は人によって年齢感が異なるようです。
ブラッドと黒ずきんの場面
「不思議な子だったな」p.42
ヴィクターと黒ずきんの場面
見るとそこには黒ずきんの男が佇んでいました。p.66
「不思議な子」と「黒ずきんの男」。まさに鏡のようにその人を写しています。
【雨降る夜、2人は洞窟で邂逅】
「指示通り待機していたのに、なぜ現れない。子供1人通らなかったぞ……」
オオカミは奥から人の気配を感じ、身構えました。p.44
黒ずきんが上手くブラッドを誘った結果が表れています。
ここの鼻を鳴らし気配を察する演技がオオカミらしくて素晴らしいです。
ここでひとつ豆知識
<多相睡眠>
電気照明が発明される以前の中世、近世ヨーロッパの人々は、夜寝始めの「第1睡眠」、夜中に目が覚めて朝まで寝る「第2睡眠」の2回の睡眠を取っていました。
なのでブラッドが夜中に一度目が覚め、また眠るのはとても自然なことです。
また、ブックレットに載っているイラストのオリオン座の見え方から計算すると、すでに夜明け前、朝方に近い時間でした。(※このリコリスの森の舞台を赤ずきんの原点であるフランス北部の山間の農村と仮定した場合です)
「目が覚めたか。随分とよく寝ていた」p.45
日暮れから夜明け前まで寝ていたとなるとこの台詞にも納得がいきます。
「怖くなんかない。あなたの目を見ればわかるもの。
それに、僕を起こさず待っててくれたんでしょ?
やっぱりいい人だよ。」
「逃げ出すどころか、近寄ってくるとはな」p.45
このシーンも以前質問をいただきました。
「ランドルフはオオカミであることを(耳や尻尾をしまい)隠していたのでしょうか?」と。
答えはNOです。
自分の罪を背負う自虐思考のランドルフが、
今更オオカミであることを隠し、取り繕うことはしません。
「ただいま、兄さん!……あ、お客さん?」p.20
このシーンと同様で、
”ブラッドは獣人に対して差別意識が全くない”というだけです。
セシル:ワタシはこの一番大好きです!
幻想的な洞窟に流れる温かな空気に心が癒されます。
レン:このシーンはセッシーだけじゃなくて
他の出ていないメンバー全員が裏手から見ているよね。
それはもう大人気さ!(プレイボタン)
裏手の視聴率100%のシーンへと入ってまいります。
たき火で濡れた体を温めていたであろうランドルフ。
夜明け前の一番寒い時間に目を覚ましたブラッドがくしゃみをすると厚手の毛布をそっと肩にかけてくれます。
「……ありがとう。でも、あなたの分は?」
「俺はいい」
「じゃあ、一緒に入ろう。仲良く半ぶんこ、ね!」p.46
「僕、いいもの持っているんだ。
とてもおいしいパンとジュース!」p.46
ブラッドはとにかく「隣人愛」に溢れた子です。
「自分の持っているものはすべて平等に分け合う。」
クリスチャンはこうあるべきというのを見事に体現しており、
父なる神も大満足の本当に美しい子です。
触れ合う部分からお互いのぬくもりが伝わります。
「どう?あったかいでしょう?」
「……ああ、そうだな。あたたかい」
オオカミは、言葉少なく寂しげに呟きました。p.46
人のぬくもりは久しぶりだったのでしょう。
遠い昔の家族との温かな記憶を思い出させ、彼は寂しげになったのだと思います。
「あなたの笑った顔、好きだよ。すごく優しい笑顔 」
「そんなことを言われたのは、お前で2人目だ。
いつぶりだろう。もう忘れてしまうくらい、
遠い過去の記憶だ。」
「大好きだったんだね、その人のこと」p.47
では1人目は誰なのか。
発売当時、様々な考察が飛び交いました。
結論はプレイボタンにあります。
トキヤ:ブラッドに面影を感じるということは同性でしょうし、
あれだけの愛着を持つという事は
近親者であることは間違いないだろうと思うのですが。
音也:俺は弟かなって思ったけど、
トキヤは父親じゃないかって。(プレイボタン)
→音也は孤児院で歳下の子に囲まれて育ち、弟のような存在が自分の中で大きい。トキヤは父親との思い出(Debutメモリアル参照)が自分の中で大きい。だからそう思ったという事実に基づく解釈の違いの描き方が凄すぎませんか?シナリオライター:武口さん…さすが…いつもお世話になっております…
きっとここ、もしトキヤが実際に双子の兄が居たら「兄」と答えるかもしれないし、そういう育ち方からくる感じ方の違いの数だけ
その人だけのリコリスの森の解釈が存在するという示しでもあって本当に素晴らしい…。
このトークを聞くまで「母親」?と思っていたのも、自然と”自分の同性で近親者で考えてしまっていた”からだったんだと腑に落ちました。
受け止め方自体は間違ってなかったのか…、と。
「父さんは出稼ぎに行ったっきり帰ってこない。
もしかして、見捨てられちゃったのかなって
思う時もある。兄さんにも言えなくて、
ずっと1人で悩んでたんだ」p.47
ブラッドは何も気づいていない子供ではないということがここで分かります。きっと兄弟のことも気づいていて、でも誰にも言えず悩んでいた。
「……オリオン。自分と同じ名前だからか……」p.50
オリオンという名前については下記の意味合いが含まれています。
【オリオンとは】
ギリシャ神話の海神ポセイドンの子で、とても力が強く、すごぶる美男子で、狩猟を愛好していた。死後、天に昇って星座となった。
【オリオンとサソリ座】
オリオンが赤いサソリに刺されて死んでしまうように
ランドルフがブラッドに刺されて死んでしまうという暗喩
【オリオンとアルテミス】
オリオン(ランドルフ)にもアルテミス(ブラッド)のように
「好き」と言ってくれる人が現れるという暗喩
その「好き」と言ってくれる人に殺されてしまうという暗喩
カトリックには「洗礼名を授かる」という儀式があり、聖人や天使の名を授かることでその人のように生きていく、その人のように生きてほしいと名づける風習があります。
なのでこのオリオンという本名は「洗礼名を授かる」ような意味で
「こういう人生を送る」というメタファーだと解釈しています。
前世が~というのはこのリコリスの森の話から大きく逸脱するので特に考慮していません。
「そうだ!僕が大きくなったら、星を取ってあげるよ。
ランドルフと同じ名前の星を 」p.51
ここでブラッドがまだ第二次性徴期の途中で身長がこれから伸びるという事がわかります。先ほどの年齢の仮説に役立ちました。
「……約束だよ。今度会ったら、もっといろんな
ことを話そう。そして……もっと広い世界を……
見て……みたい……。2人ならきっと……楽しい……」
ランドルフに体を預けて、眠りに落ちるブラッド。p.51
ここでの約束はきちんと果たされるところが素敵です。
【トッドとランドルフの会話】
「顔や気に入ったパーツは観賞用。
余った部位は食用にするそうです」p.53
カニバリズム(人肉嗜食)が横行していた時代なのでしょう。
うたプリとは思えないグロテスクな描写が出てきました。
筆者の本気さが伺えます。
「……いいか、ランドルフ。
貴様はこの稼業から一生逃れられない。
足抜けにかかる莫大な費用を立て替えてやったのは、
誰だと思っているんです?」P.54
ものすごい投資をしてランドルフと手に入れたトッドは、きっと事あるごとにランドルフを脅し、見えない鎖でつないでいるのでしょう。
マーリンの提案によってトッドはランドルフに莫大な投資をした、そう考えるとトッドはマーリンをかなり信頼・もしくは気に入っているのかな?と推察できます。
「獲物がどうなろうと俺の知ったことではない」p.53
ランドルフはこう言っていましたが
それがブラッドだと知り酷く動揺します。
「自分と同じ境遇の子を、
この手にかけるというのか……?」p.55
マーリンの言葉では響かなかった事実が彼を苦しめます。
今まで、獲物に対してすべて目や耳を塞ぎ、仕事をしてきた彼に、大きな大きな変化をブラッドはもたらします。失ったはずの心が再び彼に。
きっとこの時点で、ランドルフはもう、誰のことも殺せなくなってしまった。ブラッドに牙を抜かれてしまったのだと。言葉通りの、骨抜き、ですね。
【売ったはずのブラッドが帰宅】
「……ただいま!」
「……ひっ!!ブラッド……!お前、どうして……」
弟の帰りに飛び上り、戸惑いを隠せないグレアム。p.58
ここはヘンゼルとグレーテルを彷彿とさせます。
口減らしに森に置いてきた子供がどんな方法を使ったのか帰ってくる。
「抱きしめて、おかえりも言ってくれない。……兄さん」p.59
ブラッドは不信感を抱いています。まだ具体的には分からないけれど、今までの兄弟たちを見てきたブラッドにとっては、なんとなく予想はついているのではないでしょうか。
「現実を見ろ!今まで、お前の兄弟達は何人消えた?
遠くの親戚に引き取られるだの、理由をつけて口減らしさ!
父親は、どうしていつまでも帰ってこない?
捨てられたんじゃないのか、お前たちは?
それに、唯一の味方のグレアムでさえ、
信じられたものかどうか…」p.63
これはすべてブラッドがなんとなく気づいていたことだと思いますが、ヴィクターに実際に事実を突き付けられ、確信的疑惑に変化したのでしょう。
「こうしてはいられない。村の安全にも、
有志を募って奴をこの森から追い出さなければな!」
その熱に村人も扇動され、口々に声を上げると
オオカミ討伐に乗り出しました。p.64
賛同は大きな渦となり、村全体の空気を変えていきます。p.65
ああ…こうやって「炎上」していきますよね…
頻繁に見る光景でチクチクと胸が痛みます。
本人たちは「正義のため」に行動しているので無自覚なのがまた手におえないのがそのままです。
ブロッコリーは風刺が上手だなあ…。反面教師になれるようこの場面を思い出し日々心を戒めています。
「何と言っても、俺は村の英雄だからな!
……俺は正しい」p.65
自分を言い聞かせながらも酷く葛藤している様子です。その原因は言うまでもなく、
「ヴィクターなんて大嫌い!」p.66
私有地の森に佇む彼の前に黒ずきんは現れ、
ヴィクターの正義のウラにある本当の欲望を曝け出します。
ヴィクターに森へと入ってもらわないと森は困ります。
ランドルフがトッドの指示通りブラッドを攫ってしまっては手に入れることができないからです。
黒ずきんはヴィクターを煽るように背中を押します。
再び、お使いを頼まれるシーンとなります。
「…う、うん。あの、兄さん……怖いよ」
「おやおや、この間はあんなに楽しそうに
していたのに、おかしな子だ」
「……兄さんは、僕を愛しているよね?」p.68
ブラッドのなかで疑惑が渦巻いているのが分かります。
ブラッドがアルヴィンにあげるためにリコリスの花を摘んでいる様子を、ランドルフは葛藤しながら見つめていました。
黒ずきん(自分の心のウラ)との会話です。
「他の人間にとってはそうでも俺にとっては違う!」
腕を乱暴に振り回すも、むなしく空を切るだけでした。p.72
ここのトキヤの演技は絶品です。たまりません。
黒ずきんの姿がたとえ見えていたとしてもそれはあくまで自分自身のウラにすぎないので触れるはずもありません。
「そうだ。誰かの手に渡るくらいなら、
自分の手で終わりにしてしまえばいい」
「自分の手で殺すだと?
大切だからこそできるわけがない。
だが、そのままにしておけば、生きたままの地獄を
味わうことになる。……くそ、どうすれば」p.73
黒ずきんは「ブラッドを殺せばいい」と提案しています。
黒ずきん(森)の行動目的はそこにあるのだと分かりやすい場面です。
ランドルフの葛藤の内容は下記となります。
・たとえランドルフがブラッドを逃がしたとしても、他の誰かが捕まえに来る
・兄の元に戻ってもすでに関係は壊れているから、幸せにはなれない
「ああ……。俺に選択肢などない」p.73
ここも以前質問をいただきました。
「つまりランドルフはどうするつもりだったのですか?」と。
ランドルフには最初から選択肢はなかった。
つまり「トッドの言うとおりブラッドを傷一つつける事無く連れ去る。」です。
彼はもう牙を抜かれてしまい、誰のことも殺すことはできなくなっています。ましてや大切なブラッドを自らの手で殺すことなんてできません。
【アルヴィンの家】
アルヴィンという名前について。
ラテン語で「白」を意味する albus に由来しています。
高貴さや美しさ。カトリックに置いては「復活」の意味もあり、彼の心臓を食べることで若返るのも納得です。
「ブラッドは、こんな私のことを好いてくれている。
嫌われ者の私にも同じように笑いかけてくれた。
それでどれだけ救われたことか。」p.75
ランドルフも同じ思いだったはずです。
アルヴィンは本物の魔術師。予知力があり予言(占い)によって先の未来をみることができます。
母さんの血縁者だからこうして時々面倒を見ているだけで…ああ、口に出すのもおぞましい!占い師とは名ばかりで裏では…」p.35
アルヴィンとランドルフの会話で、
取り立て屋とアルヴィンは仕事関係にあったことが伺えます。
「私の心臓をやろう。魔術師の心臓は高く売れる。
一口、口にするだけで、体は若返り、
不思議な力を得られる」p.76
さらりと臓器売買の話が出たところから考えると、
取り立て屋から仕事を受け、アルヴィンは臓器の摘出などに関わっていた可能性があるのではと推察しました。
村人から悪い噂が立っていたのも、そういう理由かもしれません。
グレアムを問い詰め真実を知ったヴィクターが、
アルヴィンの家へと到着しました。
胸から血を流し、見るも無残な姿。
「アルヴィンの血が飛び散り、
まるでリコリスの花のようだ。なんて美しい
嫌われ者アルヴィンの美しい最後…
彼を憎むべき人はたくさんいる。死んで当然の人間だ」
黒ずきんは、喜々として話します。p.80-81
細かく読解していきます。
まず
「胸から血を流し、見るも無残な姿」
ここは後々明かされる、ブラッドが事故でアルヴィンを殺してしまったシーンから具体的な姿が想像できます。
自らの胸を刺そうとしたナイフが刺さり、
床で頭を強打し、頭蓋骨が割れ、あたりが赤く染まった。
ナイフはブラッドが持ち去ったので残ってはいないのでしょう。
「なんて美しい」
黒ずきんの台詞ですが彼は人の心のそのものです。
つまりヴィクターは「彼は死んで当然」と思いつつも「なんて美しい」とも思っているという事になります。
(御曹司エモポイント+100点)
黒ずきんが喜々としているのは森としての意思。
魔術師の養分が手に入るのですからそれは嬉しいはずです。
「本当に誰だろう?
こんなに残酷な殺し方ができるのは……」
「……オオカミだ!きっとそうに違いない!」p.81
自問自答故にヴィクターが思う一番残酷な者が白羽の矢に立ちます。
「さぁ、これで全ての駒が揃った。もう誰にも止められない」p.81
森の思惑通りに事が進んでいきます。
さあ、いよいよクライマックスです。
【リコリスの花畑、2人の再会】
「……知ってる?
リコリスの花と葉は出会うことがないんだよ。
花が咲いている時は、葉は身をひそめ、
花が散ると、葉が芽吹く。同時に存在することができない。
似ているよね、僕達に」p.84
ちょっとここ、脱線するのですがお話したいことがあるので聞いていただいていいでしょうか…。
当時のうたプリを知っている方はご存じのとおり、
音也とトキヤはまさに「同時に存在することができない」の?ってほど…「共演が事務所NG」なんて言われていました。
なので自分は「うわ~~~音也とトキヤの当て書きだ~~~エモ~~!」と思っていました…いえ、こんなハイテンションではなく…(ああ…W1だね…はは…)って泣いてました。
もう今となっては信じられない過去ですが、確かにあった事実なのでここに当時の心境と共に書き記し残させてください…。以上です…ご清聴ありがとうございました…。
「なぜ、あなたはそんなに優しい目をしているの?」
「それは、お前を見つめているからだ」
「それなのに、どうしてあなたは
そんなに悲しげに笑うの?」
「それはお前といると胸が苦しくなるからだ」
「教えて、あなたの心はどこにあるの?」
「それは、お前と共にある」P.85
「赤ずきん」としての象徴的な名場面です。
比較のために掲載します。
「あらまあ、おばあちゃん、なんて毛深いの!」
「だから暖かくしていられるのさ。」
「あらまあ、おばあちゃん、なんて長いお爪をしているの!」
「長いと体を掻くのに便利だからね。」
「おばあちゃん、まあなんて肩幅の広いこと!」
「その方が焚き木を森から運ぶのには都合がいいからね。」
「おばあちゃんたら、なんて大きなお耳をしているんでしょう!」
「その方がよく聞こえるからね。」
「おばあちゃん、なんて大きなお口なの!」
「その方がおまえを食べるのには便利だからさ!」
語り手は「その方がおまえを食べるのには便利だからさ!」と子供を脅すように脚色して読み上げます。
おばあさんの様子がおかしい、怪しい、と疑っている赤ずきんの立場にいる子供たちは驚き、オオカミが恐ろしいものだと受け止めます。
このリコリスの森でのランドルフは既に従来の「恐ろしいオオカミ」の定説を破っており、ランドルフの言葉や声からも「深い愛情」が感じられます。しかし、このやりとりには、どこか緊張感が内包されています。
「嘘つき!」p.85
ここの音也くんの演技は最高ですね…。ありがとう…。
ブラッドはアルヴィンから全てを聞いて知っていました。
「俺も同じ気持ちだった。お前といると幸せを感じた。
こんな気持ちがあるなんて知らなかった。
その気持ちに嘘はない!」p.86
本当に嘘はないのです。
ただ、ブラッドを売ろうとしていることも事実で…。
ああ…板挟み…かわいそうなランドルフ…。
「本当に好きだったのに……」
「ブラッド……どうして……ぐっ」
ランドルフの胸にナイフが突き立てられていました。
「あの瞬間を永遠にするためだよ。
かわいそうなランドルフ。
誰かにあなたを殺されるくらいなら、
僕の手で、天国へ送ってあげる……」
さらに深くナイフがランドルフの体へと入り込んでいきます。p.86-87
ランドルフに対する、ブラッドの感情は
「……ランドルフは、僕の友達さ!」p.64
もちろん友愛。
しかしそれだけではここまでの激情には至らない。
ただただ純粋に「愛している」のだなと。
たった一晩、話しただけ。でもまた会いたいと強く思った。一目惚れ。
どう比喩すればうまく表現できるのか、
語彙が見つけられずにすみません…。
失ってしまうくらいなら、あの一夜を永遠にしたい、誰かに殺されるくらいなら自らの手で…と願ったのはブラッドもランドルフも同様でした。
しかし牙を失ったランドルフにはそれはできず。
「天国へ送ってあげる」とブラッドからの祝福を受けながら、
ランドルフは死んでいくことになります。
「……それに、こうして人を手にかけることで、
あなたと同じ罪を背負うことができる……
あなたの気持ちをもっと理解することができるんだ」p.87
キリスト教(特にカトリック)に置いて、
生前、どのような罪を背負ったかが、天国へ行く前にかなり重要になります。
人は誰しも何かしら罪を犯してしまうものです。
罪を持ったものが父なる神と同じ世界である天国へはいけません。
人間は死後、「最後の審判」というものにかけられます。
これは生前どのような罪を犯してきたかによって
・天国
・煉獄経由の天国
・地獄
この3ルートの内どれかを審判されます。
大体の人は「煉獄」経由の天国です。
煉獄とは罪の重さによって清めの炎で火あぶりにされる時間が延び、
罪の分だけ、天国へ行くのに時間を要します。
罪の清算場、といえばわかりやすいと思います。
ブラッドはランドルフを手にかけることなく死んでいたら、
天国へ直行でしたでしょうし、ブラッドはそれではランドルフをもっと理解することはできないと思い、行動を起こしたと発言しています。
煉獄の炎で焼かれることができる。
最後の審判の後、同じ苦しみを味わうことができる。
これはのちに、天国で2人が再会するときのタイミングにも関わってきます。
「あなたをこの現実という檻から解放してあげる」p.87
ここも以前質問をいただきました。
「どういう意味なのでしょうか?」と。
これもカトリック観でお話してしまいますが、
アダムとイブのお話の通り人間は元々天国の住人でしたが、禁断の果実を口にしたことによって罰として地上に落され、罪を重ねながら背負い続けることを強いられます。生きていること自体が罪であるという人生観です。
ランドルフの悲痛な心の叫びが森に響きます。p.86
ランドルフが苦しんでいることは先ほどのやりとりでブラッドも感じていたでしょうし、カトリック特有の人生観も合わさって
「現実という檻から解放してあげる」となるのはとても自然だと感じました。
「ありがとう、愛している……」
ランドルフは最後の力を振り絞って
ブラッドを強く抱きしめ返しました。
「……愛しているよ」p.89
ブラッドとランドルフが深く愛し合っている様子は、
これ以上ないほど美しく、切ないです。
種族も違う、立場も違う、性別は同性。
何もかもが彼らを阻んでいたのかもしれませんが、
もはや何物も立ち入ることはできません。
一夜で恋に落ち、愛し合った2人を世界が殺す。まさにロミオとジュリエット的です。
「ふふふふふふ……」p.89
ブラッドと黒ずきんの声が重なります。
”ブラッドの心のウラにあった欲望がブラッドの表と完全に一致した”ということです。つまりどこを見ても裏も表もない。捻じれた結果のメビウスの輪状態です。
「これであなたの心は僕のものだ。
どんなに時が経ったとしても色あせることのない、
真実の想い……」
ランドルフの亡骸を、愛おしそうに抱きしめるブラッド。p.89
あくまでここは「ブラッド」です。
声は黒ずきんですが単純に「ブラッドの欲そのものの吐露」であるというだけです。
ヴィクターが駆けつけます。
ヴィクターはアルヴィンを殺したのはランドルフだと思いこみ、オオカミは死んで当然だと、オオカミを殺したブラッドを責めることはしません。
しかし
「アルヴィンを……殺したのは、僕だ」p.91
「僕だ」の声、最高ではありませんか?
この演者さん、一十木音也くんって子なんですけどすごくないですか?1994年4月11日戌年生まれ血液型O型東京都出身最近は筋トレに励むスポーツ大好きな男の子なんです。よろしくお願いします。
【アルヴィンの家・ブラッド到着】
アルヴィンはブラッドにすべてを打明けた上で、
自分の心臓を渡そうとします。
「やめて!!もう、誰も死ぬのを見たくないんだ」p.94
ここも質問がありました。
「一体以前誰が死ぬを見たのでしょうか」と。
ブラッドが「亡くなった」ことを認識しているのは母親です。
そしてこれは音也くんとの共通点でもあります。
役と役者をかすらせています。
母さんが亡くなった時のことは音也くんにとって大きなトラウマになっており、ブラッドも同様だったと考えるのが自然です。
「あは、あはははは、ははははははは!!」p.94
人間って、本当にパニックで恐怖してしまったとき、
笑うような呼吸になってしまうんですよね…。
ここ、すごいリアルです…。
読者目線でみると、またこれがなんとも恐ろしく感じる…。ああ、ブラッドは壊れてしまったのか、と。心は間違いなく壊れましたね。だからこそ理性を手放し自分が真に求めるもの(ランドルフ)を何が何でも手に入れようとした。
【ブラッドとヴィクターのラストシーン】
ブラッドに黒いずきんの男の影が重なり、
その声や振る舞いは彼ではありませんでした。
「この手で殺したとき感触はまだ残ってる。
(割愛)
これでぼくは助かるのかもしれないって……」
これはブラッドの心の声。
今まで押し殺してきた本心に他なりません。p.95
ト書きが全部きちんと説明してくれていますね!
そう、あくまでブラッド本人の本心です。
ブラッドと黒ずきんの姿がダブって見える描写は、「愛島兄弟」を上手く活用していますね…うたプリ…エグい…そういうところ…好きです…。
「あなたがいなくなれば、僕は自由の身だ……。
そして誰も僕のことを知らない世界へ行くんだ……。
ランドルフと約束したからね」p.96
これも本心です。
ブラッドとしては、どちらでもよかったのだと思います。
・ヴィクターを殺して自分のことを誰も知らないところへ逃げる
・ヴィクターに殺してもらい、天国へいく
そのどちらでもよかった。
ヴィクターの叫び声が森にこだますると同時に、
銃声が鳴り響きました。
「そう……これで……いいんだ……」
かすれる声でブラッドは、そう呟きました。p.97
銃弾とナイフのリーチを考えれば、
ブラッドのナイフが届く前に銃弾が彼を射抜きました。
ここで質問がありました。
「銃弾の音が2回?聞こえるのですが2発連発したのでしょうか?」
答えはNOです。
ヴィクターが持っているのはマスケット銃。
フリントがこすれ火花が起こる音のあと、銃弾は発射されるため、二度破裂音が聞こえた、のが正解です。
一瞬の過ちは、永遠の後悔を生む。
心に決して消えることのない爪痕を残して……。p.97
ヴィクターの後悔です。
ブラッドを殺してしまったことを永遠に後悔し、
冒頭のリコリスの花畑に佇むシーンに繋がります。
風に乗って、リコリスの微笑みが聞こえた。p.97
も、森が喜んでいる……お、おそろしい…。森怖い…。
いや、一番怖いのは人ですね…。そういうお話です。
【天国】
「天国」とは何か。
最高の、そして最終的な幸福の状態。帰るべき場所。父なる神に近い場所。です。
天国についてもブラッドはまだ最高の幸福状態にはなれていませんでした。なぜならランドルフがいないから。
ブラッドの駆け寄る足音が聞こえます
「探したよ。ここにいたんだね」p.99
ここで改めて<煉獄とは>
聖人で無い限り、普通の人は生きている限り何かしら罪を犯してしまうものです。天国へ直行はできません。しかしそれで地獄行きは無理難題です。
そこで「煉獄」という制度があります。
罪と比例した期間、火あぶりにされ清められます。
ブラッドもランドルフも罪を犯しているので煉獄で火あぶりにされていたことでしょう。そしてランドルフはたくさんの人を傷つけ、たくさんの命を奪ってきました。対してブラッドが殺したのはアルヴィン(不本意)とランドルフ(意図的)。
火あぶりにされる時間はランドルフの方が圧倒的に長かったかと。
2人が死んだのはほぼ同時期だったのにも関わらず、
天国で再会したときブラッドが「探したよ」と言ったのは、そういうことだと考えられます。
ランドルフはなかなか煉獄から出られず、その間ブラッドは天国でずっと彼を今か今かと探して待っていた。
ランドルフの場合、やっていることだけ見れば地獄行きでもおかしくないのですが父なる神は慈悲深く、ランドルフ本人の人間性や想いも理解してくださいます。
そして彼をどうか天国へと願ってくれる人間が周囲に居たのならその祈りは必ず届きます。
ちなみに初聴の際、天国のシーンが最後出てきたとき、クリスチャンの私は嬉しすぎてボロ泣きしてしまいました…。 ブラッドやランドルフが幸せになれるように、想いを込めて演じています。私たちにはそれしかできませんから。 最初にした約束、果たせてるかな? その答えは、今ここで出さなくてもいいと思いますよ。 でも1つだけ確かなことは、ブラッドがあなたで良かったです、音也。 俺もだよ、トキヤ。
もしかしたらふたりとも地獄行きかもしれない…と震えていたので、
天国で、しかも再会までできていて・・・。
天国の定義は「最高の、そして最終的な幸福の状態」です。
「僕の幸せは、あなたなしじゃ考えらえない」
ブラッドにとっての幸福はランドルフなしじゃ叶えられない。
ブラッドの祈りは、間違いなく届いたんだなあと。
【おわり】
二周年という節目に合わせ、自分の考えをまとめました。
他にも「ここを解説してほしい」などありましたらわたしなりの個人的な解釈となりますが、それでもよろしければぜひ。
リコリスの森を愛している、が示せていればいいな、と願っております。
読んだよ~という報告やご感想もお待ちしております。
糧になります。
ご感想はTwitterの@tosにてお返事。
ご質問をいただきましたら、回答は下記ページに掲載します(随時追加)
研究のために赤ずきんの関連書籍を読み漁っていましたら、いつの間にか二年経っていました。いつか赤ずきんの研究まとめもできたらいいな。リコリスの森の輪郭がよりはっきりとして大変面白かったです。その時はおすすめの本なども掲載しますね。
一応絵描きなので二周年に合わせて何かきちんと描ければよかったのですが、プリライ7thのフラスタ作業で手が回らず…。「リコリスの森フラスタ」も制作してますのでご興味がある方は覗いてみてくださいませ。 【拡散OK】#W1フラスタ
プリライ7thにてW1(音也&トキヤ)宛フラスタを贈ります
【本日12/1(日)から参加者募集開始!】
はじめての方もリピーターの方も大歓迎✨
たくさんのご参加お待ちしてます🙇♂️!
詳細はこちら→https://t.co/FC6LPQ8nfb pic.twitter.com/FXXtp1yZS6
最後まで目を通してくださってありがとうございます。
これからもリコリスの森と共に。
リコリスの森で、ずっと待ってる。
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!