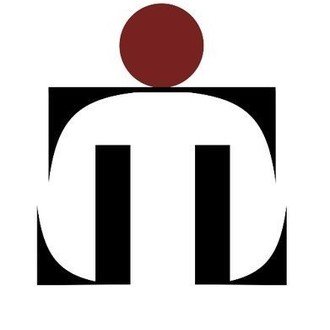作業所はあるのになぜ思考所はないのか・前編
素朴な疑問として、作業所はたくさんあるのに、どうして思考所はないのだろうか。
おそらく、ここにはいろんな問題が凝縮されている。
「作業によって、社会と関わる。」
うん。
まあ、それはそれで良いんじゃないでしょうか。
ただ、筆者にとっては、思考所がないというのはどうも窮屈な感じがする。
「思考によって、社会と関わる。」
これがあまり推奨されないように見えるのは、なぜなのだろうか。
作業所はあるのに、思考所はつくらなくていいのだろうか。
もしも思考所というものが日本にまだないならば、自分でつくってしまうことはできるだろうか。
思考所をつくるとしたら、どのようなものが適切なのだろうか。
筆者がなぜ思考所があったほうがいいと思ったのかというと、それはまあ当然ながらというか何というか、作業や管理を苦手としている筆者のような人間は思考や分析によって社会と関わっていくしかないだろう、というのがまず前提としてある。
もっとも、そもそも筆者はあまり積極的には社会と関わりたいと思っていないので、こういった言い回しも、強いて言うならば、ということにはなるわけだけれども。
思考や分析によって社会と関わるのは可能ではあるのかもしれないが、思考や分析そのものはお金にならない。
だから、思考や分析を続けるためには、作業や管理によって生活費を獲得する必要があるのかもしれないと思って、実際にそのようにしてみたこともある。
でもこれが実に難しい。
単に苦手というだけではないのだ。作業や管理というものは、思考や分析を阻害するのである。
作業をする必要がなければ、もっともっと思考の時間がとれるのに。
もちろん、世の中から作業が完全になくなる日はないだろう、という思いもある。
この記事(いまあなたが読んでいるこの「作業所はあるのになぜ思考所はないのか」)を書くにあたっても、膨大な「作業」があるのは確かだ。
単純に自分の文章を書くという作業や引用箇所の写経、画像の用意などはもちろんのこと、様々な確認作業がある。紹介する本が実際に出版された年がいつなのかの確認。引用が正確なのかの確認。引用箇所が何ページ目かの確認。
確認作業で手間取るのが、「ない」ということの確認だ。ある作品にある記述が「ある」ということを示すのは場所さえ分かれば簡単だが、「ない」と宣言する際には、本当にそう宣言してしまっていいのかどうかを確認するのはそれなりに骨が折れる作業である。
手伝ってくれる人がいないため、何もかも一人だ。
こういった、文章を書くことに付随した作業というのが実にいろいろとあるわけだが、単に作業を積み重ねていくというだけでは当然このような記事にはならない。
やはり、何らかの思考があるのだ。
自分で文章を書いている人なら一読して分かると思うが、構想を練り始めるまでにまず膨大な思考が存在していなければならないし、構想を練り始めてからも当然構想を練るという思考があるわけだ。そして実際に書き始めてからの思考も、ある程度内容に盛り込んでいくわけだ。
そして構想を練り始めるまでの思考、構想を練るという思考、実際に書き始めてからの思考、これら3種類の思考は、少なくとも筆者にとっては質的にかなり異なっているものだ。
今回の場合は、構想を練り始めるまでというのはつまり「思考所」という言葉を思いついたタイミングだ。
漢字でたった3文字だが、この「思考所」にたどりつくまでに、膨大な思考がまず存在していたわけだ。
こういう思考は極めて重要であるはずだが、どんな思考なのかということを他人に説明するのはほとんど不可能に近いようにみえる。
一方で、書き始めてからの思考というのは、どういう思考なのか比較的他人に説明しやすい。ある意味では、この書き始めてからの思考というのは、より「作業」に近いものだからだ、といえるかもしれない。問題解決型の思考といってもいいかもしれない。
でも書き始めてからの思考が何もかもすべて問題解決型の思考なのかというと、やはりそれは違う。根幹に関わるアイディアが、書き始めてから浮かぶこともあるからだ。
そういえば日本語の「作業」という言葉はなかなかに不思議な言葉であると思う。
例えば、電話をかけて、つながった直後に相手が「ちょっといま、作業中なんで」と言ったとする。
この場合、必ずしも賃金をもらう労働の最中とは限らない。
相手は、自分の部屋で誰に頼まれたわけでもない自分のためだけの本棚を作製している可能性もある。
かけた相手が勤務時間内であるということがお互いに分かっている場合、「勤務時間内であっても、作業中でなければ電話に出られる場合もあるよ」という含意がある可能性もありそうだ。
英語の「work」の場合はいろんな文脈で使える。
文脈がよく分からない中で「This work is...」で始まる文章は、たいていはまず「この作品は」といったニュアンスを連想することになるのではないかと思う。
しかしながら、例えばコンピュータのプログラミングにおいて、ちょっとした検証のためのソースコードの冒頭に「This work is...」とあった場合に、それを日本語で「この作品は」というのはおかしい気もする。
アート的要素の薄いソフトウェアは、日本語であまり「作品」とは言わないし、何より「ちょっとした」「検証のため」なのだから、「作品」はおかしい気がする。
「このコードは」とか「今回の検証では」とかで始めたほうが日本語として自然な場合もあるかもしれない。
英語では使い勝手の良い「work」に該当する日本語も、やはり存在しないのだと考えたほうがいいだろう。
少なくとも2021年現在の日本語では、「作業」に「所」という一文字が加って三文字だけの「作業所」だと、とたんに「介護」や「福祉」というニュアンスが加わる。
何らかの困難を抱えた人が、作業をすることによる何らかの効能というものを期待している施設。
英語で単に「workshop」というと、この単語一つだけでは「介護」や「福祉」というニュアンスがあるとは限らず、純粋に工作などをするためのスペースを指したり、「セミナー」や「研修会」や「研究会」を指すこともある。
筆者の場合は、この記事のような長文を完成させるまでの様々な作業は、ある程度は自己治療という側面がありそうではある。
他人に要請されてやる作業とはまったく違う、誰とも何の約束もない作業。
作業に伴う効能は、確かに存在している。
だが、筆者が逮捕や措置入院といったものを一度も経験していないのは、やはり作業による効能ではなく、思考による自己治療がうまくいっているからなのではないかという気がするのである。
思考こそが、自分を救ってきたという確信があるのである。
ところでシンクタンク(think tank)という言葉は、日本でも外来語として定着している。
でも、ここで考えている「思考所」は、シンクタンクとはかなり違う。
シンクタンクには、以下のようなイメージがつきまとっているように思う。
大学を卒業している人で、かつ健常者だけが所属
すぐに意味が分かるものしか提示できない
「えらい人」が全体の方針を決めていて、それに沿う思考や分析しかできない
まあ、これは先入観による部分も大きいかもしれない。
シンクタンクとは違い、ここで想定している思考や分析というのは、「えらい人」が頭を抱えるようなものであるか、もしくは「意味が分からない」「何の価値があるか分からない」と感じるようなものこそ価値があるものなのだ、といえるかもしれない。
ただし「意味が分からない」というのも、それはあくまで提示した直後の話であって、時間が経つとまた違うように見える場合もあるだろう。
今回のこの「作業所はたくさんあるのに、どうして思考所はないのだろうか」という疑問についても、2021年時点の日本の「えらい人」の心にはたいして響かないかもしれないけれど、2030年ごろや2040年ごろには今とはまったく違うように見えるようになっているはずだ、という期待もこめて書いているわけだ。
ちなみに今回の記事は筆者がnote(Webサービスとしてのnote)に書く初めての記事だが、2016年ごろからずっと、noteに何か書こうかなあと思ってはいた。
そうこうするうちに2017年にALISが登場して、こっちのほうが面白そうかなと思ってALISに先に書いてみた。
ALISに書いた「ずっと変わらないでいてほしい」(2018年10月公開)と「70%パラドックス」(2020年2月公開)の2つの記事は、いろんな意味で「自分が読みたかったもの」が詰まっている。
ALISの登場を知って、「きっとこんな記事が誕生するはず」「あんな記事が誕生するはず」と、いろんな想像をふくらませていた時期が、わたくしにもあったのです。
実際には、あらゆる観点から見て真逆の方向に行ってしまったようにも思える。
もし今後、ALISが何らかの刷新を経たりするのだとしたら、そのあとにどうなるのかについては分からない。
ちなみに去年(2020年)にALISで途中まで書いた「INxxのための自己啓発」のシリーズについては、構想段階においてはこれはもっと自己啓発のパロディ的なものというか、自己啓発そのものに対する嘲笑的なニュアンスが強いものだった。
なお、筆者はWebサービスが学校の代わりのものとして機能すべきだ、とは思わない。
ただ、現状の公教育は思考や分析を阻害する要素が大きすぎるのではないか、という気はしている。
公教育そのものの有害性について印象深いのが、アインシュタインが言ったとされる 私の学習を妨げる唯一のものは、私が受けた教育である
という言葉。 The only thing that interferes with my learning is my education
かなり鮮烈な印象を受ける発言だが、本当に自信を持ってアインシュタインが言った言葉だと紹介していいのか、筆者には分からない。
英語バージョンは
のようである。
比較的古いものとしては、Lee Silberの『Career Management for the Creative Person』(1999年刊行)でこの発言について記載があるようだが、この本については筆者は未見である。
まあでも、アインシュタインなら本当にそう言うかもしれないな、と思える様々なエピソードがあるのは確かだ。
そういうエピソードが紹介されているのが、1994年に日本語訳が出たトマス・G・ウェストの『天才たちは学校がきらいだった』という本だ。
この本は原題が『In the Mind's Eye』で、第1版は1991年。2021年12月時点における最新版は2020年刊行の第3版になっており今でも売れ続けているロングセラーなのだが、邦訳は1994年に出たものだけのようだ。
ぜひともこの新しいバージョンの邦訳を出してほしいと思う。
個人的にはこの挑発的な日本語版タイトルも気に入っている。
ちなみに原著については、1991年の初版と1997年の第2版がそれぞれInternet Archiveの電子図書館で読める。
この本では、ディスレクシア(読字障害)を中心として、学習障害を持つ著名人、あるいは明確に学習障害があったかは不明だが何らかの困難を抱えていた可能性がある著名人が多数とりあげられている。
学習障害を持つ人は「欠点を努力によって克服した」というように紹介されることがあるが、この本はそういう本ではない。 この本で言いたかったことは、こうした人たちが成功したり、偉大になれたのは、障害があったにもかかわらず、ではなく、その障害ゆえだったかもしれないということだ。
P.15には以下のようにある。
また、P.17では この病気の欠点は、利点と根本的につながっているらしいのだ
という言い方もしている。
これは、カメラのレンズにおける、超望遠レンズと超広角レンズの特性の違いをイメージすれば分かりやすい。
超望遠レンズは遠くのものを見ることができる。ただし近くのものは見えないし、画角(視野角)は極端に狭い。
一方で、超広角レンズは画角(視野角)は極端に広く、対象に接近できるが、遠くのものはよく見えない。
ディスレクシアそのものについては、2008年10月12日放送のTV番組「NHKスペシャル 病の起源 第4集 読字障害~文字が生んだ病~」がかなり分かりやすい。興味深い研究もいろいろと紹介されている。
映像でないと伝わらない部分もあり、2021年の日本においてディスレクシアの入門的コンテンツとして誰にでもオススメできるものとして、これを超えるものはまだ登場していないように思える。
(URL: https://www.nhk.or.jp/special/detail/20081012.html )
トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』において興味深いのは、AI(人工知能)がもたらすインパクトとディスレクシアを結びつけて論じている点だ。
例えば第3章「人間能力の不思議」の後半では、AIが知的労働を置き換えることについて述べられている。以下はP.67より。 もしこうしたことすべてが現実になるのならば、よりはっきりと「人間的」な技能や特性が大きな価値を持つことになるだろう。まさにこうした領域に対して、創造的な視覚思考型の失読症や他の学習障害を持つ人々がしばしば(常にではないが)特別な才能や能力を持っているように思われる。
この本(の第1版)におけるAIについての記述は、30年前のものとしてはかなり鋭く現在の状況を言い当てている。
単に体を使う仕事が置き換えられるのではなく、知的な仕事が置き換えられることのインパクトの大きさを強調している。
2021年現在、法律に関する文書作成など、以前なら高度に知的な業務とされていたものがAIによって置き換えられはじめており、これは近未来の話ではなくすでに「近過去」である。
読み書きを教育のコアにすえる発想を放棄し、思考とイマジネーションをコアにすえる時期が来ているわけだ。
時期が来ているというか、本来なら30年前からそういう方向に少しずつシフトしていく必要があったはずなのだが、日本ではそのようになっていないように見える。
数学者の岡潔によるエッセイ集『春宵十話』には「三河島惨事と教育」というエッセイが収録されている。「三河島事故」として有名な1962年の東京での大規模な列車事故発生を受けて書かれたと思われるものだが、この中に いま大学に入っている男性は機械文明にばかり興味を持ち、真善美は教えにくい。頭の働きも機械的になっている。むしろこれからの傾向としては機械的なことは機械に任せ、そうでないのを教えるべきだと思うのだが、ともかく、進駐軍時代にまいた種子がいま育っているので困っている。
とある(2014年刊行の角川ソフィア文庫の改版のものでP.98)。
1962年といえば、1964年の東京オリンピックの2年前だ。
「三河島惨事と教育」は以下のように締めくくられている。 実をいうと、どうも大変なときにオリンピックを持って来たものだと内心思っているのである。
トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』は読み書きを中心にした教育では才能を持った人が振り落とされやすいということが中心的なテーマとなっているが、IQテストなども要注意である。
IQテストによって、学校の試験では良い点がとれないが特別な才能を持っているような人をうまく抽出できる場合はあるものの、逆に埋もれさせてしまう可能性もある。
幅広い領域に影響を与え、成熟した知性という印象を持つ人が多いであろうフランスの数学者アンリ・ポアンカレが、ビネー・シモン式知能テストでは「不名誉な成績」(disgraceful showing)だったというのはかなり衝撃的だ。
このポアンカレのエピソードについては、若かりしころのジョン・ナッシュも読んだというE・T・ベルの『数学をつくった人びと』(原著は1937年発表)でも紹介されている。
トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』では、このエピソードに触れたのち、P.127に以下のような記述がある。 才能ある失読症や学習障害の子供は、ビネー・シモン式知能テストを改良した標準「IQ」テストで異常にばらついた点数をとることがある。彼らは、テストのある部分ではきわめてできが悪いが、他の部分では稀にみる高得点が整然と並ぶ。こうした場合には、テストのジャンルごとの高得点と低得点の異常な違いこそが重要なのである。
ところで『天才たちは学校がきらいだった』日本語版(1994年刊)には少なくとも一箇所、誤植(誤記)がある。
「名状しがたい自信」にしたかったであろう箇所が「名状したがい自信」になっている(1994年4月25日第1刷発行のものでP.162)。
他人が書いたものであれば筆者にはこういった誤字脱字の類いのものは自動的に浮き上がって見えることがある。それでも、自分で書いた文章の場合は内容をあらかじめ知ったうえで読み返すためか見逃してしまうことがある。
また、「名状」などはつい「めいふく」と読んでしまうなど漢字の正しい読みが覚えられないことがあり、また21世紀に入ってからは、パソコンでないと漢字を含む文章がまったく書けないことがある。
『天才たちは学校がきらいだった』では、P.113においてアインシュタインが 「知りません。百科事典で簡単に見つかることで頭を一杯にしたくはありません」
と言ったことが紹介されている。ここは原著P.124では "I don't know. I don't crowd my memory with facts that I can easily find in an encyclopedia."
となっており、Antonina Vallentinの『The Drama of Albert Einstein』からの引用のようである。
現代においては、「検索すれば簡単に分かることで頭を一杯にしたくはありません」と考える人は多いかもしれない。
筆者は実際に文書校正ツールなどを試してみたことはないが、「名状したがい自信」なども、今となってはAIがすぐさま指摘してくれるのだろう。
なお、P.223にはアインシュタインが幾何学の本を読んだ時のことについて「名状しがたい印象」と、正しい表記の箇所がある。この本はつづりの間違いについての話題が頻繁に出てくるため、「名状したがい自信」という書き方が、P.174にあるようなイェイツの手紙の「文体」を真似た文章の例のように意図的なものだったりするのかどうかについてはよく分からない。
Internet Archiveの電子図書館で読めるもので確認する限り、「名状したがい自信」の箇所は原著のP.162の「confidence quite indescribable」で、ここはウィンストン・チャーチルの『Thoughts And Adventures』からの引用のようだ。
ちなみに「名状したがい自信」は誤字脱字の類いのものの中では人間が確認しようとすると比較的見つけにくい部類のもので、これはタイポグリセミア現象といわれるものが作用するからである。
ところで先ほど、ある作品にある記述が「ない」ことを確認するのはそれなりに骨が折れると書いたが、これからはこういったものもAIなら簡単にできるようになる。
いわゆる曖昧検索だけでなく、
「このAという本の中に、Bという作家の文体をパロディにした箇所があったはずだから探してほしい」
とか、
「このCという本の全20章の中で、章の前半と後半で論調や記述スタイルが異なっている章をすべて抽出してほしい」
とか、
「このDという本の中から、『xはyであるという一般論があるけれども実はxはzなのだという見方もできる』というような構造を持った議論をすべて抽出してほしい」
といったような、2021年現在であれば実際に人間がじっくり読み込んでいく必要があるような確認作業が、もうすぐAIで一瞬で出来るようになる。
重要なのは思考とイマジネーションであり、2021年時点における「仕事ができる」「仕事ができない」といった基準はこれから完全に解体されていくことになる。
また、思考の跳躍性と実務能力の高さはおおむね反比例していると考えていいように思える。
トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』では主として読むことに困難を抱えるディスレクシア(読字障害)にフォーカスしているが、筆者の場合、文字を読むこと自体には何の問題もなかった。
幼稚園や小学校低学年あたりではむしろ耳からの情報を少し苦手としていた。
呼ばれても気づかないことがあったり、聞き間違いが多かったり、何度も何度も聞き返す、といったことがあった。
何度か「耳の検査」に連れて行かれたが、聴覚に異常があるわけではない。
小学2年生あたりではだいぶマシになっていたが、呼びかけられても気づかないというのは今でもかすかに残っている。
ハイパーレクシアといえるほど極端な早熟というわけではなかったが、小学校に入る前から、文字から得られる情報というのは筆者にとって重要なものだった。
文字から得られる情報というより、読むことにともなう五感全体で感じる体験が重要だったというべきかもしれない。
子供のころは、それなりに本の多い環境だったと思う。
本というのは目を一回つぶってもう一度目を開ければ、目の前にあるものだった。
「手に入れる」というものですらない。
ただし、少し年を重ねてくると、興味の範囲が広くなって、まばたきをすることによっては読むことができないものが出てくる。
その場合は、ほんの少し体を傾けて、手を伸ばしてみると、その手の中に自動的にもたらされる。
多少のタイムラグがあったとしても、本というのは基本的には自動的にもたらされるものであった。
でもさらに年を重ねると、興味の範囲がさらに広がってくる。
徐々に、親に見られたくないものというのが増えてくる。
自分の持ち金と相談しながら、一人でこっそり本屋に行って購入する機会が増える。
性的な内容を含むもの、陰謀論やオカルト関連の本。
また、犯罪を美化したものや美化していると誤解されかねないような内容のものも増えてくる。
『図解 都市破壊型兵器マニュアル』(1995年刊)なんかも持っていた。
ちなみに1990年代におけるマニュアルもののパロディ的要素を含むものとしては1993年の『完全自殺マニュアル』の空前のヒットの影響が大きい。
当時の若者を論じるものとして、あるいは日本人による日本批判として、マニュアルをどう考えるかというのは定番のネタであり、それをパロディ化したいという欲求も1980年代からずっと存在していたようだ。
浅羽通明の『ニセ学生マニュアル』が徳間書店から出たのは、1988年だ。
2021年の今からみれば『完全自殺マニュアル』が始まりであるかのようにも見えるけど、当時は「これはマニュアルもののパロディとしてはやりすぎであり、許されない」というようなニュアンスでの批判もあったように記憶している。
筆者は『完全自殺マニュアル』については立ち読みはしたけど買わなかった記憶がある。
ちなみに今年(2021年)、東京オリンピックに関連して「いじめ自慢」であるとして蒸し返された『クイック・ジャパン』の3号(1995年刊)のとあるインタビュー記事が話題になったが、『クイック・ジャパン』と『完全自殺マニュアル』は同じ太田出版である。
ところで、思考というものを考えるうえで、大学という存在をどうとらえるのかという問題は避けて通れないだろう。
大学に入学するまでの教育はともかく、研究機関としての大学は、思考をする場所としてうまく機能し続けているということになっているように思える。
だが、その認識は本当に正しいのだろうか。
石黒武彦『科学の社会化シンドローム』(2007年刊)のP.101には、以下のようにある。 これまでも、同じ大学内で、工学と理学が互いの価値観の違いによって対立することがあった。工学部系の方が、研究資金などを得る腕力の上でまさっていた。とはいえこういうことがあっても、理学部系が存続の危機に瀕することはなかった。しかし、市場原理のもとで競い合う状況下ではどうなるか。理学部系の将来への見通しは明るいとはいえない雲行きだ。大規模な大学の理学部系は何とか生き延びるかもしれないが、そうでないところの理学部系は苦境に立たされつつある。これと連動するかのごとく、大学に期待されていた批判精神は、余裕がなくなるにつれて、宿りにくい時代に差しかかっている。
また、トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』P.212では、「ある古参のガン研究者」の考えとして、研究活動の自己再生産的な性質が述べられている。 しかし彼は、実はもうこれ以上の研究はいらない、少なくとも当座はいらないのではないか、と疑っている。図書館に座って考える時間さえあれば、パズルのピースをうまくはめこめるだけの情報は、すでに集まっているのではないか、と彼は疑っている。でも、図書館に座って考えているだけでは金が出ない。だから補助金申請が出されて、同僚が復習するためのものがどんどん生み出される。これがさらなる研究と数字につながるのだ。マシンは、新たな数字をどんどん生み出すが、新たな理解にはちっともつながらない。
Internet Archiveの電子図書館で読めるもので確認する限り、「同僚が復習」という箇所は原著のP.203の「review by peers」であり、要するにピアレビュー(査読)のことのようだ。
いかに予算がとれる研究をするかという競争、そして研究が研究を生み出すという自己再生産的なシステム。
研究活動全体が「作業」の集合体と化してしまい、「思考」が脇に追いやられてしまっている、という可能性もありそうである。
ちなみに筆者自身は、中高一貫の学校に行ったにもかかわらず、高校を中退して大学には行かなかった。
そんな10代のころの筆者の大学観に強い影響を与えた、非常に思い出深い本がある。
それが浅羽通明による『大学で何を学ぶか』(1996年4月刊)である。
この本はなぜか何度も紛失し、古本で何度も書い直した。
写真に写っている文庫版のほうは最近買い直した古本である。どうせまた紛失しているだろうとよく確認せずに購入したのだが、文庫版を購入した直後にハードカバー版のほうが見つかった。
でもハードカバー版のほうも古本で、筆者が当時読んだものと物理的には同一の本ではない。
なお、初めてこの本を読んだ時には、筆者はもう高校を中退していた。
だからこの本を読んで学校をやめたわけではないということは強調しておきたい。
また、この本を手にとった時点では同じ著者による『ニセ学生マニュアル』の存在を知らなかったと記憶している。
高校を一年生の秋に中退する直前には、小林よしのり『ゴーマニズム宣言』をよく読んでいた記憶があり、そこで浅羽通明の存在自体は知っていた。当時浅羽通明に注目していた若い人は、高確率で『ゴーマニズム宣言』を読んでいた人でもあったのではないだろうか。
ところで『大学で何を学ぶか』の幻冬舎文庫版(1999年4月刊)のほうの解説で、高島俊男が「ぶったまげた」と書いている。
高島俊男は今年(2021年)4月に亡くなった人で、研究者としては『水滸伝』の研究で有名で、1995年から「週刊文春」で10年以上「お言葉ですが…」というエッセイを連載していた。
高島俊男は「十代のすえから六十ちかくまで、四十年ちかく大学にいた」というが、そういう風に大学を見たことがなかったので「ぶったまげた」のだそうだ。
『大学で何を学ぶか』が出た1996年というのは、まだインターネットがパソコン通信の延長線上のようなものというとらえ方の時代ではあるし、「大学に行かなかった人=たたき上げ」という図式がやや単純化されすぎたものであるようにみえるけれど、日本社会論としてこの本は今でも色褪せていないので、「そういう風」というのが一体どういう風なのかはぜひ読んでみてほしい。
『大学で何を学ぶか』というこの本のタイトルだけをみると「ぶったまげ」るような内容が書いてあるようにはとても思えないが、これはあえて地味なタイトルにしているわけだ。
ちなみにこの記事を書いている2021年12月現在、OB・OGが100万人を超えるという日本最大のマンモス校である日大(日本大学)の話題が連日報道されている。この日大の理事長として13年間にわたってトップに君臨していた田中英壽(田中英寿)が脱税容疑で逮捕されたからだ。
この本の中では、日大への言及があるのはP.99とP.119(幻冬舎文庫版ではP.90とP.107)の2箇所である。
それはともかく、この本の中から重要な論点を2つ抽出しておくと、「大学=世間」論と、「大学=お伊勢参り」論だ。
「大学=世間」論については、『大学で何を学ぶか』P.115(幻冬舎文庫版P.104)以下のようにある。 しかし、やはり民間企業は東大生を欲しがる。それは、彼ら個人の能力以上に、彼らの背後につながる人脈、東大OBという「世間」が欲しいのである。
当然ながら、この「世間」には、高級官僚のほとんどと多くの政治家が属している。
幻冬舎文庫版では「高級官僚」の部分は「キャリア官僚」に変更されている。
ここについては、最近だとジェンダーの観点から興味を持つ人もいるかもしれない。
この本では、企業が女性の東大卒を採用「しない」理由として、男性のほうが結婚退職などでの離職率が低く、離職さえしなければその「新入社員」の大学での同期が十数年後に官庁において重要な権限を持つ立場になるであろうという期待があることが挙げられているのである。
この本が出てから25年経った2021年現在の日本においても、そういう傾向があるのかどうかというのは気になるところだ。
「大学=お伊勢参り」論については、江戸時代のお伊勢参りが通過儀礼として機能しており、関西地方ではお伊勢参りをすませると「一人前のおとな」として認められるような村落が多かったことから、現代の日本における大学と江戸時代におけるお伊勢参りが類似しているという議論だ。
日本の大学における学問の形骸化と、当時のお伊勢参りにおける宗教の形骸化には驚くべき共通点がある。
当時のお伊勢参りでは、伊勢神宮における参詣そのものはあくまでもオマケにすぎず、伊勢神宮周辺が「総合文化レジャーランド」のようになっており、さらに遠方からの参詣者は京都や大阪を見物するというのもセットになっていた。
これだけなら「大学=お伊勢参り」論は、うん、まあ、たしかにそういう側面もあるかもね、というくらいに思う人も多いだろうが、筆者はP.191(幻冬舎文庫版P.170)の以下の指摘にかなり「ぶったまげた」。 伊勢詣でから帰ったひとは、後進の参考のため、道中日記を清書したという。これなど、まるで実習科目に課されたレポート、さらには卒論か企業へ出す志望書を思わせるではないか。
遅くとも1970年あたりから50年以上にわたって現在でもこういう傾向があるといえるため、「大学=お伊勢参り」論は日本の近現代史における一つのテーゼとなる可能性もありそうだ。
形骸化したお伊勢参りの存在により、江戸時代においては、熊野が「ガチ勢」の吸引力を持っていたとみなすこともできるかもしれない。
とすると、当時のお伊勢参りには対比しうる存在として熊野があったのに、現代の日本の大学にはそういった対比しうる存在がないのだ、と考えることもできそうだ。
ところで、浅羽通明『大学で何を学ぶか』P.246(幻冬舎文庫版P.218)では物理学の法則を「カタいもの」としてとらえすぎているように見える人もいるかもしれない。
2021年現在、多くの先進国においてニュートンはマックスウェルよりも圧倒的な知名度を誇るが、アイザック・アシモフが(おそらくは『Understanding Physics』第2巻のなかで)、ニュートン力学は近似にすぎないことやマックスウェルの理論が「相対論と量子論によって導入されたあらゆる変化の中を生き延びた」というとらえ方をしていることについて、『天才たちは学校がきらいだった』P.26に紹介されている。
物理学の法則もやはり「暫定的な仮説」なのであり、場合によっては純粋数学における理論もそのようにみなされることがある。
そういうわけで、これもあくまでも「暫定的な仮説」としてとらえてほしいのだが、大学の形骸化に限らず、あらゆるものの形骸化について考えるうえで、人間の性格という問題は避けて通れないように思えるのである。
つまり、形骸化を促進してしまいやすい人と、形骸化を阻止することに貢献することになりやすい人と、明らかに性格の違いがあるような気がするのである。
『大学で何を学ぶか』P.93(幻冬舎文庫版P.85)では、車体メーカーに就職した時期があるという塚崎幹夫について、以下のように書かれている。 しかし、技術畑や法・経・商学部系ならいざ知らず、仏文学専攻で大学院では超難解で知られる批評家ポール・ヴァレリー研究にうちこんでいた氏の「学歴」は、べつに対仏取引があるわけでもない地方企業に、どう評価されたのだろうか?
この疑問をぶつけてみると、塚崎氏は、
「現場たたき上げの職人さんや営業さんばかりでは、どうしても社の視野が狭くなってしまうんだ。本ばかり読んでいた僕だけど、事業や取引の拡張とか人事厚生の改善とかにあたっては、長期的視野からの複眼的判断が自在にできたんだ」
と、こともなげに語ってくれた。
昭和二十年代、京大卒のエリートに対する世間の評価は今日とは比較にならない。また塚崎氏の、もとより優秀な頭脳と篤実な人柄もむろん考慮する必要があろう。だが「たたき上げにはない大卒の視野の広さ」なるものは、たしかにあるらしいのだ。
「複眼的判断」の箇所は、幻冬舎文庫版では「多角的な判断」になっている。
また、『大学で何を学ぶか』P.94(幻冬舎文庫版P.86)では、『危ない大学・消える大学』に掲載されていたという不動産業界での例として 物件を売る見込み顧客リストを与えられると、高卒はそのまま突撃してゆくが、大卒はリストをよく検討して地域ボスと知り合うなど効率よい方法を考えようとする
というものが紹介されている。
ネットユーザーを中心に盛り上がりをみせる性格分類のMBTIあるいはMBTIに「似て非なるもの」について詳しい人なら、こういったエピソードに、S型とN型の対比を連想するのではないだろうか。
そう、ここで語られている行動特性の違いあるいは視点の違いというのは、これはまさに、S型とN型の違いなのだ。
ただし、「地域ボスと知り合う」というのをあらかじめ定石として認識していた場合はまた違ってくるかもしれない。
他人が提示した具体的な問題に、あらかじめ整備された定石をうまく活用して解決するのは、S型は得意だ。
通常、S型とN型の対比においては、N型のほうが広い視野を持ち、またN型は一見すると無関係なところから関連性やパターンを見い出すのが得意、といわれる。
ちなみに筆者は、性格というのはそう簡単に変わるものではないと考えている。
塚崎幹夫も本によって視野が広がったというよりは、もともとあった視野の広さに応えてくれるものが本だったのだ、と考えたほうが良いような気もするのである。
でも、N型のほうが大学に進学しやすいなんてことがあるのだろうか。
受験がテクニックに堕したといわれて久しいが、そうなるとS型のほうが有利になりそうではある。
ここでいう「テクニック」とは、まさに「定石」を「他人が提示した具体的な問題」に適用することである。
実際、以前は日本の大学に通う学生たちはN型の比率が高かったものの、徐々にS型の比率が高くなってきているのではないか、と筆者は考えている。これももちろん暫定的な仮説にすぎない。
N型にとっての大学の「効能」というものを考えてみると、大学に「行く」こと、あるいは「行った」ことによって、もともとN型だった人がN型らしくいられるような何かがもたらされるのではないか、と考えてみることもできそうである。
筆者は2002年秋から2003年夏にかけて、まんが喫茶(個室型インターネットカフェ)で9ヶ月くらいアルバイトをしていたことがある。この時のアルバイトはなかなかに印象的だった。
この時、アルバイトスタッフのうちおそらく7割か8割くらいの人が高卒で、筆者のような中卒(高校中退)も大学に進学したことがある人も少数派だったと記憶している。
アルバイトなので、高卒だがいわゆる「たたき上げ」とは違う。
そして、筆者はオープニングスタッフの一員だったこと、筆者のいた店舗だけ企業グループ内での位置づけが曖昧で治外法権のようになっていたこと、個室型インターネットカフェという業態そのものが黎明期だったこと、などの要因が重なって、自分たちで運営方法を模索することができるという幸運にみまわれた。
いろんな意味で、権威が存在しなかった空間だったともいえる。そして、先輩・後輩という感覚や年上・年下という感覚が希薄だった。
筆者は元プログラマーだったためパソコンに関することについては頼られる面もあったものの、頻繁に遅刻をしていた上に「お店をまわしていく」ということについての実務能力が低かったため、全体としては権威になりようがなかった。
この頃に他のアルバイトスタッフと交わした雑談を思い返してみると、リラックスした雰囲気、的はずれなことを言っても許されるという安心感があれば、大学に行ったかどうかとは関係なく、視野の広さを引き出すことができるといってよさそうなのである。
でもどんなに話をしても、どんなに安心感があっても、視野の広さを引き出すことができない人というのも、確かに存在はしている。
ただし、会話だけによってその人の内面を「判定」しようとするのは危険で、こっそり壮大なことを考えている可能性だってある。 ある人物の会話障害は、いろいろな形をとることがある。障害が微妙なために、すべてが会話病理学者たち専門家の注意を引くわけではない。しかしながら、会話障害のあるものは、深い心理過程の違いの現れと見ることができる。たとえば、ある種の神経組織はタスクA(つまりすばやく、打てば響く、歯切れのよい会話)にはあまり向いていないが、タスクB(非凡な問題に新奇な解答を見つける)にはまさに理想的な思考様式につながるのだ。
そういう場合、すべての会話は自分が目立たないようにするためだけに行われることになる。
意図的に目立たないようにしているのではなく、軽度の会話障害の可能性だってありうる。
『天才たちは学校がきらいだった』P.189には以下のようにある。
一つの仮定として、こんな風に考えることもできる。
大卒が少数派であるような組織においては、大学に行ったということが、心理的安全性につながっているのだという可能性。
的はずれなことを言っても「大卒の言うことだから、そこに何かあるのだろう」と、ひとまずは思ってもらえるという安心感。
最初から立場が異なっているために、「生意気言ってんじゃない」とか「そういうのは上が考えることであって」とか、そういうことを言われることがないという安心感。
浅羽通明『大学で何を学ぶか』では、大学に行かなかった場合は、いわゆる「職人さん」や「営業畑」のような現場のタテの関係に組み込まれることになりやすい、というのを前提としているのだろう。
ところで『大学で何を学ぶか』の「あとがき」にある 大学へ進学しなかったひとにも聞きたい。大学へ行けばよかったと思うことはあるか?
については、2021年時点での筆者からの回答としては、明確に「行かなくてよかった」ということになる。
「つくづく」をつけてもいい。
上記の引用箇所は、以下のように続く。 大学の勉強は役に立つと思うかetc……。
これはなかなかに難しい質問だ。
そもそも「役に立つ」とは何なのか。
人生を生きるうえで、というのなら、そもそも筆者は「人生」を生きていない、といえる。
生まれてから一度も「生活」というものをしたことがない、と言ったほうがいいかもしれない。
筆者は常に、何らかのプロジェクトの奴隷だった。
これは小学生のころからそうだった。
奴隷とはいっても、他人が設定したプロジェクトというわけではない。プロジェクトはあくまでも、筆者の頭の中に自然発生したものだ。
書きたい小説があったとしても、「小説家」になりたいわけではない。
自分が考える究極の小説を書いたら、もう二度と小説は書かなくてもいい。
プログラミングについても、「プログラマー」として生計をたてたいわけではない。
10代のころはゲームをつくりたかったからプログラミングを勉強しはじめたのだが、そのゲームについてもやはり「ゲームクリエイター」になりたかったわけではない。
だから「役に立つと思うか」という質問には、「質問のあり方自体が、根本的に世界観が違う」と答えるしかないのかもしれない。
ところで筆者はかなり長い間、『大学進学を拒否せよ』というタイトルの本が1960年代か1970年代あたりに出たということが浅羽通明『大学で何を学ぶか』で紹介されていたような気がしていた。
でも今年(2021年)になってあらためてよく確認してみると、『大学で何を学ぶか』の中では、『大学進学を拒否せよ』という本についての記載は存在していないことが分かった。
また、国会図書館のサイトなどで検索しても『大学進学を拒否せよ』という本は見つからない。
筆者が10代のころに小説以外ではじめて「本を書きたい」と思って長期間真剣に構想を練っていたのは、『大学進学を拒否せよ』というタイトルの本だった。
どの本の中で見かけたのか、あるいは夢の中で読んだのか、とにかく誰かの本の中で紹介されていた『大学進学を拒否せよ』というそのタイトルが非常に印象に残っていて、いっそのこと同じタイトルの本を書いてしまおうと思ったわけだ。
結局、この『大学進学を拒否せよ』に限らず、今に至るまで一度も、本一冊分の文章というものを完成まで持ち込めたことはない。
本は完成しなかったけど、思考そのものはずっと重要だった。
筆者にとって、いちおうは進学校だった高校をやめてしまったにもかかわらず、あるいはやめたからこそ、大学というのは筆者の思考における重要なテーマの一つになった。
単に思考のための題材というだけではなく、「世界同時大学解体革命」ともいえるような構想があり、現代版『大学進学を拒否せよ』の出版はその一環であると同時にのろしを上げるような効果を狙っていた。
だから『大学進学を拒否せよ』という本を書くプロジェクトの奴隷だった時期はあるけど、そのプロジェクトはより大きなプロジェクトである「世界同時大学解体革命」のサブプロジェクトにすぎないという側面もあった。
筆者は車の免許を一度もとったことがないのだが、これはある種の意思表示であり、高校の中退や大学進学の拒否にも似た側面はある。
ただし、免許をとらないこととは違って、退学というのは単なる意思表示ではない。
自分自身が革命の起爆剤となるためには自分自身がまず高校中退者である必要があるだろう、という考えがあったのだ。
世界同時大学解体革命における「解体」は組織的な解体だけでなく、物理的に建物を爆破・解体するというデモンストレーションをするような構想もあった。
例えば、世界中のすべての大学の主要な建物を同時に爆破・解体し、それと同時に学長を殺害し、この爆破・解体と学長殺害の様子をインターネットで中継する、というようなものである。
ちなみに爆破・解体は建物を無人状態にするのが大前提だ。
つまり、各大学において死者が一人だけという状況をつくるわけである。
「世界同時大学解体革命」というネーミングはあとづけであり、そもそも建物を解体したりなどまったくしない、もっと微妙で複雑で、人が死んだりということもまったくないようなプランを考えている時期のほうが長かった。
逆に、もっとたくさん人が死ぬようなプランもあり、最も極端なものでは、一度でも大学に入学したことがある人間全員を同時に殺害するにはどうすればいいか、ということを延々と考えていた時期がある。
建物を解体するバージョンにおいては、世界中で同時に爆破・解体することによって宇宙の物理法則に影響を与え、人類が劇的に新しいステージに導かれていくことになるのだ、というようなヴィジョンがあった。
この世界同時大学解体革命においては、実際に任務を遂行する人間を各大学に送り込む必要があったわけだが、そのための最初の一人というのがなかなか見つからないことにはものすごく困った。
この「最初の一人」が見つからないという状況は、筆者がこれ以降あらゆるプロジェクトにおいて遭遇することになるわけだ。
同じ高校の同級生の中では、筆者が高校を中退してからも継続的に連絡をとっていた唯一の友人だった人物が京都大学の工学部に入学したことによって、「おお、京大に一人、送り込むことができた」と喜んだことはあった。
ひょっとすると、世界同時大学解体革命は京大が起点になるのかもしれないな、とも考えた。
ただしその友人も含め、誰にも革命の詳細を話していなかったため、大学について筆者がそのようにとらえていたということはおそらくその友人は知らない。
なお、2001年前後にこの友人は、はてなの創業者である近藤淳也にPerlをレクチャーしていた時期があったらしい。
Perlとは、プログラミング言語の一つである。
なるほど、このはてなという存在も、世界同時大学解体革命において重要な役割を果たすことになるかもしれないな、と思っていた時期もある。
まあ、今だから言うが、そういうことだ。
筆者にとって京大やはてなはそういう場所だったのだ。
そういう目で見ていたわけだ。
ちなみにその友人は今は連絡先が分からなくなっており、生きているのかどうかも知らない。
なお、筆者ははてな関係者と直接的なやり取りをしたことはおそらく一度もない。
また筆者が実際にはてなにアカウントをつくったのは2005年になってからで、id:cleemy 以外のアカウントには一切関与していない。
ところで「最初の一人」が見つからない問題といえば、2013年に書いた、はてなブログにおける実質的に唯一の記事といえる「バナナ和音について2013年7月に考えていたこと」。
かなり異様な精神状態の時に書いた記事なので一文字たりとも読み返したくはないが、この記事の中のピアノを弾ける人を探しているというのは本気だった。
その後、ピアノやってるという人と話す機会がなかったわけではない。
「昔やってた」ならちらほら出会う気がするが、そうではなくて「今もやってる」という人と話す機会だってあったのだ。
でも、だめなのだ。
わたくし「あ、なんか、あれですか、ピアノとか。やってらっしゃるって聞いたんですけど」
ピアノ弾ける人「え、あ、はい」
わたくし「……」
ピアノ弾ける人「……」
と、そこで会話が終わってしまうことが多く、計画について具体的な話ができたことは一度たりとてなかった。
ちなみに「送り込む」という発想には、それほどこだわっていたわけではない。
逆に、意識的に送り込もうとするとうまくいかないのではないか、と思ったこともある。
筆者自身の思考とそれぞれの大学にいるごく少数の人間たちの意識が結合して集合意識のようなものが発生しているような感覚があり、こちらが無理に組織化しようとしなくても、自動的にそういう組織が誕生するのではないか、あるいはもうすでに誕生したのではないか、と考えていた時期もある。
筆者には他にも取り組んでいることがいろいろあったので、世界同時大学解体革命はあくまでもたくさんあるプロジェクトのひとつにすぎなかった。
革命は、筆者の中で少しずつ少しずつ、背景化していった。
特に2011年前後は大学についての関心自体がほとんど消失していた。
また、筆者は知の形骸化という観点から大学を解体してまったく別のものを構築するという発想とらわれていたわけだが、2012年に沖縄に来てから考えが変わった。
大学のかわりになるものをつくったとしても、結局、そのかわりのものも、いずれは形骸化してしまうのだ。
重要なのは、形骸化という現象そのものなのだ。
大学を否定するということが、こちらが意図したものとまったく違うように受け取られる可能性があることをはっきり理解したのも、沖縄に来てからだった。
何の前提もなく大学を含めた公教育を否定すると、2010年代の日本で流行した「反知性主義」を肯定しているように受け取られかねないのである。なお、この「反知性主義」はリチャード・ホフスタッターの言うものとは大幅に違っているかもしれない。
筆者にとっては、知的活動において公教育をいかに否定するかというのはごく当たり前の発想というか、「腕の見せ所」のような感覚でとらえていた。
学校という存在の有害性が重要なテーマになっている古典作品で年配の人にも通じやすいものとしてヘルマン・ヘッセの『車輪の下』があるし、20代のころに大学という場からかけ離れたところで研究したアインシュタインは誰もが知る天才として有名だ。
2021年現在の日本においてはすっかり忘れられている存在だが、ゲームクリエイターの飯野賢治をどう考えるかというのもある。
1990年代後半にはTVにも出ていたし、ゲームをよく知らない人にもある程度の知名度があった、この飯野賢治という存在が高校中退だったことはそれなりに大きい。
自分が考えていることについて、部分的には飯野賢治が代弁してくれていると感じたこともあった。一方でやはりこの人は自分とはあまりにも違うなと感じることもあった。
そして浅羽通明『大学で何を学ぶか』も、少なくとも筆者にとっては、大きな存在感を持った本だった。
1998年〜2008年あたりのウェブ論壇的なものの中において影響力を持っていた人たちの中にも、この『大学で何を学ぶか』を思い出深い本としてとらえている人はいた。
だが、知性を肯定しつつ大学を否定するというのは、いろいろと前提が必要なのだ。
まず、筆者のような人間が大学を否定できるのは、結局は大都市あるいはその周辺に暮らしているという、地政学的メリットを当たり前のように享受しているからこそ出てくる発想なのだ。
例えば離島においては、大学に進学しない限り、知のリソースにまったくアクセスできないという人が現代の日本でもいるのである。
2021年現在、ネット接続環境が離島でも充実し始めており、状況は少しずつ変わってきている、とは言えるのかもしれない。
そしてもうひとつは、男女の教育格差だ。
今にして思えば、ヘルマン・ヘッセ、アインシュタイン、飯野賢治、浅羽通明、4人とも男性である。
教育を否定できるのは、それは「男性」を「享受」しているからいえることなのだろうか。
安全な立場からの攻撃なのだろうか。
ここで、女性であるアーザル・ナフィーシーによって書かれた『テヘランでロリータを読む』とは何だったのかを考えたい。
写真に写っているのは2017年刊行の日本語版ハードカバー新装版である。なお、最初の日本語版ハードカバーは2006年刊行である。今年(2021年)になってから、河出文庫版も出た。原著は2003年発表である。
「テヘラン」とはイランの首都のテヘランで、「ロリータ」とは、1955年に発表されたウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ』のことである。
『テヘランでロリータを読む』はアメリカで150万部も売れたというが、これはかなり奇跡的なことではないだろうか。
なお作者は1997年にイランを離れてアメリカに渡ったので、この本で描かれているのはそれ以前のイランであって、今のイランと違ってはいるのかもしれない。
テヘラン大学の女性教員だったアーザル・ナフィーシーは、1981年にヴェールの着用を拒否してテヘラン大学を追放されたという。
イランでは1979年にイラン・イスラーム革命が発生した。女性はヴェールの着用が義務付けられるようになった。イスラム教徒でない人や同性愛者の人権状況も大きく悪化したとされる。アメリカは1980年4月にイランと国交を断絶した。なお当時のアメリカ大統領はジミー・カーターである。
アーザル・ナフィーシーはテヘラン大学を辞めてからもいくつかの大学の教員になるが、1995年の秋にはイランでの最後の教員職を辞職する。
そして「傷つきやすさと勇気との奇妙な混合」(peculiar mixture of fragility and courage)があるような「一匹狼タイプ」(loner)の女性ばかりを7人集めて、男子禁制の秘密の読書会を開催するようになる。
ただしずっと厳密に男子禁制だったわけではないようである。
『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版でのP.40(河出文庫版P.44)には以下のような記述がある。 ナボコフの散文の難解さにもかかわらず、私たちは彼に特別な絆を感じた。彼の描くテーマに共鳴するだけにとどまらない、もっと深い絆だった。ナボコフの小説は、見えない落とし穴、絶えず読者の足下をすくう思わぬ裂け目の上に形づくられる。そこには、いわゆる日常的現実への不信、現実のはかなさと脆さへの鋭い感覚が満ち満ちている。
彼のフィクションの中にも人生の中にも、私たちが本能的に理解できるものがあった。それは、あらゆる選択肢が奪われたときの限りない自由の可能性である。私がこのクラスをつくることになったのはそのせいだろう。私を外の世界につなぐものは第一に大学だったから、みずからそのつながりを断ち切った以上、虚空に落ちる瀬戸際で、私は「ヴァイオリン」をつくりあげるか、さもなくば虚空にのみこまれるしかなかったのである。
「このクラス」というのが、アーザル・ナフィーシーの自宅の居間で毎週木曜に開催されていた男子禁制の秘密の読書会である。
「秘密の」というのは比喩的な意味でなく、また単に秘密にしたほうが面白いからというだけでなく、本当に秘密にしなければならない理由があった。
ナボコフ作品のようなアメリカの小説は、禁書扱いなのだ。
一方で、奇妙なねじれもある。
『ロリータ』で描かれているような、中年男性が12歳の少女を「理想の恋人」に仕立て上げようとする行為は現代のアメリカにおいては非常に犯罪的な匂いがするが、結婚の「後」が前提ならイランにおいては合法とみなされるかもしれない。
古典イスラーム法の「現代的」で「一般的」な解釈では、女性は9歳から結婚できるのである。
そして上記の引用箇所でなぜ「ヴァイオリン」が出てくるのかというと、ここはナボコフが自身の小説『断頭台への招待』の英語版の序文において、この小説が万人向けのものではないという文脈の中で これは虚空で奏でられるヴァイオリンなのだ
と述べているのを受けてのものだからである。
上記の日本語訳は『テヘランでロリータを読む』日本語版の中でのものだが、2018年に出た新潮社の『ナボコフ・コレクション』の2巻ではこの『断頭台への招待』は『処刑への誘い』というタイトルで訳され、そこでは上記の箇所は これは真空に鳴るヴァイオリンだ。
と訳されている。 この小説は虚空で奏でられるヴァイオリンなのだから。
1977年刊行の『集英社版世界の文学8 ナボコフ』では、
という訳になっており、『テヘランでロリータを読む』日本語版での訳に近い。
なお、ロシア語版『ロリータ』のあとがきにおいて『ロリータ』が「アラブの各国」でも出版されたことにナボコフは言及している。
1960年代あるいはそれ以降においては、イスラム圏でのナボコフ作品の受容についてナボコフは認識していたはずである。
でも1935年ごろはどうだっただろう。
アーザル・ナフィーシーが秘密の読書会を始めた1995年は、『断頭台への招待』の連載が開始された1935年からは60年の年月が経っている。
また、ナボコフは1977年に死亡しているので、作者の死後18年が経過しているわけだ。
『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版でのP.38(河出文庫版P.41)には以下のような記述がある。 それから約六十年後、ナボコフの知らない世界、おそらくは知る術もない世界で、雪をいただくはるかな山脈を望む侘しい居間で、およそ思いがけない読者が、髪をかきむしるほど夢中になっているさまを私は何度も目撃した。
ここでこの『テヘランでロリータを読む』に注目したいのは、「変な本」というものを必要としている人に対する誤解があるかもしれないからだ。
「わけのわからない本を読むやつって、一体何を考えてるんだろうな」と、そのように考える人にこそ、この『テヘランでロリータを読む』を読んでみてほしいと思うのである。
というのも、浅羽通明の書いたものの中で『大学で何を学ぶか』だけを読んで、しかも流し読みで済ませてしまうと、誤解が深まってしまうかもしれないのだ。
実際には浅羽通明もまた「変な本」を必要といていた人であるはずなのだが、『大学で何を学ぶか』ではかなり抑制的である。
『大学で何を学ぶか』P.224(幻冬舎文庫版P.199)には以下のようにある。 彼らは、本を読むのがそれだけで苦痛なひと、読むだけで大仕事である膨大な数のひとびとがいるのを、ほとんど理解していない。この「本」を、小説や軽いエッセイ以外の本と限定したら、大多数のひとにとって、じつは読書とはそれだけでたいへんな努力と忍耐を要する苦行であるのに……。
この厳粛な事実をわきまえたうえで、それでも本を読めば、テレビ以上の「教養」を身につければ、苦労しただけのこんなによい見返りがあると、具体的なことばでみなを説得できるひとが、はたしてどこにいるだろうか。
幻冬舎文庫版では、「ほとんど理解していない。」のあとに「差別する加害者であるオレに、被害者の気持ちがまるで理解できないのと同様に、」というものが挿入されている。
教員の趣味の押し付けがひどすぎて、自分の好奇心のおもむくままに読むことができないのは確かに問題ではある。
だがここで強調しておきたいのは、自分の糧にするとか、知的虚栄心とか、そういうものではない、もっと切実なものがある人だっているのだということ。
また、「小説や軽いエッセイ」の中にもそういう切実さに応えてくれるものがあるのに、それに出会うことなしに活字全般を避けるようになるとしたらやはりそれも問題ではあるのだが、ここではまずその「髪をくしゃくしゃにして跳び上がる」読者たち(readers who will jump up, ruffling their hair)の切実さそのものに注目したいのだ。
そしてこの切実さというのは、ある意味においては「革命的」でありまた「宗教的」ともいえるのだが、現代の日本においてそういう切実さを重視したとしても、日本の若者がまた1960年代や1970年代の若者のようになるわけではないし、オウム真理教のようなカルト集団がたくさん誕生するわけでもない。
だから「変な本」を必要としている人に対する誤解を解くためにも、また解毒剤としても『テヘランでロリータを読む』をオススメしたいのである。
浅羽通明は1988年に『ニセ学生マニュアル』を出してその後シリーズ化もされたが、『テヘランでロリータを読む』にも大学の授業における部外者の出没についての話が出てくる。 すでに授業に興味をもつ少なからぬ部外者が私の講義を聴講していた。卒業後もずっと授業に出つづける教え子や、他大学の学生、若い作家、ふらりと入ってきた見知らぬ人々などである。彼らは英文学の議論にふれる機会がほとんどないなかで、単位などとれなくても、授業に余分な時間を費やす覚悟ができていた。私が彼らに出した条件はただひとつ、正規の学生の権利を尊重し、授業時間中の議論に参加するのは控えてほしいということだけだった。
以下は『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版でのP.332(河出文庫版P.393)より。
(中略)
しだいに授業の本当の主役は、正規の学生ではなく(彼らに対して特に大きな不満はなかったのだが)、こうした人々、クラスで読む作品への強い関心からやってくる部外者へと移っていった。
興味深いことに、上記の箇所は普通に読めばイラン・イラク戦争の停戦前後のことと解釈するのが妥当であるようにみえ、だとするとこれはまさに1988年前後のことである。
さて、ここに同質性を見い出すのか、それとも異質性を見い出すのか。
こういうのは、なかなかに難しい問題だ。
『大学で何を学ぶか』では、大学受験までの試験対策としての「勉強」を大学に持ち込んでしまう例がP.31〜P.35にかけて(幻冬舎文庫版ではP.31〜P.34にかけて)、多数紹介されている。
『テヘランでロリータを読む』では、これに類似したようなエピソードとして、イランの女子大学における、1980年前後と思われる出来事が書かれている。 こうした答案用紙を読んでいると、自分の講義の奇怪なパロディを見せられているような気がした。
作者のアーザル・ナフィーシーは、自分が授業で話した内容を試験の答案用紙にそっくりそのまま書いてきた学生が多数いたのでショックを受けたというのである。
ハードカバー新装版でのP.304(河出文庫版P.359)には以下のようにある。
また、同じくハードカバー新装版でのP.304(河出文庫版P.360)。 小学校に入ったその日から、先生の話を暗記するように言われた。自分の意見などどうでもいいと言われてきたのだ。
まだ教員になって間もないころだったアーザル・ナフィーシーは試験のあとの最初の授業で激怒してしまい、授業のあとでラージーエという学生からたしなめられる。
ラージーエの主張は、イランのような場所で生まれ育った女性たちに対して、いきなり独自の考えを書くように要求することは無理がある、ということのようだ。
これはイラン特有の、あるいはイスラム圏特有のことと考えていいのだろうか。
もしこの『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版P.303あたりからP.305あたり(河出文庫版ではP.359あたりからP.361あたり)を、誰が書いたものなのかは知らせずに、固有名詞は「X」や「Y」などにいれかえて、またいつの時代の話なのかや女子大でのエピソードであることが分かるような部分はカットしたうえで、いろんな国の学生に読ませてみたら一体どういう反応をするのか、というのは興味があるところだ。
海外留学や亡命の経験がない学生は、「これは間違いなく自分の国で起こったことだ」と考え、自分たちの国の事情に引きつけて考えるのではないかという気がするのである。
日本の学生であれば
「画一性の押し付けをバカ正直に取り込む若者が日本には多すぎるからだ」
とか、
「日本の受験産業が持つダークサイドを放置し続けた結果だ」
と考え、アメリカの学生であれば
「アメリカ的な経済的合理性の発想が教育現場に浸透しすぎた結果だ」
と考えるかもしれない。
また、地理的な要素だけでなく時間的な要素についても、自分と同じ世代の問題に引きつけて考える可能性がありそうだ。
つまり、2021年時点で20歳前後であるような学生であれば
「インターネットやスマホの影響で、自分で考える力を失っているためだ」
というような。
1980年前後にはイランであろうとなかろうと、インターネットは普及していないしスマートフォンもない。
そうは言っても、やはりイスラム圏の多くの国においては、女性が自分の考えを持つことを推奨されないという状況は、事実として存在しているのだろう。
ところで、この「ラージーエ」という名は、この本の中で数少ない本名での登場らしい。
それがどういうことなのかは、ぜひ読んで確かめてみてほしい。
さて、ここであらためて、日本でのことについて考えたい。
浅羽通明『大学で何を学ぶか』のハードカバー版は1996年4月に刊行された。
この前年、いくつかの大きな出来事があった。
そのうちのひとつが、地下鉄サリン事件。
オウム真理教が東京の地下鉄にサリンをばら撒いたのが、1995年3月だった。だからこの大きな事件の約一年後に『大学で何を学ぶか』が刊行されたわけだ。
今となっては分かりにくいが、この『大学で何を学ぶか』の全体を覆う雰囲気として、「どうして良い大学に行った高学歴の男性がオウム真理教なんかに」という、当時散々マスメディアでとりあげられていた疑問が背景にあるのだ。
しかし今となっては、オウム真理教もかなり政治的な産物であったという側面が指摘されている。
ソ連が崩壊したのは1991年だが、米ソの冷戦終結にともなって「メシのたね」がなくなった勢力が関与していた可能性が高いのである。
単純な陰謀論ではなく、様々な勢力の様々な思惑が反映されていたわけだ。
こういうのは、ある程度時間が経たないと分からない。
そしてここで、オウム真理教とはまったく別の、ある現象にも注目したい。
2005年に登場して10年近くにわたって日本を席巻したアイドルグループのAKB48だ。
これをどう考えるか。
もちろんメンバーの一人ひとりにはまったく罪はないのだが、あの「がんばってる姿」をショー化することの悪影響は甚大だった。
そう、オウム真理教とAKB48はコインの裏表なのだ。
ここでもう一度、MBTIあるいはMBTIに「似て非なるもの」における、S型とN型の対比を思い出してほしい。
そう、S型にとってオウム真理教とは、S型がN型に対して感じる不気味さが正当で普遍的なものであるかのように思わせてくれる存在だった。
「そんなことばっかり考えてたら、オウム信者みたいになっちゃうぞ」
というわけだ。
そしてAKB48は、長時間労働やハラスメントが許容されやすい空間をつくりあげるために、S型がその存在を悪用してきた。
「ほら、見てみい。あの子たちだって、あんなにがんばってるじゃないか」
というわけだ。
必ずしもこういった主張をする論客がS型だったというわけではなく、こういう発想が市井のS型に伝染していって、あらゆる領域のあらゆる階層に幅広く共有されていた、ということである。
今にして思えば、1990年前後にはいろいろと決定的なことが起こった。
日本においては、昭和の終焉、バブルの崩壊。
日本だけではない。ベルリンの壁崩壊。ソ連の崩壊。冷戦終結。ウェブの誕生。中東においては、8年も続いたイラン・イラク戦争の停戦と、ホメイニーの死去。
1990年前後から2020年前後までの30年間について考える時、そしてこの30年間というのは日本ではほぼイコール「平成」なわけだが、まず最初の5年経過時点の1995年にオウム真理教の事件が起こったわけだ。そして折返し地点ともいえる2005年にAKB48が登場したわけだ。
1995年前後といえば、ソーカル事件も気になるところだ。
アラン・ソーカルはわざとデタラメな内容の論文を投稿してそれが実際に雑誌に掲載されてしまい、その後発表した著書『「知」の欺瞞――ポストモダン思想における科学の濫用』において、知的な詐欺が蔓延していると告発した。
この事件によって、思想を排した科学的事実を羅列することだけが誠実な態度であるかのような「教訓」を見い出してしまう人が日本でも続出した。
なお、ソーカル事件が大きな騒動になったのは、浅羽通明『大学で何を学ぶか』のハードカバー版刊行(1996年4月)よりも後なので、『大学で何を学ぶか』はソーカル事件を念頭に置いているわけではない。
1990年代後半において、オウム真理教とソーカル事件がN型の論客たちに与えた甚大な影響。
本来であれば、N型の論客たちが前提を疑う力や視野の広さを呼び覚ます役割を担うのが自然であるはずのところが、
「いや、こういう発想を蔓延させてしまうと、『オウム信者』のような人が増えてしまうか、『知的詐欺師』を量産してしまうことになるから」
というように、自らに強力なブレーキをかけていたということはないだろうか。
部分的には、認知バイアスとしての「敵対的メディア認知」(hostile media effect)あるいは「第三者効果」(third-person effect)が作用していた、という解釈が有効かもしれない。
こういったことについては、2021年の現在においても、いまだにその余波を感じるのである。もちろん、筆者がそのように感じることにもバイアスが作用している可能性はないとはいえない。
一方で、2015年あたりからの日本においては、1990年代後半とはまた違う空気が覆い始めているようにも思える。
その空気というのは端的にいえば、結局日本における最大のカルト集団は「会社」だったのではないのかという壮大な疑惑だ。
一つひとつの会社をそれぞれ別個のカルト集団とみなすこともできるし、日本的な企業文化を共有するすべての人が大きな単一のカルト集団に入っているとみなすこともできるだろう。
そしてこの「会社」という異形の怪物に疑問を持たせないために、この怪物を無理矢理にでも延命させるために、オウム真理教やAKB48が「悪用」されてきたということはないだろうか。
1995年にオウム真理教が起こした地下鉄サリン事件では10人以上が死亡している。東京という極端な人口密集地の、しかも地下鉄という公共交通機関でのことだったため、その混乱は非常に大きい。また後遺症に苦しむ人もいる。やはり、あまり頻繁にはこういうことが起こってほしくないと思うのは自然なことではある。
一方で、日本における自殺による死者というのをどう考えるか。
日本では1998年から2011年の14年連続で、年間3万人以上が自殺した。その一件一件というのは、たいていは大した関心を呼び起こさない。
3万人を下回ってからも、2015年の統計ではG7(フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)の中では自殺死亡率はぶっちぎりの独走状態だ。
そして自殺にも、直接的な死亡者だけでなく自殺未遂による後遺症に苦しむ人というのがいる。
哲学者の高橋哲哉は『犠牲のシステム 福島・沖縄』(2012年刊)において、2011年に起こった3.11(東日本大震災)を「天罰」とみなす論者たちを批判するなかで、以下のように書いている(P.147)。 多数の死者を出す天災は地震だけではない。日本列島には毎年台風が襲来し、死者を出すケースも少なくなく、東日本大震災の約半年後、台風一二号では全国で死者行方不明者九四人を出した。前年の二〇一〇年夏には全国的に熱波に襲われ、熱中症の死者は一七一八人に上った。これらの死者が、戦後日本人の罪の償いの死者ではなくて、東日本大震災の死者だけがそうである根拠は、どこにあるのだろうか。
ちなみに上記の引用箇所の前後では、基本的には、すでに有名人であるような人が広く公衆に向けて3.11を「天罰」とみなす考えを発信したものについて問題視している。
筆者個人の考えとしては、例えば一対一の会話において、そしてその会話が外部に漏れないという前提があるならば、苦しい状況に置かれている個人に対して「神が与えた試練だととらえてみてはどうか」といったような主旨のことを言うのは必ずしも悪いことだとは思わない。
それはともかく、だ。
ここで上記の引用箇所に注目したいのは、もちろん「天罰論」の是非について考えるためではない。
そもそも「テロ」とは何か、そもそも「災害」とは何か、という疑問である。
上記の引用箇所で指摘されている、2010年の夏の暑さというのは今でも覚えている。
マスメディアでやたらと「酷暑」という言葉が使われ、そういえば「コクショ」という言葉を使うことって滅多にないよなあ、この夏だけでもう一生ぶんの「コクショ」という言葉を聞いた気がするなあ、と思っていた。
ちなみに筆者は1995年1月の阪神・淡路大震災の被災者である。
地球上で味わえるものの中では最も大きい部類の揺れを経験し、自宅は全壊し、実の母親はこの時に死亡している。
この時の死者は6000人以上だったのだが、そのうちの一名が、筆者の実の母親なわけだ。
毎年1月17日になると神戸市中央区のフラワーロード沿いの公園で追悼イベントがあり、何度か筆者も足を運んだ。
朝が苦手なので、公園で早朝からロウソクに火をともすのに参加したのは一度だけだ。
これは2016年のことで、この時は前日の深夜からJR三宮駅の近くの24時間営業のファミリーレストランに入り、ひとりで朝まで時間をつぶしていた。ピンチョンの『V.』の新訳を読んでいた記憶がある。
そういうわけで筆者も当事者だ。だから決して、地震による災害が大したことないなどと言いたいわけではない。
でも冷静に考えると、2010年における熱中症による死者が1718人というのも、やはりこれは凄い数字であるのは確かなのだ。
きっと筆者と同じように、若い時に親類を亡くすことになった人もいただろう。
なのに「熱没者追悼イベント」のようなものがないのは、なぜだろうか。
実は筆者が知らないだけで、毎年どこかでイベントが開催されていたりするのだろうか。
フラワーロード沿いの公園には、「慰霊と復興のモニュメント」というモニュメントがあり、犠牲者の名前が刻まれた銘板が並んでいる。筆者の母親の名前も、あそこにある。
では、2010年における熱中症による死者については、このようなモニュメントはあるのだろうか。
毎年1月になると何らかの形で阪神・淡路大震災の特集番組が放送され、そういったもので初めて知る事実というのもあったりする。
一方で、あの2010年の酷暑について、「あの夏を風化させてはならない」的な主旨のTVの特集番組や、遺族のその後を取材したようなTV番組はあったりするのだろうか。
ここであらためて、日本における自殺について、だ。
14年間にわたって年間3万人以上が自殺に追い込まれていたというのは、これはテロではないのか。
明確な主体が存在しないからテロではない、ともいえそうではある。
では、災害でない、というのはどうしていえるのか。
経済的に豊かでありながらこんなに自殺が多いのはなぜか。
40代や50代の男性に自殺が多いのはなぜか。
今でも年間2万人が自殺している状況について、「緊急事態」が発令されないのはなぜか。
だからこそ、なのだ。
だからいま「日本で『テヘランでロリータを読む』を読む」ことを、推奨したいのである。
『テヘランでロリータを読む』で描かれる切実さというのは、多くの人が疑問に思わない前提を、そのまま自分の前提として受け容れることができないようなすべての人にある切実さだ。
自殺死亡率の高さに注目が集まらないことは、あくまでも一例にすぎない。
こういったことを、あたかも存在しないこととして、昨日と同じ今日を送ろうとする、その異様さだ。
何か大きな出来事があっても、ほとぼりが冷めると元に戻そうとする、その異様さだ。
前提を疑うというのは、能動的な行為ではない。
「よーし、今日も1日3個、前提を疑うぞ」などと目標を決めて前提を疑うわけではない。
これは自動的にもたらされるものなのだ。
自分で制御することなどできない。だからこそ切実なのだ。
そしてこういう切実さというのは、本によって植え付けられるわけではない。
もともと存在していた切実さに、応えてくれる本があっただけなのだ。
ああ、この感覚を持っている人が自分以外にもいたのだという、その安心感と居心地の悪さ。
自分だけが知っていると思っていた、というのも一つの安定状態ではあるため、共有することには多少の居心地の悪さがあるというのもポイントである。
そして思考においては、自分だけが知っていると思っていた、という期間が長いほうがかえって良い場合もある。
そういうわけだから、変わった本を読む人について、「あの人はどうしてこういう本を読むのだろう、自分も読んでみたら同じ感覚を味わえるだろうか」と思って同じ本を読んでも、同じ感覚が味わえるわけではないのだ。
切実さがない人にとっては、切実さがある人と同じ本を読むのではなく『テヘランでロリータを読む』のような本を読むことによって、「なるほど、あの人はこういう切実さを抱えていたのか」と理解できるのではないかと思う。
なお、『テヘランでロリータを読む』を読むにあたっては、必ずしもこの本の中でとりあげられている小説について知っている必要はない。
ところで浅羽通明『大学で何を学ぶか』の第4章の前半では、大正時代や昭和初期の女性たちにとっての美意識としての教養について語られている。そこでの「教養」は、『テヘランでロリータを読む』における文学と重なり合う部分はある。
ただ、『大学で何を学ぶか』では「教養」を同時代の人間と共有することについて重きがおかれているため、じゃあ共有さえできれば内容は何でもいいのか、と誤解する人もいそうである。
決して、内容は何でもいいわけではない。この切実さに応えてくれるものでなければならないのである。
そしてこの切実さは、ナボコフの『断頭台への招待』第2章の「根本的非合法性」(basic illegality)とつながっている。
この切実さは、単に「社会」からは必要とされないだけではないのだ。
非合法性があるのだ。
小説の中で直接的にとりあげられているテーマが重要なのではない。
直接的に犯罪を美化していたり、登場人物が犯罪者であったりということが重要なのではない。
根本的な、非合法性なのだ。
アーザル・ナフィーシー『テヘランでロリータを読む』に、1979年秋のテヘラン大学での最初の授業についての箇所がある。 最初の日、フィクションは何をすべきでしょうか、そもそもなぜわざわざフィクションを読むと思いますか、と学生に問いかけた。授業のはじめ方としては一風変わっているが、おかげで学生の注意を惹きつけるのに成功した。今学期、私たちはさまざまな作家を読んで議論することになりますが、これらの作家全員に共通するひとつの点は、既成の秩序を覆す不穏な力を秘めていることです。ゴーリキーやゴールドのように、体制の打倒をめざす政治的意思が明らかな場合もあります。しかし私に言わせれば、フィッツジェラルドやマーク・トウェインのような作家のほうが、たとえそうは見えなくとも、いっそう不穏なのです。不穏というこの言葉についてはまたあとで考えてみましょう。私の言う意味は通常の定義とはちがいますから。
以下はハードカバー新装版でのP.133(河出文庫版P.155)より。
ナボコフの『断頭台への招待』は、同じロシアのドストエフスキーの『地下室の手記』(1864年発表)的な要素と、20世紀アメリカのディストピアSF的な要素、その両方を持つものとしてとらえられることがある。
ここで考えるディストピアSF的な要素とはつまり、フィリップ・K・ディックはもちろんのこと、ジョージ・オーウェルの『1984年』(1949年刊)的なもの、J・G・バラードの『ゲームの終わり』(1964年刊行の短編集『終着の浜辺』のうちの一つ、2017年の東京創元社の短編全集では『エンドゲーム』の邦題)的なものだ。
ただしナボコフはSFを見下していたかもしれない。
また、ドストエフスキーに対しても批判的だった。
カフカの『審判』(執筆は1914年ごろ)や『城』(執筆は1922年ごろ)と比較されることも多い『断頭台への招待』だが、英語版序文には「カフカなんか一行たりとも読んでへんわ」みたいなことも書いてある。ただし「偉大な芸術家」とも書いているので、英語版序文を書いた時点ではカフカの重要性を認識しつつ、執筆当時は読んでいなかったということなのだろう。
『断頭台への招待』は初稿は1934年に6月、つまりナボコフ35歳の時にロシア語で書きはじめ、1935年から連載開始である。そして英語版序文は1959年なので、ロシア語版執筆と英語版序文までには25年のタイムラグがある。
執筆していた場所はドイツの首都ベルリン。
1934年のドイツという、人類史上でも特異な熱狂の渦の中で書かれたわけだ。
有名な『ロリータ』などはアメリカで暮らしつつ英語で書いた小説だが、『断頭台への招待』はV・シーリンというペンネームで、ロシアを脱出してヨーロッパ(主にフランスやドイツ)に逃れてきたロシア人向けの雑誌に、1935年からロシア語の小説として連載された。
そしてこのころ、祖国は着々と「ソ連」になっていく。この本のもう一つの小説『キング、クィーンそしてジャック』の序文にもあるように、1920年代にはすぐにロシアに帰ることができると思っていたようだが、1930年代になっていよいよそれも怪しくなってくるという、そういう時期なわけだ。
1935年(昭和10年)といえば、夢野久作『ドグラ・マグラ』が10年近くの推敲を経て刊行された年でもあることを連想する人もいるかもしれない。
『ドグラ・マグラ』で描かれるのは『断頭台への招待』のような監獄ではなく精神病院だが、幽閉あるいは事実上の幽閉と創造性の関係について、『天才たちは学校がきらいだった』P.197には以下のようにある。 奇妙なことに、逆境は邪魔されない時間をもたらすことで、創造的な人物には有益なときがある。ひとつの実例は(昔の)監獄が、本を書くのに適していたというパラドックスだ(マルコ・ポーロが中国への旅行記を書きとめたのは監獄にいるときだった)。またマックスウェルが上下二巻の記念すべき論文を書いたのは、あまり栄光とは関係ない経歴の中で引退同然になった期間だった。
一般論として亡命という状況は幽閉に近いものになりやすいし、ロシア語で書いたのにロシア(ソ連)で流通させることができないため、ロシアから脱出したナボコフたちには「安心できない一種の非現実感」(自伝第14章、原文は「a certain air of fragile unreality」)がつきまとっていたという。
1935年は、ウィトゲンシュタインがロシアに旅行した年でもある。
『ウィトゲンシュタイン 哲学宗教日記』(2005年刊)P.256によると、1935年9月にロシア(ソ連)を訪れたが、コルホーズ(集団農場)での「単純労働」を望んでいたのに大学での研究職しか提供されなかったので10月頭にロシアを離れたようである。
「作業」を求めてロシアに行ったのに「思考」を求められたので帰ってきたのだ、というような解釈をしてもいいのかどうかは、よく分からない。
ウィトゲンシュタインはケインズへの手紙において、ロシアで暮らすという考えについて理解を求めている。
なお、ウィトゲンシュタインがケンブリッジ大学のラッセルのもとで学んだのは1911年秋から1913年にかけてであり、『論理哲学論考』の出版をめぐるゴタゴタは1919年から1922年にかけてである。この1919年から1922年にかけてというのは、ナボコフがケンブリッジ大学で学んでいた時期とちょうど重なる。
大学都市ケンブリッジの住人だった頃の20代前半のナボコフは10歳年上のウィトゲンシュタインの存在を知らなかったようではあるが、晩年のナボコフはウィトゲンシュタインを強く意識していたのだと考える研究者もいる。
なおナボコフがケンブリッジにいた頃のことは自伝の第13章に書かれているが、この第13章はかなり読み応えがある。
ところでナボコフは幼少期から蝶の採集に熱中していたが、『天才たちは学校がきらいだった』で「失読症だったことには、ほとんど議論の余地はない」(P.173)として紹介されているウィリアム・バトラー・イェイツも、蝶や蛾の採集が好きだったようだ。
イェイツはアイルランドの詩人だが、ケルト神話で蝶は特別な意味を持つ。
ナボコフは1940年代のアメリカでは博物館の研究員として数年間蝶の採集にいそしんでいる。
もちろんナボコフのような人にとっては、職業や所属といったものは何の意味も持たないだろう。
ナボコフは常に生き物を捕獲する側であるというわけではない。
手術の時に医者の前で内蔵を「さらけ出」すナボコフ自身と、標本のために羽を広げられる蛾を重ね合わせているかのような箇所が自伝の第6章にある。
また、逃げた先でまた逃げるはめになる、というのはナボコフの人生で繰り返されている。
1917月にロシア革命が発生し、18歳のナボコフはクリミア半島に逃れる。
その後1919年にクリミア半島からも離れるのだが、それはつまりロシアからの脱出だ。
ロシアを脱出してヨーロッパに向かい、1919年秋にナボコフはケンブリッジ大学に入学。卒業後ドイツで長らく暮らすが、フランスでの生活も経由しつつ1940年にはヨーロッパを離れてアメリカに移住。
『ロリータ』が話題になるとアメリカからも離れ、晩年はスイスで過ごす。
蝶の採集とディストピアSF的な世界はまったく結びつかないようにもみえるが、自伝の第6章には興味深いエピソードが書かれている。
1918年3月、クリミア半島の山道で、沖合のイギリスの軍艦に虫取り網で合図を送ったと疑われて「がに股のボルシェヴィキの歩哨」(a bow-legged bolshevik sentry)に逮捕されそうになったというのである。
この箇所は、1979年刊行の邦訳『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』(大津栄一郎による訳)では、なぜか「一九一九年の三月」となっている(1979年11月20日第3刷発行のものでP.101)。
1940年5月、ナボコフ41歳のときにフランスからアメリカに移住するのだが、40代にもなって虫取り網を持ってうろうろする正体不明の人物はアメリカのほうぼうで不信や好奇のまなざしを引きだしていたようである。
「病的な関心」(morbid interest)を向けてくるのは人間だけではなかったようで、普段は人間に無関心な犬がナボコフに対しては威嚇してきたりだとか、馬に一マイル以上もあとをつけられたりだとか、そういうことがおもしろおかしく書かれている。
虚実入り混じったものとしてとらえられることもあるこの自伝だが、この自己認識のあり方は重要である。
ナボコフ自身が何よりもまず現在進行形の不審者としてアメリカを生きるという、そういう認識のなかで『ロリータ』が書かれたわけである。
なお、自伝は1948年や1949年に『ニューヨーカー』誌に掲載されたものがメインで、『ロリータ』脱稿は1953年である。
自分がヨソ者であり不審者であるという認識は、少なくともナボコフのような人にとっては、思考に良い影響を与えたのではないかと思えてくる。
自伝の第6章は章全体が蝶や蛾についての話だが、思考について書かれている興味深い箇所がある。
ナボコフによれば、ドイツ人の研究者は「philatelylike side」(切手蒐集的な側面)にこだわり続けたが、英語圏の研究者は「microscopic」(微視的、あるいは顕微鏡を使用した)な知見を活用して昆虫の分類方法を刷新しようとしていた。
そしてこのドイツ人による「一般蒐集家」(average collector)には「解剖させるべきでない」(should not be made to dissect)という姿勢が、小説を手がける「神経質な出版社」(nervous publishers)による「一般読者」(average reader)には「考えさせまい」(should not be made to think)とする姿勢と類似している、というのである。
このとらえ方が妥当なのかはともかく、ナボコフにはそう見えていた。
ヴァイオリンの比喩を用いたナボコフだが、インタビュー集『知の逆転』(2012年刊)でオリバー・サックスは ナボコフは音楽を理解することができない音楽不能症でした。こういう人は前頭葉のある部分の結合が欠けているのです。
と語っている(P.150)。
『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』(大津栄一郎による訳)P.26には以下のようにある。 私の両親はどちらも絶対音感の持主だったが、残念ながら、息子はいまでも音楽というものはいらだたしい騒音の恣意的持続としか思っていない。情緒的気分しだいではヴァイオリンの痙攣性の太い音程度までは我慢できないわけではないが、グランドピアノや管楽器になると、音が小さければ退屈なだけだし、大きければいらだたしいだけなのだ。
ナボコフは共感覚の持ち主としても有名だ。
共感覚であるがゆえに音楽を楽しめなかったのか、あるいはオリバー・サックスの言うように音楽不能症なのか、両方なのか、あるいはもっと別の理由があるのか、そのあたりはよく分からない。
『断頭台への招待』英語版序文のヴァイオリンの箇所は、電子書籍(ASIN: B004KABDU2 )で確認するかぎり、原文では以下のようなシンプルな文だ。 It is a violin in a void.
「void」が物理的に空気がないという意味での「真空」という含みを持たせていたのかどうかは分からない。
物理的に空気がない場合、当然ながら音は伝わらない。
音楽用語としての「air」も意識していたりするのかどうかはよく分からない。
V・シーリン氏による小説を「a violin in a void」だと評するV・ナボコフ。
自伝の第2章での共感覚の描写によると、アルファベットの各文字が特定の色と結びついており、「v」は紅水晶色(rose quartz)であるという。
ちなみにナボコフ研究で有名なブライアン・ボイドは、日本語(カタカナ)では同じ「ボイド」だが「void」ではなく「Boyd」である。
真空といえば、『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』の第6章では、珍種の蝶とその食樹に囲まれている時の恍惚感の背後にあるものについて、P.107(1979年刊の邦訳でのページ)には以下のようにある。 それは私が愛する一切のものを吸収してしまう一瞬の真空状態のようなものである。
電子書籍(ASIN: B004KABDWA )で確認するかぎり、原文では以下のようになっている。 It is like a momentary vacuum into which rushes all that I love.
また、自伝の第14章では、当時のロシアを飛び出して思考する人々を賛美する文脈の中において(思考という言い方はしていないけれども)、肯定的なニュアンスで「working in an absolute void」や「the books produced in vacuo」という表現が登場している。
邦訳の『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』では、この箇所はそれぞれ「完全な真空のなかで生きている」(P.228)「真空のなかで生み出した作品」(P.229)と訳されている。
これらの訳は1979年刊行の『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』(大津栄一郎による訳)のもので、2015年刊行の『記憶よ、語れ――自伝再訪』(若島正による訳)は筆者は未見である。
ところで今年(2021年)になって、まったく意外な方面から、女性の書き手による大学の有害性について論じたものに出くわした。
『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』(原題は『The Artist's Way』)という本である。
作者のジュリア・キャメロンは1970年代にマーティン・スコセッシと結婚していた時期がある人だ。
この本の原著は最初の版が1992年で、英語圏ではかなり有名らしいのだが、筆者は最近まで知らなかった。
この『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』(2017年刊)には、P.250からP.252にかけて以下のような記述がある。 大学は、創造する精神を妨げる、はるかに微妙な恐るべき障害を抱えている。このことに気づくまでに、それから数年の教員生活が必要だった。明確な敵意なら対処の仕方もあるだろう。しかし、さらに危険でぞっとするのは、教師が学生たちの創造性に関心を示さず、無視していたことだ。
(中略)
創造性は、その性質上、数値にして語ることはできない。作品を分析し、批評することに重点をおく大学では、創作活動そのものはあまり支援してもらえず、理解もされない。歯に衣着せず言うなら、ほとんどの大学の教師たちはものを分解する方法は知っているが、組み立てる方法を知らないのだ。
(中略)
アーティストが厳しさに欠けると言いたいのではない。アーティストの厳しさは、知識人のそれとは異なったものに根ざしていると言いたいのである。
(中略)
若いアーティストたちは言わば苗木のようなものである。彼らの初期の作品は森の中の茂みや下生え、あるいは雑草にたとえらえる。高尚な知的法則を好む学問の殿堂は、森の地面近くで生きている生命に、ほとんど温かな目を向けようとしない。才能に恵まれた多くの学生が、自分に無関係の基準に無理やり合わせようとして失敗し、不当にも脅かされているのを見るのは、教師として忍びなかった。
日本語版タイトルはいかにも自己啓発という趣きだが、自分のためというよりも、濃厚なN型がどのように世界を見ているかを理解するために『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』のような本をオススメしたいのである。
濃厚なN型が世界に向けている視線というのは、その人の隣に座って同じ本を読めば分かるようになるわけではない。
そして、『テヘランでロリータを読む』にあるような切実さを、まったく違う角度からとらえることが、『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』によって可能になるわけだ。
また、アーティストは「めざす」ようなものではないということも、この本を読めばよく分かると思う。
この本は表面的には個人の創作について語られているが、「どうしてうちの会社からイノベーションの芽が育たないのだろう」と考える経営陣にも、参考になるものがあるかもしれない。
濃厚なN型の当事者から見た世界というものを理解しない限り、何がイノベーションの阻害要因になっているのかというのは分かりにくいからだ。
しかしこれを読んでしまうと、「うちの会社では、とうてい無理だ」ということに気づいてしまう、ということもあるだろう。
その場合、イノベーションとは無縁だとしてあきらめるか、もしくはイノベーションの種を守るために良い意味での隔離が必要だということになる。
そしておそらく、それがどのような「隔離」になるのかというのは、ここで考えている「思考所」に近いものになるはずなのである。
ところで先ほどの引用箇所で「ほとんどの大学の教師たちはものを分解する方法は知っているが」とあったが、独自に分解できているならいいほうかもしれない。
以下は浅羽通明『大学で何を学ぶか』P.57(幻冬舎文庫版P.53)より。 さらに、学会で先生や先輩の学者から評価されたいなら、文学研究の例でいえば、主観的と思われたり、古い学者たちに受け容れられがたいユニークな視点による批評的論文よりも、作品の制作年代や作家の伝記的事実を実証した地味で手堅い論文のほうが、無難であるという。
ちなみにアーザル・ナフィーシーは、大学での授業には強い手応えを感じていたのに、自分の論文には満足していなかったようだ。 私の論文は注目されたが、本当に納得のゆくように書けたことはめったになかった。ほとんどはきれいにまとまりすぎていて、気取りと学識が鼻につくように思えた。とりあげた主題には情熱を感じたけれど、文章では従わねばならないしきたりや規則があるため、授業のように熱中して衝動的に語れないのが物足りなかった。教室では学生と刺激的な対話をしているような気がしたが、論文の中の私はいささかつまらない教師になった。
以下は『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版でのP.239(河出文庫版P.282)より。
ちなみにナボコフも教壇に立ってはいたが、ナボコフのように現役の小説の書き手でありながら教員でもあるような人は、『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』では念頭に置いていないのかもしれない。
ただ、ナボコフの自伝の中に、自分がかつて「些細な欠点」(trivial faults)をあげつらった「意地の悪い書評」(ill-tempered review)によって若い詩人を傷つけたかもしれないことを後悔しているような記述がある。
以下は1979年刊行の『ナボコフ自伝 記憶よ、語れ』(大津栄一郎による訳)の第14章P.235より。 他にもおおぜいロシアの亡命作家に会った。ポプラフスキーには、若くして死んだので、会えなかった。彼は、バラライカの合奏の間を縫って聞えてくる、遠くのバイオリンだった。彼の詩の朗々たる調子はけっして忘れないだろうし、彼の若い頃の詩の些細な欠点をあげつらった私自身の意地の悪い書評もけっして許さないだろう。
「けっして許さないだろう」というのは、ナボコフ自身が、である。
このポプラフスキー(Poplavski)というのは、亡命詩人のボリス・ポプラフスキー(英語表記では、Boris Poplavsky)のことだろうか。
ボリス・ポプラフスキーはナボコフより4歳年下で、1921年にロシアを離れてフランスに移り住んだ詩人である。
そして、ここにヴァイオリンが出てきている。 a far violin among near balalaikas
電子書籍(ASIN: B004KABDWA )で確認するかぎり、原文では、
である。
『断頭台への招待』で、気になる箇所がある。 「おまけに、ぼくの頭のなかには、いろんな時期に手をつけたけれども中断したままになっているたくさんの計画がいっぱい詰まっているのですよ……処刑執行前に残っている時間が、ちゃんとした成果を得るのに十分でないとしたなら、いくらぼくだってそんな計画を実行に移そうなんて思いませんよ。だからこそ……」
以下は『集英社版世界の文学8 ナボコフ』P.227(第1章)での訳。
同じ箇所は、2018年刊行の新潮社版『ナボコフ・コレクション』2巻のP.14(第1章)では以下のような訳になっている。 「それからもうひとつ、ぼくの頭のなかには手はつけたもののそのつどやりかけになってしまった仕事が大量にあって……。処刑されるまで時間がなくてどうせきちんと仕上げられないなら、とてもとりかかる気になれませんから。そういうわけです」
電子書籍(ASIN: B004KABDU2 )で確認するかぎり、英語版では以下のようになっている。 "And furthermore, I have in my head many projects that were begun and interrupted at various times ... I simply shall not pursue them if the time remaining before my execution is not sufficient for their orderly conclusion. This is why ..."
筆者はボリス・ポプラフスキーが書いたものを読んだことはないが、ナボコフやポプラフスキーにこういう傾向があったのかどうかというのは、それなりに気になるところではある。
というのも、筆者もまさにこういう「中断したまま」のもので頭がいっぱいだからだ。
いま書いているこの記事(いまあなたが読んでいるこの「作業所はあるのになぜ思考所はないのか」)も、もし無事にnoteにアップロードできたとしらそれはほとんど奇跡のようなものなのであって、筆者のような人間には、公開に至ったひとつの記事の影には公開に至らなかった100以上の記事があるのが常なのである。
なお、『テヘランでロリータを読む』ハードカバー新装版でのP.282(河出文庫版P.333)には 私の知識は衝動的でまとまりがなく、彼女の知識は綿密で完全だったから、たがいに相手にないものを補いあえた。
とあり、またハードカバー新装版でのP.314(河出文庫版P.371)には 私だったらたぶんメモを残すのを忘れたはずだ。私の頭の中は雑然としているから。でも彼はちがう――彼なら忘れない。
とある。
この本の中の「私」も、頭の中に衝動性と乱雑さが常にあるという自己認識のようだ。
ちなみにジュリア・キャメロン『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』では、アイディアのサルベージについて、第9章(第9週)のP.303に以下のようにある。 自分で放棄したり、他人に妨害されてやめてしまったりした作品の中で、救出できるものがないかどうかを穏やかな気持ちで探してみよう。挫折は、あなただけではなく、誰にでも起こることを忘れないように。もし救い出せそうなものがあったら、それを完成させてやろう。
電子書籍(ASIN: B083X758NX )で確認するかぎり、原文では以下のようになっている。 Very gently, very gently, consider whether any aborted, abandoned, savaged, or sabotaged brainchildren can be rescued. Remember, you are not alone. All of us have taken creative U-turns.
原文では「brainchildren」とあるので、作品として具体化するための「作業」を開始し始めていたとは限らないような、アイディア全般の救出について言っているのだろう。
なお、突然創作意欲が萎えることについては、筆者の考えは『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』の第9章(第9週)で述べられていることとは違う。
筆者は、こういったものは必ずしも恐怖によるものではないのではないかと感じているのだ。
筆者の場合、熱中し始めてから40日後と60日後というのが、飽きやすいタイミングとして君臨している。
これはどんなジャンルのことであっても、そうなのだ。
そのタイミングで、熱中していたことにまつわるあらゆる要素が一気に色褪せるということになりやすいのである。
そして、ここ数年は、飽きる時はとにかく飽きるに任せる、というのが良いのだと割り切ることが出来るようになった。
興味を持続させようとしてあがくことよりも、また関心が戻った時にいつでも続きを始めることができるようにしておくほうが重要だと考えるようになったのだ。
これは必ずしも創作や研究に限らない。
プレイする側としてのコンピュータゲームなどにおいても、やはり突然飽きるタイミングというのはある。
ゲームプレイにも40日後と60日後というような飽きやすいタイミングがあるのかどうかは自分で検証できていない。ただ、あんなに熱中していたのに、すべての要素がいったん色褪せて感じられるという、あの感じがとても似ているのだ。
そしてゲームプレイの場合は創作や研究に伴う恐怖とはほとんど関係がないわけだ。
だから少なくとも筆者の場合は、恐怖と無関係にとにかく飽きるタイミングというのはあるものなのだ、ということを前提にすることで気が楽になった。
また、飽きることには、思考において極めて重要な意味があるとも考えている。
この記事(いまあなたが読んでいるこの「作業所はあるのになぜ思考所はないのか」)もまさに、まったく別のことに取り組んでいたものが飽きた直後に書き始めたものだ。
筆者は2021年8月20日あたりからプログラミングにかなり熱中していたが、今となってはこの夏の終わりに一体何をそんなに熱中していたのかよく思い出せない。
もちろんソースコードを見れば思い出せる、というのは分かっている。
でも今は、その時のコードをじっくり読みたいと思わない。
あとになって分かることなのだが、今回の場合は8月20日の約60日後である10月20日に実質的にいったん飽きたとみていいのである。
その後も2週間ほどの間はなんとか興味を持続させようとはしていたものの、11月5日あたりから文章を書くほうに衝動的に一気にシフトしたわけだ。
11月15日以降は、10月20日までに熱中していたことなどほぼ完全に忘却して、文章を書くことに熱中していた。
日常生活といえるようなものは存在していないので、11月5日から12月16日までは、起きてから寝るまでずっとほぼ完全にnoteの記事のことしか考えていない。寝ている時も夢の中にテーマに関連することが出てくる。
気になっているニュースはあるものの、ニュースを一切チェックしない日も多かった。
なお、11月5日から11月15日あたりまではnoteに書く予定の別の記事も並行して書いていたのだが、11月15日あたりからはほぼこの「作業所はあるのになぜ思考所はないのか」だけに専念している。
2021年12月現在、意識的に確保しようとしなくても、ひとりの時間がたっぷりあるのはとてもありがたい。
ジュリア・キャメロン『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』P.191には以下のようにある。 アーティストは何もしないでいる時間をもたなければならない。こうした時間をもつ権利を守るには、勇気や信念、さらには切り替えの能力がいる。
ひとりで静かに過ごしていると、家族や友人には引きこもりと映り、心配の種となる。だが、アーティストにとって、引きこもりは必要である。創造のための孤独が確保されないと、私たちの中のアーティストはイライラして怒りをつのらせ、不機嫌になる。そのような状態が続けば、やがて意気消沈して憂うつになり、他人に敵意を抱くようになる。
「引きこもり」の箇所は原文では「withdrawal」である。
筆者は他人が提示した「課題」(task)をこなすのは苦手なので、この本に書かれていることを直接的な意味では実践していないのだが、上記の箇所については、筆者はすでに実践しているといえなくもない。
実践というより、家族がいないために、ひとりでいることのハードルはとても低い。
2021年10月20日あたりからずっと、72時間以上連続で一言も発しない、などというのはザラである。
もし今回、この記事が無事に完成したとしたら、それはひとりの時間をたっぷり確保できたからである。
ただし、筆者は2021年12月16日現在、現金であったり換金しやすい資産(暗号資産など)といったりしたものがほぼ完全に底をついた状態に陥っており、買いだめしておいた食糧も残りが少なくなってきている。
たとえ完成に至ったとしても、そのあとにひとりの時間を確保できるのかどうかというのは不透明な状況である。
ところで上記の引用箇所については、最初の2つの「アーティスト」の部分を「思考所の住人」に置き換えても、それなりに意味が通りそうだ。
というより、この本の多くの箇所において、「アーティスト」を「思考所の住人」に置き換えて読んでみると、筆者が考える「思考所」についての巧みな説明になっているような気がする。
なお、「課題」(task)とシンクロニシティの関係について、『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』P.25には以下のようにある。 本書に掲げられているツールを活用し、毎週の課題をきちんとこなしていけば、多くの変化が起こるだろう。
なかでももっとも明らかなのは、シンクロニシティが起こりやすくなることかもしれない。
私たちが変化すると、宇宙がその変化を後押しし、広げてくれるのだ。
私の机の上に貼ってある「飛べ。そうすればあなたを受け止めてくれるネットが現れる」という言葉は、それを端的に言い表している。
ネット云々の箇所は、原文では以下のようになっている。 Leap, and the net will appear.
「ネット上」においては、これは自然主義者のジョン・バロウズの言葉だと信じられているようだ。
ちなみに虫取り網は英語では「butterfly net」あるいは単に「net」である。
シンクロニシティという概念を認めるかどうかは別として、自分の好奇心のおもむくままに行動したり考え続けていたりすると、奇妙な偶然の一致に遭遇する頻度が上がるように感じられるのは確かだ。
無理やり関心を持続させるのは「意識化」の方向で、「ゆだねる」という感覚とは逆である。
「ゆだねる」というのは、好奇心と深い関係にある。
そして「意識化」というのは、義務と深い関係にある。
『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』P.62には以下のようにある。 義務は私たちを無感覚にさせ、興味を失わせるが、神秘は私たちを引きつけ、導いてくれる。創造の井戸を満たすときは、神秘的な感覚を大切にしてもらいたい。
電子書籍(ASIN: B083X758NX )で確認するかぎり、原文では以下のようになっている。 A mystery draws us in, leads us on, lures us. (A duty may numb us out, turn us off, tune us out.) In filling the well, follow your sense of the mysterious, not your sense of what you should know more about.
「義務」(duty)の有害性はそのとおりだが、この本では「課題」(task)をこなすことを要求している。これをどう考えるか。
筆者はこの本の「課題」(task)を一切こなしていない。
ただし、筆者の場合は、少なくとも2021年現在においては、しがらみといえるものがほぼ完全に皆無である。
作業というしがらみ、世間というしがらみを振りほどくことが必要な大部分の人にとっては、この本が指定している程度の義務は、ある種の劇薬として必要になってくるのかもしれない。
なお、上記の箇所は日本語版では重要な要素が抜け落ちているように見える。
上記の「原著」は電子書籍(ASIN: B083X758NX )からのものだから底本が違っている可能性があるし、「訳者あとがき」には「一部、割愛させてもらった」という記載がある。
上記の箇所は原文では、「sense of what you should know more about」ではなく「sense of the mysterious」を追いかけろ、と言っている。
今回、この記事で考える「思考」においては、この部分はかなり重要だ。
「もっと知っておかなくては」という感覚は、思考において邪魔になるのだ。
あれも把握しておかなくては。これも把握しておかなくては。
上記の引用箇所の直前には、 think mystery, not mastery
というフレーズもある。 うまくやろうとせず、神秘を大切にしてほしい
日本語版での訳は
である。
こういうものは一般的な意味での「アーティスト」だけが心得ておくべきことではない。
思考において最も重要なものは神秘的にみえるという感覚、謎めいているという感覚である。
神秘的な感覚と義務を対比的にとらえている箇所をとりあげたが、神秘的な感覚を阻害するものとして「訓練」あるいは「鍛錬」もある。 自己鍛錬はそもそもナルシシズムに根ざしている。自分はこんなにもすばらしいことができるんだと、自分で自分を称賛するのだ。このタイプの人にとっての目的は、何かを作り出したり、成し遂げたりすることではなく、鍛錬すること自体にある。
以下は『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』P.286より。
(中略)
私たちの中にいるアーティストも、軍人と同じように早起きし、朝の静寂の中、タイプライターやキャンバスに向かうかもしれない。しかし、それは厳しい訓練というよりは、子どもたちの秘密の冒険に近いものである。
ここでの「自己鍛錬」や「訓練」は、電子書籍(ASIN: B083X758NX )で確認するかぎり、原文はすべて「discipline」である。
また、「ナルシシズムに根ざしている」の部分は「rooted in self-admiration」である。
この本では、日本語版で同じように「訓練」と訳されていても、違うニュアンスが込められている場合がある。 インスピレーションの流れを、いつも放送されているあらゆる種類の電波として思い描くとイメージしやすいと語る人もいる。私たちは訓練を積むことによって、好みの周波数にチューニングを合わせ、自分のアーティスト・チャイルドの声を親のように聞き分ける方法を学ぶのだ。
例えば、P.228の以下の記述。
ここでの「訓練を積むことによって、」は、「With practice,」となっており、「discipline」ではない。
数学者のグレゴリー・チャイティンは『メタマス!』(2007年刊、原著は2004年発表、原著はPDF版あり)P.211で以下のように書いている。 あなた方は、自分でアイデアを求めようとしない限り、実際に信じることがない限り、それを見つけることができない。
スポーツの場合のように、そのための訓練をする方法はあるだろうか? いや、私はそうは思わない。あなた方は、魔物にとりつかれなければならない。ところが、我々の社会はそのような人があまり多くいるのを望まないのだ。
なお、ここの「訓練」はPDF版で確認する限り、原文では動詞の「train」である。
15歳以上の人間にとっては、訓練とはスパイスにすぎないのだととらえるのも可能だろう。
一切の訓練を経由していないものが強い影響をおよぼすこともあるから、訓練は絶対に必須というわけではない。
牛丼における、七味とうがらしのようなものと考えてみるのもいいかもしれない。
訓練は器でもないし、お米でもないし、牛肉でもない。
あくまでもスパイスなのだ。
そして、どんぶり茶碗いっぱいの七味とうがらしを食べ続けるような日々を送っている人は実際に存在する。
岡田尊司『パーソナリティ障害 いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)では、強迫性パーソナリティ障害の章において以下のような記述がある(P.272)。 このパーソナリティの人は、人生を苦行にしてしまう傾向がある。
また、診断基準として有名なDSMは診断基準以外の解説部分が読み物として面白いのだが、DSM-5の強迫性パーソナリティ障害の項目の解説部分には以下のような記述がある(2014年刊の医学書院から出ている『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』P.671)。 趣味や余暇の活動は, 入念な計画と厳しい仕事を体得するために必要な真剣な課題として取り組まれる. 完璧な行為が強調される. この人達は遊びを組織化された課題に変える (例:幼児が正しい順序に従って輪を棒にかけなかったのを直させる, よちよち歩きの幼児に三輪車に乗り一直線上に走るように言う, 野球の試合を過酷な“授業”に変える).
本人が幸せなら放っておけばいいという見方もできる。
ただし、立場の違いや社会的なステータスを背景にして他人に苦行を強要するようになったり、七味とうがらしを大量に食べない人(あるいは食べ続けた日々というのを経験していない人)には不利益を与えてもかまわないなどと考えるようになると、周囲に大きな苦痛を与える存在となる。
強迫性パーソナリティ障害と強迫性障害は、強い関連があると考えられている。
だが、強迫性パーソナリティ障害は強迫性障害の軽症バージョンではない。
強迫性障害の場合は、本人にも違和感を自覚できる侵入的な強迫症状(強迫観念や強迫行為)が重要なのだが、強迫性パーソナリティ障害の場合は、明確な強迫症状ではなく「規律」と「秩序愛」がベースにあるのがポイントである。
強迫性パーソナリティ障害は、明確に「パーソナリティ障害」といえるほど重くない場合には単に「強迫性パーソナリティの傾向がある」といった表現がなされる。
性格分類のMBTIあるいはMBTIに「似て非なるもの」について詳しい人なら、強迫性パーソナリティの傾向がある人というのは、J型とP型の対比におけるJ型との重なり合いを意識するのではないだろうか。
強迫性障害の場合は、P型でありながら強迫性障害である、というのもそれなりにありそうな気はする。
でも強迫性パーソナリティの傾向がある人というのは、ほとんどがJ型と考えていいのではないだろうか。
一方で、その逆、つまりJ型のほとんどが強迫性パーソナリティの傾向があるといえるのかというと、それはおそらく違うだろう。あくまでもJ型の一部だけが強迫性パーソナリティの傾向を持つ人だ。
また、強迫性パーソナリティの傾向がある人は、xSxJ、つまりS型かつJ型である人が多そうである。
最近では、オンラインゲームにおける「効率厨」といわれる人々の中にも、強迫性パーソナリティの傾向がある人がそれなりに含まれている気がする。
ただし、オンラインでは相手の事情が見えないため、表面的にあらわれる言動だけを見て簡単に判断できると思わないほうがいいかもしれない。
その人がそういう行動をとることには、何か想像だにしないような理由があるかもしれないからだ。
ところで、この「規律」と「秩序愛」は、重篤すぎると孤立化しやすいものの、軽微なものであればタテ社会と相性が良いというのは言うまでもない。
ここで、50年以上前に刊行された中根千枝『タテ社会の人間関係』に着目したい。
この本で、日本の大学について以下のような記述がある(P.92)。 同質のものを序列によって差をつけるから、同僚との連帯意識はきわめて低調で、その代わり、教授・助教授・講師・助手・学生という驚くべき「タテ」の関係によって結びつけられており、教授は同僚の教授より、弟子である講師・助手・学生との関係がより親しかったり、それに重きをおく場合が多い(教授会の内容が外に漏れるということは、この線の機能を示す一つのよい例であろう)。
さらに学生の間では、一年生、二年生、三年生という序列意識が、成績とか能力を越えてまで強くみられるということは、実に日本社会における序列意識の強さを物語るよい例証である。
そういえば今となっては、日本の漫画やアニメの影響で「センパイ」が海外でも通用するらしい。
ただ、日本の漫画やアニメでは、『タテ社会の人間関係』で指摘されているような生々しい「タテ」の論理における「先輩」とは大幅に違っているものが多いかもしれない。
また、英語における外来語としての「senpai」は、生々しい「先輩」とも漫画やアニメの「センパイ」とも違っているかもしれない。
「先輩」や「後輩」という言葉は、ふだんは海外をあまり意識しない日本人にとっても、日本という場と結びついているのではないだろうか。
ほとんどの日本人にとって、「ウィトゲンシュタインはナボコフの先輩なのだ」という言い方は若干奇妙な感じがするはずだが、同じ日本の大学に通った2人の日本人のことについての話だったとしたら、こういった言い回しはごくごく普通のものだ。
なお、『タテ社会の人間関係』は1967年の刊行である。
今でも売れ続けているロングセラーで、英語にも翻訳されて日本社会論の世界的スタンダードになっている。
また、作者の中根千枝は女性初の東大教授としても有名だ。
『タテ社会の人間関係』では「場」と「資格」を対比的にとらえているが、少なくとも2021年現在の日本を見るかぎり、狭義の資格試験の存在がタテ社会という「場」を強化する装置として利用されているように見える。
例えば「君はそろそろ管理者になるべきだから、この資格をとってね」と職場から促されるような場合が非常に多いのである。
この「そろそろ」という言葉にある様々な含み、そして本人がどんなことに興味を持っているのかということとは無関係に「この資格」と職場が指定しているのがポイントである。
そして、組織がどの資格かを指定するにもかかわらず、試験勉強の時間に給料が出ないのは当然という発想が横行する。
また、「そろそろ管理者に」の「管理者」とは最末端の労働者よりもより濃厚な労働者であるともいえる。
この勤務時間外の「勉強」とより濃厚な労働者への「格上げ」を考えると、『タテ社会の人間関係』でいうところの「個人に全面的参加を要求する」(P.65)ために資格が利用されていると言わざるをえない。
浅羽通明『大学で何を学ぶか』のP.89(幻冬舎文庫版P.81)でのサラリーマンをやめて弁護士への転身を決意した大山健児の例では、職場の要請と弁護士資格というのがあまりにもかけ離れている例と言える。
『タテ社会の人間関係』で考えているような「場」と「資格」を対比的にみる視点における「資格」とは、2021年時点の日本においては狭義の資格試験ではなく、例えば「適性」であるように思える。
日本語の「個性」という言葉はあまりにも汚染されているので、あくまでも「適性」あるいは「分類」が重要であることを強調しておきたい。
単に汚染されているというだけでなく、「個性」を「極めて特殊」と同義にとらえ、「適性」や「分類」を覆い隠すための手段として悪用される場合がある。
つまり、「個性」という言葉を巧妙に運用することによって、「適性」や「分類」を無効化しようとする力がはたらいてしまう場合があるのである。
「場」の論理や「タテ」の論理を重視する人にとっては、適性や分類という発想は非常に居心地の悪いものとなる。
逆にいえば、「場」の論理と「タテ」の論理を弱めたいと考えるなら、適性や分類を重視するとよいのだ、と考えることもできる。
特に重要なのが、同質性のためではなく異質性を担保するために適性や分類を利用するものである。
ここで考えているのは必ずしも性格分類だけを想定しているわけではないが、例えば
「各ユニットの構成員は、40パーセント以上がN型であることが必要」
とか、
「各ユニットのリーダーと副リーダーは、片方がJ型で片方がP型でなければならない」
というような制約が有効なのではないか、という発想である。
大組織において適性や分類を重視する発想をトップダウン的に導入しようとした際に当然予測されうる事態としては、「あの人はこういう適性を持っていたのだということにしてしまおう」というように形骸化させようとする力が発生することである。
ところで浅羽通明『大学で何を学ぶか』P.169(幻冬舎文庫版P.152)に、日本の会社になじめない人についての話題を紹介する中で以下のような記述がある。 自殺はまぬがれたものの、一流企業に採用されたエリートが、入社後、数か月、もしくは一、二年で突然退職してしまう例は相当に多いみたいだ。
『大学で何を学ぶか』が出たのは1996年、つまり今から25年前だ。 因みに、近年増加したといわれる転職のケースをみると、その大部分が入社してまもない、たとえば二〜三年内の若年層に集中している。彼らの場合は、まだ社会的資本の蓄積が低く、転職による損失が少ないためである。
そして驚くことに、1967年、今から54年前に出た中根千枝『タテ社会の人間関係』P.56にも以下のような記述がある。
2021年現在においても、こういった議論はよく見かける。
本当に増加しているのかどうか、よく考えたほうがいいだろう。
もしかしたら本当に増加しているという可能性はあるが、少なくとも最近になって増加しはじめたわけではない、ということはいえそうだ。
ところで、思考というものを考えるうえで『タテ社会の人間関係』P.86の以下の記述は気になるところだ。 日本では、表面的な行動ばかりでなく、思考・意見の発表までにも序列意識が強く支配しているのである。
これは、「思考・意見」の発表ということではなくて、「思考」と「意見の発表」ということなのだろうか。
発表はともかくとして、もし「思考」そのものにまで序列の意識が入り込んでいるとしたら、暗澹たる気分になってくる。
思考について、『タテ社会の人間関係』P.170には以下のような記述もある。 このあまりにも人間的な――人と人との関係を何よりも優先する――価値観をもつ社会は宗教的ではなく、道徳的である。すなわち、対人関係が自己を位置づける尺度となり、自己の思考を導くのである。
「対人関係が自己を位置づける尺度」になるというのが筆者にはイメージしにくいが、それがさらに「自己の思考を導く」となると、もはや何を言っているのか分からない。
分からないけれど、これが答えなのかもしれない、という思いもある。
筆者は物理的には日本以外の国に住んだことはないが、ずっと感じていた違和感の答えが、ここにあるのかもしれないのだ。
関係性と思考が一体化している人の発言というのは、筆者からみれば思考というものが存在しない、非常に不気味なものににみえることがあるのである。
発表については、『タテ社会の人間関係』P.177での書き方が面白い。 こうした場合の、学会での反論の仕方をみると、まず、不必要な賛辞(それも最大限の敬語を羅列した)に長い時間を費やし、そのあとで、ほんのちょっぴり、自分の反論を、いかにもとるにたらないような印象を与える表現によってつけ加えたりする。
そういえば、この記事(いまあなたが読んでいるこの「作業所はあるのになぜ思考所はないのか」)も、「不必要な賛辞」は排除したものとなっている。
もし今後筆者がnoteに書く記事あるいはそれ以外の場所において、特定の個人あるいは特定の作品に対して不必要な賛辞を過剰に並べ立てはじめたら、それは「タテ」の論理を意識しているわけではなく、また真剣に感銘を受けたわけでもなく、単に精神的に不安定になっているだけだと考えてもらったほうがよい。
日本のWebサービスにおいては、少なくともQiitaなどではコメント欄で気軽に誤りを指摘することが文化として定着しているように見える。
noteがどうなのかはよく分からない。
Qiitaについては、筆者はあくまでも検索によってQiitaの記事にたどり着くことが多いというだけで、2021年12月時点では筆者自身がQiitaを利用したことはない。
なお、日本のネット史においてはvoid先生(日下部陽一)やモヒカン族が有名であるが、ここでは掘り下げないことにする。
掘り下げることはしないが、一点だけ、ウェブが持つある特性を提示しておきたい。
その特性とは、軽い気持ちで書いた側の「楽しくおしゃべりしてるだけなのに」と、誤りに気付いた側の「そうは言っても、検索でたどり着いた人が誤解するだろう」のギャップが発生しやすいということである。
そして、その誤解の可能性というのが、些細なものなのか重大なものなのかを判断するのはとても難しいということだ。
時々話題になるテーマとして、生後1歳未満の赤ちゃんにハチミツを食べさせてもかまわないかのようにみえる発言をどうすればよいのか、というものがある。
プログラミングなどの技術的な話題に限らず、誤りを指摘「しない」ということが潜在的には犯罪になる可能性すら秘めているのは確かである。
(後編に続く)