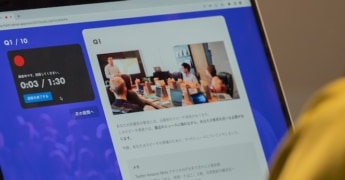急展開のロシア「プリゴジンの乱」「ワグネルの反乱」とは何だったのか
戦略学の視点、3つの考察ポイント- ロシアのプリゴジンによる騒乱、奥山真司氏が3つの視点から考察
- クーデターなのか?プーチン政権への影響は?プリゴジンの目的は?
- 核使用の危機も!? 我々の眼前の出来事を表するレーニンの言葉
ロシアで事態が急展開している。ロシアによるウクライナ侵攻中の2023年6月23日に、ロシアの傭兵部隊ワグネル・グループの創設者であるエフゲニー・プリゴジン(61)が呼びかけた反乱についてだ。
プリゴジン率いるワグネルはモスクワへ進軍、プーチンもこれを「反逆」「裏切り」と非難したが、25日、ベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介で撤退を開始、プリゴジンはベラルーシへ亡命することになった。
あまりの急展開に情報が錯綜しているが、ここでは状況を落ち着いて見る際の、大きな枠組みだけでも以下の3点から提示してみたいと思う。

プリゴジンの乱はクーデターに非ず
第一に、これはいわゆる「クーデター」(coup d’état)ではない、という点だ。
まず今回の事案を整理してみよう。そのきっかけは、単純にいえばロシアの正規軍の代わりにウクライナとの前線で戦っていた傭兵会社(Private Military Company: PMC)であるワグネル社を率いるエフゲニー・プリゴジンが、ロシア政府に使い捨てにされたことに腹を立て、現地6月23日に武装蜂起を宣言して、ロシア軍のウクライナへの侵攻における拠点である南部ロストフ州にある南部軍管区司令部の施設を支配し、同時にモスクワへ向けて進軍を開始した、という事態だ。
この事案が明らかになった当初、日本のSNSやメディアでは「クーデターが起こったのか?」とする意見やコメントが見られたが、拙訳の戦略家エドワード・ルトワック著『クーデター入門』にある定義を参考までに見てみると
国家中枢の小さくても枢要な部分への浸透から成り立ち、この部分を利用し、その政府の支配を置きかえること (p.42)
とある。フランス語では「国家への一撃」 (coup d’état)を示すのだが、今回の事案はとりわけ首都モスクワでプーチン大統領という国家元首のすり替えが(まだ)行われておらず、その実態は武装した傭兵会社が国家のリーダーに反抗したものなので、むしろ「武装蜂起」(armed uprising)や「反乱」(mutiny)という状況の方が正確だと言えるだろう。
もちろん事態の進展によっては、ロシア国民からの支持を受けた「革命」(revolution)や、さらには「内戦」(civil war)にも変化する可能性があったが、「クーデターではない」という点は当初から明らかだったと言える。
定着するかわからないが、個人的には今回の反乱のリーダーの名前をとって「プリゴジンの乱」(Prigozhin Mutiny)と呼ぶのが妥当ではないかと考えている。
プーチン政権への大打撃
第二に、プーチン政権にとって大打撃であるという点だ。
これについては長年に渡ってプーチンを研究しているイギリスの専門家であり、日本でも最近『プーチンの戦争』という訳書が出たばかりのマーク・ガレオッティの意見が参考になる。
ガレオッティによれば、プーチンの政治体制というのは、以下の3つの柱に支えられているという。
- プーチン個人のカリスマ性
- 安保機関の掌握
- 豊富な資金力
こう考えると、たしかにウクライナとの戦争を開始した2022年2月までのプーチンには(2014年の侵攻によって欧米から経済制裁を受けていたが)3つとも揃っていたと言える。
ところが今回の戦争でそれらが失われ、プーチン政権は第一次大戦に参戦したロシア帝国のような「脳死」の状態になっていると解説している。
もちろんその「脳死状態」でロシア帝国は3年も戦い続けたという史実についてはガレオッティも認めており、そういう意味では今のプーチン政権も無能をさらけ出しながらも戦争を続けるだろうと予測している。なぜならプーチンは個人的に東独とソ連という2度の「政権崩壊」を経験しており、その際に「政権側の意志の強さ」がなかったためだと結論づけたからだと言う。
もちろんこの分析は妥当だと考えるが、今回のように急速に事態が動き、エルドアンのようにすぐに声明を出すことができず(のちに緊急声明を発表)、しかもモスクワから脱出したとさえ報道されてしまった後で、果たしてプーチンが「強い意志」をリーダーとして示すことができるのか疑問だ。
事態がどのように収束するにせよ、プーチン個人として今後の政権運営はよほどの締付けを行わない限り打撃から立ち直れないように思える。
プリゴジンは何をしたかったのか
第三に、プリゴジンの戦略のなさである。
今回の事案においてもエンドステートというか、その戦略目標というものが反乱を起こしたプリゴジンから見えてこない。
当初はロシア軍参謀総長であるワレリー・ゲラシモフ(67)と、国防長官のセルゲイ・ショイグ(68)を名指しで非難するコメントを繰り返していたのであり、プーチン大統領を直接非難するようなことは行っていなかった。

ところが2日目になって録画で声明をようやく発表したプーチン大統領に「裏切った」と非難されたことにより、完全に敵視されてしまったプリゴジンはプーチン(政権)を倒すことしかオプションがなくなっていた。
つまりこれは、ワグネル率いるプリゴジンにとって、モスクワ入城からの首都制圧、そしてクーデターに失敗すれば、内乱か破滅しか残っていなかった、ということになる。
また、これは一見するとロシアに侵攻されているウクライナにとって有利に働くように見えるのだが、たとえば仮にワグネルを率いるプリゴジンがプーチンに代わって政権を担ったとしても、プリゴジン自身はロシアの戦争のやり方を「生ぬるい」と考えていた超タカ派であることを忘れてはならない。
そういう意味では、プーチンが政権についていたほうがまだ良かった、という事態にもなりかねない皮肉な状態となる可能性もあった。
核使用の危機もあった!?
1995年の「クリムゾン・タイド」という映画では、ロシアでチェチェン紛争をきっかけとした反乱が勃発し、超民族主義者であるウラジーミル・ラドチェンコの武装勢力が日米を核攻撃すると脅迫するというシナリオがあった。これに対してアメリカ政府はオハイオ級原子力潜水艦「アラバマ」を出撃させ、その内部での葛藤を描いたサスペンスだったのが、まさに今回の事態は、流れによってはプリゴジンがラドチェンコのような存在になる可能性もあった。
また、ワグネルに対して「ロシア国内で」戦術核が使用される可能性もあった。というのも、パキスタンが持つとされる「インドが領内に侵入してきたら使う」というドクトリンが存在するからだ。ワグネルに対して核兵器を使うというのは荒唐無稽かもしれないが、追い詰められたプーチンが「国内であれば」と判断して使用してしまうような事態は考え過ぎとは言えないだろう。
かつて革命家レーニンは、「何も起こらない数十年間があると思えば、数十年分のことがたった数週間で起こることもある」という印象的な言葉を残しているが、いま我々の眼の前で起こっているのはまさにこのようなこと、なのかもしれない。事態はプリゴジンの亡命で一応の収束を見たが、その余波が何をもたらすか、注視したい。
(2023年6月25日昼現在)
■
奥山真司さんが翻訳を手がけた新刊「デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突」(飛鳥新社)、好評発売中です。
【編集部より】本記事は26日午前9時ごろからは会員限定の公開になります。
- 違法に北朝鮮で撮影された12枚の写真がとにかく恐ろしすぎたAD(ティップアンドトリック)
- 琉球王家の現当主、沖縄復帰50年で初めて見解示す。八重山日報が歴史的独占手記政局・政策
- 「二重国籍」騒動、河野太郎氏がブログで真意「議論する余地がある」政局・政策
- “世田谷自然左翼”な区長に伏兵襲来!自民・維新が区長選に29歳元財務官僚擁立政局・政策2023年02月20日
- コンビニでタバコのカートン買いは大損!喫煙者が知らない超意外な”盲点”AD(DR.STICK_typex)
- 一瞬で崩壊した夫婦愛…妻の自撮り写真が原因?AD(ティップアンドトリック)
- 5%減税でも…名古屋市の市税収入増加に注目。河村市長「減税で経済を盛り上げる」政局・政策2022年05月17日
- いじめと総裁選のW衝撃...旭川市長選で自民系候補圧勝の衝撃政局・政策2021年09月27日
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ
ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ 「強訴」「御所巻」…ワグネル撤兵に日本史ワードが話題に
「強訴」「御所巻」…ワグネル撤兵に日本史ワードが話題に 全局“テレ東化現象”…日本の地上波テレビ、ロシア・ワグネル武装蜂起で終日特番なし
全局“テレ東化現象”…日本の地上波テレビ、ロシア・ワグネル武装蜂起で終日特番なし “キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか?
“キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか? 初の税収70兆円?思わぬ税収増が政局に与える影響、最後に笑うのは誰だ
初の税収70兆円?思わぬ税収増が政局に与える影響、最後に笑うのは誰だ ミツカン父子引き離し事件:辣腕弁護士が尋問で暴いた創業家会長の傲慢
ミツカン父子引き離し事件:辣腕弁護士が尋問で暴いた創業家会長の傲慢 ワグネル武装蜂起の2日前、ロシア政府系メディアが「本能寺の変」ツイート
ワグネル武装蜂起の2日前、ロシア政府系メディアが「本能寺の変」ツイート ロシアの日本人63人“出禁リスト”、笑えるところと笑えないところ
ロシアの日本人63人“出禁リスト”、笑えるところと笑えないところ フジテック前会長の弁護士は13兆円勝訴のレジェンド、香港ファンドのモサド式(?)情報戦を論破
フジテック前会長の弁護士は13兆円勝訴のレジェンド、香港ファンドのモサド式(?)情報戦を論破 大谷に朗報!MLBが今季から両リーグでDH制へ、日本のセ・リーグでも導入なるか⁉
大谷に朗報!MLBが今季から両リーグでDH制へ、日本のセ・リーグでも導入なるか⁉
 “キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか?
“キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか? 部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ
ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ 「24時間、僕の社長室は3シフト制」ソフトバンク孫正義社長の発言が話題
「24時間、僕の社長室は3シフト制」ソフトバンク孫正義社長の発言が話題 マイナンバーカード問題:河野デジタル相の踏ん張り時、騒ぎすぎのメディアに負けるな
マイナンバーカード問題:河野デジタル相の踏ん張り時、騒ぎすぎのメディアに負けるな 安倍元首相、布石を打ち始めていた共同親権
安倍元首相、布石を打ち始めていた共同親権 上田清司、猪瀬直樹…参院決算委で見せた知事経験者の質問力、やはり参院は“貴族院”たるべし
上田清司、猪瀬直樹…参院決算委で見せた知事経験者の質問力、やはり参院は“貴族院”たるべし 安全保障対話の意義:なぜ日米中の防衛トップが「シャングリラ・ダイアローグ」で一堂に会するのか
安全保障対話の意義:なぜ日米中の防衛トップが「シャングリラ・ダイアローグ」で一堂に会するのか 維新の候補者集めが話題、鳩山ジュニアや河村ジュニアより本当に面白いキーパーソン
維新の候補者集めが話題、鳩山ジュニアや河村ジュニアより本当に面白いキーパーソン 「強訴」「御所巻」…ワグネル撤兵に日本史ワードが話題に
「強訴」「御所巻」…ワグネル撤兵に日本史ワードが話題に
 【特報】文春もひろゆきも言わない岸田翔太郎の真実 〜 首相公邸「寝そべり写真」なぜ流出したのか?
【特報】文春もひろゆきも言わない岸田翔太郎の真実 〜 首相公邸「寝そべり写真」なぜ流出したのか? “キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか?
“キャンドル・ジュン式”記者会見で、望月衣塑子を撃退できるか? エマニュエル大使は内政干渉か?政女・浜田氏の質問に日本政府の見解は…
エマニュエル大使は内政干渉か?政女・浜田氏の質問に日本政府の見解は… 信託型ストックオプション“大増税”騒ぎ、ほとばしる国税と日経の「後出しジャンケン」
信託型ストックオプション“大増税”騒ぎ、ほとばしる国税と日経の「後出しジャンケン」 部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か
部活推薦は「地獄への道」〜 工学部の入試に“アスリート枠”は必要か ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 望月衣塑子記者の国会不規則発言問題、朝日新聞が“論点そらし”で自民・世耕氏に矛先
望月衣塑子記者の国会不規則発言問題、朝日新聞が“論点そらし”で自民・世耕氏に矛先 ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ
ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ 「マイナンバーカード、全預貯金口座と紐づけ義務化」…2年前の記事が突如バズったワケ
「マイナンバーカード、全預貯金口座と紐づけ義務化」…2年前の記事が突如バズったワケ ストックオプション“大増税”騒ぎ、スタートアップ側の「記者顔負け」国税への“追及”シーン再録
ストックオプション“大増税”騒ぎ、スタートアップ側の「記者顔負け」国税への“追及”シーン再録
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間