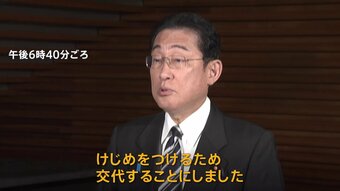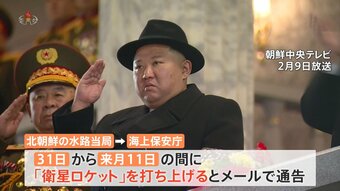「ハードは同じものでソフトを更新することでハードの性能域を変えていく」
EVへのシフトという点で中国に水をあけられた日本だが、今までの自動車がEVに変わるということは、エンジンがモーターに変わるとか、ガソリンタンクが電池に変わるとか、そういったハードの変化ではなく、車の作り方、使われ方が変わる産業革命で、日本の産業構造そのものがEVに対応していないことが問題だと語るのは、かつて日産自動車でCOOを務めた志賀俊之氏だ。

元日産自動車COO 志賀俊之氏
「EVが出遅れてる現象に目が行きがちだが、今起きているのは車の作り方使われ方が変わる産業革命。今、世界の新しいEVというのは“SDV(ソフトウエア・ディファインド・ビークル)”と言ってソフトウエアが車の性能を定義する。私たちの時代は機械工学部出身のエンジニアがメカニカルな物を作るのがクルマ作りだった。SDVは、ハードは同じものでソフトを更新することでハードの性能域を変えていく…いま工学部出身のエンジニアがソフトも開発するように勉強する。産業構造の変革なんです」
日本の自動車は、定期的にモデルチェンジし、性能や機能を変えると同時に装備やデザインを変えることで新車を売り、下請けの部品メーカーも新しい仕事を受注していた。
しかし、例えば『テスラ』はモデルチェンジをしない。何年たってもハードはほとんど変わらない。だが、ソフトウエアは随時、最新のものに更新され性能は向上していく。こうしたクルマ作りに日本の自動車業界の構造が適応していけるのだろうか。
自動車アナリスト 中西孝樹氏
「(EVかその他か)迷う必要はないんです。マルチソルーションと言われる全方位に世界は最終的になっていく。だから日本が全方位を掲げるのは何ら間違いでない。ただ目的化してはいけないんです。目的はあくまでカーボンニュートラルで、全方位は手段なんです。結果として全方位になるんですが、物事には順番というのがあって、まずEVが来てそのあと燃料電池、そしてカーボンニュートラル燃料のようなモノが来て水素なんです。順番を違えず、2-3年の迷いがいまの差になっているだけなので、まずはEVを日本のものにするそれが大事なんです」