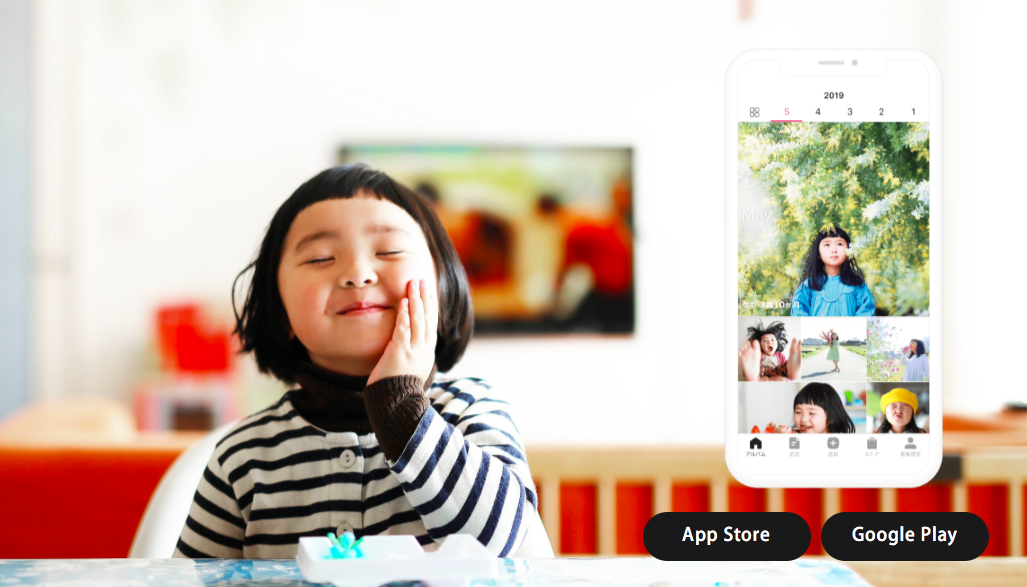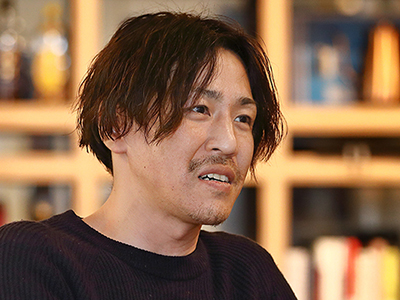新型コロナウイルスという未曾有の危機は、「社会にとって企業がどんな存在であるべきか」を問い直すきっかけももたらしている。
安倍首相が全国一斉休校を発令した2月末以降、食材宅配や学習塾など、さまざまな分野の事業者が「サービスの一部無料提供」を次々と打ち出していったことは記憶に新しい。あるいは、独自の基金を立ち上げて、特定の団体へ寄付を届ける企業の動きも見られた。
そんな中、独自に支援先のNPOを選考し、具体的なプロジェクトを指定した上で必要な資金を届けるという活動を始めたのが、ミクシィ創業者で現在は会長を務める笠原健治さんだ。同社のVantageスタジオが提供する家族向け写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」の社会貢献プロジェクトとして、4月13日に「みてね基金」の設立を発表した。
基金設立にあたって、笠原さんは、個人資産から10億円の資金提供。設立の動機となったのは、5年前に「みてね」をリリースして以来感じてきた、「家族の絆を感じられる価値」だった。
実績あるプレイヤーを基金で後方支援
「もともと『みてね』を開発したのは、僕自身が親となり、家族の利用に限定した写真・動画共有ができたらいいな、と求めたから。ユーザーとして使っていくうちに、子どもが愛情を感じて喜ぶ姿や、その喜びが健やかな成長につながる実感を得てきました。
この価値をより多くの人に届けられないだろうかと考えた結果、外部のソーシャルセクターを支援する基金の構想がまとまったんです。たまたまコロナ発生の時期と重なりましたが、昨年冬頃から準備していました」
日本に先んじてロックダウンを実施した欧米のユーザーの家族間コメント投稿数が、通常の2倍強になったことからも、新型コロナによって、家族を支援する事業の社会的価値を再確認できたのだという。
企業が社会に貢献する方法には、いくつかの選択肢がある。同社はコロナ禍の家族支援として、有料サービスの一部無料開放も実施してきた。
しかし、笠原さんは、あえて自社の新規事業に狭めず、“外部の団体とつながる”方法として基金設立を選んだ。
「自社の事業を成長させることも、家族の絆を深める価値提供につながると自負しています。しかしながら、それだけでは届かない人たちにどう届けるか。その回答として、多様な社会事業ですでに実績のあるプレイヤーの皆さんを後方支援する役割を選びました」
6月までに実施した第1期の活動として、国内53、海外14の計67ものNPOへの支援完了を報告。
特定非営利活動法人ウィーズの「虐待防止のためのシングルマザーLINE相談事業」に500万円、社会福祉法人むそうの「医療ケア児の在宅療育開発プロジェクト」に1000万円など、それぞれの課題に応じた支援を行い、累計金額は4億円を超えた。
いずれも「新型コロナウイルス感染症に伴う 子どもやその家族に関する困りごと支援への助成」と位置付けられている。
社会と有機的につながり、相互に持続可能なレバレッジを効かせる。それが新しい企業の役割なのだという。笠原さんは何度も「困ったときはお互いさま」という言葉を発した。
「少しでも明るい話題を」と個人資産10億円提供
東京大学在学中だった1997年に求人サイトを立ち上げ、2004年には日本版SNSとして爆発的な人気を博した「mixi」を立ち上げた。2012年3月には月間ユーザー数1500万人超に達し、時代の寵児ともてはやされた笠原さんが今、「社会」に目を向けるのはなぜか。
「一つは、2011年の東日本大震災で得た気づきが大きいです。当時、電話やメールがつながらない被災者の方々のために立ち上げたmixiコミュニティや、ユーザーの皆さんから集めた義援金活動を通じて、社会における存在価値を再認識できました。緊急時に支援に動ける企業がアクションを起こし続ければ、平時にも“お互いさま”の行動が広がるきっかけになるのではないかと思うんです」
加えて、「みてね」の欧米での展開で身についたグローバル視点の影響も大きいという。
「欧米では、社会が困窮している事態において企業が何らかの行動で意思表示するのは当然と思われている。何もしないことは事業上のデメリットにもなり得る。海外に向けても、4月時点で100万ドルの寄付を実施しました」
基金の元手として10億円もの個人資産を提供したのは、「少しでも明るい話題になればと思って」と控えめに語る。
企業だからできる柔軟な支援がある
選考にあたってのオンライン面談には、笠原さんも自ら参加し、団体の活動目的や実績についての質問をした。
「支援先として選んだのは、地域密着型で地道に活動を行ってきた団体です。また、オンライン化やそれに向けての研究開発など、新たな取り組みに挑戦しようとする活動への支援もしたいと考えました」
一般的に、オンラインや活動のフィールドが海外になる事業は、政府による助成の対象外になる傾向があると、NPOなどへのヒアリングから実感していたという。そんな事情からチャレンジに足踏みしていたNPOの背中を押す。民間だから可能になる柔軟な支援が、自らに求められている役割だと考えている。
「例えば、難病の子どもたちを支援する団体では、コロナの影響で訪問型のサービス提供ができなくなっていた。そこでオンライン面談を試してみると、当事者のご家族にとても喜ばれたそうです。
この手法が本格的に導入できれば、支援できる子どもたちの対象はもっと広がる。すでに行っている取り組みを伸ばすのも大事ですが、未来志向の“開発”の部分に投資することも同じくらい大事だと考えます。これは事業家ならではの目線なのかもしれないですね」
家族限定という「閉じた空間」の理由
インターネットの恩恵を、社会課題解決に向けて生かしていく。笠原さんの頭にはそんな価値体系が染み付いているようだ。匿名による誹謗中傷がネット上で問題化する中、「みてね」では「家族限定」(招待制によって自由に設定可能)という“閉じた空間”での安心感を担保しているのが特徴だ。
「今後は、支援先のNPOの活動を紹介する取材レポートを『みてね』ユーザーに向けて発信していきたい。サポートが必要な人たちの存在を広く知らせていくことで、より多くの人のアクションのきっかけになればうれしい」
かつて「mixi」の最大の特徴とも言われた機能、閲覧者が分かってコミュニケーションを促進する「足あと」に象徴されるように、笠原さんがネット空間でこだわってきたのは“人のつながりの可視化”や“安心できるコミュニケーションの促進”なのだろう。「みてね基金」もまた、その延長上にある。
お互いさまのカルチャーを育む歩み止めない
第2期の時期は未定だが、中長期的に続けていく方針を決めている。
「社会を明るくする事業を引き続き伸ばしていく。一方で、事業だけではカバーできない部分も積極的に補っていく。社会貢献は当たり前の行動として、事業と両輪でやっていきたい」
みてね基金の実施から得られた手応えとして、笠原さんは「実は社内の反応が一番うれしかった」と答えた。
「『自社のサービスがこういう行動をするのが誇らしい。自分も関わりたい』と賛同してくれる社員が多かったんです。事務局も有志の力であっという間に立ち上がって。僕の勝手な行動を応援してくれるのが、ありがたかったですね。特に若い世代は共感してくれました。
正直、手間のかかるプロジェクトではあるのですが(笑)、社内でも社会でも“お互いさま”のカルチャーを育む歩みにしていきたいと思います」
(文・宮本恵理子、写真・稲垣純也)