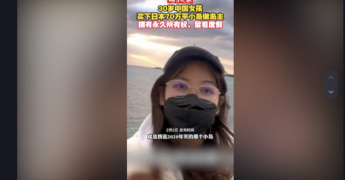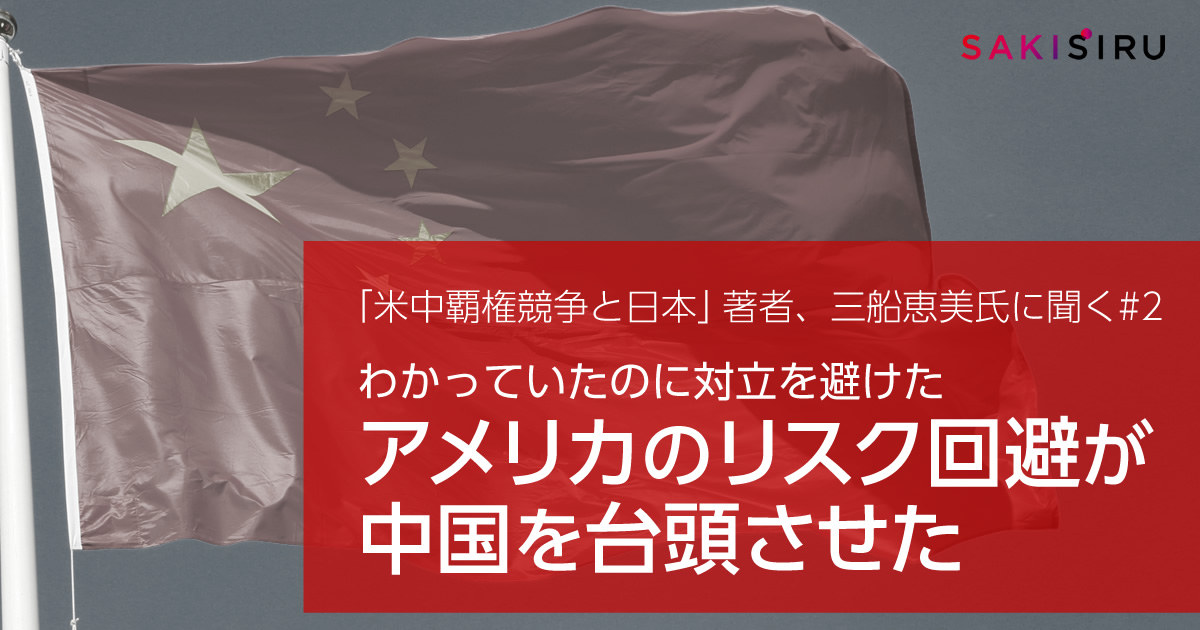台湾有事より怖い中国問題とは?『デンジャー・ゾーン』が教える本当の危機
ビジネスリーダー必読の「対中戦略」- アメリカが中国に今後どう臨もうとしているのか?
- 台湾問題は刺し身の「ツマ」?より本質的な危機とは
- ワシントンに広がる新たな対中認識、日本に迫られる選択
バイデン政権、そしてその次のアメリカの政権は、いまや最大のライバルとなった中国に対してどのような姿勢で臨んでいくのだろうか?
この質問は、現在の日本の人々、とりわけ台湾有事を考えなければならない防衛関係者たちだけでなく、日本のビジネス界のリーダーたちにとっても無視できないほどの、致命的な重要性を帯びたものになってきている。

決定的な「戦略文書」
この質問にダイレクトに答える本が2022年8月にアメリカで出版され話題になり、それを本稿の著者である私が翻訳したものが日本で出版された。ハル・ブランズとマイケル・ベックリーという若手の研究者たちによる『デンジャー・ゾーン』(飛鳥新社)という本だ。
この本の概要を一言でいえば、それは今後数十年間続くアメリカの対中戦略の指針を示した、決定的な「戦略文書」である。その最大の理由は、本書が戦略を提唱する本や文書によく見られるような2つの構成、つまり「現状はこうである」という問題認識を踏まえつつ、その解決法として「だからこうすべきだ」という方針を提案しているからだ。
第一の柱:中国がもたらすリスクとは
ところがこの本の帯にも見えるように、日本の独特な関心からか、日本では本書の序章に出てくる「台湾有事」のシナリオだけがフォーカスされがちである。ところが本書における台湾有事に関する議論は刺し身の「ツマ」程度のものでしかなく、やや誤解を生みがちだ。
そこで、かなり宣伝めいた形になってしまうが、今回は誤解されがちで見えなくなってしまいがちなこの本の主張の核心や、その議論のロジックなどについて、簡潔に解説してみたい。
では本書の「第一の柱」は何か。それは、中国が何を狙っており、しかもどのような行動をする可能性が高いのかを、一つの明確な「モデル」として描くことだ。
具体的には、中国は世界覇権を狙うほどの野心を持っているのだが、実は国力がピークを迎えており、それが落ち始めたと実感するために冒険主義に出る、というものだ。

本当の危機は別にある
これまでの学者やジャーナリストたちの間では、中国はいずれアメリカを追い抜くことになる、というものや、その優位が過去の大国同士の間で行われたような「覇権」の交代時に起こる戦争を誘発することになる、という意見が多かった。
そのようなロジックを提唱したものとして代表的なものは、ハーバード大学教授を長年つとめるグレアム・アリソンによる『米中戦争前夜(Destined for War)』(ダイヤモンド社)という2015年の本の中で強調された「ツキュディデスの罠(Thucydides’s Trap)」という概念だった。
ところが本書では、そのような「罠」は実態を反映しておらず、よく調べてみると成長のピークに直面した大国が「まだチャンスがある」と実力を過信して、焦って冒険主義的に軍事拡大を行ってしまう例が大半だと指摘する。
その実例として、原著者であるブランズとベックリーたちは1930年代の大日本帝国の例や、第一次世界大戦までのドイツ帝国の例、そして現在のロシアの例を挙げつつ、そのようなピークを迎えた大国の、落ち始めの焦った期間が危険になるとしているのだ。
そしてこの「焦った危険な期間」こそが、本書のタイトルである「デンジャー・ゾーン」ということになり、どこかの地理的な場所(もしくは映画トップガンの挿入歌)を示しているのではなく、時間軸のフェーズを表しており、これが2030年代のはじめ頃まで続くとしている。
つまりこの「戦略本」の前半では、中国の現状分析とそれがもたらすリスクについて、一つの明快なモデルを示すのだ。
第二の柱:米中競争は「短距離走」
「第二の柱」は、そのような中国との戦略的な競争のやり方については、アメリカは過去の具体例について学べる、としていることだ。そしてその実例とは、第二次大戦後の冷戦初期にソ連と対峙した、トルーマン政権(1945-53年)の行動である。
とりわけ原著者の一人であるハル・ブランズは冷戦期の歴史を得意とする学者であり、この時期のトルーマン政権が、戦後の混乱期にソ連に対抗するためにマーシャルプランによる欧州への大規模経済投資や日本の国際社会への復帰の支援、そして朝鮮戦争への対応などによって「ソ連封じ込め」に迅速かつ大胆に動いたことを評価しており、この短い期間の動きが、後に長期化する冷戦における西側の優位を決定づけたとしている。
そしてこの例にならって、現在中国に対峙しはじめたアメリカは「マラソン」のような長距離走ではなく「短距離走」で優位を築いておけ、そのためにはここ5年から10年が勝負だ、というのだ。そしてこの短距離走を戦うための戦略を「デンジャー・ゾーン戦略」と名付け、そのための原則を明快に提示している。
ここでの「マラソン」(marathon)というのは、アメリカのシンクタンク、ハドソン研究所で長年中国を研究していて、過去に共和党政権にアドバイスをしていたマイケル・ピルズベリーが2017年に『China2049(The Hundred-Year Marathon)』(日経BP)の中で主張した概念だ。アメリカと中国との戦いは「百年マラソンになる」ということだが、これはワシントン界隈でもすでに広く知られている。
ところがブランズとベックリーは、「マラソン」ではなく「短距離走」(sprint)を戦えと提案しているのだ。

ワシントンに広がる新たな対中認識
実は以前に、私はバイデン政権を仕切る「戦略的競争派」を紹介し(参考)、この派閥の中に、原著者のブランズとベックリーらも属していると説明したが、彼らがさらに発言権を持ってきたその動きの一端は、アメリカの連邦議会でもよく見られるようになった。

2022年11月の下院の改選で多数派に返り咲いた共和党だが、彼らは翌年1月に議会に戻ると、さっそく「中国特別委員会」(正式名称は「アメリカと中国共産党の戦略的競合に関する米国下院特別委員会」)を創設している。そしてその委員長には、マイク・ギャラガーという38歳のウィスコンシン州選出の共和党の下院議員が就任している(参考)。
彼は冷戦史で博士号を取得した後に、海兵隊の士官としてイラクでの戦闘にも参加しており、政治家としてはすでに4期目を務めている若手の注目株だ。そしてこの彼が、メディアの前で何度も中国との「マラソン」競争に 勝つためには、 今すぐ「短距離走」に 勝たなければならない。
という発言を行っている。そして注目すべきは、この下院議員のギャラガーが中国との競争を言い表すのに「マラソン(marathon)」ではなく、ブランズやベックリーのように「短距離走(sprint)」という表現を使っていることだ。
ギャラガーのこの委員会の就任について書いたワシントン・ポスト紙の保守派の名物コラムニストであるジョージ・ウィルによれば、これはまさに『デンジャー・ゾーン』の世界観に一致しているのだ(参考)。
実際のところ、つい先日私が著者の一人であるベックリーにインタビューをした際、彼らは「頻繁にワシントンの連邦議会に呼ばれて議員に説明を行っており、米国防総省(ペンタゴン)でも2人でブリーフィングしてきたばかりだ」と言っていた。
端的にいえば、『デンジャー・ゾーン』で示されている対中戦略は、ワシントン周辺でかなり共有されているといえる。
日本が迫られる厳しい「選択」
このような性格の本書であるが、日本への示唆はどのようなものだろうか?
実際に著者らにインタビューをしてみると、日本が行っている対中戦略への評価は高いことがわかった。だがその方向性は良いとして、やはり有事などへの備えに対する日米両国の全体的なペースが遅いことには満足していない様子であった。
また、本書を読んでみればわかるように、この戦略がさらに追求されることになると、日本の経済的な立場が苦しくなることも容易に予想できる。

とりわけ日本にとっては後半の第七章で提案されるデジタル面での対中戦略がさらに進展すると、たとえば半導体などの先端技術や戦略物資、知的財産などをめぐる争い(デカップリング)に巻き込まれる形で、経済安保面での運営が厳しくなるはずだ。
その意味では、本書は日本について安全保障の面だけではなく、経済面でも財界に厳しい選択が迫ってくる見通しを立てており、無視できるものではない。
未来を見通すための「必須文献」
繰り返しになるが、本書において注目されがちな、序章の「台湾有事のシナリオ」は、たしかに参考になるものかもしれないが、それは本書の本質的な論点ではない。
その本質は、現在のアメリカにおいて実際に政府の戦略文書を執筆するような立場にある若手の学者や戦略家の考えが、実に明確に提示されている点だ。
そしてアメリカの今後数十年を含む対中方針、少なくともバックにある考え方やロジックを教えてくれるという意味で、実に示唆に富む戦略文書だということだ。
私は単なる訳者でしかないが、これからの日本の未来を考える上で、あらゆる分野のリーダーたちに本書をぜひ読んでいただきたいと、心の底から思っている。
■
【編集部より】本記事は28日昼過ぎまで特別に無料公開します。
奥山真司さんが翻訳を手がけた新刊「デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突」(飛鳥新社)、好評発売中です。
関連記事
編集部おすすめ
ランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
 参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に
参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に 河野さん大丈夫? TikTokがデジタル庁と連携でマイナンバー啓発動画、小林前経済安保相も疑問
河野さん大丈夫? TikTokがデジタル庁と連携でマイナンバー啓発動画、小林前経済安保相も疑問 後藤田正純氏まさかの落選で、妻・水野真紀さん「意味深」ブログ
後藤田正純氏まさかの落選で、妻・水野真紀さん「意味深」ブログ 奈良県知事選で維新の勝利が現実味…自民は高市氏の失態で保守分裂も、大幹部は敢えて静観か
奈良県知事選で維新の勝利が現実味…自民は高市氏の失態で保守分裂も、大幹部は敢えて静観か 「屋那覇島が人民解放軍の橋頭堡に」沖縄の無人島“空騒ぎ”で笑うのは誰か
「屋那覇島が人民解放軍の橋頭堡に」沖縄の無人島“空騒ぎ”で笑うのは誰か ロッテリア売却の背景、グループ創業者長男が示した「懸念」
ロッテリア売却の背景、グループ創業者長男が示した「懸念」 橋下氏、宗男氏の炎上やまず…やっぱりロシアが維新の「鬼門」だった
橋下氏、宗男氏の炎上やまず…やっぱりロシアが維新の「鬼門」だった “世田谷自然左翼”な区長に伏兵襲来!自民・維新が区長選に29歳元財務官僚擁立
“世田谷自然左翼”な区長に伏兵襲来!自民・維新が区長選に29歳元財務官僚擁立 「ハマのドン」藤木会長、横浜市議に「まとめて火を付けようかと思ってる」と発言していた
「ハマのドン」藤木会長、横浜市議に「まとめて火を付けようかと思ってる」と発言していた 20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
20年前に殺害された国会議員の資料にネット注目。鳩山氏が「入手」
 「出来レース」「陰謀論やめて」Colabo問題、川松都議と小池氏側近が舌戦
「出来レース」「陰謀論やめて」Colabo問題、川松都議と小池氏側近が舌戦 Colabo問題、都議会で自民が追及するも、小池知事は福祉保健局長に“丸投げ”
Colabo問題、都議会で自民が追及するも、小池知事は福祉保健局長に“丸投げ” 奈良県知事選で維新の勝利が現実味…自民は高市氏の失態で保守分裂も、大幹部は敢えて静観か
奈良県知事選で維新の勝利が現実味…自民は高市氏の失態で保守分裂も、大幹部は敢えて静観か 参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に
参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に 日本人が知らないウクライナの国民感情…「まずは停戦論」はなぜ間違っているか
日本人が知らないウクライナの国民感情…「まずは停戦論」はなぜ間違っているか ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !?
ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体がついに判明 !? 橋下氏、宗男氏の炎上やまず…やっぱりロシアが維新の「鬼門」だった
橋下氏、宗男氏の炎上やまず…やっぱりロシアが維新の「鬼門」だった 4年前は音喜多氏を撃退、東京・北区長選、無双の“米寿”区長に2つの死角
4年前は音喜多氏を撃退、東京・北区長選、無双の“米寿”区長に2つの死角 “世田谷自然左翼”な区長に伏兵襲来!自民・維新が区長選に29歳元財務官僚擁立
“世田谷自然左翼”な区長に伏兵襲来!自民・維新が区長選に29歳元財務官僚擁立 河野さん大丈夫? TikTokがデジタル庁と連携でマイナンバー啓発動画、小林前経済安保相も疑問
河野さん大丈夫? TikTokがデジタル庁と連携でマイナンバー啓発動画、小林前経済安保相も疑問
 【特報】沖縄・屋那覇島の中国人買収騒動、元所有者の証言から浮かぶ“きな臭さ”
【特報】沖縄・屋那覇島の中国人買収騒動、元所有者の証言から浮かぶ“きな臭さ” 沖縄最大の無人島、中国人が買収?女性起業家の投稿がバズるも、日本では警戒論
沖縄最大の無人島、中国人が買収?女性起業家の投稿がバズるも、日本では警戒論 日銀総裁人事 “誤報”、「日経テレ東大学」閉鎖…日経は大丈夫なのか?
日銀総裁人事 “誤報”、「日経テレ東大学」閉鎖…日経は大丈夫なのか? Colabo問題、小池都知事に直接“追及”へ 自民・川松都議が見通し
Colabo問題、小池都知事に直接“追及”へ 自民・川松都議が見通し 原英史氏、森ゆうこ氏に二審も勝訴!判決で全否定された毎日新聞の「新証拠」とは?
原英史氏、森ゆうこ氏に二審も勝訴!判決で全否定された毎日新聞の「新証拠」とは? ロッテリア売却の背景、グループ創業者長男が示した「懸念」
ロッテリア売却の背景、グループ創業者長男が示した「懸念」 「出来レース」「陰謀論やめて」Colabo問題、川松都議と小池氏側近が舌戦
「出来レース」「陰謀論やめて」Colabo問題、川松都議と小池氏側近が舌戦 Colabo問題、都議会で自民が追及するも、小池知事は福祉保健局長に“丸投げ”
Colabo問題、都議会で自民が追及するも、小池知事は福祉保健局長に“丸投げ” 参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に
参院選比例個人票、東京・港区ではガーシー氏が“トップ当選”で話題に 山口県は北朝鮮か?岸信千世氏のHP「家系図」炎上、問われる世襲政治
山口県は北朝鮮か?岸信千世氏のHP「家系図」炎上、問われる世襲政治
人気コメント記事ランキング
- 週間
- 月間