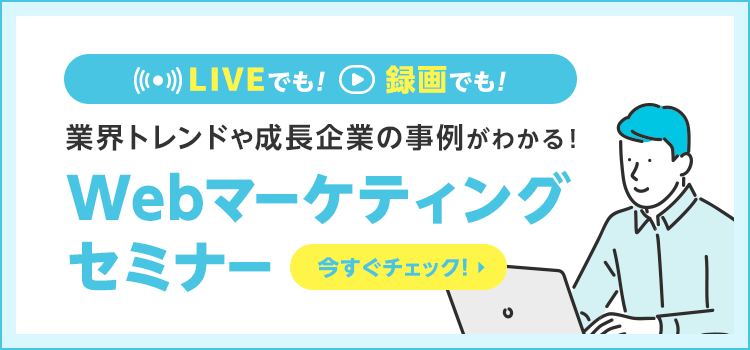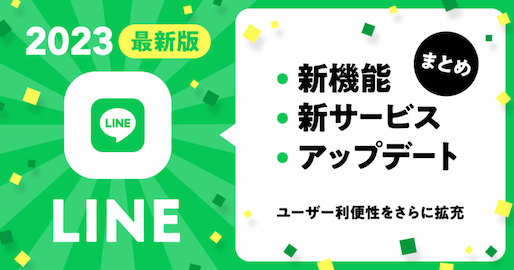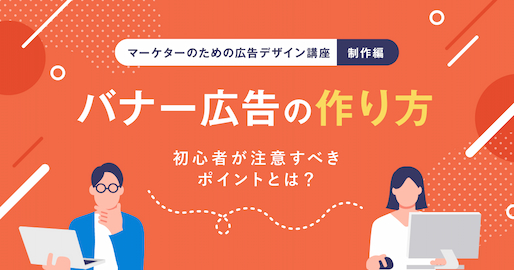近頃耳にする「分散型SNS」「連結型SNS」という言葉。その意味をご存知ですか?今回は2023年注目キーワードとして「分散型SNS」の意味や特徴、注目されている背景について解説します。
おすすめの資料
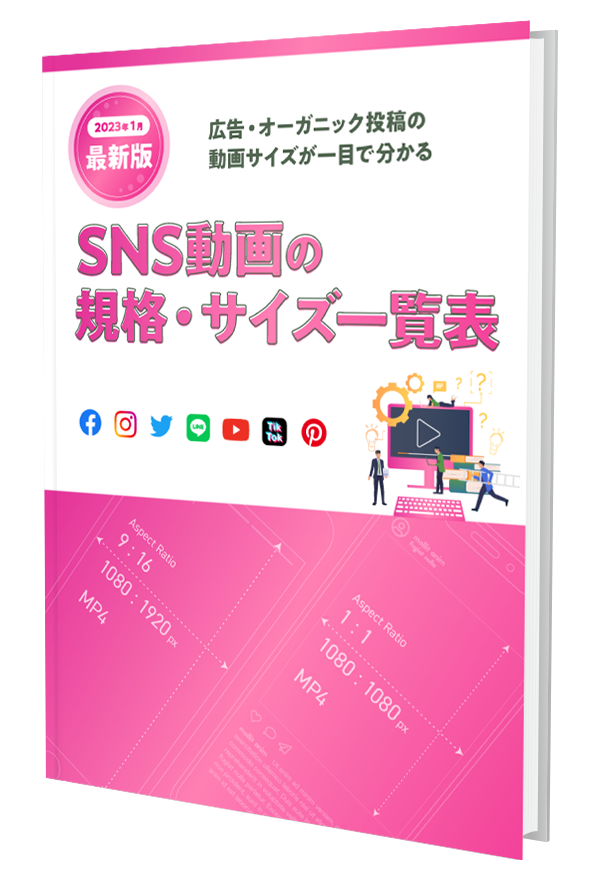
【2023年最新版】SNS動画の規格・サイズ一覧表
~広告・オーガニック投稿の動画サイズが一目で分かる~
広告出稿とオーガニック投稿の2つの場合に分けて分かりやすく表にしています。
これからSNSへの出稿を考えている方、動画広告について知りたいという方はぜひダウンロードください。
分散型SNSとは?
分散型SNSはその名の通り、異なる運営者に分権化・分散化されているソーシャルネットワーキング・サービスのこと。TwitterやInstagram、Facebookなど従来のSNSはそれぞれ運営会社があり、その運営会社によってひとつのプラットフォームとしてひとつのサーバーのもと管理されています。
一方、分散型SNSは、イーサリアム(ETH)などのブロックチェーン上に構築されたSNSで、誰でも利用が可能なDApp(分散型アプリ)として提供されているSNSです。ひとつの中央集権的なサーバーの上ではなく複数の民主的な方法で分散的に管理・運営されているという特徴があります。
▶︎用語解説
分散型:ある仕組みをひとつの組織が運営するのではなく、個人同士で共同運営できるモデルのこと。
イーサリアム(ETH):分散型アプリケーションのためのプラットフォームのひとつ。プログラムによって契約を自動化するスマートコントラクトを実装したアプリケーションを、誰でも設計・開発できるようになっていることが特徴
例えば、TwitterのアカウントでInstagramにログインしたり、コメントすることはできません。しかし分散型SNSのひとつであるMastdonなら同じネットワーク内であればサーバーAに参加しながら、サーバーBのユーザーの投稿を閲覧したりコメントしたりすることも可能です。

Web3.0時代のSNSとして注目
分散型SNSが注目されてきた背景にはWeb3.0時代の到来があります。
Web3.0は分散型のインターネットと表現されています。
これまでのインターネット(Web2.0)では、GoogleやFacebookなどのプラットフォームをもつ企業が個人情報や利益を独占していました。しかし、こうした中央集権的なインターネットの仕組みにおいては「情報漏洩リスク」「サーバーダウンによるサービスの停止」など様々な問題も指摘されています。実際、2021年には「2019年にFacebookで5億人の情報漏洩が起きた」と報じられ、大きな問題となりました。(※)
また、個人情報そのものに対する関心が高まるなかで、それぞれのプラットフォームがもつアルゴリズムの不透明性やそれに対する不信感をもつユーザーがいるのも事実です。
Web3.0はブロックチェーンなどの技術を使い、情報を分散的に管理し、大企業からの脱却を目指しています。分散型で管理運営することで、これらの問題を解決する新しいインターネットの形と位置付けられます。
分散型SNSも同様に、分散型に管理、運営されておりまさにWeb3.0時代のSNSの形を表しているもの。特に、イーロン・マスク氏のTwitterCEO就任以降、Twitterからの避難先として分散型SNSに注目するユーザーもいるのです。
イーロン・マスク氏CEO就任後の出来事をまとめました
▶今Twitterで何が起きている?イーロン・マスク氏CEO就任後の主な出来事まとめ

※)Facebook、流出の5億人情報が再び閲覧可能に 米報道|nikkei.com
分散型SNSと中央集権SNS(従来のSNS)の違い
続いて従来のSNSと分散型SNSを比較した時の違いについて見ていきます。
1:中央集権的な管理者がいない
TwitterやFacebook、Instagramなど従来のSNSはそれぞれプラットフォームを運営している会社がサーバーを掌握しています。そのため、提供されるサービスやルールやポリシーについては、その会社が策定しています。
しかし分散型SNSにはこうした管理者がおらず、DAO(分散型自立組織)など、ユーザーの参加による民主的な方法によって管理されています。ソースコードなども公開されており、参加ユーザーによるコミュニティ全体で運営されているのが特徴的です。
▶︎用語解説
DAO(分散型自立組織):中央の管理者が存在しなくてもユーザーの活動によって組織が機能するように、コンピュータープログラムとしてエンコードされたルールによって構築された組織のこと。
2:中央管理されているデータベースがない
従来のSNSではユーザー名やメールアドレス、電話番号などの情報から、SNS上での行動、投稿内容にいたるまで全てをひとつのデータベースで中央集権的に管理しています。
一方分散型SNSにはこういったデータベースが存在しません。その代替として使われているのが「分散型ストレージ」と呼ばれる仕組みです。この分散型ストレージでは、ある特定のネットワークに参加するパソコンやスマートフォンなど「ノード」に存在する空きストレージを利用してデータを保存します。P2Pやブロックチェーンの技術が使われているサービスです。
▶︎用語解説
ノード:「ノード(nord)」は結び目、集合点、中心点といった意味をもつ言葉。コンピューターネットワークにおいては、そのネットワークを構成するひとつひとつの機器のことを指す。
P2P(Peer-to-Peer):ネットワークに参加するコンピューター同士の連携や通信のやり方のひとつ。コンピューター間に役割の違いなどがなく、全てのコンピューターが対等な状態でやりとりが行われるのが特徴。
3.簡単に仮想通貨を利用できる。
Instagramでは一部のクリエイターがNFT(またはデジタルコレクション)を使って収益を得るためのテストを開始。TwitterでもTwitter Blueの加入者に向けてNFTプロフィール画像が利用できる機能の提供開始や、仮想通貨による決済機能構想の発表を行なっています。このように従来のSNSでもブロックチェーンを利用したサービス開発に乗り出していますが、新しくサービスを開発するのに時間や工数がかかっているのが現状です。
Instagramの新機能アップデートはこちらの記事でご紹介中
▶Instagram(インスタグラム)の新機能&アップデートまとめ・最新版【2023年のInstagram活用に】
一方で分散型SNSはブロックチェーンを基礎に構築されています。その点で仮想通貨を利用しやすく、報酬システムやサブスクリプションなど仮想通貨を利用した機能を比較的容易に持つことができるという特徴があります。
分散型SNSがもつメリット5つ
これらの特徴を踏まえ、分散型SNSがもつメリットをまとめると以下のようになります。
1.データ漏洩リスクが下がる
従来型のSNSはひとつのデータベースにおいてユーザーデータを管理しています。そのため、そのデータベースがハッキングなど他者からの攻撃に晒された場合、データベースに保管されているユーザー情報が漏洩してしまうというリスクが伴います。
この点に関して、分散型SNSは分散型ストレージを使っており、データを地理的に分散させて保存することで、耐障害性をもつことができます。そのため、データ漏洩リスクを下げることができるのです。
2.プライバシー侵害を防ぐ
また、前述の通り、従来のSNSではユーザーデータはひとつのデータベースで管理され、そのプラットフォームの運営者が管理しています。
一方で分散型SNSにはこうした管理者がいません。そのため、管理者によってユーザーデータが恣意的に利用されるといったプライバシー侵害として問題とされているような事象が起こりにくいと言えます。
3.システム障害やサービス停止が起こりにくい
従来型のSNSは中央管理されたシステムのうえで稼働しサービスを提供しており、一度障害が起きるとシステムが停止してしまう可能性があります。
しかし、ブロックチェーンを基盤にしている分散型SNSでは、どこかで障害が起きてもネットワーク全体で補完しており、障害に強い仕組みとなっています。
4.民主的な運用ルールが採用されている
従来型のSNSはプラットフォーム側に決定権があり、機能の廃止やポリシー変更はプラットフォームの意向によって決まります。例えば便利だと思って使っていた機能が突然廃止されてしまったり、アップデートによってインターフェースがいつの間にか変わっている、ということも珍しくありません。
これに対してDAOによって運営されている分散型SNSでは、全ての意思決定は投票など民主的な方法で行われます。そのため意思決定において、コミュニティにいるユーザーの意向がより反映される形となっています。
5.投稿を収益化しやすい
各SNSプラットフォームでは、インフルエンサーやクリエイターがプラットフォームを通して収益をあげられるモデルを模索しています。例えばTikTokではクリエイターに対して収益を分配する新広告プログラム「Pulse」が導入されました。またInstagramでもクリエイターの収益化を目的とした広告メニューのアップデートを進めています。
しかし、これらの機能を活用して収益を得られるのは、一定数以上のフォロワーがいるクリエイターに限られる傾向があり、全てのユーザーが利用できるものではない、というのが現状です。
Instagramの新機能・アップデート情報はこちらにまとめました
▶Instagram(インスタグラム)の新機能&アップデートまとめ・最新版【2023年のInstagram活用に】
一方、分散型SNSはブロックチェーンの技術をもとに作られているため、ほとんどのプラットフォームで独自仮想通貨を得ることが可能です。コンテンツのエンゲージメントによる収益だけでなく、投げ銭のような形もとることができ、アカウントの大小問わずに収益をあげることができるモデルを作りやすいというメリットがあります。
注目の分散型SNS6選
最後に、現在提供されている分散型SNSをいくつかご紹介します。
1.Mastodon(マストドン)
Mastodonはドイツのオイゲン・ロホコ氏が2016年に立ち上げた、分散型ソーシャルメディアサービス。2022年には、月間アクティブユーザー(MAU)数が102万8,362人に達したと、同氏が明かしており、分散型SNSのなかでも大きなサービスのひとつとなっています。
使用感はTwitterと非常に似ており、「ブースト」と呼ばれるリツイートのように投稿を拡散する機能もあります。
タイムラインには自分が参加しているサーバー(インスタンス)に存在するユーザーの投稿が表示される「ローカル」と、自分が参加しているインスタンスと関連のある他のインスタンスの人の投稿などを含めた投稿が表示される「連合」という2種類があり、一度に投稿できる文字数は最大500文字までとなっています。
2.Phaver(フェーバー)
分散型のTwitterとも呼ばれている「Phaver」。イーサリアムの創業者であり仮想通貨業界でも有名なvitalik氏も利用していることで知られています。
基本的な機能はTwitterと似ていますが、大きく異なる点に「Share to Earn」という思想があります。これはPhaverで投稿することで、投稿に対してトークンを稼ぐことができるというもの。Phaver上で価値のあるコンテンツを作成したクリエイターや、それを広めたキュレーターが報酬を得られる仕組みが採用されています。Twitterに置き換えれば、バズったツイートをしたユーザーや、これからバズりそうな投稿にいいねやリツイートをすることで、トークンを稼ぐことができるイメージです。
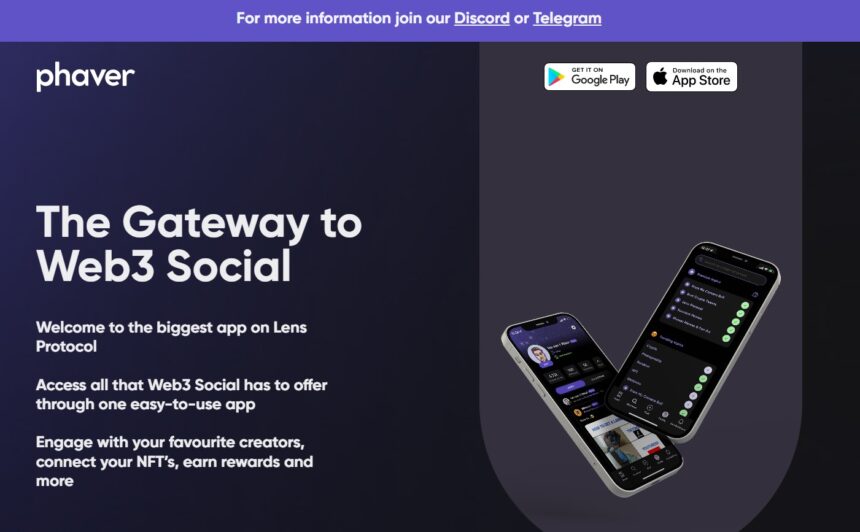
3.Bluesky(ブルースカイ)
Twitter創業者のジャック・ドーシー氏が先導している分散型SNSが「Bluesky」です。Blueskyという名前には「広く開かれた可能性の空間」という意味が込められており、オープンで分散化されたSNSを目指して開発されています。開発段階において、開発中の一部のコードを公開するなどプラットフォーム開発過程の透明性にも配慮しているBlueseky。現段階ではまだローンチされていませんが、ウェイトリストに登録することができます。

4.Mirror(ミラー)
記事を投稿して、その投稿主が報酬を得られるプラットフォームである「Mirror」。端的にいうとブロックチェーンと繋がっているブログのプラットフォームのようなサービスです。Mirrorでは記事を執筆し公開するだけでなく、執筆した記事のNFT化や、クラウドファンディングなどの機能を利用することができます。読者は公開されNFT化した記事を収集することでクリエイターをサポートすることが可能。また、記事には収益を分配するSplitという機能があるため、個人だけでなくグループやプロジェクト単位で資金調達をすることができるのも特徴です。

5.Minds(マインズ)
反Facebook、反Googleを掲げ、個人のプライバシー保護、言論の自由を最重要視した真の自由なSNSを目指しているのは「Minds(マインズ)」。ローンチが2015年と分散型のソーシャルメディアのなかでも古株に位置しているプラットフォームです。
最も特徴的なのが「Take back control of your social media(あなたのソーシャルメディアのコントロールを取り戻す)」という思想に基づき、投稿コンテンツの管理権限がユーザーに与えられていること。通常のプラットフォームでは、コンテンツの管理(削除など)はプラットフォーム側によって決められますが、Mindsはユーザーの中からランダムに12人を選びコンテンツがプラットフォームに適しているか否かを決めています。
6.Odysee(オディシー)
動画に特化したプラットフォームであるOdyseeは、Web3.0時代のYouTubeとも呼ばれています。YouTubeではAIの判断によって突然チャンネルが閉鎖されたり、コンテンツが削除されることがありますが、投稿コンテンツがブロックチェーン上に格納されているOdyseeではそういった懸念がなく、クリエイターにとって安心なプラットフォームになっています。また、P2P形式でコンテンツを共有することで、サーバーダウンなどの障害によってサービスが停止されることを防いでいます。