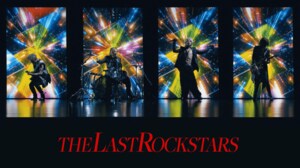例としてサブプライム向けローンを1000個集めて証券化した場合を見てみましょう。それを使って3種類の証券をつくります。
第3証券のグループ 最初に返せなくなったローンから400番目までに返せなくなったローン
第2証券のグループ 次の401番目から700番目までに返せなくなったローン
第1証券のグループ 701番目から最後の1000番目までのローン
こうして、債務者が破産するなどして、返済できなくなるといちばん下の第3証券のグループから損をし始めます。その意味では、第1証券のグループは1000個中、700個のローンがダメになっても全部返ってくるわけですからかなり安心です。
このように危ない度合いが証券ごとに異なりますので、金利も第3証券がいちばん高く、第1証券の利回りがいちばん低くなります。ローンを借りている人の誰かひとりが破産しても、全員が一斉に同時に破産するわけではありません。こうやってローンの集合体としてみれば、ひとりに全額貸しつけるわけではないので、リスクも分散できたと思うわけです。
また、今にも破産しそうな危ない人たちに貸し付けたローンを束ねたものであるにもかかわらず、第1証券のグループはかなり安全なグループ、ということになりました。格付けもとても高く、なんと最上位のAAAの格付けが付けられました。
格付けとは格付会社が債券やその発行体、金融機関などの債務支払能力を評価し、信用力を示したものです。格付けが低くなるほど、借りたお金を返せない可能性が高いと格付会社が考えているということになります。会社によって違いますが、AAAがいちばん安全だということです。
しかも、サブプライムローンでは、世界的な格付会社S&P、ムーディーズが格付けをしました。世界最強のクレジット評価です。なのに、普通の社債ではまったく得られないような高い金利が提示されたので、それはもう飛ぶように買われました。
『マネーショート 華麗なる大逆転』という映画がおもしろく説明しています。証券化商品は証券会社がつくって販売しますが、つくる際に格付会社に頼んで格付けをしてもらいます。
その際、作成側がS&Pとムーディーズの両方を競わせて高い格付けをした方と契約すると伝えます。そうすると両社とも、お金欲しさに合法的なぎりぎりの線で格付けを高くしようとします。しかし、このあたりはさすがにインチキをするわけではなく、許される範囲でもっとも格付けが高くなるような工夫をしました。
当時、この証券化商品には格付手数料がたくさん入ってきたので、格付会社では証券化商品の格付担当分野の人が多く出世するという情けない状態になっていました。
いちばん恐ろしいのは「安全だと言われていた」こと
サブプライム問題の恐ろしいところは、このAAAの債券を世界中の金融機関や投資家が買っていたことと、「これはリスクが極めて少ない、非常に安全な商品」として購入していたということです。
つまり「リスクがあるけどリターンが高いので、最悪の場合、やられるのを覚悟で買う」というのではなく、リスクを避けたつもりであったということです。安全な商品だということで、世界中にばらまかれました。
この手の商品の販売額は、世界で1000兆円ともいわれています。そのインパクトが非常に大きかったことがうかがわれます。
ここでひとつ、疑問が生まれます。