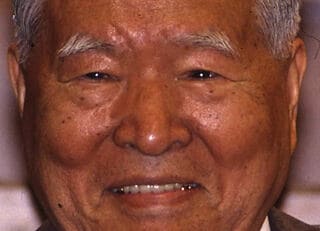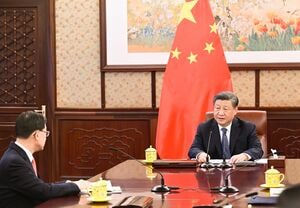中央委員、准中央委員は200名を超えているが、すべて中央委員会から給料が支給されている。鈴木氏が所属する京都府委員会なども同じ状態らしい。党のさまざまな会議はほとんどが専従活動家で組織されている。ここで異論を唱え役員から外されるようなことになれば、生活危機に直結することになる。だからどんな無理難題な目標が志位氏らから提起されても、異論を唱えないのだ。
専従者以外で党の中枢にいるのが議員である。国会議員や都道府県会議員は、党の公認がなければ絶対に当選できない。地方議員でも、若干の例外はあるが党の公認はほとんどの場合、不可欠である。党の指導部には逆らえないのである。
鈴木氏は、専従者は3分の1ぐらいにして、民間企業や法人、自営業者などから役員を選ぶべきだと主張している。もっともな主張だ。こうすれば、「志位さんの主張に感銘した」「党の歴史に誇りを持てた」「130%増大賛成」などというゴマすり発言はなくなり、侃々諤々の議論になるだろう。
いつでも全会一致などというのは、そもそも無気力、無責任の証なのだ。
共産党の幹部政策の大きな誤り
日本共産党が1961年に今日の路線を確立して以来、60有余年経つが、トップは宮本顕治、不破哲三、志位和夫の3人だけだ。この異常さは、朝日新聞も昨年7月16日付社説で指摘し、党首の選出方法が党員の直接選挙でないことや、組織原則である民主集中制を「閉鎖的な体質」だと批判していた。
これに対して、2022年8月23日に、日本共産党中央委員会党建設委員会の名前で反論文が発表された。「革命政党の幹部政策とは何か」を明らかにしたものだった。この文章の中で、浜野忠夫副委員長の報告が紹介されている。2020年1月の第28回党大会で、中央委員会の推薦による「中央役員候補者名簿」を提案するにあたっての報告だ。浜野氏は次のように報告していた。