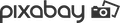10年住んだ賃貸アパートの退去費用は?
「賃貸アパートに10年住めば退去費用が安くなる」と耳にしたことがありませんか?
賃貸アパートは退去時に退去費用が発生しますが、10年も住んでいれば経年劣化によってある程度の汚れや傷を考慮してくれるという話です。
この記事では賃貸アパートに10年住んだ後の退去費用はどれくらいの相場になるのか、退去費用相場について紹介します。
賃貸アパートの退去費用を相場より安くしたい人は、最後まで記事を読んで参考にしてみてください。
10年住んだ賃貸アパートの退去費用は安くなる傾向にある
10年住んでいた賃貸アパートの退去費用は相場より安くなります。
噂では聞いたことがあっても「どうして10年住んでいれば退去費用が安くなるのか」理由を知らない人も少なくありません。
まずは賃貸アパートに10年住むことで、何故相場より退去費用が安くなるのか理由を解説していきます。
設備の傷や汚れが経年劣化と見なされる
人が同じ場所に10年もの年月住んでいれば、設備に多少の傷や汚れができても経年劣化と見なされます。
経年劣化とは年月によって必然的に劣化してしまう部分のことを指し、日差しによる壁や床の劣化や湿気による窓枠のゴム傷みなどが挙げられます。
賃貸アパートに10年も住んでいれば経年劣化は起きて当然なのです。
賃貸物件の経年劣化は入居者負担にならない
賃貸物件の場合、経年劣化は入居者負担になりません。
10年も賃貸アパートに住んでいれば、経年劣化は起きるということを考慮して、経年劣化による退去費用は大家さんや管理会社が負担してくれるのです。
つまり賃貸物件は長年住めば住むほど、経年劣化と見なされ多少の傷や汚れを考慮してくれる可能性があります。
入居者負担になる場合の傷・汚れ
経年劣化による普通に生活していればできる汚れや傷の原状回復費用は、入居者負担にはなりません。
しかし入居者が原因で生じた傷や汚れは経年劣化と見なされませんので注意しましょう。
入居者負担になる設備の汚れや傷は次の例が挙げられます。
入居者負担になる設備の汚れ例
- タバコのヤニによる壁や天井の汚れ
- 窓やドアに生じたカビ汚れ
タバコのヤニやカビ汚れは入居者の努力次第で、付着しなかったと考えられますので退去時の原状回復費用は入居者負担です。
一般的に6〜8年で安くなる
賃貸アパートに10年住んだ際の経年劣化を例に挙げていましたが、賃貸物件は相場として入居6〜8年で退去費用が安くなります。
経年劣化として見なされる年月は設備や汚れによって異なりますが、多くが6〜8年で生じる経年劣化です。
つまり賃貸物件に6〜8年住むことで汚れや傷が経年劣化と見なされ、退去費用が相場より安くなるでしょう。
経年劣化になるもの
例としてどのような傷や汚れが経年劣化として見なされるのか確認していきます。
退去費用が安くなる経年劣化に該当するものは次の通りです。
経年劣化に該当するもの
- 日焼け、日光による壁や床の変色
- 冷蔵庫やテレビなど電化製品による壁の電気焼け
- ポスター、カレンダーなどの設置跡
- 画びょう、ピンで開けた穴
- エアコン設置によるビス穴、跡
- 自然災害によるガラス破損、損傷
- 耐用年数経過による設備品の故障破損や紛失以外の鍵の取り替え、鍵交換費畳の表替え、裏返し
- フローリングのワックスがけ網戸の張り替えエアコンの内部洗浄台所、トイレの消毒
長年住むことによって生活によって生じる汚れや傷の多くが、経年劣化として判断されます。
経年劣化による原状回復費用免除こそ、10年賃貸物件に住むことで退去費用が安くなる理由です。
【設備別】耐用年数
目安として賃貸物件に6〜8年住めば経年劣化と判断されますが、すべての設備が同じ年月で経年劣化となる訳ではありません。
経年劣化と判断されるには設備別の耐用年数が関係しています。
設備によって年月で風化する個体差があるので、耐用年数によっては6年住んでも経年劣化にならない場合もあるのです。
設備別の耐用年数を確認して、経年劣化になる年月を確認しておきましょう。
| 耐用年数 | 設備 |
|---|---|
| 5年 | 流し台 |
| 6年 | 壁紙、カーペット、エアコン、インターホンなど |
| 8年 | 書棚、タンス、戸棚などの金属製ではない家具 |
| 15年 | 便器、洗面台の給排水設備、金属製の家具など |
【賃貸アパート10年】退去費用相場
賃貸アパートの退去費用はどれくらいの相場になるのか確認しておきましょう。
退去費用の相場は、住んだ年数によって経年劣化となる範囲が異なるので変動します。
しかしおおよその退去費用の相場を知っておけば、退去時の参考にすることができます。
「賃貸アパートに2年住んだ際の退去費用」と「賃貸アパートに10年住んだ際の退去費用」を参考に相場を確認していきましょう。
法律で金額は決められていない
退去費用の相場はどれくらいが妥当かと明確な金額は、法律によって定められていません。
上限や下限が定まっていない退去費用は、賃貸アパートの原状回復にかかる費用によって決められます。
法律で決められていないので退去費用の相場は一律ではありませんが、あくまで参考として確認しておきましょう。
アパートに2年住んだ場合
賃貸アパートに2年間住んだ場合の退去費用の相場を参考にしていきます。
2年となると初回更新時に退去を決めた場合の退去費用の相場です。
短大生や専門学生は2年間だけ賃貸アパートに住むことも多いので、参考にしてみてください。
敷金
賃貸アパートの部屋条件は家賃6万円の1Kとしましょう。
家賃6万円の賃貸では相場として家賃1か月分の敷金を入居時に支払っていますので、退去時に敷金6万円分が原状回復費用として当てられます。
また退去費用が敷金6万円以下だった場合は、残った金額は返金されますので安心してください。
部屋の修繕費用
次に退去時の原状回復費用として部屋の修繕費用を確認しておきましょう。
賃貸アパートに2年間住んだ場合の部屋の修繕費用相場は8万円です。
この時点で敷金6万円分はオーバーしていますので、追加で退去費用を支払わなければいけません。
ハウスクリーニング代
賃貸アパートでは原状回復費用としてハウスクリーニング代も請求されます。
ハウスクリーニング業者に依頼して、次の借り主を見つけるために部屋を綺麗にする業務料金が発生するのです。
ハウスクリーニング代は2万円が相場でしょう。
退去時の支払い
家賃6万円の1K賃貸アパートに2年間住んだ場合の退去費用は次の通りです。
| 項目 | 退去費用内訳 |
| 敷金 | 6万円 |
| 部屋の修繕費用 | 8万円 |
| ハウスクリーニング代 | 2万円 |
| 退去費用 | 4万円 |
アパートに10年住んだ場合
次に賃貸アパートに10年住んだ場合の退去費用相場を参考に見ていきましょう。
10年も住んだことで退去費用相場は安くなります。
2年間住んだ場合の退去費用と比較して、確認してみてください。
敷金
賃貸アパートに10年住んだ場合でも部屋の条件は先程と同じく家賃6万円の1Kです。
敷金も同様に家賃1ヶ月分が相場ですので、敷金6万円が退去費用に当てられます。
部屋の修繕費用
部屋の修繕費用ですが、先程は2年住んで8万円かかったところを10年住んだことにより経年劣化が考慮されるので安くなります。
賃貸アパートに10年住んだ場合の部屋の修繕費用は2万円が相場でしょう。
10年住んだことにより経年劣化と見なされる汚れや傷が多く、部屋の修繕費用は軽減されたのです。
ハウスクリーニング代
何年住んでも退去時には、次の借り主を見つけるためにハウスクリーニングをおこないます。
そのためハウスクリーニング代はアパートに10年住んだ場合でも2万円が相場でしょう。
退去時の支払い
家賃6万円の1K賃貸アパートに10年間住んだ場合の退去費用は次の通りです。
| 項目 | 退去費用内訳 |
| 敷金 | 6万円 |
| 部屋の修繕費用 | 2万円 |
| ハウスクリーニング代 | 2万円 |
| 退去費用 | −2万円 |
10年賃貸アパートに住めば、経年劣化が適応されることでお得に退去することができるでしょう。
アパートに10年住むと貸主負担になる箇所
賃貸アパートに10年住むことで、経年劣化と見なされて原状回復費用が貸主負担になります。
上手くいけば退去費用を支払わずとも敷金だけで、原状回復費用をまかなうことも可能でしょう。
しかし経年劣化によってお得に退去するためには、「10年住めば貸主負担になる箇所」がどこなのかを把握しておかなければいけません。
10年住むことによって貸主負担となるもの
フローリング・壁紙の日焼け
家電による壁の電気焼け・黒ずみ
壁にあけた画鋲の穴
エアコン設置によるビス穴・跡
ベッド・タンスで凹んだフローリング
耐用年数経過による設備品の故障
自然災害による損傷
破損紛失以外の鍵の取り替え
- 専用業者でないと清掃できない部分の汚れ
フローリング・壁紙の日焼け
日差しによるフローリングや壁紙の日焼けは、経年劣化によって貸主負担となります。
壁の近くに棚やテレビ台を置いておくことで、家具の形に壁紙が変色した場合も日焼けと見なされ貸主負担です。
畳の日焼けも同じく貸主負担となりますので、退去費用を支払う必要はありません。
家電による壁の電気焼け・黒ずみ
冷蔵庫やテレビなど壁に面する家電を長年使っていると、電気焼け・黒ずみが発生します。
長年使用してできる電気焼け・黒ずみは経年劣化によるものなので貸主負担です。
漏電による電気焼けは自己負担
家具の長期使用による電気焼け・黒ずみは経年劣化と見なされ、貸主負担となります。
ただし、洗濯機からの水漏れや電子レンジからの漏電によって生じた電気焼けは、経年劣化ではありませんので自己負担となりますので注意しましょう。
壁にあけた画鋲の穴
生活する上ではカレンダーやポスターなどを画鋲で壁に貼ることがあります。
壁にあけた画鋲の穴も経年劣化ですので貸主負担です。
しかし画鋲の穴より大きな釘の穴などは自己負担となりますので、注意しましょう。
エアコン設置によるビス穴・跡
エアコンを設置する際にはビス留めをおこなうため、ビス穴・跡が残ります。
貸主に許可されているエアコン設置に関するビス穴・跡は長年生活するために必要な傷ですので貸主負担です。
エアコンを無断で取り替えた場合
エアコン設置の際に生じたビス穴・跡は経年劣化と見なされますが、あくまで貸主が許可したエアコン設置のみです。
貸主の許可なしに無断で設置したエアコンのビス穴・跡は自己負担となります。
ベッド・タンスで凹んだフローリング
ベッドやタンスを長期間フローリングに置いていると、フローリングが凹んでしまいます。
フローリングの凹みは長期間家具を置いていたことによる自然摩耗と見なされるので経年劣化です。
つまり家具によるフローリングの凹みは、貸主負担となります。
家具の設置が多い場合
家具によるフローリングの凹みは経年劣化と見なされて貸主負担となりますが、家具の設置が多い場合はどうでしょう?
実は家具がどれだけ多くても、家具設置によるフローリングの凹みは自然摩耗と見なされますので貸主負担となります。
耐用年数経過による設備品の故障
設備は耐用年数の経過により壊れてしまうことがあります。
耐用年数経過により壊れてしまった設備は、経年劣化として扱われますので貸主負担です。
しかし壊れた際に貸主に報告していなかったものは自己負担となりますので注意してください。
自然災害による損傷
台風や地震など自然災害によって損傷した箇所は、入居者の責任ではありません。
自然災害によって損傷した原状回復費用は貸主負担です。
建物の構造上、勝手に破損した窓ガラスや網戸なども貸主負担となります。
破損紛失以外の鍵の取り替え
鍵を紛失したり破損した場合は、入居者が自己負担で鍵を交換します。
しかし破損紛失以外で次の入居者のために鍵を交換する場合は、次の入居者か貸主負担です。
ただし賃貸契約書に「次の鍵の取り替え費用も入居者が負担する」と記載があった場合は、自己負担となります。
専用業者でないと清掃できない部分の汚れ
退去時にいくら掃除しても清掃できない部分があります。
トイレやお風呂場、キッチン、給排水設備や換気口洗浄、エアコンの内部洗浄など専門業者でないと清掃できない部分は貸主負担です。
専門業者でないと清掃できない部分は入居者ではどうしようもないので、経年劣化として扱われます。
アパートに10年住んでも入居者負担になる箇所
アパートに10年住んでいると、多くの部分が経年劣化として扱われ、貸主負担となります。
しかし10年住んでいても入居者負担となる箇所もあるので、注意しましょう。
経年劣化による摩耗・汚れではないと判断された箇所は基本的に入居者負担です。
賃貸アパートに10年住んでいても次の箇所は入居者負担になります。
タバコによるクロスの黄ばみ
タバコのヤニによる壁紙・天井の汚れは入居者負担となります。
タバコを部屋で吸っているとクロスが黄ばんでしまい、張り替えが必要ですので、クロス張り替え費用を請求されるでしょう。
喫煙者の方は部屋でタバコを吸わないか、ベランダや外で喫煙することをおすすめします。
引っ越し時にできた傷・汚れ
引っ越し時に家具や家電をぶつけて、できた傷や汚れは入居者負担です。
自然にできた傷ではありませんので、家具をぶつけてフローリングが凹んだ場合も入居者負担となります。
引っ越し業者がつけた場合
引っ越し業者が付けた傷であっても入居者負担となります。
退去費用を抑えるためにも引っ越しの際には、引っ越し業者にぶつけないようにお願いしておきましょう。
長期放置した油汚れや腐食
長年放置してこびりついた油汚れや腐食は入居者負担となります。
生活していればできる汚れですが、油汚れや腐食・カビや煤は入居者の努力次第で取り除けた汚れです。
掃除を怠った責任として入居者負担となります。
しかし専門業者でないと清掃できないような内部の油汚れや腐食は、経年劣化となりますので安心してください。
物をかけるために開けた穴
物をかけるためにあけた穴は入居者が故意であけた傷ですので入居者負担です。
画鋲程度の穴であれば経年劣化として扱われますが、自分でも修復できないような穴をあけた場合は入居者負担となるので注意しましょう。
キャスターによる傷・凹み
家具設置によるフローリングの凹みは経年劣化と見なされて貸主負担となりますが、キャスターによる傷・凹みは入居者負担です。
キャスターを転がすことによって傷・凹みが生じることを予測できるので、経年劣化には含まれません。
放置した故障設備
設備が耐用年数経過によって故障した場合も経年劣化として貸主負担となりますが、設備故障を連絡をしていなかった場合は入居者です。
また自分で故障を修理して使用していた場合でも、貸主に連絡をしていなかったので入居者負担での修理となります。
鍵の紛失・破損
鍵が壊れたり変形した場合は、鍵交換費用が入居者負担となります。
また鍵を紛失した場合でも入居者負担となりますので注意しましょう。
鍵穴の破損の場合
鍵穴の破損はよほど故意に壊していない限りは、貸主負担で修理となるでしょう。
鍵穴は乱暴に扱わない限り、あまり破損するものではありませんので、多くの場合は経年劣化として扱われます。
ペットによる傷・汚れ
ペットによる傷や汚れは飼い主の責任となりますので、入居者負担です。
またペットの糞尿により匂いやシミも、こまめに掃除をしていれば防げた汚れですので入居者負担となります。
その他の故意的な傷・汚れ
その他の故意的な傷や汚れも入居者負担となります。
例えば、壁を蹴ってあけた穴や食べ物を落としたまま放置した汚れなどは、故意的な傷・汚れと見なされるでしょう。
普通に生活していて経年劣化によってできた傷・汚れ以外は、入居者の故意的にできた傷・汚れと判断されます。
【アパート10年】退去費用の支払い方法
10年住んだ賃貸アパートを退去する際の、退去費用の支払い方を確認しておきましょう。
「退去費用はクレジットカードで支払うことはできるのか?」「分割払いはできる?」と退去費用の支払い方法で気になっている点を確認していきます。
退去時に慌てなくて済むように、事前に退去費用を用意しておきましょう。
基本的に分割できない
アパートの退去費用は基本的に分割払いに対応していません。
基本は現金一括払いでの振込となります。
退去する前に、まとまった退去費用は残しておきましょう。
クレジットカードに対応している場合
中にはアパートの退去費用を支払う方法として、クレジットカード対応がされている場合もあります。
クレジットカード払いであれば「リボ払い」などを活用して、貸主には一旦まとめて退去費用を支払い、カード会社に分割で支払うことが可能です、
初期費用を分割することで負担が抑えられる
退去費用を現金一括払いで支払えない場合は、新居の初期費用を抑えて退去費用を支払いましょう。
新居の初期費用を抑えることができれば、浮いたお金を退去費用に回して支払うことができます。
退去費用を支払わなければ、新居での新生活をスタートさせることもできませんので、しっかり支払っておきましょう。
原状回復ガイドラインとは
原状回復ガイドラインとは、国土交通省による退去時のトラブルを防ぐための指標です。
退去費用相場やどこまでが経年劣化に該当するのかまとめられています。
退去時のトラブル防止のために「原状回復ガイドライン」について理解しておきましょう。
原状回復の費用負担をまとめたもの
賃貸アパート退去時には「この傷(汚れ)は入居者か貸主どちらの負担になるか」でトラブルになることが多々あります。
このような退去時のトラブルを無くすために「原状回復ガイドライン」が存在しているのです。
原状回復ガイドラインには原状回復の費用負担がまとめられており、どちらの負担になるか判断ができない場合の指標となります。
法的な強制力があるわけではない
原状回復ガイドラインは国土交通省が発行している指標ですが、法的な強制力を持っている訳ではありません。
あくまで指標として、どちらの費用負担になるのか参考としてトラブルを回避しましょう。
アパートに10年住むと経年劣化と見なされ退去費用は安くなる!
賃貸アパートに10年済むと退去時費用負担が安くなります。
長年住んでいて生じる傷や汚れに関しては経年劣化と見なされて、貸主負担となるので10年賃貸に住むと退去費用が相場より安いです。
しかし故意的に傷・汚れがついた箇所に関しては、10年住んでいても入居者負担となりますので注意しましょう。
入居者か貸主どちらの費用負担になるのか判断ができない場合は、国土交通省がまとめた「原状回復ガイドライン」を参考にしてください。
また多くの箇所は6〜8年住めば経年劣化として判断されますので、5年で退去を検討している人はもう数年住むことで退去費用が安くなることを考慮して退去時期を検討しましょう。
賃貸アパートは10年住んでから退去することで、退去費用を安くできるのです。
引っ越しを考えている方必見!「賃貸」vs「購入」結局どっちがお得?
賃貸のメリット・デメリット
賃貸のメリット
- 気軽に引越しをすることができる
- ローンがない
賃貸で暮らすメリットは、なんといっても飽きたり嫌になったりしたらすぐに引っ越せることですよね。
転勤・転職、結婚などのライフイベントが考えられますが、何かあっても賃貸なら簡単に引っ越せます。
賃貸のデメリット
- 家賃はただの消費・生涯払い続ける
- 内装や間取り、設備などが自分で決められない
- 更新料も取られる
- 持ち家と違い資産にならない
引っ越しが手軽な賃貸ですが、デメリットもあります。
ほとんどの物件で2年に1回の更新料が発生します。賃貸だと気軽に引っ越せるのがメリットですが、その分引っ越し費用も相当な金額になるでしょう。
また、若い世代の方は気にしないかもしれませんが、高齢者になると家を借りることが難しくなるとも言われます。
なにより、いつまでたっても家賃を払い続ける、このサイクルから抜け出せないのは賃貸で暮らす最大のデメリットです。
マンションや戸建て購入のメリット・デメリット
購入のメリット
- 毎月支払う家賃が資産に変わる
- リノベーションなど自分好みの部屋に自由に変えられる
- 政府の支援金等措置が豊富
- 老後、収入が無くなっても住むところには困らない
賃貸だと、毎月支払う家賃は当然一生返ってきません。
しかし、購入の場合は支払うお金はローンの返済にあたるため、自分の資産へ変わります。
また賃貸と違い持ち家は自分が所有するものですから、間取り変更など将来のリフォームも自由です。
さらに住宅購入は経済を活性化させる効果があるため、国の経済対策の一環として手厚くもてなされている部分も見逃せません。住宅ローン控除やすまい給付金、各種税金の軽減措置などが豊富です。
また、住宅ローンを完済すれば老後の住居費の負担が抑えられますし不要になれば売却や貸し出すことも可能です。
購入のデメリット
- 賃貸に比べて気軽に引っ越しづらい
- ローンが通るかわからない
よくデメリットとして挙げられているのが引っ越しが気軽にできないことです。
しかし、ライフスタイルが多様化し変化が激しい現代でも、購入した物件であれば売ることも貸すこともできるので、住まいもフレキシブルに変えることが出来ます。
実は20代や30代でのマンション購入が主流化してきています。
毎月誰かに家賃を払い続けるよりは家賃と変わらない支払いでローンを組み、
自分の家を資産として所有したいという人は少なくないのです。
マイホームは一生に一度の買い物ではありません
“35年もローンを払い続けなきゃいけない”
“引っ越ししづらくなる”
それは時代とともに変わってきています。
購入することで物件そのものがあなたの「資産」なので、ローン返済中に住み替える場合でも売りに出して“売却益"によって完済することも貸しに出して家賃収入をローン返済にあてることもできるのです。
このように様々な方法であなたのライフスタイルの変化に合わせて住み替えることが可能なのです。
「賃貸」よりも「購入」をおすすめする3つの理由
- 家が自分の「資産」となり、選択の幅が増える
- "売却益"によってローンを完済することが可能
- 広い家で快適な暮らしを送ることができる
このようにあなたのライフスタイルの変化に合わせて住み替えも考慮した上で、ieyasuでは資産価値の高い物件をご紹介させていただきます。
ieyasuが選ばれる理由
ieyasuが選ばれる理由とは?
- お客様に寄り添った物件提案
- ライフプランの変化にも柔軟に対応
- 専門スタッフによる徹底サポート
まずは「ieyasu」(イエヤス)の無料個別相談へ!
「ieyasu(イエヤス)」なら、住宅販売の経験豊富な専門のスタッフがあなたのパートナーとしてあなたと同じ目線で、将来を見据えた物件選びをしてくれます。また基礎的なご質問から具体的なプランまで、あなたのマイホーム購入のお手伝いをしてくれます。
これをきっかけに気になった方は「ieyasu(イエヤス)」の無料個別相談を受けてみてはいかがでしょうか?今なら無料面談完了でAmazonギフト券10,000円プレゼント中です。
関連記事
- 引っ越しの知識マンションとアパートの違いや定義ってなに?選ぶ際のポイントまで詳しく紹介!
- 引っ越しの知識引っ越しで住民票をそのままにするとどうなる?デメリットや移す手続きも解説!
- 引っ越しの知識犬の室内での飼い方は?部屋のレイアウトのポイントや注意点を徹底解説!
- 引っ越しの知識二人暮らしの間取りのおすすめは?人気や家賃別の広さから注意点まで詳しく紹介!
- 引っ越しの知識土地購入の注意点は?規制がある土地の特徴や税金について知り失敗を避けよう!
- 引っ越しの知識引越しに伴って住民票を移す方法は?必要書類や移さない際のデメリットを紹介!
- 引っ越しの知識期間限定の定期借家ってどんな賃貸?メリット・デメリットや注意点を詳しく紹介!
- 引っ越しの知識バルコニーとベランダの違いとは?物件探し時に役立つ!定義や区別・注意点を解説
- 引っ越しの知識賃貸の解約や退去の手続きは?引越しするタイミングから注意点まで伝授!
- 引っ越しの知識新卒の家賃はいくらが目安?初任給や適正な生活費から必要な設備まで紹介!