一人暮らしの食費の平均はどのくらい?
すべての一人暮らし世帯の食費
| 項目 | 平均金額(1ヶ月) |
| 食費 | 38,257円 |
| 外食(食費のうち) | 7,515円 |
| 調理食品(食費のうち) | 7,029円 |
2022年1月24日作成
一人暮らしの食費の1ヶ月平均は38,257円になっています。
これは2021年8月に更新した総務省の2020年の家計調査によるもので、勤労者とそうでない人を含めたすべての一人暮らしの平均です。
このうち、外食費の平均が7,515円、弁当や惣菜・冷凍食品が含まれる「調理食品」が平均7,029円となっています。
このように1ヶ月の食費の約38%程度を外食や調理食品が占めており、大きな割合となっています。
一人暮らしですべて外食の人の食費
一人暮らしですべて外食の人の食費は、1ヶ月で70,000円以上と言われています。
先ほど解説した「一人暮らしの1ヶ月の食費38,257円」と比べても2倍近くになる数字です。
どうしても外食の回数が増えると食費が増えてしまう傾向があります。
自炊ができない10~30代の食費の平均
自炊ができない10〜30代男女の食費の平均は、約72,000円程度と言われています。
この金額は、外食だけではなく弁当・惣菜などの調理食品も含まれた金額です。
自炊ができないとなると、食費だけでかなりの生活費がかかってしまうと言えるでしょう。
男性
自炊ができない男性の食費の平均は、約75,000円程度です。
実際に1日でどれくらいの食費がかかるのか例を挙げてみましょう。
10代〜30代男性の食費
- 平日の外食例
朝:おにぎり2つとペットボトルのお茶→約400円
昼:牛丼チェーンの牛丼→約600円
夜:ラーメン屋のセットメニュー→約1,000円 - 休日の外食例
朝:カップ麺→約200円
昼:近所の定食屋→約1,000円
夜:スーパーのお惣菜→約1,000円
上記のように男性の一人暮らしでは、1日2,000程度の食費がかかっています。
女性
自炊ができない女性の食費の平均は、約68,000円程度です。
女性の一人暮らしの場合の1日の食費を見ていきましょう。
10代〜30代女性の食費
- 平日の外食例
朝:コーヒーとサンドイッチ→約400円
昼:会社近くのおしゃれなカフェでランチ→約1,000円
夜:スーパーのお惣菜→約700円 - 休日の外食例
朝:なし
昼:冷凍食品やコンビニ→約600円
夜:デリバリーでオシャレなお弁当→約1,200円
上記のように、女性の場合は1日1,500円〜2,000円程度の食費がかかっています。
一人暮らしの1ヶ月の食費の平均
すべての一人暮らし世帯の1ヶ月の食費の平均は、約38,000円程度でした。
先ほども述べましたが、これは一人暮らしのお年寄りなどを含めた平均です。
ここでは、総務省が発表した2020年の家計調査をもとに「一人暮らしの勤労者世帯」に注目し、男女別・年齢別に食費の平均を解説していきます。
単身者の勤労者世帯
一人暮らしの勤労者世帯
| 項目 | 平均 |
| 食費 | 40,235円 |
| 外食 | 10,828円 |
| 調理食品 | 8,322円 |
2022年1月24日作成
一人暮らしの勤労者世帯の食費は、1ヶ月の平均で40,235円です。
すべての一人暮らし世帯と比較すると食費が2,000円程度多くなっています。
外食と調理食品の合計が約19,000円なので、食費の半分くらいが「自炊ではない」ということになります。
やはり、社会人になると仕事が忙しくなり、外食や調理食品で食事を済ませてしまう傾向があるということです。
男女別一人暮らしの食費の平均
男女別一人暮らしの勤労者世帯
| 項目 | 男性 | 女性 |
| 食費 | 44,720円 | 34,127円 |
| 外食 | 13,127円 | 7,740円 |
| 調理食品 | 8,953円 | 5,522円 |
2022年1月24日作成
一人暮らしの勤労者世帯を男女別で見てみると、男性のほうが1ヶ月あたり約10,000円多いです。
外食や調理食品も、男性のほうが多くなっています。
単身者(男性)
男性の一人暮らしの食費は、平均で44,720円です。
女性の一人暮らしと比べても、10,000円程度多くなっています。
さらに、外食や調理食品も女性より多く、食費の半分ほどを占めています。
男女別で比較してみると、男性のほうが自炊している割合が少ないと言えるでしょう。
単身者(女性)
女性の一人暮らしの食費は、平均で34,127円です。
先ほども述べましたが、男性の一人暮しと比べると大きく下回ります。
女性のほうが男性よりも食費にお金をかけない傾向があるようです。
外食費も倍くらいの差が出ています。
年齢別一人暮らしの食費の平均
年齢別一人暮らしの勤労者世帯
| 項目 | 35歳未満 | 35〜59歳 |
| 食費 | 36,400円 | 42,600円 |
| 外食 | 13,626円 | 9,630円 |
| 調理食品 | 7,528円 | 8,993円 |
2022年1月24日作成
一人暮らしの勤労者世帯を年齢別に見てみると、35歳〜59歳のほうが1ヶ月あたりの食費が多いです。
年齢を重ねるにつれて収入が増え、食費にお金をかけられるようになるのが理由と言えるでしょう。
しかし、年齢を重ねるごとに外食の回数が減るようで、外食費が低くなっています。
35歳未満
35歳未満の一人暮らしの食費は、平均で36,400円です。
収入に合わせて食費も少なくなる傾向があります。
しかし、外食費の平均は13,626円と多くなっており、若い世代のほうが会社の付き合いで外食をするケースが多くなると言えるでしょう。
35~59歳
35歳〜59歳の一人暮らしの食費は、平均で42,600円です。
年齢を重ね収入が増えると、食費にお金をかけられるようになります。
そう考えると生活費の大半は、食費が占めていると言っても過言ではないでしょう。
一人暮らしの食費はいくらにするべきか
一人暮らしの食費は35,000円〜45,000円くらいが平均的な食費といえます。
では、実際に食費の目安はあるのでしょうか。
ここでは、収入に対しての食費の目安について解説していきます。
食費は収入の10%~15%が理想
一人暮らしの食費は収入の10%〜15%が理想と言われています。
理由は、貯金やそのほかの出費にお金をかけるなら食費を節約するのが1番だからです。
実際に、光熱費や携帯電話などの支払いを考慮すると食費を10%〜15%に抑えないと支払いが厳しくなります。
さらに、貯金をするとなると「節約できるのは食費しかない」と言えるでしょう。
このように食費は収入の10%〜15%にすることが理想です。
ちなみに、収入は額面の金額ではなく手取りの金額で計算する必要があります。
収入が20万円の例
収入が20万円の場合を例に挙げて、食費の目安を計算していきます。
ここでは手取りが20万円として計算します。
収入が20万円の例
- 計算式
200,000円×10%=20,000円
200,000円×15%=30,000円
食費は20,000円~25,000円
先ほどの計算のとおり、収入(手取り)が20万円の場合の食費の目安は、20,000円〜30,000円となり、25,000円程度が理想と言えます。
例えば、手取りが18万円の場合は18,000円〜27,000円で23,000円程度。
手取りが25万円の場合は25,000円〜37,500円で32,000円程度が理想の食費です。
一人暮らしの食費節約のため最初にすること
一人暮らしの食費節約のため最初にすることは、食費にいくら使っているのかを知ることです。
毎月の食費にどれくらい使っているのかを知ることで、具体的な節約プランが見えてきます。
まずは、家計簿を付けたりクレジットカードの明細書を確認したりして、毎月の食費をチェックする習慣を付けましょう。
毎月の食費を把握する
一人暮らしの食費を節約するためには、毎月の食費を把握する必要があります。
理由は、現状の食費を把握しなければいくら節約すればいいのかがわからないからです。
どんなことにも言えますが、目的を決めなければ達成することはありません。
その目的を決めるためには現状を把握して、どうするのかを明確にする必要があります。
まずは、過去の食費を確認して「食費にいくら使っているのか」を把握することが大切です。
1ヶ月の上限を決める
食費を節約するには、1ヶ月の上限を決めることが大切になります。
なぜなら、上限を決めることで無駄遣いをなくし予算を決め買い物をする習慣が付くからです。
現に「食費にいくら使っていいのか」を把握していないと、浪費の原因となります。
自分の収入に対して「食費は○万円まで」と予算建てをすることで、計画的にお金を使うことが可能です。
このように1ヶ月の上限を決めて食費を節約しましょう。
予算を1週間単位で決める
1ヶ月の食費の上限が決まったら、1週間単位の予算を決める必要があります。
その訳は、なるべく短い期間で予算を決めれば具体的な買い物プランが考えられるからです。
例えば1週間で7,000円とします。
そうすると1ヶ月の食費を28,000円に抑えることが可能です。
また、1週間7,000円でどのような食事にするのか具体的なメニューも考えやすくなります。
このように1ヶ月の食費の上限を決めたら1週間単位で予算を決めることが大切です。
一人暮らしで食費を節約する方法
一人暮らしで食費を節約する方法は「外食を減らす」「自炊する」の2つが挙げられます。
外食を減らすことで食費を抑えることは可能ですが、その代わりテイクアウトやデリバリーばかりになってしまっては食費を節約することはできません。
一人暮らしで食費を節約するには、外食を減らし自炊をすることが大切です。
女性
食費は生活費の大半を占めていますが、家賃はさらに大きな出費となります。
一人暮らしをするときに「家賃はどれくらいが目安なのか」知りたいという人もいることでしょう。
下記の記事では、一人暮らしの生活費の目安について解説しています。
家賃の目安や節約のコツも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
外食を減らす
一人暮らしで食費を節約する方法は、外食の回数を減らすことです。
その理由は、食事が外食ばかりになると食費が倍増するからです。
この記事でも解説しましたが、自炊ができず外食ばかりの人の食費の平均は70,000円以上と言われています。
手っ取り早く食費を節約するには、外食の回数を減らす方法が大切です。
外食の内容を見直す
外食の回数を減らすには、外食の内容を見直しましょう。
例えば、仕事の付き合いでどうしても外食しなければいけないことがあります。
しかし、それ以外で必要以上の外食を避けるようにすれば、食費を減らすことは可能です。
また、牛丼チェーンやお弁当チェーンなど比較的安価な外食チェーンやお弁当チェーンを利用するのも節約につながります。
ただ単に「外食をしない」というのはどこかで負担がかかってしまうので、上手に食費を使うことを心がけましょう。
自炊する
一人暮らしで食費を節約する方法は、自炊をすることです。
また、自炊をする上でのポイントは「買い物の頻度を減らす」「買うものを決めておく」など8つ挙げられます。
自炊するポイントを押さえて、上手に食費の節約をしましょう。
買い物の頻度を減らす
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、買い物の頻度を減らすことです。
買い物をする回数を減らせば、自然とお金を使うことが減り食費の節約が可能になります。
買い物は週に1〜2回にして、1週間分の予算の範囲内で買い物するようにしましょう。
買うものを決めておく
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、買い物に行く前に買うものを決めておくことです。
1週間分の予算に合うように買うものを事前に決めておきましょう。
買い物に行ったら、予定の商品以外のものを買わないように注意してみてください。
安い店で買う
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、できるだけ安い店で買うことです。
基本的にコンビニよりもスーパーのほうが食材は安い傾向にあります。
また、スーパーによっても値段の違いがあるので、なるべくお買い得なスーパーを見つけるようにしましょう。
セールや特売日に買う
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、セールや特売日に買うことです。
特にスーパーは、曜日によって特売日が決められているところが多いと言えます。
そのようなセールや特売日を利用することで、普段よりも2〜3割安く買い物することも可能です。
スーパーのチラシや掲示板などを確認して「このスーパーは○曜日が安い!」という情報を仕入れるようにしましょう。
プライベートブランドを買う
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、プライベートブランドの商品を積極的に買うことです。
プライベートブランドとは、小売店や卸業者が企画の段階から商品開発に参加し独自に販売している商品のことを言います。
独自ブランドのため余計な仲介が入らないので、普通の商品と比べると安いです。
例えば、AEONの「トップバリュ」やセブン&アイホールディングスの「セブンプレミアム」など。
上記の商品を意識して選ぶようにしましょう。
無料でくめるお水をもらってくる
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、無料でくめるお水をもらってくることです。
スーパーで、イオン水やRO水などがもらえる場合は利用するようにしましょう。
例えば、毎日2リットルのペットボトルの水を買った場合は、1ヶ月で約3,000円です。
容器代が必要にはなりますが、初回だけ300円ほど支払えば「1ヶ月3,000円の節約」が可能になります。
作り置きする
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、作り置きをすることです。
作り置きをすれば、多めに買った食材を使わずに腐らせることがありません。
また、時間があるときに作り置きをして、時間がないときの食事やお弁当のおかずなどに活用しやすいことも特徴です。
冷凍保存する
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、冷凍保存を活用することです。
冷凍保存ができれば、食材を腐らせる心配はありません。
また、電子レンジがあればいつでも温めて食べることが可能です。
特に、作り置きをする場合は冷凍保存を活用するようにしましょう。
ちなみに、冷凍保存に向いている食材とそうではない食材があります。
肉類や魚の切り身・水分が少ない野菜(ブロッコリー・ほうれん草・小松菜など)は冷凍保存がしやすいです。
反対に、水分が多い野菜(トマト・レタスなど)やじゃがいも・豆腐などは冷凍に向いていません。
食材を無駄にしない
自炊をしてさらに食費を節約する方法は、食材を無駄にしないことです。
自炊の場合「食材を使い忘れて腐らせる」「作りすぎて食べ残してしまう」などやむを得ず食材を無駄にしてしまうことがあります。
食材はすべて食費を使って購入したものです。
食費を節約したいのに食べられずお金だけ無駄にしてしまっては、節約する意欲もなくなります。
食材を大切に使い、残さず食べることが重要です。
買い物内容で節約する
一人暮らしで食費を節約するには、買い物内容を節約することが大切です。
安くて・量が多くて・使い回しが効くものを探して、上手に買い物することが節約の近道と言えます。
ちょっと工夫するだけで大幅な節約が期待できるので、ぜひ実践してみましょう。
コスパの良い食材を買う
一人暮らしで食費を節約するには、コスパの良い食材を買うことが重要になります。
先ほども述べましたが「安くて・量が多くて・使い回しが効くもの」を見つけて効率よく使用することがポイントです。
「肉類」「魚類」「野菜」など7種類の品目で、コスパの良い食材を紹介していきます。
肉類
肉類でコスパが良い食材は「豚コマ切れ」「鶏ムネ肉」です。
豚コマ切れは100gあたり約130円、鶏ムネ肉は100gあたり約70円になります。
やはり牛肉は少々高くなるので、豚肉や鶏肉がおすすめです。
なかでも鶏ムネ肉は安いところで100gあたり50円くらいになるので、コスパがとても良い食材といえます。
安いときに購入し使いやすい大きさにカットして冷凍保存しておけば、使いたいときに使えて便利です。
魚類
魚類でコスパの良い食材は「鮭の切り身」「サバの切り身」「サンマ」です。
鮭の切り身は1切れで150円〜200円程度、サバの切り身は1切れで100円〜150円程度、サンマは1匹で100円〜200円程度になります。
サンマは季節によってないときもありますが、鮭やサバは年中売っていて比較的値段は変わりません。
魚焼きグリルさえあれば、焼くだけで食べられるので調理も簡単です。
サンマの冷凍はあまりお勧めできませんが、鮭やサバはそもそも冷凍で販売しているものもあるので、扱いやすい食材と言えるでしょう。
野菜
野菜でコスパの良い食材は「キャベツ」「もやし」「じゃがいも」です。
キャベツは1玉あたり約200円、もやしは1袋で10円〜20円程度、じゃがいもは1袋で約200円になります。
もやしは早めに使用しないと水が出てしまい使えなくなりますが、じゃがいもは冷蔵庫で保管すれば2週間程度日持ちします。
また、キャベツは芯の部分に竹串を刺したり切れ目を入れたりすることで長持ちします。
ただし、キャベツはカットした部分から色が変わるので、カットしたら早めに使うか変色した部分を取り除いて使うようにしましょう。
豆類
豆類でコスパの良い食材は「豆腐」「納豆」です。
豆腐は1パックで20円〜30円程度、納豆は3パックセットで50円〜150円程度になります。
豆腐も納豆も賞味期限が1週間程度あるので、日持ちは長いほうです。
また、納豆は冷凍保存が可能で食べる直前に解凍し、すぐに食べれば問題なく食べられます。
キノコ類
キノコ類でコスパが良い食材は「しめじ」「えのき」「エリンギ」です。
どれも1パックで100円程度と価格が安く、豚肉やもやし・キャベツと一緒に炒めて食べれば、栄養価も高くボリュームも満点です。
ただし、キノコ類は日持ちがしにくい食材と言えます。
見た目にしんなりしてくる前に、早めに調理して食べましょう。
果物類
果物類でコスパが良い食材は「オレンジ」「りんご」「バナナ」です。
オレンジは1個で150円〜200円程度、りんごは1個で約100円、バナナは1袋で100円〜150円程度になります。
オレンジやリンゴはそのままの状態で冷蔵庫に入れておけば、1週間程度は持ちます。
バナナは色が変わりやすいですが、3〜5日は持つので朝ごはんなどにおすすめです。
麺類
麺類でコスパが良い食材は「パスタ」「そうめん」です。
どちらも1袋で100円〜200円程度になります。
パスタソースやめんつゆを一緒に購入しておけば、簡単に食べられて便利です。
飲料
一人暮らしで食費を節約するには、飲料にお金をかけすぎないことが大切です。
例えば、水はスーパーなど無料でくめるものを利用したりお茶やコーヒーなどは自分で作ったりすると安く済みます。
コンビニでペットボトルの飲料を購入すると割高なので、注意しましょう。
お茶類は買わずに自分で作る
お茶やコーヒーなどは、出来上がったものを購入せずに自分で作るようにしてみてください。
例えば、麦茶パックを購入して自分で沸かせば、500mlを約50円程度で作ることができます。
また、コーヒーもインスタントコーヒーを購入して自分で作ったほうが安いです。
ちょっとした工夫で節約できるので、ぜひ試してみましょう。
お徳用や業務用を買う
一人暮らしで食費を節約するには、なるべくお徳用や業務用の食材を買うようにしましょう。
理由は、お徳用や業務用のほうが小さいパックよりも値段が安いからです。
例えば、お肉はお徳用パックの方が100gあたり30円〜50円ほど安くなっています。
使わない分はフリーザーパックに入れて冷凍保存しておくといいでしょう。
このように冷凍保存できるものや日持ちするものは、お徳用や業務用の食材をうまく活用するようにしてみてください。
食費の節約は毎日の積み重ねが大切
一人暮らしの食費の平均、自炊や外食の1ヶ月の目安と節約方法を解説しました。
勤労者世帯の一人暮らしの食費は、平均で40,235円です。
また、一人暮らしの食費の目安は、収入の10%〜15%が理想と言えます。
食事のほとんどを外食にしてしまうと1ヶ月あたり70,000円くらいになってしまうので、ある程度自炊することが大切です。
毎月の食費の上限を決めて計画的に買い物することで、食費の節約をすることが可能になります。
食費を節約するには食事の大半を自炊することが重要となるので、できるだけ自炊をするようにしましょう。
食費の節約は、毎日の積み重ねが大切です。
まずは、過去の食費を見直し、改善できるところから始めてみてはいかがでしょうか。
引っ越しを考えている方必見!「賃貸」vs「購入」結局どっちがお得?
賃貸のメリット・デメリット
賃貸のメリット
- 気軽に引越しをすることができる
- ローンがない
賃貸で暮らすメリットは、なんといっても飽きたり嫌になったりしたらすぐに引っ越せることですよね。
転勤・転職、結婚などのライフイベントが考えられますが、何かあっても賃貸なら簡単に引っ越せます。
賃貸のデメリット
- 家賃はただの消費・生涯払い続ける
- 内装や間取り、設備などが自分で決められない
- 更新料も取られる
- 持ち家と違い資産にならない
引っ越しが手軽な賃貸ですが、デメリットもあります。
ほとんどの物件で2年に1回の更新料が発生します。賃貸だと気軽に引っ越せるのがメリットですが、その分引っ越し費用も相当な金額になるでしょう。
また、若い世代の方は気にしないかもしれませんが、高齢者になると家を借りることが難しくなるとも言われます。
なにより、いつまでたっても家賃を払い続ける、このサイクルから抜け出せないのは賃貸で暮らす最大のデメリットです。
マンションや戸建て購入のメリット・デメリット
購入のメリット
- 毎月支払う家賃が資産に変わる
- リノベーションなど自分好みの部屋に自由に変えられる
- 政府の支援金等措置が豊富
- 老後、収入が無くなっても住むところには困らない
賃貸だと、毎月支払う家賃は当然一生返ってきません。
しかし、購入の場合は支払うお金はローンの返済にあたるため、自分の資産へ変わります。
また賃貸と違い持ち家は自分が所有するものですから、間取り変更など将来のリフォームも自由です。
さらに住宅購入は経済を活性化させる効果があるため、国の経済対策の一環として手厚くもてなされている部分も見逃せません。住宅ローン控除やすまい給付金、各種税金の軽減措置などが豊富です。
また、住宅ローンを完済すれば老後の住居費の負担が抑えられますし不要になれば売却や貸し出すことも可能です。
購入のデメリット
- 賃貸に比べて気軽に引っ越しづらい
- ローンが通るかわからない
よくデメリットとして挙げられているのが引っ越しが気軽にできないことです。
しかし、ライフスタイルが多様化し変化が激しい現代でも、購入した物件であれば売ることも貸すこともできるので、住まいもフレキシブルに変えることが出来ます。
実は20代や30代でのマンション購入が主流化してきています。
毎月誰かに家賃を払い続けるよりは家賃と変わらない支払いでローンを組み、
自分の家を資産として所有したいという人は少なくないのです。
マイホームは一生に一度の買い物ではありません
“35年もローンを払い続けなきゃいけない”
“引っ越ししづらくなる”
それは時代とともに変わってきています。
購入することで物件そのものがあなたの「資産」なので、ローン返済中に住み替える場合でも売りに出して“売却益"によって完済することも貸しに出して家賃収入をローン返済にあてることもできるのです。
このように様々な方法であなたのライフスタイルの変化に合わせて住み替えることが可能なのです。
「賃貸」よりも「購入」をおすすめする3つの理由
- 家が自分の「資産」となり、選択の幅が増える
- "売却益"によってローンを完済することが可能
- 広い家で快適な暮らしを送ることができる
このようにあなたのライフスタイルの変化に合わせて住み替えも考慮した上で、ieyasuでは資産価値の高い物件をご紹介させていただきます。
ieyasuが選ばれる理由
ieyasuが選ばれる理由とは?
- お客様に寄り添った物件提案
- ライフプランの変化にも柔軟に対応
- 専門スタッフによる徹底サポート
まずは「ieyasu」(イエヤス)の無料個別相談へ!
「ieyasu(イエヤス)」なら、住宅販売の経験豊富な専門のスタッフがあなたのパートナーとしてあなたと同じ目線で、将来を見据えた物件選びをしてくれます。また基礎的なご質問から具体的なプランまで、あなたのマイホーム購入のお手伝いをしてくれます。
これをきっかけに気になった方は「ieyasu(イエヤス)」の無料個別相談を受けてみてはいかがでしょうか?今なら無料面談完了でAmazonギフト券10,000円プレゼント中です。
関連記事
- 費用賃貸を退去する費用はどのくらい?原状回復や経年劣化についても徹底解説!
- 費用オール電化の電気代はいくら?料金プランや節約方法についても詳しく解説!
- 費用【戸建て】土地ありの建て替え費用相場や坪数別目安は?リフォームと比較!
- 費用手取り20万円の家賃の相場は?一人暮らしに必要な生活費や物件の探し方を解説!
- 暮らし二人暮らしの光熱費はどのくらい?電気代やガス代の平均から節約術まで徹底解説!
- 費用賃貸の管理費とは?共益費との違いや物件選びの注意点を知り賢く部屋探し!
- 費用手取り18万円の家賃の目安はいくら?生活費を節約するコツや注意点も解説!
- 費用中古住宅に消費税はかからない?売主が個人・法人によって物件の消費税は異なる!
- 費用新築の登記費用の相場はいくら?必要な書類や流れを知って引越しに備えよう!
- 費用持ち家の税金にはどんな種類がある?減税制度や計算方法を知って家計管理しよう!



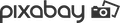

食費だけではなくて、一人暮らしの家賃の目安はあるのかなあ?