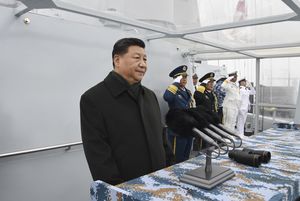3.ウクライナの突進止められないロシア軍
今後の南部の戦闘を予測するには、前述の地理的特性や地形の特性の他に、ロシア軍戦力の損失(損耗率)と増援兵力(新たな動員)の実態を知る必要がある。
(1)ロシア軍の損失が多く組織的戦闘ができる戦力ではない
侵攻開始から8か月間に投入した戦力(当初投入した戦力と事後他軍管区から転用した戦力)の損失を見る。
ウクライナ軍参謀部の資料を参考に算定した損失と損耗率は、戦車等が2584両(損耗率33%)、装甲車5284両(63%)、火砲等1667門(53~91%)*1、多連装ロケット374門(53%)、戦闘機270機(38%)、ヘリ(82%)、兵員が6.7万人(27%)だ。
*1=ウクライナ参謀部が発表する火砲(artillery)の損失数には、加農砲・榴弾砲のほかに迫撃砲が入っている可能性がある。そのため、投入数に加農砲・榴弾砲に迫撃砲(mortar)を加え、損耗率を算定した数字も併せて入れることにした。その結果、迫撃砲を入れた数値53%、加農砲・榴弾砲だけで算定した数値91%となる。
兵員の損失には、将軍(旅団級以上の指揮官)やこれまで果敢に戦ってきた部隊の骨幹であった古参兵が多く含まれる。
この損失は、部隊の機能や兵士の士気を低下させている。これだけの損耗率が出ると、ロシア軍は戦意を喪失している部隊が多くあるとみてよい。
さらにこれらのほかに、多数の弾薬庫や指揮所が「HIMARS」(高機動ロケット砲システム、High Mobility Artillery Rocket System)などで攻撃を受け破壊されている。
以上のことを総合的に考えると、ロシア軍は戦う意識も低く、実際に防御戦闘を行う準備もできていないことから、逐次後退せざるを得なくなる。
東部のハルキウの戦闘のように、混乱して後退するとみている。
(2)新たに動員された20万~30万人のロシア兵は戦闘には使えない
数日あるいは数週間の訓練を受けただけの兵は、軍務経験が少しあったとしても、小銃の使い方、戦闘地域で生活する方法、いくらかの軍事知識を学ぶだけで、分隊(約5人で編成)や班(約10人)の一員として組織的戦闘はできない。
専門的な戦車・火砲・防空兵器の操作もできないし、警備兵としても使えない。
それぞれに指揮官がいなければ部隊として戦えない。分隊長・班長の下士官を育成するのに数年、小隊長で数年、中隊長で5~6年、大隊長で10年、連隊長以上になれば、専門職のほかに戦術・戦略の教育に15~20年はかかる。
旅団長・師団長以上とその参謀になれば、20年以上の各級指揮官の経験が必要だ。
戦時とはいえ、急速に育成するにしても、この戦争の期間では間に合いそうもない。
軍務経験が豊富な分隊長・班長がいなければ、弾が飛び交う戦場では戦えない。これら各級指揮官と幕僚がいなければ、大部隊での戦闘はできない。