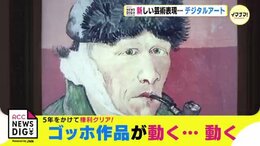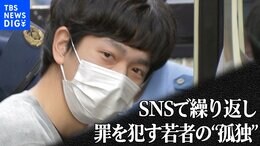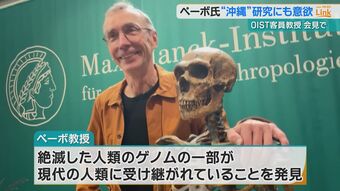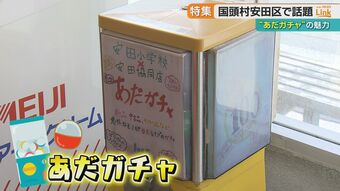結局Aさんはその場にいられなくなり、入場券を預けたまま、その場を後にしたといいます。
Qその日は投票せずに帰ったということですか?
Aさん「そうですね、というのが数回はありますね」
県選挙管理委員会などによると1950年に定められた公職選挙法施行規則に基づき、票の集計は、戸籍上の男女別に行わなければならず、投票所で性別を判断することは、避けられないということです。
投票所入場券に何を書くかは、各市長村の判断に任されていますが、RBCが県内41市長村の選挙管理委員会にアンケート調査を行ったところ、23の自治体が入場券に性別や性別を記入する欄を記載していると回答しています。
性別や性別欄を記載していない自治体では、どのような取り組みが行われているのか、沖縄市選挙管理委員会に話を聞きました。
沖縄市選挙管理委員会 事務局 宮城行広(みやぎ ゆきひろ)事務局長
「性別ではなくて(男性の方には)このアスタリスクで(男性と)わかるような感じで作って送付している」

沖縄市選管では2019年の参院選から入場券の性別欄をなくし、記号で男女を判別。
また、名前を呼ばれることに抵抗感を持つ有権者に配慮し、去年から生年月日で本人確認をしてなりすましを防いでいます。
さらにー
沖縄市選挙管理委員会 事務局 島袋牧子(しまぶくろ まきこ)庶務係長
「以前は青が男性、ピンクが女性と色分けをして投票された方のハガキを分けていたが、これを白で統一して今年度よりこの目隠し板で有権者からは見えないように配慮している」
このほか投票用紙を交付する際、男女の判別ボタンにカバーを設置し、有権者が目の前で性別を判断され、苦痛を感じないよう工夫しています。
ADVERTISEMENT
沖縄市選管 宮城事務局長
「沖縄市でもそれ以外に取り組めるものがあればどんどん取り組んで小さな取り組みではあるが有権者の方が気持ち良く投票できるような形で環境を整えられれば」
沖縄市選挙管理委員会の取り組みは、「ジェンダー平等を実現しよう」というSGDsの目標につながっています。

Aさん
「こういった一定数以上の人たちもいるっていうことを分かって欲しいなっていうことと、本当に選挙に携わる方々がそういった知識をですね含めて持っていただけたら今以上にですね足を運びたくなるような選挙になるのかなぁって思います」
【記者MEMO】
選挙の際の投票所入場券をめぐっては、総務省がことし5月、性の多様性に配慮して表現を検討するよう全国の自治体に通知していて、男女別に集計するという法律上の制約がある中で、各自治体が様々な工夫をしています。
県内のそのほかの事例を見てみますともっとも多かったのは、石垣市などで『1』と『2』の数字で男女を分類。また浦添市では、『★』マークの有無で、分類しています。そして、投票所入場券を見直す動き、県内では今後さらに広がりそうなんです。
RBCが行ったアンケート調査で、入場券に男女の記載があると回答した23の自治体のうち12の自治体が、今後、変更予定、または変更を検討すると回答しています。
より多くの人が投票しやすい環境づくりが少しずつ進んでいます。