ラッコは何科?どこにいる?おもしろ可愛い!ラッコの生態と特徴
みなさんラッコは何の仲間かご存知ですか?
ぷかぷか水に浮き、動物園というより水族館の人気者ラッコ。
しかし、ラッコの正体やその生活を知らない方が意外に多いのでは?
そこで今回のzoo zoo diaryは、ラッコの生態と特徴に注目します。動物の予習をしてラッコに会いに行きましょう!
ラッコとは?
ラッコは食肉目イタチ科。さらに細かくみるとカワウソ亜科に属します。
英語ではシーオッター【Sea Otter】海カワウソと呼ばれます。
- IUCNレッドリスト 危機(EN)
- ワシントン条約 附属書Ⅰ/Ⅱ
- 生息 北太平洋の岩場 12.5万頭
- 体長 150cm
- 体重 30kg
生息地のちがいから3亜種が確認されています。
- 食肉目 Carnivora
- イタチ科 Mustelidae
- ラッコ属 Enhydra
- ラッコ Enhydra lutris
- ロシアラッコ E. l.lutris
- キタラッコ E. l. kenyoni
- ミナミラッコ E. l. nereis
- ラッコ Enhydra lutris
- ラッコ属 Enhydra
- イタチ科 Mustelidae
頭部は白っぽく見えますが、全体的に濃い茶色や灰色です。
ラッコは頭から尾までの長さ約1.5メートル、体重30kg以上とイタチ科で最も大きな種です。
毛が長く陸地にあがることの少ないラッコ。見た目もすむ場所もちがうため、ラッコがカワウソだと気付いていない方がいるかもしれません。
ラッコはアラスカ、カナダ、ロシアなど北太平洋に分布。岩場の多い海辺を好みます。
日本では北海道・霧多布岬など一部地域で確認されています。20頭ほどのラッコが暮らしているといわれています。
ラッコの生息数は減りつづけ、現在は推定12~13万頭。その80%以上がアラスカに生息しています。
IUCNレッドリストでは絶滅のおそれが極めて高い危機(EN)と評価されています。
天敵(シャチやサメ等)の増加や石油流出による海水汚染、毛皮目的の狩猟などがラッコを苦しめています。
ここ20年間で千島列島およびカムチャッカ半島のラッコは半数以下に。
現在のところ、その理由は確定されていません。食糧難や感染症などいくつもの原因が重なったのではといわれています。
ラッコの種類|生息地のちがい
北太平洋に生息するラッコ。分布域がひろいため生息地による違いがあります。
現在、3亜種に分類されています。
- 千島列島からカムチャッカ半島、コマンドルスキー諸島
- 1.5万頭
- アリューシャン列島から太平洋岸カナダとオレゴン州
- 10万頭
- アメリカ・カリフォルニア中央部
- 3千頭
- ちいさい
野生ラッコの80%以上はアラスカに生息しています。
ロシアラッコは1~2万頭、カリフォルニアに生息するミナミラッコは3千頭ほどしかいません。
ラッコはワシントン条約で国際取引が制限されています。なかでもミナミラッコは商業目的の取引ができない附属書Ⅰに掲載されています。
ワシントン条約は別記事でくわしく解説しています↓
ラッコと海
水が好きなカワウソですが、ラッコはカワウソのなかで唯一完全な海生動物。繁殖や睡眠など、すべての行為を海の上でおこないます。
後ろ足は「ひれ」のように平たく進化。潜水時に活躍するぶん、地上を移動するのは不得意となりました。そのため、ほとんど上陸しません。
一方、捕獲のおそれがなくラッコがたくさんいる地域では陸地にあがる姿が確認されています。
ラッコの群れ
ラッコは数十頭の群れをつくり、通常、雌雄は別々に行動しています。
オスのみが縄張りをもちます。しかし、他のカワウソのような分泌腺はなくパトロールして敷地をアピールします。
一方、メスは自由にオスのテリトリーを移動することができます。
藻があるところにラッコあり!
ラッコは休息するとき、ジャイアントケルプ(オオウキモ)という海藻に自分の体を巻きつけて、流されないよう工夫しています。
親ラッコが狩りに出る際は、海藻で子ラッコを固定します。子が潮に流されて迷子にならないためです。
つまり、ラッコが生きていくには藻が必要不可欠。多くの地域でジャイアントケルプとラッコの分布は重なっています。
海にいるのに泳ぎは苦手?!
ラッコは水深40メートルまで潜ることができます。オスはさらに深く潜水できます。
ところが、ラッコは泳ぎが得意ではありません。そのため、泳ぎまわる魚を捕るのは苦手。
水中でしか生活しないというのに、とても不思議。潜水と水泳は別物なんですね。
ラッコの冷え対策
水温10度以下という冷たい海の中に生息するラッコですが、寒さをしのぐ脂肪はついていません。
超毛深い!ラッコの毛
代わりに「動物一」といわれている極めて密度の高い体毛がはえています。おかげで、海に潜っても皮膚が濡れることはありません。
悲しいことに、ラッコのあたたかく上質な毛は人々のターゲットとなりました。現在もなおラッコの毛皮の密猟はおこなわれています。
毛づくろいはラッコの生命線?!
海上で生き抜くために毛をふやした結果、ラッコは毛づくろいに多くの時間を費やすことになりました。
ラッコは体をくねくねと動かしながら全身をくまなく毛づくろいします。清潔に保たなければ本来の毛がもつ能力を発揮しきれないのです。
なかには、1日6時間ほどかけて毛づくろいする個体も確認されています。
また、毛づくろいは保温力と浮力を高める効果があります。
毛づくろいをすると毛と毛の間に空気が取りこまれます。ときには息を吹きいれ、密集した毛の間に空気の層をつくります。
すると、ダウンジャケットのようにふわふわ暖かく、浮き輪のようにぷかぷか浮くことができます。
ラッコが体温を保てる本当の理由は「密度の高い毛」のおかげではなく、この「空気層」のおかげかもしれません。
ラッコのバンザイ
ラッコは手を水上にあげてバンザイのような格好をしていることがあります。
これは、手のひらには毛が生えていないため、海の中に浸けたままだと冷えてしまうから、と考えられています。
目や耳に手を当てる行為も冷え対策のひとつ。
見る人を笑顔にする、ラッコの愛くるしい姿です。
ラッコの食事
寒冷地帯に生息するラッコは、体温を維持するために10kgもの食事を摂ります。
狩りは早朝と夜間におこないます。
おもに貝類や甲殻類を好むが、ヒトデなどさまざまな海洋生物を食します。なかでもラッコの大好物はウニ。
棘皮動物であるウニは海藻を食べます。ウニが大量増殖すると、ジャイアントケルプは食べ尽くされてしまいます。
それを防ぐ存在がラッコです。ラッコは自らのすみかを守るために、ウニを食べているのかもしれませんね。
カワウソのなかまは噛む力がつよく、強靭な歯が生えています。
とくにラッコは体も大きいため、とても立派な歯を持っています。外見とは裏腹に、口の中を見るとおそろしささえ覚えます。
ウニや貝に穴をあけたり、殻を噛みくだけるのも納得です。
道具をつかって殻をわります
ラッコは、水中でエサを捕らえたら水面まであがります。
そして、歯で嚙みくだく、もしくはおなかに乗せた石などを使い殻をわります。
野生ラッコは岸壁や船体、飼育下ラッコは壁やガラスなどを利用することもあります。
霊長類以外で道具を使うのは非常に稀。ラッコはとても賢い動物なのです。
ラッコの石のかくし場所とは?
前述したように、ラッコはエサを食べるときに石を使います。
さて、その石はどこからやってくるのでしょう?
まさかの「脇」から出てきます!
ラッコは気に入った石を見つけたら、皮ふのたるんだ部分に隠す習性があります。
食事の時間にこそっと取りだし、おなかの上にテーブルのように乗せるのです。
地域によっては陸地に置き場所をつくっているラッコも観察されています。
ラッコの石は殻わりのときだけでなく、潜水の重りとしても利用されていると考えられています。
ラッコにとって自分の石はパートナー。とても大切にしています。
【YouTube】BBCで野生ラッコの様子をチェック!
ラッコの繁殖と寿命
繁殖期に入ったメスは、自らオスの群れへ近寄って行きます。
着床遅延が起こるため、見かけ上の妊娠期間は比較的長め。野生では、5~6月ごろに出産のピークを迎えます。
※着床:受精のあと胚が子宮内に定着し発育を始めること
※着床遅延:受精後すぐに着床せず、一定期間もしくは条件が整ったのちに着床すること
他のカワウソとは異なり、通常、1度に1頭の子が誕生します。
おなかの上で育つラッコの赤ちゃん
父親の育児参加はなく、8か月ほどは母親が面倒を見ます。
背を下にしてぷかぷか浮く姿はラッコ特有。子育ても、おなかの上でおこないます。
ラッコの赤ちゃんは明るい茶色のモフモフ、まるでぬいぐるみのよう。成獣よりも密度が高い毛を有し、沈むことはありません。
およそ3か月でおとなと同じ毛に生え変わります。
また、ラッコは成長とともに頭から胸の毛が白くなっていきます。
性成熟は遅く、5歳ごろと考えられています。
しかし、オスが実際に繁殖をはじめるのは、その数年後のことが多いという報告もあります。
ラッコの天敵とは?
海にすむラッコの天敵はシャチやホホジロザメ。
とくに母親が狩りに出ている間、無防備な子どもが捕食されることは少なくありません。
また、寄生虫により病死したり漁の網にかかって溺れたり、ラッコは幼獣だけでなく成獣の死亡率も高いといわれています。
天敵に襲われなければ、野生ラッコの寿命は15年~20年。
飼育下では30年近く生きた個体も確認されています。
2か所だけ!ラッコに会える施設
多くの水族館で展示され、日本に100頭以上いたラッコ。
繁殖能力の低下とともに、その数は減りつづけ、現在、2施設で3頭しか飼育されていません。
- メイ(2004年生)
- キラ(2008年生)
- リロ(2007年生)
リロは繁殖能力があるかもしれませんが、キラは妹なので交配できません。また、メイは高齢となってきたため妊娠は期待できません。
つまり、今後あたらしいラッコが来ないかぎり、日本の水族館でラッコが生まれることはありません。
かつては一大生息地であるアラスカを有するアメリカからラッコが輸入されていました。
しかし、絶滅の危険性や保全意識が高まった近年、取引はおこなわれていません。
ラッコに会えなくなる日はもうすぐです。
ラッコの過去と未来
ラッコはロシアからアラスカ、カナダなどの北太平洋から北海道やメキシコのバハ・カリフォルニア半島まで広く分布していました。
生息数は15~30万頭でした。
1780年ごろからラッコの毛皮目的の狩猟が活発化し、生息数は急激に減少。一時は数千頭にまで落ち込みました。
1911年、国際的な毛皮取引条約が施行されラッコ猟は禁止されました。
ところが、他の絶滅危惧種と同様、密猟が未だにおこなわれています。
近年は、油による海洋汚染がラッコの最大の脅威。油が付いた毛は機能を発揮できず、低体温症をまねきます。
さらに、毛づくろいのときにラッコが油を飲んでしまうため、胃腸障害など体調不良におちいることもあります。
現在の生息数は12~13万頭と推定されています。全体として減少傾向であり、絶滅のおそれが極めて高い状態です。
わたしたちヒトは200年以上前からラッコの生活を苦しめいています。
だからこそ、今、わたしたちにラッコを守る義務があります。
不法投棄や採掘等を規制できる保護区の制定・維持がラッコ保全の大きな鍵となっています。
最大のイタチ、ラッコ。
海のカワウソ【Sea Otter】と名付けられるように、カワウソとの共通点がたくさん見つかることでしょう。
ラッコが「もっとも毛深い動物」ということは、よく知られているかもしれません。
しかし、ラッコとウニと藻の関係や実は泳げないこと、石を大切にすること、バンザイの理由など、知れば知るほどおもしろく、そして可愛らしい動物です。
ラッコにしかない特徴や生態をぜひ実際に観察してみましょう!
以上、ラッコの豆知識でした。
【参考】


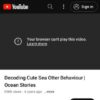








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません