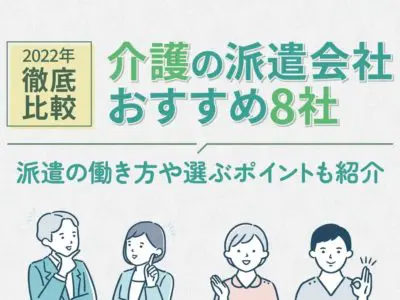音楽は私たちに感動や喜び、感銘をもたらします。
しかしそれだけではなく、近年では、「音楽にはリラックス効果やリフレッシュ効果があるのではないか」と注目が集まるようになりました。
音楽の力を借りてリラックスしたり、リフレッシュしたりすることができれば、人生はもっと豊かに、そしてもっと過ごしやすくなるはずです。
ここでは、音楽のもたらすリラックス・リフレッシュ効果に注目をして解説をしていきます。
目次 [表示]
音楽が感情に対して良い影響を与えることは科学的に実証されている
「音楽」は、私たちにとって非常になじみ深いものです。
世界でもっとも古い文明のうちのひとつであるメソポタミア文明の遺跡からは、太鼓やハープを奏でる人を描き出した石碑が発見されています。当時どのような音楽が演奏されていたかははっきりとはしていませんが、人間にとって、音楽が古き良き友であったことを伝えてくる発見だといえます。
このように昔から存在する音楽ですが、現代ではこれが精神に対して良い方向に作用することが医学的・科学的な分析によってはっきりと実証されています。
「音楽と感情」の関わりを研究したデータはたくさんありますが、ここではそのうちの2つを取り上げます。
成人女性の「怒り」に対して、音楽は良い方向に働きかける
まず取り上げるのは、日本で行われた研究です。「音楽を用いたリラクセーションの効果と心身健康科学-成人女性の怒りの気分に及ぼす影響から―」というタイトルで、日本赤十字病院の看護師である大谷喜美江氏が研究を進めたデータがあります。
この研究は、成人女性43人(乳幼児の保護者を含む)を対象としたものです。43人のうちの20人(うち、乳幼児の保護者17人。その他3人)に音楽を使用させ、残りの23人(乳幼児の保護者15人、その他8人)には音楽を使用させませんでした。
実験前の気分を確認し、その後に音楽を聴いた(あるいは聴かなかった)ときの感情の変化をみたこの研究結果では、非常に面白いことがわかりました。
音楽を聴いた人は、「精神の張りつめが緩んだ」「不安感が薄れた」「疲れが軽減した」と答える割合が多かったのです。また、「勢力がみなぎってきた」「生き生きしてきた」などのような、プラスの変化がみられた人も多かったという統計が出ています。
反対に、マイナスの反応である「かっとしやすい」「不機嫌である」「落ち着かない」などのようなマイナスの感情を持つ人は大きく減少しました。
特に、「精神の張りつめが軽減した」「怒りの感情が軽減した」「生き生きとした気持ちになった」は、音楽使用群は音楽未使用群に比べて2~5倍もその結果が高かったとされています。
「疲れを感じた」「不安感がある」「褒められるのに値しないと感じる」の設問については、音楽未使用群の方が高い結果が出ています。
この結果から30項目のうちの実に27項目において、「音楽を聞いた人の方が良い結果を得られた」ということは特筆に値するべきことでしょう。
ご年配の人の心持ちを明るくさせる効果もある
また、奈良県の老人福祉センター内で60歳以上の高齢者を対象とした研究もあります。平均年齢72.75歳の被験者40人を対象として行われたこの研究では、月に1回のセッションを4か月の間継続して受ける、というやり方がとられました。
人間の体に存在する生体物質に対して良い影響を与えた結果、被験者の抑うつ・不安感が軽減されたとの結果が出たのです。
ヒトの生体物質にまで言及したこの実験によって、「音楽は、両方のひとつとして数えられる可能性がある」と示唆されました。
このように、音楽には私たちの心を癒し、安心させ、怒りを軽減させ、リフレッシュさせてくれる効果が見込めます。音楽を上手に生活に取り入れることは、ストレスの少ない生活を送るために非常に有用なのです。
- 出典:
- 福井一「研究課題:高齢者を対象とした音楽療法効果の検証」-科学的根拠に基づいた臨床モデル構築を目指して―
- 大谷喜美江「音楽を用いたリラクセーションの効果と心身健康科学-成人女性の怒りの気分に及ぼす影響から―」
リフレッシュ効果のある音楽を探そう! その選び方

では、実際にはどのような音楽を取り入れればよいのでしょうか。
音楽には好き嫌いがあります。そしてこの「好き嫌い」は非常に重要なものです。
「心が安らぐ音楽」としてよく取り上げられるものに、ヒーリング系の音楽や自然の音があります。しかし「これらがあまり好きではない」という人にとっては、これを聞くことは逆に苦痛になるでしょう。
そのため、「自分が好きな音楽を聞き、嫌いな音楽を避けること」は大前提となります。
ただ、「特に音楽にこだわりがあるわけではない」「好きな音楽を聞くのはもちろん、音楽を『効果別』で選び分けるだけの知識もほしい」と考える人もいるでしょう。また、音楽によって得手不得手があるのも事実です。
今回は、これを踏まえて、「(個人差はあるものの)多くの人にリフレッシュ効果をもたらす音楽」を取り上げていきます。
なお、一口に「リフレッシュする」と言っても、「活動的な方向でリフレッシュして元気になりたい」という人もいれば、「じっくりと時間をかけて自分を癒してリフレッシュしたい」と考える人もいるでしょう。
どちらの考え方をとるかによって選ぶべき音楽も変わってきますから、このあたりについても解説します。
活動的な方向でリフレッシュして元気になりたいのならば
アクティブな方向でリフレッシュしたいということであれば、
- 1.歌詞付きの音楽
2.激しいアップテンポの曲
3.軽快で明るいジャズ
がおすすめです。
1.歌詞付きの音楽
「活動的な方向に気持ちを切り替えたい」「元気いっぱいになりたい!」という方向でリフレッシュしたいのであれば、歌詞付きの元気な曲を選ぶと良いでしょう。
自宅で聞くことを前提とするのであれば、声を出して一緒に歌える曲をチョイスしてみるのもおすすめです。
「声を出すこと」は、心と体をリフレッシュするための方法として広く知られています。
2.激しいアップテンポの曲
激しくてテンポが速い曲は、テンションを上げてくれます。また、スピーディな曲はストレス解消に最適な曲であり、活気をもたらしてくれます。
明るくて陽気な曲を選ぶのが良いでしょう。ポップなインストゥルメンタル曲も良いのですが、マーチなども良いです。マーチは、リフレッシュと同時に、やる気を呼び起こしてくれる音楽でもあります。
3.軽快で明るいジャズ
アメリカの南部で生まれたジャズの種類は、実にさまざまです。
ノスタルジックさや哀愁を感じさせるものもありますが、明るくて軽快なジャズもあります。
ピアノやギターといったおなじみの楽器で奏でられるライトなジャズは、気持ちをリフレッシュさせてくれることでしょう。
じっくりと時間をかけて自分を癒してリフレッシュしたいならば
「リラックスすることでリフレッシュもできる」という人の場合は、以下のような曲がおすすめです。
- 1.自然の音で構成された曲
2.クラッシック
3.琴や笙で構成される音楽
1.自然の音で構成された曲及びヒーリングミュージック
「自然の音で構成された曲」は、リフレッシュ(リラックス)効果の高い音楽として非常によく取り上げられます。
滝の音や鳥のささやき、虫の鳴き声などを取り入れたものが多く、心を解きほぐしてくれます。
また、「ヒーリングミュージック」も非常に高い人気があります。穏やかで優しい音色で構成されたものが多く、落ち着いた緩やかな流れをとっています。
自然音やヒーリングミュージックは、「かけながら眠ること」を前提としたものも多く、安眠効果もあります。
部屋を暗くして、ベッドの中で聞きながら眠るのも良いですね。
2.クラッシック
クラッシックは、リラックスとリフレッシュをもたらすものだといわれています。
クラッシックは人間のやる気を出させるとともに、自律神経のバランスを整えることができる音楽です。
また、上で挙げた「自然音」が心地よく感じるのは、自然音が独特のゆらぎを持っているからです。
この「ゆらぎ」は1/fゆらぎと表されますが、クラッシックにもこれが含まれており、とくにモーツァルトの音楽は、リフレッシュ(リラックス)効果が高いと専門家は指摘します。
3.琴や笙で構成される音楽
日本古来の楽器である琴や笙も、人の心をリフレッシュ(リラックス)させます。
これらが使われている「雅楽」は世界最古のオーケストラと言われていますが、人の心を安心させ、落ち着かせる効果があります。
リフレッシュ音楽を取り入れるときの注意点

音楽は、ひとつの「習慣」にもなります。
「リフレッシュをするときはこの曲を聞くのだ」「眠るときはこの曲を聞くのだ」と自分自身を習慣づけることで、よりその効果を得られやすくなります。
ただ、音楽を聞くときには注意点も。
リフレッシュ効果を得たいと考える場合、音楽をより身近に感じたいとしてヘッドホンやイヤホンを使う人もいるでしょう。
しかし、使い方を誤ったり、あまりにも長時間使い続けていたりすることで、耳が聞こえにくくなってしまうこともあります。特に、「活動的な方面でリフレッシュをするために、アップテンポで激しい曲を大音量で聞く」という人は注意をしてください。
ヘッドホンやイヤホンを使う場合は音量を絞り気味にします。また、ヘッドホンをベッドで使用する場合は、タイマー設定にして途中で音楽が止まるようにしてください。
まとめ
太古からあった音楽は、現在ではより体系的に、より医学的・科学的に整理され、分析されています。それによって、目的にあわせた音楽も選びやすくなっています。
私たち人間にとって、音楽は非常に身近であり、また欠かすことのできないものです。
楽しみとリフレッシュとリラックスのために、毎日の生活に積極的に取り入れていきたいものですね。