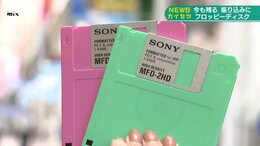高知県内3つの遺跡で出土していた板状の石6点が、弥生時代の硯とみられることが分かりました。四国で初めての確認で、弥生時代に県内で文字が使われた可能性を示す貴重な資料となります。
このほど発見された、弥生時代の方形板石硯(ほうけいいたいしすずり)と呼ばれる硯です。現在の硯とは異なり平たく、長方形や台形に近い形をしています。方形板石硯については、国学院大学の柳田康雄客員教授の研究により、近年、九州の北部から近畿・北陸にかけて、確認事例が増えています。県内3つの遺跡から出土していた弥生時代の遺物でも、6点が方形板石硯だったことが分かり、26日、県立埋蔵文化財センターで記者発表が行われました。弥生時代の板石硯が確認されたのは、四国で初めてです。これにより、弥生時代に、一部の地域では文字が使われていた可能性があることが分かりました。
「見てあっと驚いたのが、きれいな長方形が2点もあるということ。(福岡の)御床松原遺跡以外で、5ミリ以下の板石が見つかったのも初めて。今回の硯が発見されたことで、一定の文字文化を前提とした交流が(九州と)あった」(国学院大学 柳田康雄 客員教授)
今回発表された方形板石硯は、南国市の県立埋蔵文化財センターで、4月28日から5月8日まで展示されることになっています。
ADVERTISEMENT