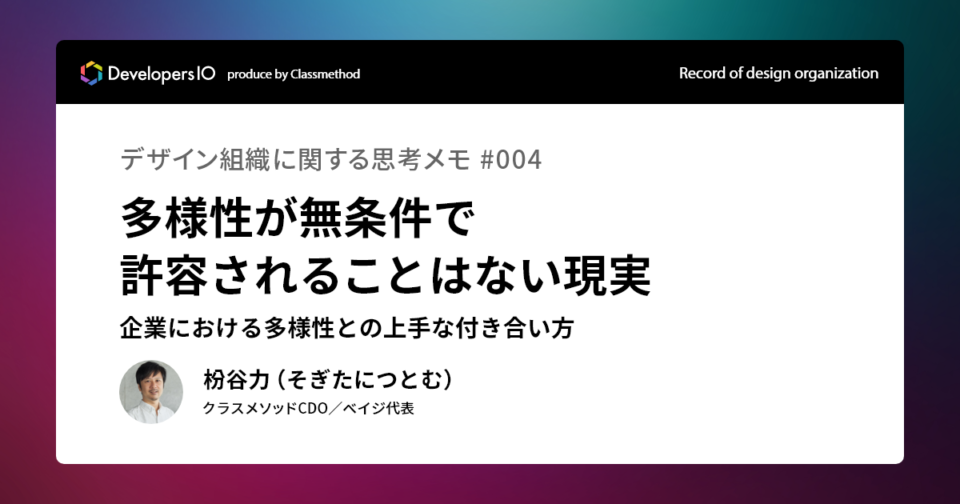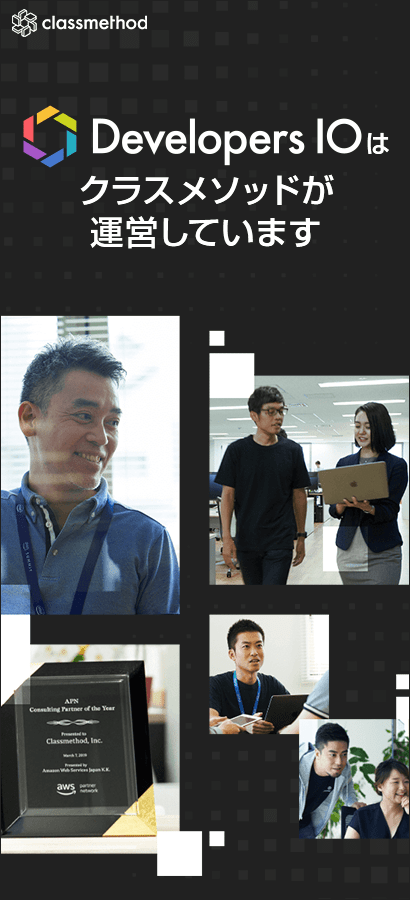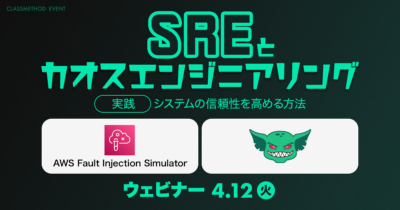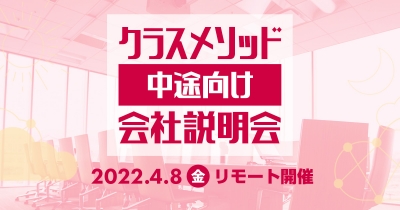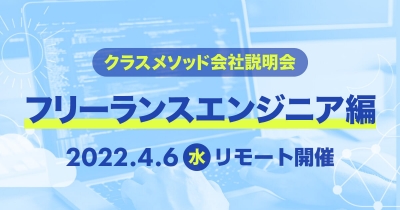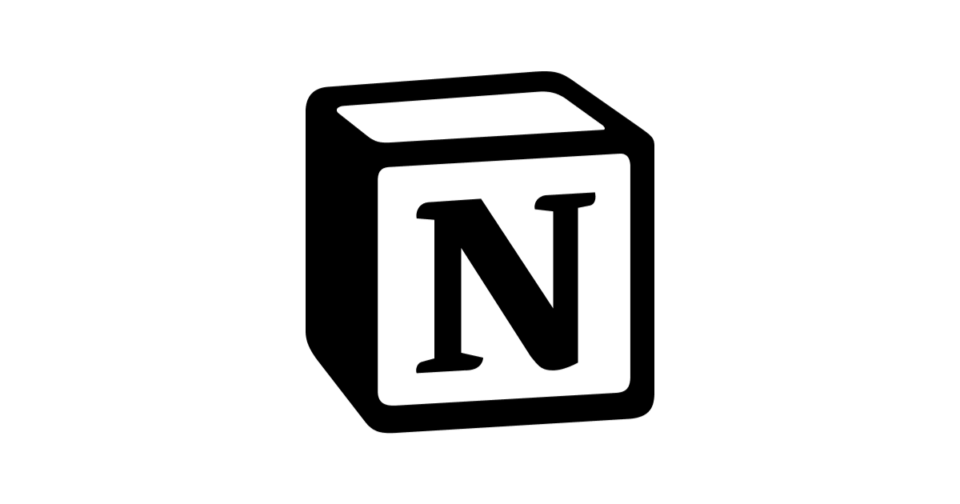ダイバーシティという言葉は以前からありましたが、SDGsの考えが拡がる中で、日常的に接する機会が増えているように思います。クラスメソッドのカルチャーを言語化した「Classmethod Leadership Principle」の中にも「ダイバーシティ」という項目があり、クラスメソッド社員にもなじみ深い言葉でしょう。
ダイバーシティを日本語に直訳すると「多様性」になります。しかしながら、人権や雇用機会の文脈で使われる「カタカナのダイバーシティ」は、すべての多様性ではなく、人のタイプやライフスタイル、働き方の多様性を差していることが多いです。つまり、多様性とダイバーシティは、日本においては微妙に異なったニュアンスの言葉といえます。
このエントリーは主に、ダイバーシティではなく多様性の話を中心にしています。
多様性は無条件に許容されるか?
多様性という言葉は既に一般用語となっており、特別な説明を加えず使われることがほとんどです。しかしよくよく考えると、一筋縄では解釈できない概念でもあります。
例えば、以下のような多様性を、私たちは多様性として受け入れることができるでしょうか。
- 人を殺したい
- 人の財産を奪って働かず暮らしたい
いうまでもなく、このような多様性は、社会的には受け入れられません。
そう考えると、世間一般で言ってる「多様性」とは、「無条件の多様性」ではなく「条件付きの多様性」ではないかと思います。
「人を殺したい」「人の財産を奪いたい」は、何らかの条件に反するから社会に許容されないわけです。
ではその条件とは何になるのでしょうか?
多様性が許容される条件
私は、「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」というのが、多様性の前提条件ではないかと思います。
「人を殺したい」「人の財産を奪いたい」は、人類や国家というコミュニティ全体が追い求めている「繁栄」や「幸福の総量の増加」という条件に反しています。憎い人を殺したり、金持ちから財産を奪ったりした本人はある種の幸福感を得られるかもしれませんが、それはその人だけの部分最適に過ぎません。人を殺したり財産を奪ったりする行為を社会で許容したら、社会全体は良い方向には進まないと考えられます。
だから多くの人間社会(≒国家)では、人を殺したり、財産を奪ったりする権利は認められていません。法律で禁止し、そのルールを破った人には罰則が与えられるようなシステムになっています。
逆に考えると、「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」と考えられる場合において、人を殺すことが許容されることもあります。それが死刑制度であり、戦争という名の国家による他国民の殺人です。死刑の執行や他国での戦争によって支持率が上がるという現象は、そのコミュニティの内側にいる多くの人が、ある特定の人々を殺すことによって、社会の全体最適に繋がると考えるからでしょう。
※ちなみに私自身は、例え国家の全体最適になるとしても殺人を肯定すべきではなく、回り回って全体最適にならないと考えています。これは、人類や歴史や国家レベルでは必ずしも人命を最優先に選択しないことがある、という現実社会のメカニズムを説明しているだけであって、私自身の理想の国家観はこれとは違うところにあったりします。
話がズレてきたので引き戻しますが、「無条件の多様性」は存在せず、「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」という前提条件が付くと認識しておくことは、多様性という概念と付き合う上で非常に重要なことだと私は思います。なぜならこの前提条件は、コミュニティのサイズが変わっても変わらないからです。例えば「企業における多様性」においても、「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」という前提条件がそのまま当てはまります。
企業が認める多様性
日本企業は、多様性をダイバーシティと外来語のカタカナで表現することが多いですが、それは、企業が推奨しているのは「あらゆるすべての多様性」ではないからでしょう。より具体的には、企業が推奨する多様性とは、主に以下のようなものです。
- 年齢の多様性
- 性差や性的志向の多様性
- 人種や国籍の多様性
- ライフスタイルの多様性
- ライフステージの多様性
- 宗教や政治信条の多様性
- 肉体的特性(障がいや病気など)の多様性
- 働く環境の多様性
企業がこれらの多様性を積極的に受け入れるのは、「事業の成長」というコミュニティの目的に対して、全体最適になると考えられるからです。
もちろん、創業者やオーナーの中にはそうした打算的な考えではなく、倫理観で選択していることもあるでしょう。あるいは社会の要請への最適化という受動的な側面もあるかもしれません。しかしいずれにせよ、社会の要請にきちんと応える倫理的な企業であった方が、市場からの支持を得られやすくなり、中長期的に事業の発展につながるだろう、という読みが根底にはあるのではないかと思います。
企業が認めない多様性
一方で、企業が認めない多様性も、存在します。
例えば、企業が締結する契約書には、反社会勢力の排除を謳う文言が記載されていることがほとんどです。これは、反社会勢力という現実社会に明確に存在する多様性を排除しているといえます。また、前科がある人は、国家としては(形式上)受け入れていますが、企業としてはより厳格に対処します。犯罪の内容が重大な場合、排除という判断をしてしまうことの方が多く、そのことは企業側の権利として社会的にある一定は認められています。
このように「企業が許容する多様性」とは、「国家が許容する多様性」と比べると、より狭いものになります。なぜなら企業というコミュニティの目的は「国家の存続」ではなく、「事業の成長」だからです。この目的に悪影響を与える多様性を受け入れると、事業の存在そのものがなくなり、コミュニティに属する人(従業員やその家族)に、不利益をもたらすリスクが生まれるからです。
反社会勢力や前科のような法律と交わる深刻な部分以外でも、企業が受け入れる多様性には、様々な制約が加わります。
例えば以下のような社員の要求は、多くの企業では多様性として受け入れられないでしょう。排除までいかなくても、「評価を下げる」という判断になることは多いはずです。
- 責任を負いたくないが権利は主張したい
- 他者には貢献せず、自分の利益は守りたい
- 新しいことを学ばず、できるだけ挑戦もせず、給料は上げたい
- 問題が起こったら誰かのせいにして火の粉を払いたい
- 後輩の面倒は一切見たくない
- 自分がやりたくないことはできるだけ拒否したい
- 周囲に貢献することより自分のプライドやスタイルを優先させたい
- 相手の手間を増やしてでも自分の手間を減らしたい
- 過去の成功体験を維持してできるだけ変わりたくない
- 人を陥れるズルい技を使ってでも自己の利益を得たい
- 嘘をついてでも出世して高い報酬を得たい
こうした希望も多様な価値観の一種ではあり、人として否定されるものではありません。しかしながら、これらを多様性として受け入れると公言する企業はほぼ存在しないでしょう。なぜなら「コミュニティが追求する目的(事業の成長)に対しての全体最適になる」という前提条件を満たしていないと判断されるからです。
上記のような希望を多様性として認めることは、本人にとっては都合がいいかもしれません。しかし、企業が求める「事業の成長」という目的に反し、全体最適にならない可能性があります。事業に貢献している社員、学ぶ意欲が高い社員、素直に地道に努力する社員、変わることを恐れず柔軟に挑戦していく社員の、モチベーションダウンや離反を招く可能性があります。そのことによって、事業や組織が弱体化するリスクが生じます。
だから多くの企業では、このような希望は多様性として受け入れません。人事評価でも有利に働きません。コンピテンシー評価をしている企業では、こうした考えに繋がる行動を推奨していないはずです。また、採用の選考においても、上記のような価値観や要求を持つと判断された場合には、高い確率で見送りにしてしまうでしょう。
こうしたことをまとめると、企業における多様性としては、以下のようなことが言えます。
- 企業においても「多様性」は「条件付き多様性」に過ぎない
- 企業においても「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」という前提条件が外れることはない
- 企業においては、「事業の成長」という目的に反する多様性は排除、もしくは評価の対象外になる
- 企業の多様性は、人間社会や国家の多様性よりも狭い
マネジメント側が考えること
企業や組織における多様性には前提条件があるため、マネジメント側はまず、その前提条件をより細かく定義する必要があります。つまり、「何を受け入れて」「何を受け入れないか」を、明確に言語化することです。
多くの企業が定義しているミッション、ビジョン、バリューもその一つと言えます。また、より具体的な行動指針も「その企業なりの多様性をデザインするツール」といえるでしょう。
ただ、言語化だけでは企業が求める多様性は完全に追求できません。なぜなら言葉には必ず解釈の幅があり、人には自分が都合がいいように言葉を解釈してしまう特性があるからです。
例えば「心理的安全性」という概念があります。この概念自体は非常に素晴らしいものだと私も思っています。実際に心理的安全性の重要性を明文化している企業も多いことでしょう。
一方、自分から歩み寄ることをしない他責思考の人が「うちの会社は心理的安全性がない」といって、厳しく社内批判をしていることがあります。ある人が「私の心理的安全性を確保してほしい」と主張することで、周囲の心理的安全性が削られてしまうようなケースです。このように、責任転嫁したい人の伝家の宝刀として心理的安全性という言葉が使わてしまい、経営者やマネージャーが頭を悩ませている、という話をしばしば耳にします。
実は、「多様性」という言葉にも似たような性質があります。他者の多様性に歩み寄りたくない人が「私の多様性を認めろ」と主張する、という複雑な構造になるケースです。これらの用法を私は「心理的安全性の勝手運用」「多様性の勝手運用」と呼んでいます。
言葉を尽くして言語化しても、それでも結局自分が好きなように解釈してしまう傾向が人にはあります。そのため言葉を定義するだけではなく、採用や組織編成の時点で、解釈の軸や目線が合うかを見極めることも必要です。心理的安全性や多様性のような抽象的な概念を、自己肯定のために解釈するのではなく、組織の成長、組織の全体最適に繋がるように解釈してくれるか、ということです。基本的な解釈軸が合っている人たちが集まってはじめて、言語化されたバリューや行動指針が有効になり、企業や組織の成長と多様性が両立していくのではないかと思います。
働く側が考えること
一方、社員や従業員、スタッフの立場としては、企業における多様性とどう付き合っていくべきなのでしょうか。
上記でお話ししたような「多様性の勝手運用」を行ってしまうと、多様性という誰もが否定しにくい素晴らしい概念を支持しているにも関わらず、社内では孤立してしまう、という現象が起こってしまいます。
そのため原点に立ち戻る必要があります。企業においても許容されるのは「条件付きの多様性」である。「コミュニティが追求する目的に対しての全体最適になる」という前提条件から外れることはない。「事業の成長」にとって全体最適になることが最優先。その上での多様性。ということを改めて認識しておく必要があります。
あえてドライな言い方をすれば、多様性は、事業を成長・発展・存続させるための手段に過ぎません。企業や組織は、「完全体の多様性」を実現するために事業を衰退させる判断をすることはありません。(もちろん、中長期的なメリットを期待して短期的な衰退を許容することはあるでしょうが)
「多様性」を錦の御旗にして自らの希望を訴えても、「事業の成長や存続」に貢献しないと経営者や上司に受け取られたら、おそらくその希望は通りません。企業は慈善事業ではないからです。これがビジネスの現実です。
多様性を自分のものにする
ビジネスの現実を踏まえた上で、もう一つ覚えておきたいのは、自分視点だけではなく、他者視点、組織視点をパラレルで持つ、ということです。
「多様性の勝手運用」の大きな問題点は、視点が自分・自己の利益にしか向いておらず、相手、周囲、会社、組織に向いてないことにあります。この視点を、自分ではなく、相手、周囲、会社、組織に向けるのです。そうすると、求められる多様性、許容される多様性が見えてきます。全体最適が理解できるようになります。
それさえ見えれば、自分の要求と、組織の要求が重なる領域を見つけ出すことができます。経営者や上司が受け入れられる、的確な交渉ができるようになります。こうした行動を積み重ねていくことで、組織の中での信頼が蓄積されていき、自分が望む多様性がそのコミュニティの中で許容されていきます。
例えば、コツコツと勉強するのが苦手で、それよりは人間関係を作っていくことの方が得意な人がいるとします。「学び続けることが大事」という価値観を表明する会社で、こうした人が「私はできるだけ学ばずに楽に給与を上げていきたいです」と主張すれば、おそらくその多様性は認められないでしょう。排除されることはなくても、人事評価上は不利な状況に追いやられてしまうでしょう。
しかしここで視点を自分から組織に視点を変えてみます。自分はできるだけ学習せず、組織の成長には繋がる方法を考えるのです。
例えば、自分自身は多くを学ばないが、学ぶことが得意な人たちを支援し、彼らのパフォーマンスが最大化するような環境を作ることに尽力します、このような考えであれば、それを受け入れる会社や上司は存在するでしょう。実行に移し、活動が周囲から認められれば、「自分は学ばないけど他の方法で貢献する」という希望が、その組織の中の多様性として受け入れられるはずです。そのシナジーが絶大であれば、もしかしたら学ぶ人よりも高い評価を得られることもあるかもしれません。」
「無条件の多様性なんて存在しない」「企業の多様性は国家や社会より遥かに狭い」などというと、随分と悲観的に思えるかもしれません。しかしこの前提条件を逆手にとって、自分の希望と相入れる方法を創意工夫すれば、企業にはやはりそれなりの多様性があり、懐が深いコミュニティであることが実感できるのではないかと思います。
社員や従業員、スタッフの立場として企業の多様性と付き合っていくには、このように視点を自分から外に向けてメタ的に捉える発想と、諦めずに創意工夫する姿勢が、必要なのではないでしょうか。
※この文章はあくまで私個人の意見であり、クラスメソッドという会社が考える多様性とは異なる可能性もありますが、ご了承ください。