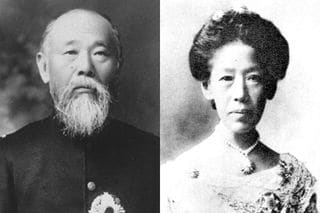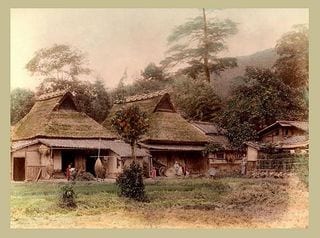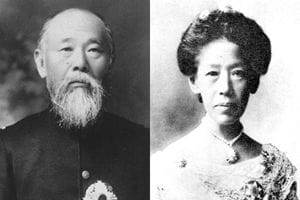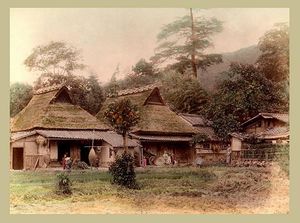日本男児としての理想的な陰茎の構成要素の組み合わせとしては、長さは17センチ以上で径は4センチ以上。
形は先端の鬼頭が大型の松茸型で、硬度の高いものが情事において、他人に引けを取ることなく、女性を悦ばせるための威力と効果が発揮されるようだ。
男女問わず男性の陰茎の大きさとその形は国内外を問わず関心が高いが、日本で巨根の代表者を挙げるならば、奈良時代の僧侶、道鏡であろう。
天皇になろうとした男、道鏡とは
日光の金精峠は道鏡の男根を金精神として峠に祀ったのがその名の由来だが、道鏡の巨根伝説は全国各地に伝えられ、数々の歴史書にも記されている。
淳仁天皇(733-765)は「あの禅師(道鏡)、放っておいては為にならぬ。(孝謙)上皇の寵遇を嵩(かさ)にきて増上慢ぶりは目に余る」と、その憤激を家臣である藤原仲麻呂にぶつけた。
その背景には、天皇の地位にありながら、孝謙上皇の背後で糸を引く妖僧、道鏡の介入が原因で思うように権力を握れない苛立ちによるものだった。
道鏡は「大化の改新」の中大兄皇子で知られる天智天皇(626-672)の子・志貴皇子の落胤説で皇位を授かる資格があったとの説もある。ちなみに志貴皇子の孫は平安京に遷都した桓武天皇である。
だが、物部氏の一族・弓削氏の末裔、弓削櫛麻呂の息子として生まれたというのが、道鏡の出自で最も有力な説とされる。
道鏡は修験道の開祖・役行者が開山した葛城山で苦行を重ねて呪験力を身につけたという。
その後、法相宗の高僧、義淵の弟子となり、さらには東大寺の華厳宗の名僧良弁の弟子となる。道鏡の祈祷は平城京の都で評判となり、やがて宮中に招かれる。
宮中に設けられた仏教道場に仕える看病禅師として、道鏡は病に伏せった孝謙上皇を治療する役目を拝命する。