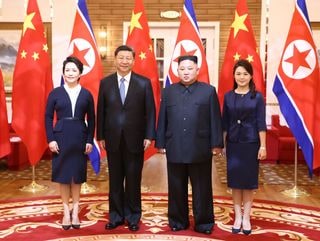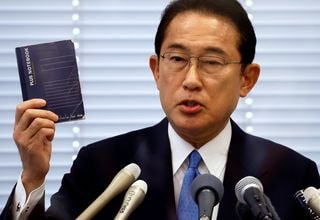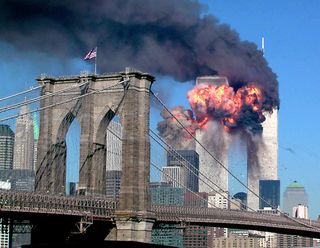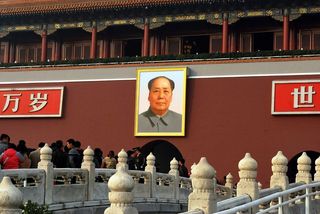「生きてゆくために必要」というお言葉の問題点
天皇と皇室は、その私的行為も含めて、ひとえに「公」の存在である。憲法に明文化されていない「皇族の基本的人権」でなし崩し的に、天皇の公的な存在意義を相対化・無力化することは、憲法の精神から逸脱するものではないか。
「小室さんは本当に素晴らしい男性なんです」と西村泰彦宮内庁長官に迫られた(文春オンライン)という内親王におかれては、「30歳までに結婚したい」「早く窮屈な皇室を出て、自由な生活を送りたい」(週刊女性)との願望から、「結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です」と仰せられている。切迫感があり、思い通りになければ天地がひっくり返ると思わせるようなお言葉である。
しかし、その「生きていくために必要な選択」ができない若い国民が増えている。経済格差の拡大により、憲法上の結婚の自由を持っていても絵に描いた餅に過ぎず、結婚したくとも社会構造的にできないのだ。
たとえば、国立社会保障・人口問題研究所が行っている出生動向基本調査によると、「いずれは結婚しようと考える未婚者の割合」は9割弱で推移しており、依然として高い水準にある。にもかかわらず、経済的事情や社会的意識の変化などにより、2015年時点での「50歳時の未婚率」は男性が23.37%、女性は14.06%と、両性で2010年よりも3ポイント以上も上昇している。
働く人の38%が非正規雇用で、その平均年収が179万円(国税庁2018年発表)であれば、結婚できない人の数が増加していることは驚くに当たらない。また、単身所帯の38%が貯蓄ゼロである(金融広報中央委員会2019年調査)。
こうした背景に加え、コロナ禍で多くの国民が対面の活動や仕事が制限され、心理的にも経済的にも追い詰められて苦悶している。だが、生きるに生きられず、死ぬに死ねない状況下においても、笑顔を見せながら、耐えがたきを耐えている国民がたくさんいる。
皇室制度に詳しい静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次氏は、「世界中で、そして国内でどれほど多くの人びとが新型コロナで命を落としたでしょうか。経済的に追い詰められて自ら道を絶った人もいます。そうした状況のなかで、『生きてゆくために』といった脅し文句を、皇族が口にすべきではなかった」と語っている。
また、元宮内庁職員の山下晋司氏も、「(2020年11月13日に出された眞子内親王殿下のお気持ちの文書には)“公”のお姿が見えず“私”が前面に出ている」「ご本人のみならず役人が動く財源は税金です。ご本人の意思は尊重されるべきですが、民間のお金持ちのお嬢さまが好きに恋愛して結婚するのとは、まったく異なる話です」と述べている。
勤労の義務を負う国民(憲法第27条)の血税による一時金あるいは事実上の公費援助を「拒否できない」とマスコミに解釈される内親王にあらせられては、自身の結婚を決定事項として急がず、ひとりひとりの国民の苦しみに寄り添って再考されることが、皇族のあり方ではないだろうか(参考)。