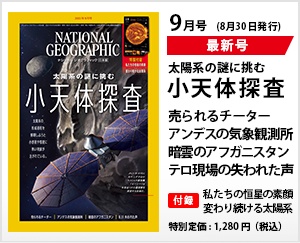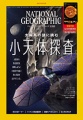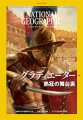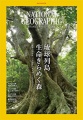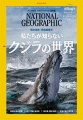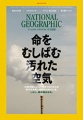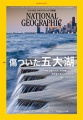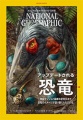第4回 「分離脳」だから分かった感覚のつながりとは
ひとつは、「多感覚統合」について。ぼくたちはいろいろな感覚を通して、この世界を認知したり、それをもとに行動したりしている。その際、ひとつだけの感覚に頼っていることは、実はあまりない。様々な知覚が、脳の中でどんなふうに並列処理され、統合されるのかというのは、とても重要なテーマだ。実は、前回の時間の知覚の研究も、視覚と聴覚がせめぎ合うという意味では、すでに多感覚統合の研究だったともいえる。
深く突っ込めば、どんどん専門的になってしまうが、ここではできるだけ分かりやすい例を挙げてもらおう。
「ちょっと変わり種の共同研究なんですが、臨床研究をやろうとしたら、基礎研究になってしまったみたいなプロジェクトがあるんです。脳の左の脳と右の脳が生まれつきつながっていない患者さんがいらっしゃって、分離脳と呼ばれています。さっきお見せした川端さんのMRIでは、左右の脳の間に太いコネクションが白く見えていたと思うんですが、分離脳の人は、それがないんです」
分離脳、英語ではスプリット・ブレインという。右脳と左脳をつなぐ脳梁がないために、研究対象としてよく取り上げられてきた。もともと脳梁を欠く疾患の人もいれば、重たいてんかんを患い片側の脳で起きた発作が隣の脳にまで波及するのを防ぐために脳梁を切断した人もいる。本来あるはずの情報伝達経路がない人たちを見ることで、分かってくることがあるという。
「人の視覚って右の視野に何かを見せると、その情報は左の脳にいくんですね。一方、左の視野に見せると、その情報は全部右の脳にいく。我々の脳は、視覚情報を左右別々に処理して、脳梁を介して情報をやりとりする仕組みになっている。なので、分離脳の人の右視野にだけ何かを出すと、その情報は左の脳しか知らないわけです。一方で、右の脳は左手を、左の脳は右手をコントロールしています。なので、右視野に何かを出すと、左の脳はそれを知っているけれど、右の脳は知らず、右脳がコントロールする左手でそれをつかむことができない。ただ知らないから」
実は、ここまではよく知られている実験で、四本さんたちが発見したのは、「その先」だ。