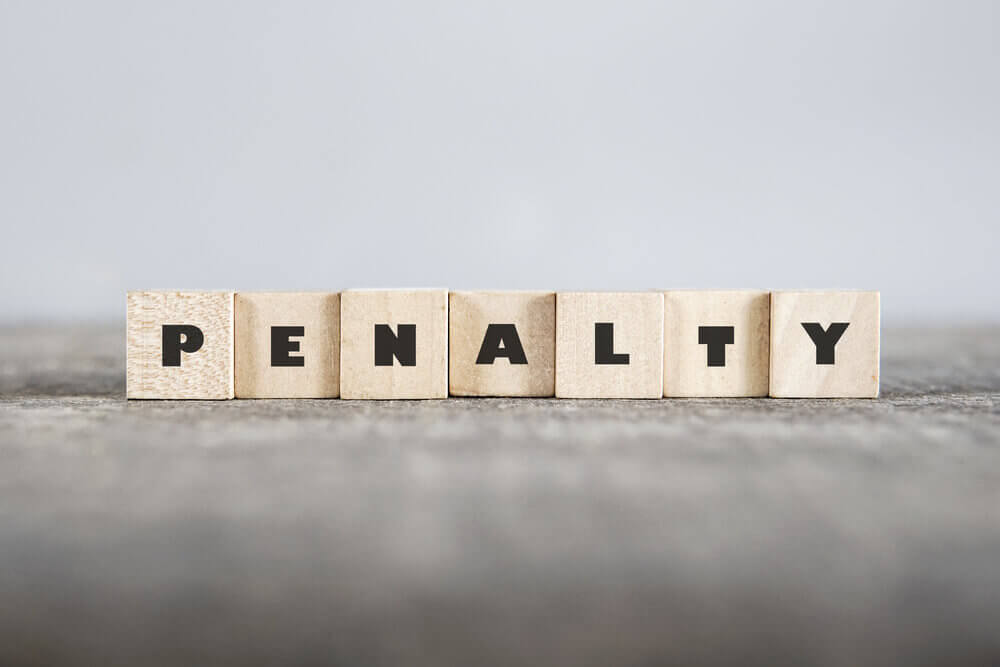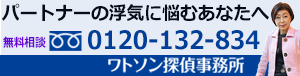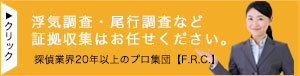離婚後、妻が子どもの親権者になったけれど、養育費を払わないとどうなるのかな……。
離婚して親権を失った方で、養育費についてこのような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年では、養育費の不払いが社会問題として取り上げられることも少なくなくありません。
養育費の不払いに対する社会の目も厳しくなりつつあります。
とはいえ、
- いったん取り決めた養育費はどんなことがあっても払わなければならない
- 養育費を支払わないなら子どもに会わせない
などといった、養育費の支払い義務者に酷な要求まですべて受忍しなければならないわけではありませんし、場合によっては、養育費を支払わなくてよくなる場合もあります。
今回は、多くの離婚問題を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、
- 養育費を払わないことによるリスクとは?
- 養育費を払わなくてよくなる方法とは?
- 養育費を減額できる方法とは?
について解説していきます。この記事が、養育費の支払いでお困りの方の手助けとなれば幸いです。
養育費を求めている方向けの記事はこちらです。
関連記事目次 [hide]
1、養育費を払わないとどうなるか
まずは、養育費を払わないといったいどうなってしまうのかという問題についてご説明します。
(1)養育費を払わない場合の罰則
養育費の支払い義務は、民法第877条第1項に法的根拠があります。そして、離婚する場合には父母の協議によって養育費に関する事項を取り決めることとされており(民法第766条1項)、協議がまとまらないときは家庭裁判所が決めることとなっています(同条2項)。
このように、養育費については民法にその根拠があり、仮に支払義務者が養育費を支払わなかったとしても民法は特に罰則は設けていません。養育費の不払いが何らかの犯罪に該当するわけでもありません。
ただし、養育費の不払いを続けた末に、裁判所による一定の手続きに違反した場合には、刑事罰が科される可能性があります。
まず、養育費の支払いについて定めた確定判決や調停調書、審判書、公正証書といった「債務名義」がある場合、親権者は支払義務者の財産を差し押さえる前提として裁判所に「財産開示手続」を申し立てることができます。
裁判所が財産開示手続を実施した場合、支払義務者が裁判所に対して財産を開示しなかったり、虚偽の内容を開示した場合には、「陳述等拒絶の罪」として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります(民事執行法第213条1項5号、6号)。
(2)民事上のペナルティ
また、罰則というわけではありませんが、養育費を払わないことによって民事上の不利益を被る可能性もあります。
養育費も民事上の金銭債務ですから、定められた期限までに支払わないと、通常の借金と同じように遅延損害金が発生します。
民法上の遅延損害金の利率は3%(2020年3月31日以前に養育費について取り決めていた場合は5%)ですから、銀行預金の利率よりもはるかに高い利息といえます。
一般的には、養育費の支払いがちょっと遅れたからといって遅延損害金まで請求する場合は少ないと思いますが、何年も支払わないでいると、思わぬ金額になってしまうということがありますので、注意が必要です。
(3)財産の差押え
養育費を払わないことによる最も現実的な不利益は、給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があるということです。
先ほどご説明した「債務名義」がある場合、親権者はすぐに裁判所へ強制執行を申し立て、支払義務者の財産を差し押さえることができます。
仮に給料を差し押さえられた場合、未払いとなっている養育費を完済するまでは毎月、給料を一部しか受け取れなくなってしまいます。
債務名義がない場合は、いきなり財産を差し押さえられることはありません。
しかし、その後、調停や裁判を起こされて金額が定められると、債務名義がある状態となってしまい、それでも支払わないと、上記で述べたように、給料や預金口座、不動産などの財産が差し押さえられてしまうという事態に発展してしまいます。
(4)養育費の不払は面会交流に影響するか
離婚した夫婦の間でよくあるのが、親権者がもう一方の親に、「養育費を支払ってくれないのであれば、子供には会わせない」などといって、子供に会わせることを養育費の支払いと交換条件にすることです。
しかしながら、子供との面会交流と養育費の支払いを交換条件とすることはできません。
面会交流も民法第766条1項及び2項の法的根拠を有する権利です。
これは、子供と同居していない親が子に会う権利であると同時に、子が親に会う権利でもあります。
ですから、面会交流は、親が子に暴力をふるったり、虐待したりする可能性がある場合のように、面会交流を行うことが子供のためにならない、と判断されるような例外的な場合でない限り、親権者はこれを拒絶することはできません。
特に、近年、親が離婚した場合であっても、子供にその責任はないのだから、両親が子供にとって何が一番よいかを建設的に考えて関わっていくべきであるという考え方が推奨されてきています。
法務省も離婚後の面会交流についてパンフレットを作成する等して、適切に面会交流を行うことの重要性を説いています。
裁判実務においても、面会交流が制限されることは少なく、面会交流を行う回数や場所、方法等をしっかりと定めて面会交流を促す方向にあるといえます。
ですから、養育費を支払わないからといって、面会交流が制限されることは基本的にはありません。
もちろん、当事者間で、「養育費を支払わないときは面会交流できない」などと取り決めを交わしても無効ということになります。
とはいえ、養育費を払わないと親権者が子供に会わせてくれないという事態は現実によくあることで、その場合には面会交流を求めて調停や審判を申し立てる必要があります。
現実問題としてスムーズに面会交流ができなくなるというリスクは頭に入れておくべきでしょう。
2、離婚後子供に会っていない!こんな場合も払わないといけないの?
なかには、離婚後子供に会っていないことを理由に養育費を払いたくないとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
元妻が子供との面会交流を拒否する場合の他、自分も子供にどう接するべきかわからないので会いたくないという場合、あるいは、そもそも子供に会いたいと思わない場合もあるかもしれません。
しかし、上でご説明したとおり、養育費の支払いは面会交流との相関関係にありません。
離婚しても、またその後子供に会っていなくても、親子関係は継続し、子供に対する扶養義務があるのです(民法第877条1項)。
したがって、離婚後子供に一切会っていない場合でも、養育費を支払う必要があります。
他にも、以下のような事情がある場合には養育費を払いたくないという気持ちになるかもしれません。
- 元配偶者の両親などの親族がお金持ち
- 離婚原因が相手側にあった
- 財産分与でほとんどの財産を分与した
- 子供が一切自分に懐いていない
しかし、これらの事情があっても、法律上は、養育費は支払わなければなりません。
3、養育費を払わなくてよい場合
離婚後子供と会えても会えなくても養育費を支払わなければなりませんが、事情によっては、例外的に養育費を払わなくてもよい場合があります。
それは、以下のケースです。
(1)支払い能力がない場合
養育費を支払いたくても支払う能力がない場合にまで、支払う必要はありません。
例えば、リストラや病気などで失業し、無収入のまま次の仕事が見つからないような場合には、養育費の支払い義務を免れることができます。
養育費の法的根拠は、親族間の扶養義務(民法第877条1項)にあります。
親族間の扶養義務とは、自分と同じ程度の生活を相手も維持できるようにする義務のことです。
ある程度の収入がある場合には、多少は自分の生活レベルを落としてでも養育費を支払う必要がありますが、余裕がない場合にまで支払わなければならないという義務ではないのです。
(2)相手方の方が収入が高い場合
養育費の支払い義務や、支払う場合の金額は、一般的に裁判所が公表している養育費算定表を基準として決められます。
養育費算定表では、支払う側と受け取る側の収入のバランスに従って養育費の金額が定められています。そのため、支払義務者の収入が低く、受取権利者の収入が高い場合には、養育費の支払い義務を免れるケースもあります。
実際のところ、父親が親権者となったケースの多くでは、母親に対する養育費の請求は行われていません。
その理由は、父親の方が母親よりも収入が高いケースが多いことによります。
したがって、母親が親権者となった場合であっても、母親の収入が極端に父親よりも多い場合には、父親は養育費を支払わなくてよい可能性があります。
(3)相手方の同意がある場合
養育費を支払うかどうかは、父母の協議によって自由に決めることができます。
したがって、養育費を支払わないことについて相手方の同意がある場合には、支払う義務はありません。
実際のところ、離婚後は相手方と一切関わりたくない場合や、養育費代わりに財産分与で多額の財産を分与するような場合で、継続的な養育費の支払いはしないことを離婚時に取り決めているケースも少なくありません。
(4)相手方が再婚して子供と養子縁組した場合
離婚後に相手方(親権者)が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をした場合は、そちらで親子としての法律上の扶養義務が発生します。
そのため、離婚した親が養育費を支払う義務は免除される可能性があります。
(5)子供が成人に達した場合
養育費は、基本的に未成年の子供の養育にかかる費用のことを指します。
2021年4月現在の民法では成人年齢は20歳とされていますので、原則として子供が20歳に達したら、その後は養育費の支払いを拒否できます。
ただし、離婚時の取り決めで「大学を卒業するまで」「22歳まで」などとしていた場合には、その取り決めどおりに支払う必要があります。
なお、2022年からは成人年齢が18歳に引き下げられる予定ですが、養育費の支払いについては引き続き20歳まで支払うのが原則になると考えられています。
また、既に取り決めた養育費の支払い期間が、成人年齢の引き下げによって自動的に変更されることもありません。
(6)子供が未成年でも就職した場合
子供が成人に達する前でも、就職して自活できるようになった場合には、親族の扶養義務として養育費を支払う義務は消滅すると考えられています。
例えば、子供が高校を卒業して就職し、給料をもらうようになったら、たとえ離婚時に「20歳まで養育費を支払う」と取り決めていたとしても、その後は養育費の支払いを拒否できるようになります。
4、養育費を減額できる場合
養育費の支払いを拒否できない場合でも、減額なら可能な場合があります。以下で詳しくご説明します。
(1)支払う側の収入が減った場合
前記「3(2)」でご説明したように、養育費の金額は支払う側と受け取る側の収入のバランスに応じて決まります。
したがって、支払う側の収入が減った場合には、支払うべき養育費の金額も下げられることになります。
リストラや病気などによる失業の他、勤務先の会社や自営している事業の経営状況の悪化による減収などでも養育費の減額が認められる可能性があります。
(2)受け取る側の収入が増えた場合
養育費の金額が支払う側と受け取る側の収入のバランスで決まる以上、親権者である相手方の収入が増えた場合にも、非親権者が支払うべき養育費の金額は下げられることになります。
(3)支払う側が再婚して子供ができた場合
離婚して母親が子供の親権者となり、父親が養育費を支払っていた場合に、父親が再婚し、再婚相手との間に子供ができた場合にも養育費を減額できる可能性があります。
この場合、父親は、前妻との間の子に加えて、配偶者である現在の妻とその子の扶養義務を負います。
扶養義務者が増えることにより一人当たりにかけられる金額は少なくなる、という考え方から、前妻との間の子に対する養育費が減額されるということになるのです。
5、養育費の免除・減額を勝ち取るまでの流れ
離婚時に養育費の支払いについて取り決めていた場合は、上記「3」及び「4」でご説明した事情がある場合でも、自動的に養育費が免除されたり減額されたりするわけではありません。
養育費の免除や減額をしてもらうためには、以下のように適切な手順を踏む必要があります。
自己判断で勝手に養育費の不払いをした場合には、前記「1」でご説明したリスクを負うことになりますので、ご注意ください。
(1)相手との話し合い
まずは、相手方と話し合うことによって、今後も養育費を支払うかどうかや、支払う場合の金額について新たに取り決めましょう。
話し合いがまとまったら、新たに合意書を作成することが大切です。
取り決めた内容を書面の形で残しておかなければ「言った・言わない」のトラブルが発生する可能性があり、前記「1」でご説明したリスクを負ってしまうおそれもあります。
(2)養育費減額調停を申し立てる
相手方との話し合いがまとまらない場合や、話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所へ「養育費減額調停」を申し立てましょう。
調停では、調停委員を介して相手方と話し合いを進めることになります。
その際、収入や生活環境の変化を証明できる証拠を提出することが重要です。
調停委員に対して、証拠に基づいて養育費の免除や減額が相当であることを説明するのです。
調停委員が、養育費の免除や減額が相当であると判断した場合には、相手方の説得に努めてもらえるので、話し合いがまとまる可能性が高まります。
話し合いがまとまると調停が成立し、その後は合意した内容に従うことになります。
(3)養育費減額審判を求める
調停で話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となりますが、自動的に「審判」の手続きに移行します。
審判では、当事者双方から提出された主張や意見に基づいて、裁判所が相当と認める判断を下します。
したがって、審判で納得できる結果を獲得するためにも、収入や生活環境の変化を証明できる証拠を提出することが重要です。
なお、養育費減額調停を申し立てず、最初から審判を申し立てることも可能です。
しかし、ほとんどの場合は家庭裁判所の職権で「まずは話し合ってみましょう」ということで調停に付されます。
そのため、通常は養育費減額調停から始めることになります。
6、養育費を払わない方法をお考えの方は弁護士へ相談を
養育費を「払いたくない」、あるいは「払いたくても払えない」と思ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
自己判断で養育費を不払いにすることには大きなリスクがありますので、まずはご自身のケースで養育費の免除や減額が可能かどうかについて、弁護士のアドバイスを受けてみましょう。
免除・減額が可能な場合は、弁護士に依頼すると複雑な手続きをすべて任せられます。
法律のプロとして的確に手続してもらえますので、納得できる結果を獲得しやすくなります。
リスクを回避して養育費の負担を軽くすることに役立つでしょう。
まとめ
養育費の不払いについては、世間の目が非常に厳しくなりつつあります。
だからといって、過剰な要求に応える必要はありません。確かに、養育費は、子供に対する親としての義務ですからこれを支払うのは当然です。
ただ、いったんお金として渡してしまうと、本当に子供のために使われたかどうかわからないような場合もあります。
ですから、納得して養育費を支払うためにも、その使途等について明確な報告を求めること等も大事です。
また、子供名義の積み立てや保険を利用して養育費替わりにする等、真に子供の将来のために利用できるものとする方法を選択するという手段もあります。
親である以上、養育費として一定の負担をすることは当然ですが、その額は適切かどうか、また、支払った養育費が本当に子供のために使われているかどうか、ということを常に意識することが大切です。
悩ましい点があれば、気軽に弁護士の無料相談を利用してみるとよいでしょう。