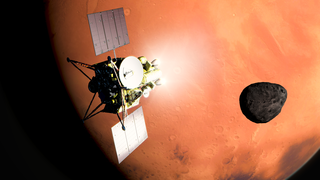「好きを仕事にしよう」「やりたいことで生きていこう」という言葉は聞き飽きてしまった若者も少なくない(写真はイメージです)。
shutterstock/ Wunlop_Worldpix_Exposure
「好きを仕事にしよう」「やりたいことで生きていこう」
数年前からこんな耳ざわりのいい言葉が流通した。メディアのキャリア系インタビューやSNSはこういう言葉であふれたし、ブームっぽくなっていたのも事実だ。
ただ、Z世代はじめ若年層にとって、この言葉は少々鬱陶しいものになっているのかもしれない。
「やりたいことって、ないといけないの?」
「やりたいことを見つけるためには」「好きを仕事にする方法」
SNSにあふれるこんなキャリアに関する「考え方」は、キャリアに悩む人や就活生といった当事者「以外の人」たちからの発信が多い。
20代の人たちと話していると、明らかにこういう情報を本人の希望とは関係なく浴びすぎて疲れている。アレルギーっぽくなっていると思うことがある。
「やりたいこととか特にないですね。何かやたら聞かれるので面倒臭いです」
「やりたいことって、ないといけないんですか? ない自分はダメなのかなと焦ります。」
「著名人の人のインタビューって憧れたりするんですけど、自分にはそんな壮大なビジョンとかないなぁって思います」
「ずっと働きたいので、そのために(やりたいことより)まずはできることを増やしたいです」

ツイッターの呟きには「やりたいこと」を探す若者の声が見られる(写真はイメージです)。
shutterstock/viewimage
たしかに、キャリアに関して流れてくる情報は超暗い話か、超キラキラした話か両極端な気がする。
Twitterのタイムラインには、リストラがどうだとか、就活や転職が大変というシリアスなニュースに事欠かない。その一方で「日本を変える」的なキラキラビジョンや、「私らしく生きる」的なピカピカの写真が交互に流れてくる。
過度に不安を煽る情報か、過度に美化された個人の解釈はインパクトがあるのでウケがいい。特にPVが大事なメディアにおいては「インパクトをつくらねば」という力学も働くのだろう。
筆者は普通の「働く人たち」が仕事や会社を選ぶ「等身大の理由」を一カ所に集めたいと思って、働く人のホンネが見られるキャリアの地図のようなサービスをつくっている。それも、その両極端な情報に対する違和感があるからだ。
「いい●●」という成功や幸福のモデルが苦手

世に流通する「成功モデル」を、全ての若者が夢見るわけではない(写真はイメージです)。
shutterstock/Matej Kastelic
筆者は現在33歳だが、20代の頃は「いい会社に入って楽するために、今我慢して勉強しよう」「老後にゆったり旅行するために、今我慢して働こう」などという、「いい●●」という人生の成功や幸福のモデルが苦手だった。
そうしたモデルが常に「今我慢すること」を強いてくるのが気持ち悪かったからだ。
そんなに先のことなんて分からないし、今の方が大事だった。
「今我慢すれば、将来ラクだよ」と、上の世代から押し付けられていた成功や幸福のモデルに対するしんどさは、今の20代にしてみると「やりたいことをやるためには●●すべき」がそれなのかもしれない。
知らないうちに自分が押し付ける側になっていないか、ドキッとする。
「社会をよくしたい」を裏返すとどうなるか
「もう、ウチら向けの社会じゃないよねって話してます」
ある学生と話していたときに出た言葉だ。
若い世代からしばしば聞こえてくる「社会をよくしたい」という声も、裏を返せば「社会がよくなさすぎて絶望している……」というのが本音らしい。
自分が何か頑張ってよくなる程度ではないくらいに、彼ら彼女らの目に映る社会は見るに耐えないし、自分たちがその一員だと思うには疎外感が強すぎるようだ。
「コロナ報道で、ひたすら若者が悪者にされているし、ワクチンも若者が悪者、オリンピックは若い人の案が年配のエラい人に潰されたんですよね」
とある大学3年生の男性は言う。
「セクハラパワハラも当たり前。就活でSDGsの気になるテーマについて話をしたら、面接官の人に『意識高いね』って笑われました。何か社会ってアウェイな感じがしてます」
確かに「そうだな」と思った。
環境やジェンダーに上司や先輩が「無知」

女性蔑視発言をきっかけに辞任した森喜朗氏。
GettyImages/Yoshikazu Tsuno - Pool
学校で当たり前に習っている多様性や環境やジェンダーなどの社会課題に対して、先輩が無知だったり、意識が低かったりするのを目の当たりにすると、確かに「この人たちを敬って働かないといけないのか」となってしまうのも無理はない。
とはいえ、宝くじが当たったりしない限りは、生活するために働かないといけない。しかも寿命はどんどん伸びてしまうらしいし、年金も不安だ。
「やりたいことはないけれど、やりたくないこととか、ムカつくことは無限にあります」(前出の大学3年生)
という言葉が印象的だった。

過去につくられた、矛盾し、「ムカつく」社会システムはまだ根強く存在する(写真はイメージです)。
shutterstock/Fotoluminate LLC
前の世代が築いてきた社会システムは、環境の変化に耐えられなくなっているし、バグばかりだ。
若い世代がその古いシステム自体、自分たち向けとは感じられないのであれば、そのシステムの中で成功している企業にも、そのシステムを維持するための仕事にも、魅力を感じられないのは無理もないかもしれない。
ただし、一見古いその社会システムも、これまでも「変えたい人たち」と「維持したい人たち」のせめぎ合いの中で進化してきた。
そういう意味でも、ムカつくことからキャリアを探すというのは、今の大きな社会変化の中では、自然な仕事選びなのではないかと思う。
例えば、筆者の場合は、仕事選びの情報があまりにも不透明で、会社に入ってみるまでわからないことが多すぎるということが「ムカつくこと」だった。
だから今は、ずっと不透明な仕事選び(就活や転職)の構造を変える仕事を、HRのベンチャーで葛藤しながら続けている。これも毎日ムカつくからこそ、やり続けられると思う。

やりたいことがないからと言って焦る必要はなく、自分のエネルギーに目を向けてみるとヒントが見つかるかもしれない(写真はイメージです)。
shutterstock/Tijana Moraca
「怒り」は創造のエネルギー
「『怒り』は創造のエネルギー。自分の理想があって、現状をちゃんと認識していて、そこにギャップを感じているから怒ることができる。だから怒りの感情は美しいもの、大切にした方がいいんだよ」
仕事選びに関する情報の不透明さに怒り狂っていた4年前の僕は、ユニリーバ取締役・人事総務本部長の、島田由香さんのこの言葉に救われた。
やっていないのに文句を言ってはいけない。異議を唱えては波風が立つ。そんな抑圧感の強い不自由な社会のムードの中で自己嫌悪に陥っていた筆者は、「この怒りを創造に使おう」と、この言葉によって初めて素直に思えた。
もしあなたが、やりたいことなんてないよ……とモヤモヤしているのならば、時代の転換点ならではの、ムカつくことでキャリアを選ぶという考え方をぜひ、試してみて欲しい。
もちろん、怒るエネルギーすらないよ、という人もいるだろう。たしかに筆者も、コロナで物理的に孤立したときにはエネルギーが枯渇し本当に苦しかった。
そんな時、まずは一人でもいいから、愚痴でもボヤキでも、感情を吐き出し合える相手を探してみて欲しい。きっかけさえつかめれば、怒りやエネルギーはまた湧いてくることもある。
とにかく「やりたいことがない」「エネルギーすらない」となったって、焦らなくていいと思うのだ。
(文・寺口浩大)