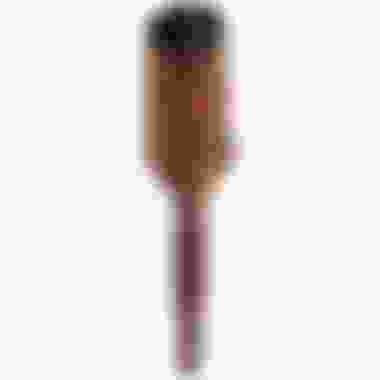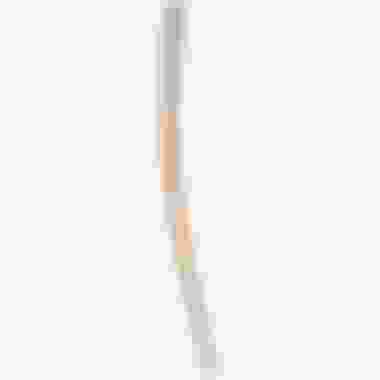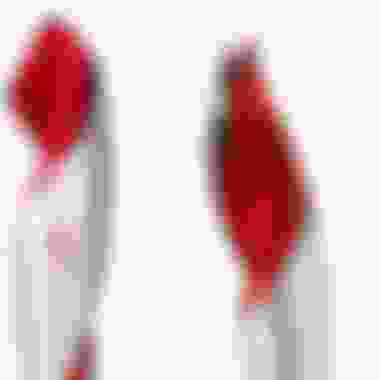札幌1972トーチ
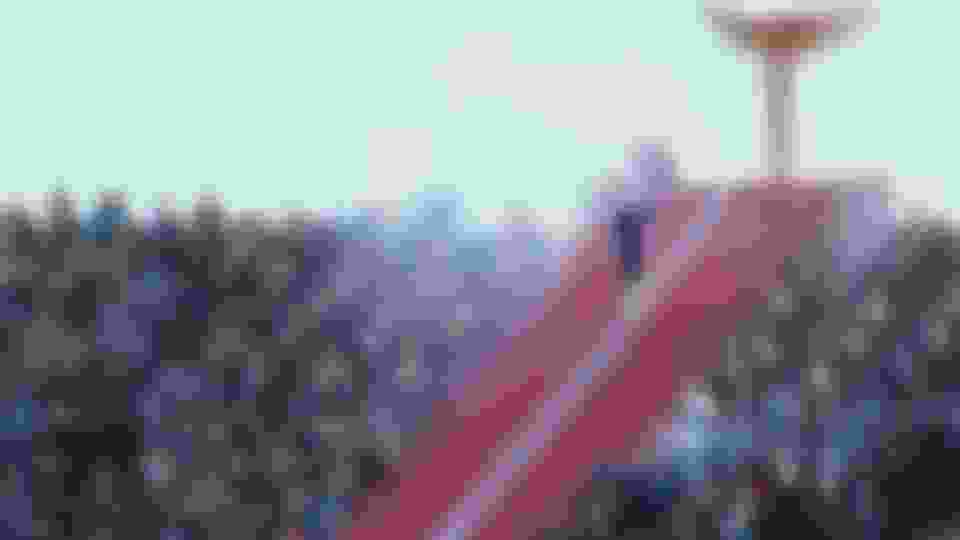
ルート概要と詳細
オリンピアで採火された聖火は自動車でアテネに運ばれ、そこから空路で日本へ向かいました。
1971年12月30日、トーチは沖縄本島に到着。翌日に島内を巡る60kmの聖火リレーが行われました。
1972年1月1日、聖火は東京に到着し、 国立競技場で記念式典が行われました。
聖火はまず韮崎に運ばれ、そこから本州を東西から北上する2つのルートに分岐。最北端の青森で合流し、津軽海峡を経て北海道へ。北海道上陸後は3つのルートをとり、函館、釧路、稚内を通過して札幌に向かいました。
1月29日、3つの聖火が札幌に到着。
1月30日、3つの聖火はアベリー・ブランデージIOC会長が出席した式典で再会し、続いて市庁舎広場に運ばれました。
2月3日、聖火が開会式に到着。フィギュアスケーターの辻村いずみからトーチを受け取った高田英基が聖火台に点火しました。
ルートマップ
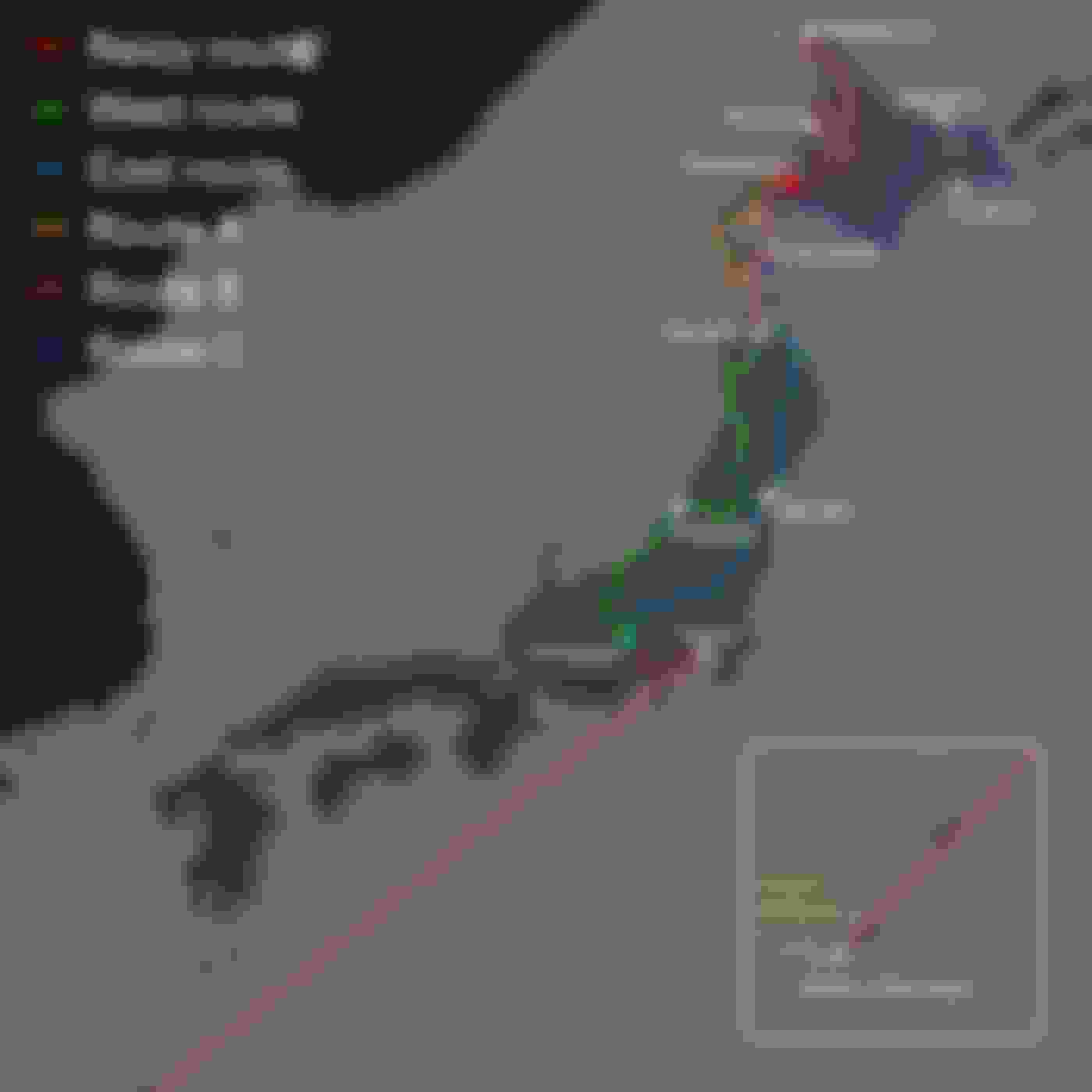
事実とデータ
開始:1971年12月28日、オリンピア(ギリシャ)
終了:1972年2月3日、真駒内スピードスケート競技場、札幌(日本)
第1走者:ヤニス・キルキレシス、ミュンヘン1972オリンピック夏季競技大会でも第1走者を務めました。
最終走者:高田英基、札幌に住む16歳の学生
走者数:〜16,300
走者募集:日本の聖火リレーで走者に選ばれたのは、11歳から20歳までの少年少女のみ。最後の走者2人を選んだのは、組織委員会の竹田恒徳副会長でした。竹田副会長は1967年から1981年までIOC委員を務め、その後に名誉会員となっています。
距離:18,741km:335km(ギリシャ)、66km(沖縄本島)、4,754km(日本本州・北海道)、13,586km(空路・海路)
経由国:ギリシャ、沖縄(当時はアメリカ統治下)、日本
トーチ詳細
概要:トーチは円筒形の燃焼管と持ち手で構成。「Sapporo 1972」の刻印と大会エンブレムが刻まれ、持ち手は聖火台に似た形状となっています。
色:黒
長さ:55cm(燃焼管のみ)
燃料:点火薬と発煙剤。燃料の主成分は赤リン、二酸化マンガン、マグネシウム、木粉。 燃焼時間はランナーのトーチが10分、自動車で運ばれたトーチが14分。
デザイン/製造:柳宗理/日本工機株式会社

トリビア
ランタンの燃料は高純度灯油で、48時間の燃焼時間を誇りました。自動車で運ぶ際の衝撃を和らげるため、エアクッション搭載の保護システムが採用されました。
真駒内スピードスケート競技場を見下ろす聖火台は、マットな質感の金でコーティングしたブロンズ製。左右非対称のデザインで、サイズは2.78x2.18m、高さは2.98m。燃料はプロパン。トーチと同じく柳宗理がデザインを手掛けました。
開会式終了後、聖火は手稲山と恵庭岳の競技会場に運ばれ、大会終了まで分火台でともされました。
オリンピックを深く知ろう
ブランド
ビジュアル・アイデンティティは、各オリンピックごとに作成されるブランド
メダル
オリーブ冠に始まり、メダルのデザインも年々進化メダル
トーチ
オリンピックを象徴するものとして、開催国独自のバージョンを提示トーチ