
- グーグル、ヤフー、バイドゥからの買収オファー
- 若きギークが集った「鴨邸」
- 年商1000万円超の高校生
- 「大人になってもみんなでワイワイ楽しむための箱」
- 検索は子どもの頃からの原点
- グーグルに真っ向勝負を挑む
- 検索エンジンでの惨敗と、「プランB」
- 「楽しむための箱を大事にした」買収オファーの裏話
- 外国の優秀な人材を採用する方法
- 「ヤバい失敗」を表彰する理由
- 次なる壮大な野望は「マーズのインフラ化」
- 私塾を開いて日本のギークを支援
グーグル、ヤフー、バイドゥからの買収オファー
2010年某日、渋谷のセルリアンタワーの一室に、武井信也氏はいた。検索エンジンの開発を手掛けるベンチャー、マーズフラッグのCEOが向き合っていたのは、グーグルの日本法人幹部と、アメリカ本社の幹部たち──。
「検索」の世界を手中に収める巨人はその日、武井氏にマーズフラッグの買収を提案した。マーズフラッグは独自のサイト内検索技術を用いた「MARS FINDER」を有し、ホームページ内の検索ツールとして日本の並みいる大企業を顧客にしていた。例えば、トヨタやソニーのホームページを開くと、右端に虫眼鏡のアイコンがある。その検索ツールが「MARS FINDER」だ。グーグルも無料で日本企業向けに検索サービスを展開していたが、日本でのシェアでは「MARS FINDER」が優勢だった。それなら買収して、日本のBtoBの検索市場も手に入れようということだ。
実は、グーグルのオファーに前後して、武井氏のもとには日本のヤフー、そして2007年に日本に進出していた中国最大の検索エンジン「百度(バイドゥ)」からも同様の話があった。しかし、アメリカ、日本、中国を代表する3社からの買収提案が実現することはなかった。
それから、10年。マーズフラッグは現在、日本企業の数千サイトに「MARS FINDER」を提供するほか、日本の官公庁や自治体、台湾政府にも採用されており、20億円から30億円と推定されるサイト内検索サービス市場の「ほぼすべて」(武井氏)を独占するまでに成長した。
サイト内検索という局地戦とはいえ、武井氏は「日本で唯一、グーグルに勝った男」と言えるだろう。その男のもとに今、国内外から有能なエンジニアが集っている。現在、約40名のマーズフラッグの社員のうち、外国人の比率は4割。国籍は6カ国に及ぶ。武井氏は今後さらに、国内外からの採用を強化すると話す。
日本企業のサイト内検索市場でひとり勝ちした武井氏は今後、多国籍チームを率いてなにを目指すのだろうか? 「日本で唯一、グーグルに勝った男」は、驚きの計画を明かした。その内容に触れる前に、これまでほとんど表に出てこなかった武井氏の歩みを振り返る。
若きギークが集った「鴨邸」
恐らく、これまでグーグル、ヤフー、バイドゥから買収提案を受けた日本人起業家は、ほかにいない。それなのに、武井氏の名前がそれほど知られていないのは、検索というニッチな世界の出来事だったことに加えて、10年前は今ほどスタートアップが注目されていなかったこと、さらに本人が積極的に前に出るタイプではなかったことも影響しているはずだ。
しかし、1971年生まれの武井氏と同世代で、80年代から90年代にパソコン通信や黎明期のインターネットにはまっていた元祖ギークたちの間では、少年時代から有名人だった。
武井氏は、まだ世の中にパソコンが存在しない小学生の頃から、祖父の「ワンボードマイコン」でプログラミングをして遊び、父親からもらったポケットコンピュータ(ポケコン)でゲームを自作した。そのゲームを見た学校の先生から雑誌への投稿を勧められて、『マイコンBASICマガジン』(電波新聞社。2003年休刊)に投稿していた。初めてパソコンに触れたのは、小学校4年生の時。2人の同級生の家にNECのパソコン「PC-8001」があり、「教えてあげる」という名目で両家に入り浸ったという。
それから少し時が経って高校時代、武井氏はパソコン通信のホストをするようになっていた。現在のオンラインサロンの走りのようなもので、武井氏が主催する「聖まりあんぬBBS」の会員になると、そのなかで会員同士やり取りができる。聖まりあんぬBBSは最盛期、2000名の会員が集っていた。
会員はそこで自作のゲームや音楽、アニメ、小説などを公開し、気に入ったものがあればダウンロードした。しかし、当時は電話線を利用したダイヤルアップ接続しかなく、大きなサイズのデータをダウンロードするには、膨大な時間と電話料金がかかる。そのため、武井家に来て、直接データを交換し合う会員が現れ始めた。武井氏の部屋は、あっという間にギークたちのたまり場と化した。そこは、必然的にパソコンを自作したり、ソフトを改造したりするアンダーグラウンドのラボになった。武井氏の部屋はいつしか「鴨邸(かもてい)」と呼ばれるようになった。諸説あるものの、そこに集うギークたちから「萌え」の概念が生まれたとも言われている。
年商1000万円超の高校生
鴨邸には、大人たちがよく訪ねてきた。その頃、武井氏たちが投稿していた雑誌『バックアップ活用テクニック』(三才ブックス)などの編集者だけでなく、若きギークの技術力に注目していたマイクロソフトやIBMの関係者も来た。そのため、武井氏の両親は「片目をつぶったり、時には両眼をつぶって」(武井氏)容認していたそうだ。ところで、武井家の電話代や電気代はどうなっていたのだろう?
「親には頼れないので、電気も電話回線も自分で契約していました。高校生の時から、年商が1000万円以上あったので」
その収入はすべて、鴨邸で仲間と培った技術によって生み出された。専門的な話になるので詳細は省くが、企業が武井氏たちの技術を頼って、さまざまなことを依頼してきたのだ。もちろん、合法的な仕事である。
大学に入学してからも生活はさほど変わらず、武井氏は鴨邸のメンバーと稼いでいた。そのうち、仲間たちと「みんなでなにかやりたいよね」と話をするようになった。
「僕ら、その頃は“無敵艦隊”だと思っていたんですよ。IBMとかマイクロソフトの人も、困ったことがあると僕らに助けを求めに来たし、『僕たちができないことは、誰にもできない』という自信がありました。僕はスティーブ・ジョブズに憧れていたのもあって、せっかくこうやってギークが集まったんだから、みんなでビジネスにしたら、ずっと楽しく過ごしてられるんじゃないかと(笑)」
そこで考えた。ビジネスをするなら、経営的な視点が必要だ。そればかりは、遊んでいたら身につかない。鴨邸の主で仲間たちのリーダー的存在だった武井氏は、経営学を学ぼうと香港に留学した。
「大人になってもみんなでワイワイ楽しむための箱」
帰国した武井氏は、すぐに起業を考えた。しかし、ゼネコンで強度設計エンジニアをしていた父親からの言葉で、就職する道を選ぶ。
「世の中そんなに甘くないぞと諭されましたね。まずはお前の価値を認めてくれる会社で、そこのボスに対してしっかり仕事するということをやってみろ、いずれ人を雇うつもりなら、まずは使われてみろと言われました。それは一理あるなと思ったんです」
1994年、武井氏は付き合いのあった雑誌の編集長からの紹介で、レーザーのコンピューター制御技術の開発などを手掛けていたレイ・コーポレーションというベンチャーで働き始めた。武井氏はそこで、東京モーターショーのIT化などを担当した。
一方で、鴨邸の仲間たちとのビジネスも続けていた。その頃は、テレビ番組への技術提供が大きな収入になっていた。
「『関口宏の東京フレンドパーク』のアトラクションをたくさん作っていましたね。その頃、楽器とコンピューターをつなげて、人の動きに合わせて音や光が高速で反応するようなハードとソフトを作れる会社がなかったんですよ」
こうして二足のわらじ生活を続けた武井氏は、1998年、満を持して「大人になってもみんなでワイワイ楽しむための箱」として、鴨邸の仲間3人と、ビーボイド(現・マーズフラッグ)を設立した。ボイドとは、英語で「中身のない」「役に立たない」という意味。ビーボイドは、直訳すると「無駄になれ」ということだ。武井氏は「今、振り返ると中二病的な名前ですよね」と苦笑する。しかし、日本の元祖ギークの視線は未来を捉えていた。
「起業した時、なにをするか具体的には決まってなかったんです。ただ、自分たちがすごく得意で好きだったのは、大量のデータを自動分類したり検索する技術の開発でした。だから、検索を軸にしたなにかのビジネスっていうのはボンヤリあったけれど、当時はまだ検索エンジンという言葉も世にない時期で、なんだかモヤモヤしていましたね」
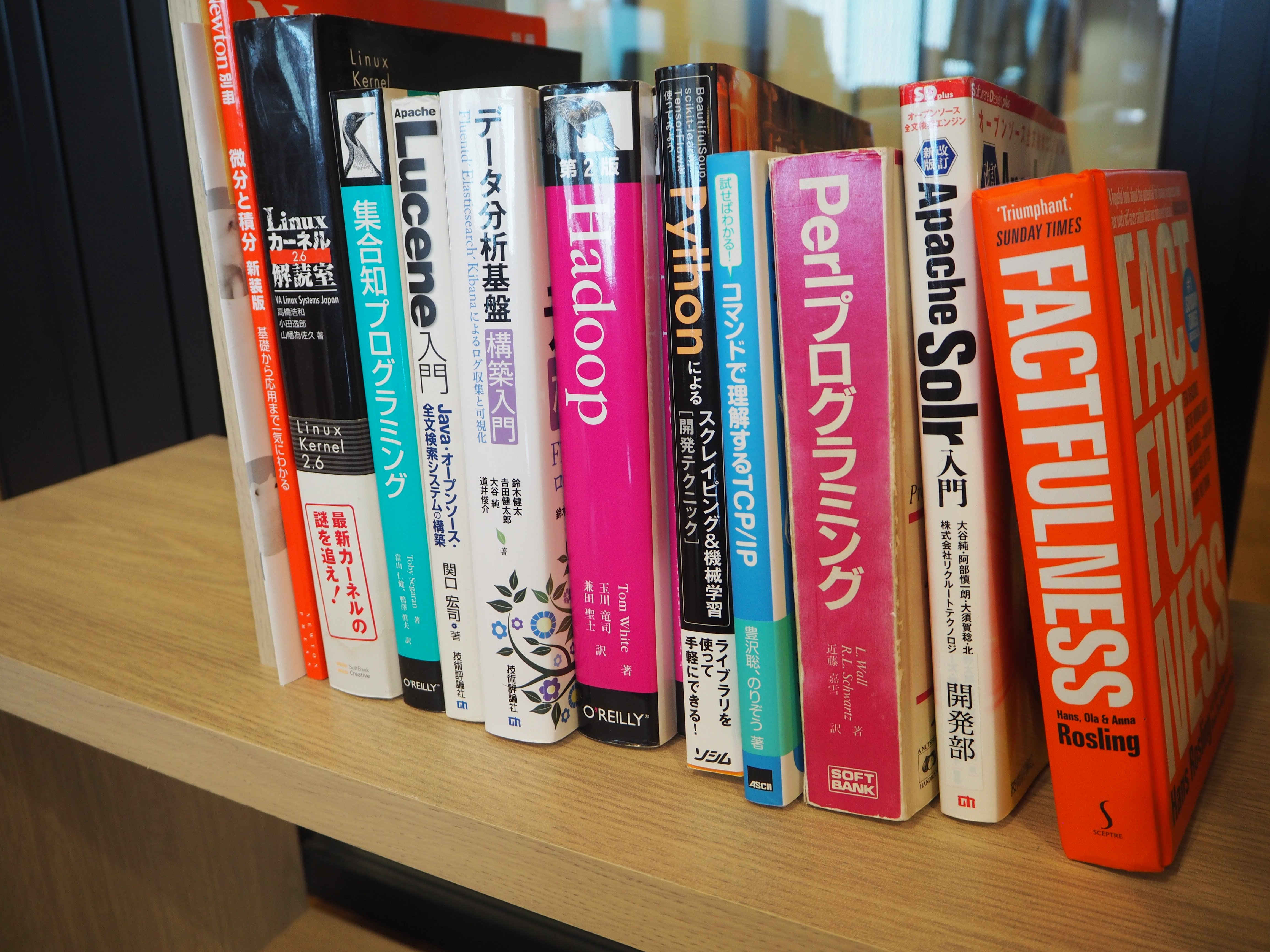
検索は子どもの頃からの原点
1998年といえば、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンがグーグルを設立した年。日米のギークがまったく同時期に「検索」をビジネスにしようと動き始めていたのは興味深い。
ちなみに、武井氏は子どもの頃、なんでもかんでも両親に「これはなに?」「なんで?」「どうして?」と聞きまくる質問魔で、小学1年生の時、うんざりした親から百科事典を買い与えられた。それ以来、全16巻の分厚い百科事典が武井氏の疑問を解消するツールになった。武井少年は、よく開くページや好きなことが書いてあるページにどんどん付箋を貼って、すぐに目的の言葉にたどり着けるように工夫した。そう、「検索」は好奇心旺盛で知りたがりだった武井氏の原点でもあるのだ。
まだ世界で数人しか「検索」がビジネスになると考えていなかったこの頃、武井氏たちは自分たちの武器を先鋭化する準備を始めていた。検索に関する独自技術の特許をいくつも出願し、知財戦略を進めていたのだ。
例えば、検索窓になにかのキーワードを打ち込むと、その後に続く言葉を予測して表示する技術はマーズフラッグが開発したもので、日本の特許を持っている。検索履歴に応じて、ひとりひとりにパーソナライズして検索結果を変える技術の特許も有している。
「98年からの5、6年は、特許ばっかり取っていました」(武井氏)というこの戦略が、のちに大きな意味を持つことになる。
特許を申請したり、メシを食べていくためのお金は、テレビ局の仕事やNECやIBMのコンサルティングをして稼いでいた。武井氏は同時進行で1999年、熊谷正寿氏(GMOインターネット代表取締役会長兼社長 グループ代表)、穐田誉輝氏(カカクコム元代表取締役社長、クックパッド元代表執行役)らと広告オークションサイト「サイバーコム(翌年、アド・マーケットプレイスに商号変更)」を創業し、取締役に就任。2001年、DAC(デジタル・アドバタイズ・コンソーシアム)に事業を売却したタイミングで、取締役を辞任している。
グーグルに真っ向勝負を挑む
この頃、アメリカではすでにグーグルが「検索革命」を起こしており、2004年に最初の株式を公開した。この動きに共鳴するように、武井氏は大きな勝負に出る。
2004年、ビーボイドから「火星に旗を立てる=不可能を実現する」という想いを込めてマーズフラッグに社名を変更。そして翌年、検索エンジン「MARS FLAG」ベータ版のサービスを開始した。なにかの言葉を検索すると、検索結果にページのイメージ画像が掲載される独自技術を持つ「MARS FLAG」の評価は高く、武井氏はソフトバンク・インベストメントなどから10億円超を調達。その資金を元手に、グーグルに真っ向勝負に挑んだ。
「当時、日本のIT業界の人たち、金融業界の人たちはグーグルに対してすごい危機感を抱いていました。検索という新しいビジネスで市場を席巻する黒船に対して、日本の若者はなにやってるんだ! と焦っていた。そこに僕が『はい!』と手を挙げたんです」
2005年当時、ベンチャーが10億円超を調達するというのは異例のことだった。IT業界では武井氏の名前と技術力が広く知られていたことに加えて、グーグルが開拓した検索ビジネスのポテンシャルを表す数字でもある。
2006年5月、「MARS FLAG」が正式にサービス開始。当時の心境を、武井氏は「お台場の砲台」と表す。グーグルという黒船に対して、「MARS FLAG」という砲撃で迎え撃つのだ。

検索エンジンでの惨敗と、「プランB」
しかし、武井氏はすぐに気づいた。自分たちが持っている武器は、大砲じゃない。グーグルにとっては、竹槍みたいなものだと。
「すぐに、まったくかなわないと気づきましたね。人材だけを見ても、当時からグーグルはスタンフォードやハーバード、MITといった大学のドクター出身の連中がゴロゴロいた。検索エンジンは自然言語学から数学、物理とか幅広い知識が必要だから、アカデミアの世界から来た人がすごく強い。一方で、当時の日本のコンピューター好きはオタクです。10億円調達したところで、僕ら日本のオタクが勝てる世界じゃなかった」
無敵艦隊だと思っていた日本のオタクの挑戦は、10億円の資金が尽きて終わった。投資家たちは「まだ資金を用意する」と鼻息荒かったそうだが、グーグルとの圧倒的な力の差を肌で感じた武井氏は、「もうやめましょう。絶対勝てません」と自ら白旗を挙げた。
ただし、尻尾を巻いて完全撤退するつもりはなかった。熱心に声を掛けてくれていた三菱電機の後押しもあって、検索ポータルからプランBに切り替えたのだ。それが、企業のホームページに埋め込むサイト内検索サービス。グーグルがまだ手を出していなかった領域だった。
2006年に月額課金制のサイト内検索サービス「MARS FINDER」をリリースすると、最初に三菱電機が導入を決め、2社目に本田技研、3社目にキヤノンと続いた。通常、ベンチャーのサービスを大企業が採用するまでには時間がかかるもので、異例の扱いだった。
「僕、検索ポータルで派手にずっこけたでしょう。大企業のIT好きの人たちが、それを知っていたんです。みんな好意的で、僕の潔い負けっぷりを評価してくれる人たちが、マーズフラッグを救ってくれたんですよ」
日本を代表する大企業がユーザーになったことが信用となり、「MARS FINDER」の導入企業は右肩上がりで増えていった。
「楽しむための箱を大事にした」買収オファーの裏話
ところがしばらくすると、グーグルが日本でサイト内検索サービスにも手を伸ばしてきた。しかも、無料。これに対して「二度目は負けるわけにかない」と考えた武井氏は、奇策を講じた。なんと、「MARS FINDER」の導入費用を値上げしたのだ。そして、ユーザー企業や導入を検討している企業にこう訴えた。
「機能的にはほとんど同じです。個人の好みがありますけど、検索結果はたいして変わりません。ただし、グーグルが無料なのは、ポータルの検索の質を良くするために、ラストワンマイルの行動履歴とか検索履歴を取り込みたいからです。そういう情報はぜんぶアメリカに持っていかれます。うちは特許を持っていて、メイドインジャパンのサービスです。有料ですが、しっかりサポートします」
この話を聞いて、「いや、うちは無料のグーグルで」という日本の企業は少なかった。日本の名だたる企業が「MARS FINDER」を導入し、それが周辺企業にも波及していった。武井氏はプランBで、雪辱を果たしたのだ。
それから、冒頭のシーンを迎える。グーグル、ヤフー、バイドゥから買収のオファーを受けた武井氏は、「条件面で交渉決裂して、破断に終わったということではないですよ」と前置きしながら、当時の心境を明かした。
「ベンチャーキャピタル(VC)の担当者は上に下にの大騒ぎでしたけど(笑)、創業メンバーでも話しあったんですよ。僕らは大人になってからもみんなでワイワイ楽しむための箱として会社を作りました。今も十分に楽しいし、大金を貰ったとして、買収されて大企業で働く?って。その頃、みんな三十代半ばだったから、若かったのかも。今だったらみんな幾らでもいいから売れって言うかもしれない(笑)」

外国の優秀な人材を採用する方法
それから10年が経ち、現在。日本でサイト内検索サービスをほぼ独占したマーズフラッグは40名規模になり、高校時代の鴨邸のようなギークが集まる場になっている。鴨邸と違うところがあるとすれば、多国籍になっていることだ。グーグルに敗れた時、日本のオタクだけで構成する組織の限界を感じた武井氏は、外国人の採用に力を入れている。
その採用方法は、独特だ。マーズフラッグは上海とシンガポールに支社があり、ほかの海外の都市にも多くの代理店と顧客を持つため出張する機会がある。武井氏はその際、街なかのスターバックスコーヒーに入り、清潔感のある服装でマックブックを開いて仕事をしていそうな若者を見つけると、「ハーイ!」と声をかける。それから簡単に自己紹介をして、どこの企業でどんな仕事をしているのかを尋ねる。すると、ほとんどの場合、外資系の有名企業で働いているそうだ。そこで気軽なやり取りをした後、こう話す。
「君の上司や社長は本国から派遣されていて、2年ぐらいで交代するんじゃない? 君がその会社にいる限り、どんなに才能があってもガラスの天井にぶつかるよ。出世できないだけじゃなく、給料も上がらないし、やりたいこともできない。会社の部品で終わる。でも、うちは違うよ。うちで働かない? もし興味があるなら、今、決めて」
このいきなりのオファーに対して、あっさりと断る人もいれば、迷う人もいる。迷うということは、可能性があるということだ。武井氏はその場で連絡先を交換すると、やり取りを重ねながら、さらに一歩踏み込む。「親に会わせてほしい」と頼むのだ。その若者がOKを出したら、たとえどんな辺鄙な場所にでも出向いていく。自分ひとりだと怪しまれるため、マーズフラッグの社員を連れて。

「北京のスタバで会った女の子は、大連理工大学を出てIBMで優秀なエンジニアとして働いていました。彼女の故郷は大連の北にあるタンシェン(唐山)というすごくのどかなところでね。タクシーもなくて、リヤカーみたいな乗り物を3回乗り継いで行きましたよ。そこでお父さんと一緒に餃子を作ったり、風呂を沸かすための薪割りをしてね。1泊して翌日、娘さんを私にください、必ず幸せにます、育てますって頭を下げて。ほとんど結婚の申し込みですよね(笑)。それで彼女も決心してくれて」
本当の話かと疑う読者もいるかもしれないが、この取材に同席していた社長秘書のケイさん(中国・上海出身)は、「結婚の申し込み」に同席したことがあるという。武井氏が惚れ込んだニューヨーク産まれの台湾系才女にアタックするために、一緒に台湾の山奥にある小さな村に行って、その女性の両親を訪ねたのだ。外国籍の社員は、こうして武井氏がひとりひとり口説き落としてきた。
「ヤバい失敗」を表彰する理由
人数が増えても、多国籍になっても、「みんなでワイワイ楽しく過ごすこと」を忘れないために、武井氏は「マーズウェイ」を定めた。プリンシプル(信条)には「楽しさやワクワクを優先しよう。我々の幸せは全ステイクホルダーの幸せである(以下略)」と記されている。
社員のための「アクションガイド」には、8つの項目が掲げられていて、なかでもユニークなのは「挑戦への失敗は笑い飛ばす」。実際、同社では月に一度、社員が自身の失敗を全社員の前で発表する「マーズブレイブ」という会がある。
「仕事でもプライベートでも構いません。発表が終わったらみんなで爆笑して、ポジティブにいじるんです。そうすることで、いい思い出に昇華させてあげる(笑)。そして発表した人が、翌月に発表する人を指名する。そうすると、いつ自分にまわってくるかわからないから、失敗をストックしないといけないでしょ。それで、年に一度、『マーズブレイブベスト』として、最もヤバい失敗に社長賞として金一封を贈っています」
これまでどんな失敗があったか尋ねたところ、以下のエピソードを教えてくれた。武井氏がクライアントとミーティングをしている時に、高校時代からの仲間で創業メンバーのひとりが「どんな様子なのか知りたい」と、ドローンを飛ばして社内に実況中継。途中で操縦を誤って、クライアントの頭の上にドローンが墜落した。これは確かにヤバい事態だが、武井氏は「お客さんにはちゃんと謝りましたけど、メンバーのことは褒めました。お前は本当におもしろいって。ほんとバカらしくて、うちの会社らしい」と振り返る。
失敗を発表するというと、「僕はこんなチャレンジをしたけど、力が及びませんでした」「うん、よく頑張った」という前向きなトライを称える会になりそうなものだが、リアルにやらかしてしまったことを話すのが、マーズブレイブ。ほかに武井氏から聞いたいくつかの失敗は、ここには記せないレベルのものだった。
なぜ、そこまで失敗を評価するのか?
「うちの社員はみんな超優秀なんで、普通に仕事しているとほとんど失敗しないんです。でも、失敗しないことをよしとすると、そのうち仕事が安全なほうに流れるんですよ。これぐらいでいいかって。それはやめてほしい。面白いこと、新しいことにどんどん挑んでほしい。だから、普段から失敗を笑って褒めることで、あなたが失敗しても会社は怒ったり、給料を下げたりしませんよと意思表示をしているんです」
振り返ってみれば、武井氏は10億円を集めてグーグルに挑み、見事に散った。これはまさに、武井氏の人生のマーズブレイブベストと言える。その時、資金を出した人たちは誰も武井氏を責めず、プランBに移行した時には支援までしてくれた。この経験が、今に活かされているのだろう。
次なる壮大な野望は「マーズのインフラ化」
国内外から強力な仲間を得た武井氏は再び、壮大な野望を抱き始めている。マーズのインフラ化だ。
「例えば、明日アプリの会社を作りたいとするじゃないですか。そうすると、プログラマーとデザイナーを集めて、アマゾンウェブサービスあたりのデータセンターと契約する必要があります。これをグーグルで検索すると、結果が分断されているから、ひとつずつ自分でやらなきゃいけない。でも、希望する条件を打ち込むと、アプリの会社を作るための最適なセットを提案されるサービスがあったら、みんな使うと思いません? そのサービスを作りたいんです」
これは、レストランの料理として考えるとわかりやすい。レストランでカレーを頼む時に、ニンジン、ジャガイモ、牛肉などの具材をひとつひとつ自分で選んで注文するのは面倒だろう。現在のウェブは、まだその状態だ。
武井氏が思い描く未来は、メニューを見て、グリーンカレーが食べたいと注文したら、自分好みのグリーンカレーがすぐに出てくること。そのためには、膨大なデータが埋没しているクラウドのなかから希望に沿ったレシピを検索できなくてはいけない。
クラウドと検索を掛け合わせた新サービスによって、アイデアを形にする費用と手間と時間を大幅に省くことができる、そうすればもっと世の中が豊かで面白くになるというのが、武井氏のビジョンだ。
「実現にはまだまだ程遠いですけど、今からこつこつと関係する特許を取っていますし、マーズの採用も強化しています。やっぱり根がハッカーだから、オープンなインフラにして、誰でも簡単に使えるようにしたいんですよね」
私塾を開いて日本のギークを支援
同時並行して準備しているのが、日本の若きギークへの支援。武井氏は子どもの頃、自分の知識や技術を分かち合える仲間が雑誌の投稿欄にしかいなかった。しかし、鴨邸でたくさんのギークと出会ったことで腕が磨かれ、今も事業を共にする仲間ができた。
日本では今も、子どものギークは宇宙人扱いで、孤独を感じている子も多い。もしかすると、そのなかにGAFAと互角に争うようなサービスを生み出す才能がいるかもしれない――。そう考えた武井氏は、将来有望な中高生のギークを集めた「私塾」を開くという。
その全貌はまだ明かされていないが、参加希望者を募り、数が多ければ選抜試験を行い、10名から20名のグループで開催される。国内外での合宿を行い、武井氏とつながりのある起業家やクリエイター、アーティストが講義を行うそうだ。
「今後10年で、100人から200人の若いギークたちに、元祖ギークである僕や仲間たちが経験してきたことを伝えたいんです。さらにアートやクリエイティブに触れることで、幅広い刺激を受けてほしい。単なるオタクの集まりではなくて、日本の未来を担う、世界を変えるような存在になってほしいし、その可能性はあると思います」
近年、日本でもさまざまなジャンルのスクールができているが、中高生のギークを対象にした私塾は日本初だろう。恐らく、武井氏がイメージしているのは、子どもたちだけで集っていた鴨邸の進化版。腕利きのギークがメンターを務める「ネオ鴨邸」から、どんな才能が生まれてくるのか?
マーズのインフラ化、そしてギークのための私塾。日本でグーグルと真剣勝負をした唯一の男は、再び世界を見据えている。

