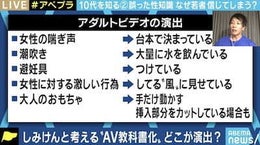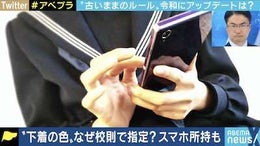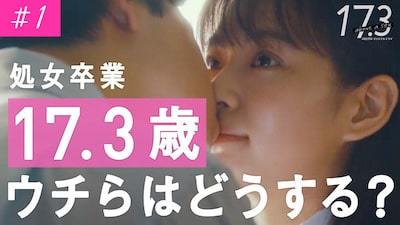7日の『ABEMA Prime』では、伊是名さん本人に、改めて経緯を訊ねるとともに、“合理的配慮”のあり方について話を聞いた。
・【映像】車いすコラムニストに聞く "誰もが移動しやすい社会"実現までの壁とは
■「今回だけ“合理的配慮”をするという姿勢なら残念」
しかし15分前に行ってみると、今度は“すみません、来宮駅には階段しかないので、ご案内できません。熱海まででいいですか?”と言われた。来宮駅には階段しかないということはその時に初めて知ったので、“そうなんですか。でも行きたいのでどうにかなりませんか。お願いします”と言うと、“無理です”という感じで言われた。ただ、“ちょっとお待ちください”とも言われたので待っていると、別の駅員さんが出てきて“やっぱり来宮には階段しかないし、無人駅なので無理です”と言われた。私が“30分前にも来ていたし、レストランもホテルも予約しているので、どうしても行きたい”と話した。
再び“もうちょっと待ってください”と言われたので待っていると、3人目の駅員さんが来た。乗りたかった電車はすでに発車した後だったが、話をしていると、やはり“来宮駅には階段しかない”“もう無理です”と、また同じことを言われてしまった。私としては“無理だ、無理だ”と簡単に言われている感じがして、“ちょっとおかしいな”と思い始めた。
さらに、“駅員さんを集めて、階段で持ち上げることはできないですか?”と聞いた。もちろん、駅員さんを集めるのには時間がかかり、30分、1時間と待ったり、“この時間に来てください”と時間を指定されたりしたこともあるが、そういう配慮を何回もやっていただいたことがあったからだ。しかしこの時は“一切無理です”という感じで言われた。
「もちろん、事前連絡をした上での対応というのも、“合理的配慮“の一つの方法ではあるし、私としてはとてもいいことだと思う。ただ、そのことをどうやって知ればいいのか、という問題がある。私も行く前に“JR 来宮駅”と調べてみたが、無人駅だということも、車椅子の人はいつまでに連絡を下さい、ということも記載はなかった。だから“いつもは持ってもらったりするし、そのまま行けばいいのかな”と思ってしまった。JRではないところがやっている、バリアフリーについて書いてある『らくらくおでかけネット』というサイトもあるが、ちょっとアクセスがしにくい。それがわかりやすかったら、私でも調べられたかもしれない。
そして、何か問題が起こった時に“これは問題だと思う。差別だと思う”と、声を上げて話し合う。それが“合理的配慮”への第一歩だ。JR全体ではあったと思うが、その駅では声を上げる人がいままでいなかったか、いたとしても取り上げられなかったのだと思う。そこは“どういう形だったら対応できるのか”という話し合いをしていくしかないし、それは1回で終わるわけではない。
例えばデンマークでは電車に段差がなく、事前の連絡がなくても乗ることができる。日本の新幹線のような長距離列車は事前に連絡をしないといけないが、車椅子の障害者には自動車とドライバーが無料で支給される。だから実際は電車を使わなくても十分に移動ができる。そのようにして、2重にも3重にも合理的配慮がなされている。ここで“合理的配慮”をしたから解決ではなく、時間をかけて、色んな選択肢を重ねていくことが大事だと思う。」
■「合理的配慮について考えてもらうために、声を上げ続ける」
そのことで“客観性”が冷たいとか、“わがまま”であるかのように受け取られてしまったことは私の失敗だったが、ではどういう方法だったら色んな人に知ってもらえたり、JR側の改善がなされたりするのか、そこは私の中でも答えが出ていない。もし方法があるなら教えていただきたいなと思う。ただ、交渉の仕方としては一つのやり方ではあると思っているし、粘り強く駅員さんに“どうしますか。でもやっぱり乗りたいので乗せてください。持ち上げてください”と言うのは、今まで障害者の方がやってきたやり方でもある。
ただ、エレベーターの設置など、駅のバリアフリー化は、ベビーカーの人とかお年寄りなど色んな人にとっても幸せで便利になることなのに、私が提案をすると、“おかしい”とか“わがままでないか”と言われてしまう。今回こうして議論をできたことは良かったと思うが、これが分断を生んでしまったり、障害のある人たちが外に出たくないと思ってしまうきっかけになってしまったりするのだとしたら、とても悲しい。すでに色々な誹謗中傷が来ているので、障害を持っている人の中には、駅で助け求めたらネットに書かれるかもしれないと思っている人もたくさんいる。私はそれがとても悲しい。そういう悲しみを少しでも減らすためにも、声をあげ続けなければいけないなと思い、今回ブログを書いた。
いつも車椅子の人は皆さんの2倍、3倍の時間をかけて目的地へ行っている。まずはそのことを皆さんに知っていただいて、次にどうやったら変えていけるかを考えたいのであって、駅員さんや手伝ってくれない人に対して怒ったり、責めたりしているわけではない。そのためには障害のある人だけではなくて、みんなに一緒に考えてもらう。そのきっかけ、手助け、チャンスが欲しいということだ」。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)