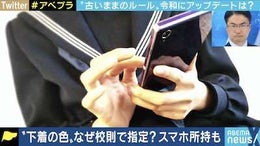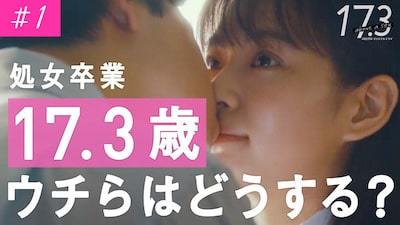これは誰にでも起こりうるある症状を当事者目線で再現したVR映像。自分がどこにいるかもわからず、目的地も乗り換える駅も忘れてしまい、混乱する女性。彼女が抱えるのは「認知症」だ。
【映像】“若年性認知症”当事者と家族の苦悩
全国に460万人いるとされる認知症患者。その数は今も増え続け、2025年には高齢者の5人に1人になるとされている。このVRはそんな認知症に対する理解を深めようと、サービス付き高齢者住宅を運営する企業が開発した。
とはいえ、若い人は「まだまだ遠い未来の話」と思っていないだろうか。実は、認知症は高齢者に限った話ではない。認知症当事者コミュニティが開催したイベントで、参加者のほとんどは高齢者の中、43歳の男性の姿も。渡邊雅徳さんも認知症の当事者だ。
渡邊さんは現在、認知症患者が集うカフェで、当事者たちに対し自身の体験談を踏まえ明るくサポートを行っている。彼に異変が起こったのは今から3年前の当時40歳の時だった。「朝起きたら、自分がどこで働いているのか、なんの仕事をしているか、どんな人と一緒に働いているかとか、仕事に関する記憶が一切なくなっていた。職場に相談して病院に行くよう言われて診察を受けたら、認知症だと言われた」。
渡邊さんは当初違和感はあったものの、仕事のストレスだと思っていたという。しかし、書類の手直しを事務員にお願いしようとするも、名前が出てこないために自分の席に戻るということがあった。
渡邊さんは認知症という診断を聞いた時、「助かった」という思いが強かったという。「僕の場合は当時働いていた事務所を潰しかねないほどの失敗をしていて、『お前みたいなやつがわけわからなくなって、刃物を振り回して人を傷つけたりするんだから隔離された方がいい』とか言われた。認知症の症状もそうだけど、その状況がすごく辛くて」と話す。
認知症に対するイメージは“高齢者に起こる”こと。その結果、若い年代で発症しても周囲から気付かれにくいだけでなく、理解さえしてもらえない。認知症が発覚して一時休職をしていた渡邊さんだが、最終的に退職を決断した。現在は、企業に定められた障害者雇用枠での再就職を目指している。
下坂さんによると、「意外と子どものころのこととかは覚えていて、最近のことほど覚えていない」という。現在の症状としては、簡単な計算が難しいために「キャッシュレス決済で小銭の計算などを不要にする」、通勤ルートを間違えてしまうために「スマホの地図と外の景色を見ながら確認する」などの対策を取っている。
また、若年性認知症の問題点として3つをあげる。「お年寄りと比べてまず多いのは、交通事故や頭部外傷のいわゆる高次脳機能障害。頭がダメージを受けて起きる認知症がある。それ以外の原因としては、お年寄りと同じようにアルツハイマー病が多い。その後、血管性認知症と続いて原因は同じだが、違いが3つある。1つはお年寄りに比べて進行が早い。2つ目は家族への経済的なダメージ、3つ目は精神的なダメージがお年寄りの場合よりもずっと大きい」。
笑って接した方が気持ちは楽なのか。下坂さんは「そうだ。その方がだいぶ助かるし、やはりありがたい」と答えた。
周囲の人の理解が必要な点について、新井氏は「アルツハイマー病になったからといって、その人が社会生活で影響を受けるというのは一部だ。進行が早いといっても、20年くらいの長いスパン。そこが大事で、診断を受けても軽度障害の場合は5年くらい全部自分で生活できるし、その人なりの生活はできる。今日の(下坂さんの)お話を聞いてみても、1人の人間として普通に生活できるし、生活も自立していける。そこをまず皆さんに理解してもらわないと、誤解がどうしても生じてしまう。病気になったとしても脳の一部で、他は正常。ひとつ記憶のボタンの掛け違いがあったとしても、それ以外は普通に判断して喜怒哀楽もあり、皆さんと付き合えるわけだ。そこが認知症になると全部破綻してしまうみたいな重いイメージを持ってしまうのが、誤解を生じる一番のポイントだと思う」と説明した。
認知症の人が働く上で、周囲の理解があればどこでも働くことができるのではと下坂さん。では、理解が得られれば元の鮮魚店の仕事に戻りたいのだろうか。「23年やってきて魚屋がすごく好きだっただけに、やはり自分が衰えていき、だんだんできなくなっていくのを仲間や後輩には見せたくなかった。そこはすごく葛藤があったが、すっぱり諦めて違う人生を歩もうかなと思った」。
最後に下坂さんは「認知症になってできなくなることは増えていくが、できることを頑張ってやっていったら進行も緩やかになっていくのかなと、自分自身思う。(認知症に)なったからといって、悲観せずに前向きに頑張っていけたら」と語った。
(ABEMA/『ABEMA Prime』より)