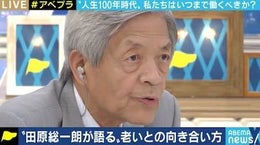・【映像】EXITと考える震災報道 感動ポルノやお涙頂戴いつまで?
そんな高橋さんの気持ちを一層強くさせたのが、震災で亡くなった祖父について話をしていたときのことだ。「泣いてしまって、言葉が出なくなった。その様子を見ていたディレクターが何かを達成したような顔になり、カメラマンも“いい画が撮れた”みたいな笑顔を堪えるのに必死な顔をしていた。“ああ、俺はお前らの素材か”と目が覚めた」。
■キー局は「“演じてくれる人”を探すようになっている」
自分で自分を“メディアソムリエ”と言っているが(笑)、500件も取材を受けてきたので、取材する前のアプローチ、あるいは会って5分でだいたい分かる。“こういう取材がしたい”と依頼してくる人は、最初から震災のネタを撮りに来る人だ。“話を聞かせてもらえないか”という人は震災の悲しい話ではなく、女川の街づくりや、どんな未来に向かっているのかを撮りに来る人たちだ」。
■「次の命が助かるのであれば、むしろ震災のことは忘れてもらってもいい」
「それが抜け落ちて、ただ辛い、悲しいばかりだ。“孫を津波で亡くしたおばあさん、10年経っても心が癒さません”という話を聞いた時、“震災を忘れません”とは思っても、“では、自分がその立場になったら、どうすれば命を守れるか”という気づき、教訓が得られない。それでいいのか、メディアの方が。震災のことを忘れなかったとしても、死んでしまっては意味がない次の命が助かるのであれば、むしろ震災のことは忘れてもらってもいいとさえ思っている。
いまスタジオにいらっしゃる皆さんは『災害伝言ダイヤル』の使い方、番号をご存知だろうか?いま住んでいらっしゃる場所の最寄りの避難場所をご存知だろうか?(スタジオ沈黙)…他人事ではないというのは、そういうことだ。もし南海トラフ地震が起きた場合、自分の住む地域に津波がどのくらいの時間でやってくるのか。それをシミュレートし、覚悟した上で暮らしているだろうか。そして、テレビはそのために必要な情報をなぜ頑張って伝えようとしないのか。とても残念だ」。
■ローカル局・テレビユー福島の元報道局長「心を折るような報道が少なくなかった」
「僕の場合はローカルメディアの人間ということもあり、原発の問題が大きかったが、それに関しても東京とは少し違うなという感じがあった。やはり中央のメディアには、不安を不必要に煽るような、センセーショナルな報道の仕方をしていたと思う。放射線によって遺伝的な影響が起きることはまずないと分かっているのに、どうしてもそういうことは報じてくれない」。
大森さんもまた、「これから前を向こうとしている福島の被災者の人たちの心を折るような報道が少なくなかった」と、キー局のスタンスに疑問を投げかける。
背景にあるのは、“権力に対峙し、チェックしていくのが報道の仕事だ”という教えだと思う。僕自身、記者になりたての頃にすごく言われたことだ。ただ、それを強く持ち過ぎてしまうあまりに裏付けのための話ばかりが欲しくなり、被災者の気持ちを忘れてしまう。そういう部分があったのではないか。最低限の事実は押さえるということ、そして、たとえ当事者でなくとも、その思いを想像することはできるはず。“寄り添い”という言葉はもう聞くのも嫌だという人も知っているが、それでも相手の少しでも幸せになるために何ができるのか、ということを考えながら取材するようになれば、行動も根本的に変わるのではないか」。
■テレビ朝日の平石アナ「キー局ならではの“分業制”が背景に」
「やはり共通しているのは、“ストーリーありき”ではないかということだ。そして、そのためのピースを探しに行っているということだ。本来、取材に行く時には仮説を持って行くが、現地で話を聞いているうちに違うと思えば方向転換して進めていける。しかしここに東京、キー局ならではの問題がある。それは分業制だ。取材に行くディレクター、記者、アナウンサーが構成・企画をし、原稿執筆と編集も行えればいいが、すべてが分業になっているので、どうしてもピースを埋める、ということが現実に出てくる。そこに抗わないといけないが、現場で取材する人の立場が弱いと“こういう画だけ撮りにきた。こういうコメントだけ欲しい”というようなことが起きてしまう。高橋さんを2日間も密着したのに出さなかったというのも、申し訳ないがそのような作業や優先順位付けの中で起きたのだと思う」。
りんたろー。は「僕たちも言いたくないことを言わされたり、都合のいいところだけ使われていたりと、似たような経験をした。そしてテレビに慣れている僕らはいいけれど、一般人の方、しかも被災されて傷ついている方なら、なおさらケアしないとダメだめだ。そして、各局が同じような映像を流しているところも変わらないといけない。そうやってどんどん衰退してきたと思うし、見ている人もバカじゃないから気づき始めている。もっと違う角度で流す局や番組があってもいいのかなと思う」とコメント。
兼近大樹は「震災が起きたのは19歳の時だったが、“こんなにつらい人がいたんだ”っていうことしか分からなくて、“この人のために何ができるんだろう”ってところにたどり着けるような報道にはなってなかったと思う。僕みたいなクソみたいな人生を送ったヤツが震災のことを知れただけでも意味はあったと思うけど、そこまで教えてくれれば、もっと深く入っていけたのかなと思う。そして報道、ニュース番組というのは、事実を受け取るためにあると思うし、面白い、面白くないはニュースまでの時間をつなぐバラエティが考えればいい。報道まで“面白ければいい”なら、クソみたいな話だ」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)