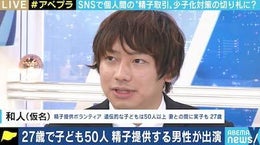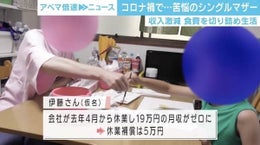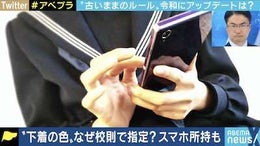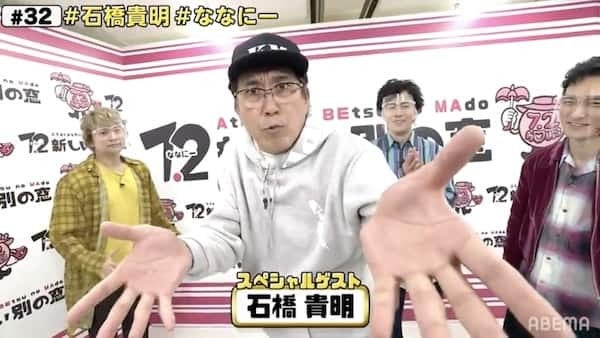アメリカのハーバード大学マサチューセッツ総合病院で働く脳神経外科・柳澤毅医師は、2回目のワクチン接種を終えた心境について「安心感を覚えた」と話す。
【映像】ワクチン接種の瞬間 米ハーバード大学医師の実体験
「2回目の接種で、確実に免疫を付けることができると考えている。正直、待ち遠しかったですね。早く3週間経ってほしいなと思っていた。打ち終わった後は『これで一安心』というか、そういう感覚はありました」
柳澤医師が働くマサチューセッツ総合病院では、医療従事者や研究者などを合わせ、2万6000人以上の職員が勤務。既に8割ほどの人が2回目の接種を済ませているという。
「残りの4000人も既にスケジュール組まれていますので、まもなくほぼ100%達成という形になると思う。組織としてかなり統制のとれた体制だった。2か月経っていない時点で、(接種率が)ほぼ100%なのはかなり早い。組織として全職員を順番に優先順位を設けて、必ず(ワクチン接種を)受けさせるという、かなり強いリーダーシップが発揮された結果だと思います」
「ワクチンを打った後に、どういった症状が出たかなど、必ず追跡をしている。もちろん国レベルでもやっていて、米国疾病予防管理センター(CDC)が出している『V-safe』というアプリなど、他にもいくつかワクチン後の症状をトラッキング追跡していくシステムがある。私の病院でも独自でアプリを開発して、職員にリマインダーが毎日ある。例えば『けだるさがありますか?』や『熱が出ましたか?』など、そういったのを登録して、蓄積しているんです。なので、例えば『重篤な反応が出た』や『副作用が出た』という情報があれば、すぐに共有されます」
「やはり一番は、組織として情報を全職員に常に共有していたということ。あとは透明性を保つためにいろいろな努力をしていた。それによって職員全体の信頼が得られたと思う。
包み隠さず『こういった計画でいくんだよ、みんな一緒に協力して』という姿勢が職員に伝
わったと思います」
また、情報の透明性は一般での接種でも「重要になってくる」と話す。
「むしろより重要になってくるんじゃないかなと思います。なぜこういう順番なのか、なぜこういう体制にしているのかなど、きちんとやはり説明されないと不安を抱いてしまう」
マサチューセッツ総合病院では2万6000人超の職員を5つのグループにわけ、接種スケジュールを組んだという。優先順位の高い順に接種が開始され、2月3日には職員の98.4%が1回目の接種を終えた。「ソーシャルディスタンスを保つため、15分以上前の到着は禁止」「看護師からワクチン接種に対する同意とアレルギー症状の有無をヒアリング」「注射後はアレルギー対策として15分間待機し、副反応などについて説明を受ける」などの順序があり、全行程30分未満、1日500人弱のワクチン接種を行った。
米食品医薬品局(FDA)では、モデルナ社やファイザー社が開発した新型コロナワクチンについて「承認用量の2回接種が必須」としており、日本の厚生労働省も「1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください」と呼びかけている。「1回目より2回目の副反応が強い」という声も寄せられているが、前述の柳澤医師は「接種した部位の鈍痛のみで、副反応は出なかった」と明かす。
「(2回目は)副反応が出やすいと言われている。僕の周りで10人中4~5人が微熱や気だるさ、頭痛などを感じていた。ただ、みんな1日~2日でよくなって戻ってきた。接種した後に毎日追跡するシステムがあり、3日以上長く症状が続いたり、高熱が出たりすると、PCR検査を受けて休むよう言われる」
その上で、日本で効率的にワクチン接種を行うには「計画をきちんと共有することが重要」だと述べる。
「病院なのか自治体なのか、組織の単位によると思いますが、各組織の情報を共有して、透明性を保つこと。マサチューセッツ総合病院では、かなり前に準備の段階からオンラインミーティングやメールなどで計画がきちんと共有されていた」
柳澤医師の話を聞いた東京工業大学准教授の西田亮介氏は「ハーバード大学といえば公衆衛生の本場だけにマサチューセッツ総合病院は世界で最も進んでいる医療機関の1つ。日本と医療や情報の管理の仕方、さらに透明性の考え方が違う。優先順位をつけたワクチン接種実施もここでならできるかもしれないが、日本の自治体主体の接種の参考にすることはかなり難しいのではないか」とコメント。