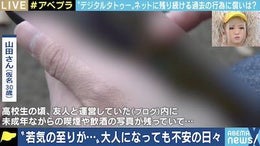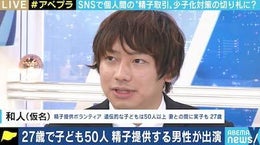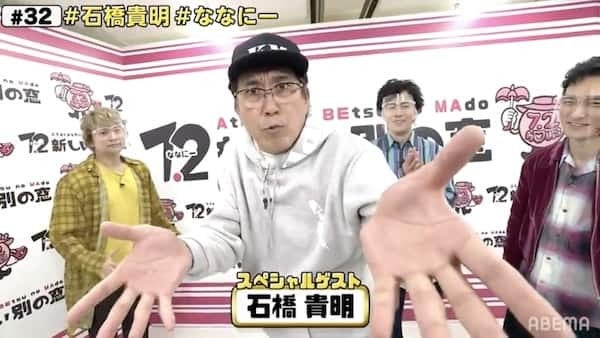そして解剖の大きなハードルになっているのが、遺族感情であるといい、「宗教観や、法医学がヨーロッパを中心に発達した学問だということもあるかもしれないが、私がいたミュンヘン大学では、年に約2500体の解剖をこなしていたし、そのための法制度も整っていた。一方、日本的な感覚でもあるが、多くのご遺族に、亡くなった方にメスを入れたくないという気持ちがあると思う。だから我々がご遺族の同意をいただく時にお話ししているのが、解剖という行為は“人が受ける最後の医療行為だ”ということ。単に身体に傷をつけるだけではなく、亡くなられた原因を明らかにすることが尊厳を守ることにもつながる、ということだ。実際、解剖後に結果を説明させていただくと、承諾して良かったと言っていただける場合も多い」と言及した。
その上で近藤教授は、解剖の意義について「確かに我々が解剖した結果が直ちに治療や新薬の開発に活かされるというわけではない。しかし、例えばドイツのデータを見てみると、肥満の合併率が高いことが亡くなっている要因の一つに挙げられている。そういうことが分かってくれば、リスクファクターの高い方に対する集学的な治療も行えるし、血栓症を防ぐことにつながれば、死亡率を下げることにもなると思う。亡くなった方から得た知識を、今これから生きていく方々に少しでも還元したい。それが解剖の役割だと思っている」と訴えた。
(ABEMA/『ABEMA Prime』より)