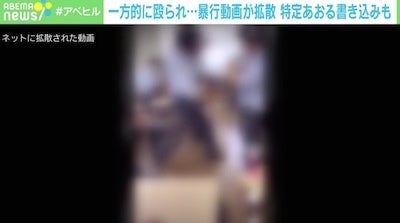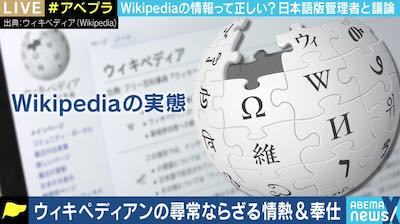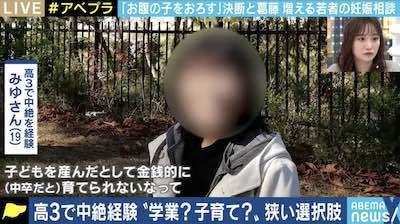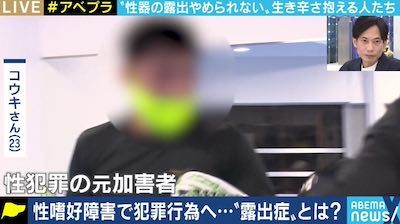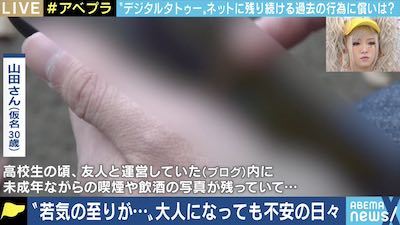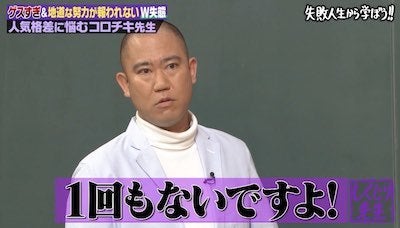・【映像】“感染症対策の司令塔“保健所長が生出演
こうした状況に対し、加藤官房長官は「保健所が保健師等の専門職を中心に重要な役割を果たしている一方で過大な業務負担が生じている。引き続き、保健所でクラスターを特定するための積極的疫学調査が滞りなく実施がされるよう、国としても支援に努めていきたい」と話している。
一方で、「陽性になった場合は原則的に入院かホテルかを選んでいただき、どうしても自宅がいいという方に対しては認めてもいるが、その時にトラブルになってしまうことはある。また、外国の方の場合は文化も異なるので、日本の法制度を理解いただくのが難しいと感じることもある。さらに家庭や職場、会食など、感染の原因が追えている方は3割程度で、残りの7割程度については聞き取りの中では追えない状況にある」とした。
■事後的な対策に注力することで、どれほど流行を抑える効果があるのか
厚生労働省は「感染者の行動履歴確認」から重症化リスクのある人が多くいる場所や、3密、大声を出す環境といった、「感染リスクが高い場所の調査」を優先することに方針を転換している。約150人の人員を抱え、現在では比較的円滑に業務が行えている「みなと保健所」でも、課題は少なくないようだ。
「みなと保健所の予防課にはもともと20名くらいしかいなかったが、さらに生活衛生課と健康推進課も合わせて保健所全体で200名くらいになっているので、足りているといえば足りている。とはいえ対応が可能な職種は限られているし、私たちもこの生活を1月から続けている。かなり疲弊してきている部分はあるし、この体制でどこまでやり続けるか、という問題はある。やはり陽性者を病院に送り込んでいるのは保健所なので、病院の前に保健所が逼迫してしまうことにはなるし、そこは保健所の数が減っていることも背景の一つにはある。今後は全国的にもお辞めになる方が出てくる可能性もあるだろう」。
「例えばインフルエンザであれば発熱後の数日、自宅にいていただくだけなのに、コロナの場合はほとんど症状がない方についても手厚い対応をしている現状がある。そこは重症の方だけ対応するといった方針にしていかないと、本当に必要な人が医療に繋がらなくなってしまう。単に保健所の人数だけを増やすというよりは、指定感染症の問題も含めた法制度の検討が必要ではないか。そもそも新しい感染症がでて、十何万人もが指定感染症のままというのは、史上初めての事態だと思う。新型インフルエンザの時も、致死率が低いとか、軽症の方が多いといった理由で、いきなり解除になった。その後に立てられた行動計画でも、初期には封じ込めてピークを下げ、その間に様々な準備をするが、やはり流行期には重症化対策にシフトしていくことになっている」。
■第1波と第3波、感染者数だけで単純な比較はできない
「GoToトラベルがどれくらいの影響があったかというのは私には分からないが、これを止めたとしても結局は会食をされていたりするわけで、それだけで済む話なのかどうか。港区では保育園での感染についての報告書を出しているが、園児やスタッフが陽性になられても、手指消毒とマスクなどの対策により、実際に広がってはいないということも分かっている。感覚としては、やはり発症される方の前2日くらいの、体調が悪くない時に飲み会に行かれてしまう、その感染力は高いと思う。そういう意味では、どこまで検査をして無症状の方を見つけていくのか、という問題もあるし、やはり基本の感染対策をやっていただきたい。マスクを外した時が最もリスクが高まるのは事実なので、特に気をつけていただきたいし、体調が悪い時には自宅で休んでいただきたい」。