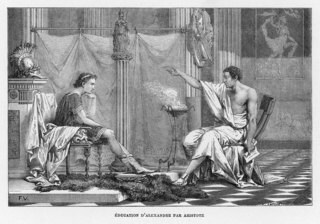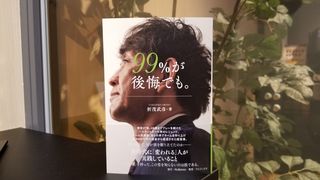学術会議がダメなところ(3)
縦割りタコツボの元凶
私は、東大では「大学院情報学環」などという正体不明の組織に籍があり、実際には音楽屋ですから、私の商売、作曲も指揮も、学術会議とは縁がありません。
翻って「学術会議」会員は、エスタブリッシュメントの学会推薦で、「学際新領域」などからは普通は選ばれません。ときおり「名誉白人」みたいなケースはあり得ますが、新領域に居場所はありません。
逆に私は楽隊という別の持ち分で、自分の畑ではノーベル賞も別段何とも思わない程度に仕事はしてきましたから、何も臆することなくノーベル賞審査員諸氏とも同じ目線で仕事させてもらってきました。
ノーベル賞審査員諸氏は立派な仕事をしておられますが、別段組織的に上下があるわけではない。
また、政策マン、戦略マンとしてきっちり仕事はしますが、定年後の名誉職お達者クラブにお仕えする趣味もない。
私の著作物から名を消されて、その人たちの業績を作ってやる義理もありませんから、見捨てたという、今年に入ってから現実にあった事例を引いて、学術会議の一つの横顔として紹介しました。
そこまでひどいのが学術会議のすべてと誤解されませんように。もっとまともな分科会もたくさんあると思います。
ただ、旧来からの学術分野、その縦割り・タコツボ温存の大本が、部に分かれて構成された「学術会議」にあるのは間違いありません。
「学際」何ちゃらかんちゃらと名のつく所の実態も、これは別原稿としますが、およそ極北の寒さにあります。今回ハネられた6人にしても、
小沢隆一:(憲法)
岡田正則:(行政法)
松宮孝明:(刑事法)
加藤陽子:(史学)
芦名定道:(キリスト教)
宇野重規:(政治学)
と、どなたも確立された領域の人間ばかりでしょう?
つまり、学際新領域などというものは、背景となる歴史の古い学会が存在しないので、実質的には学術会議に正会員として推薦される可能性がゼロなわけです。