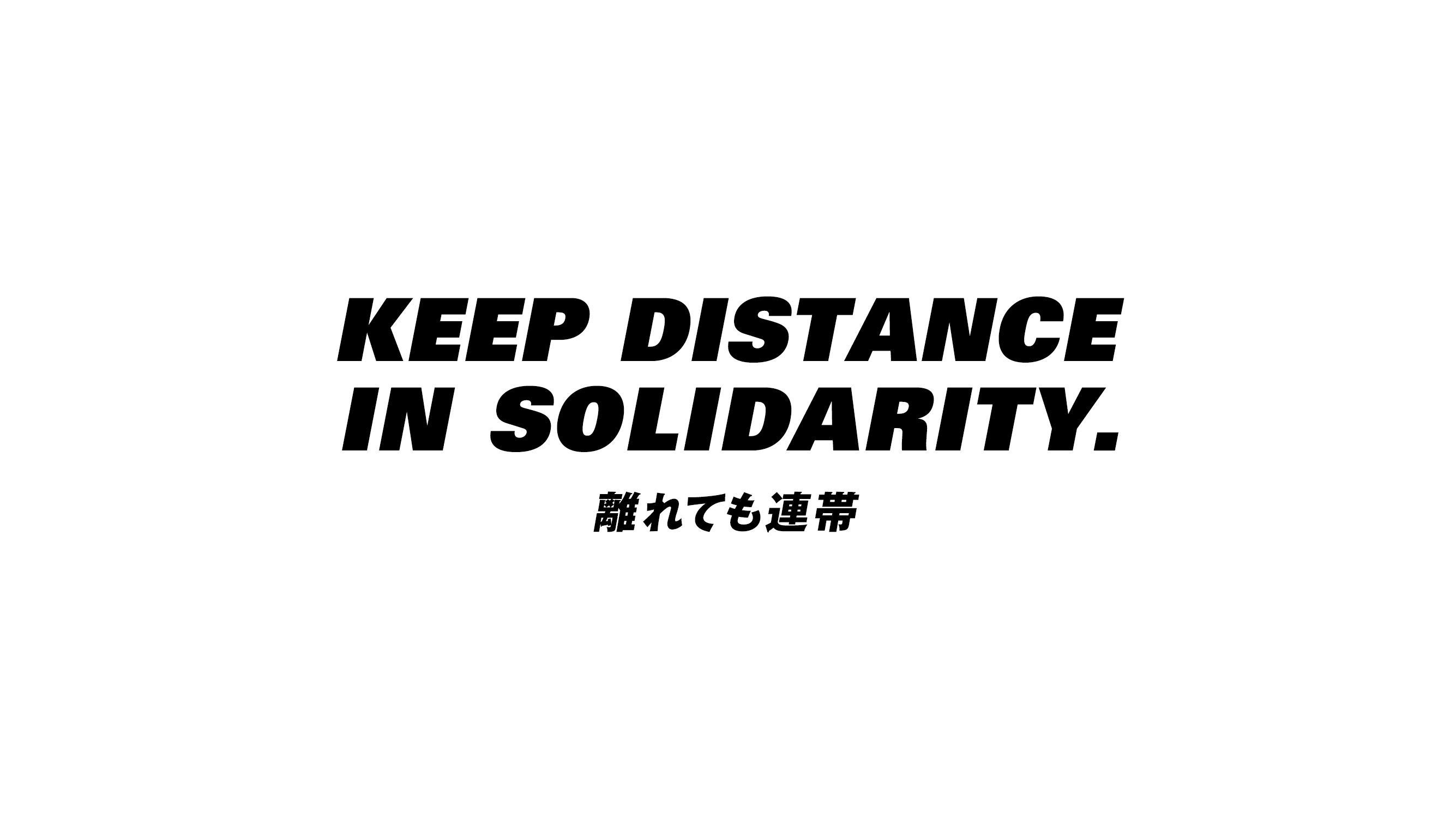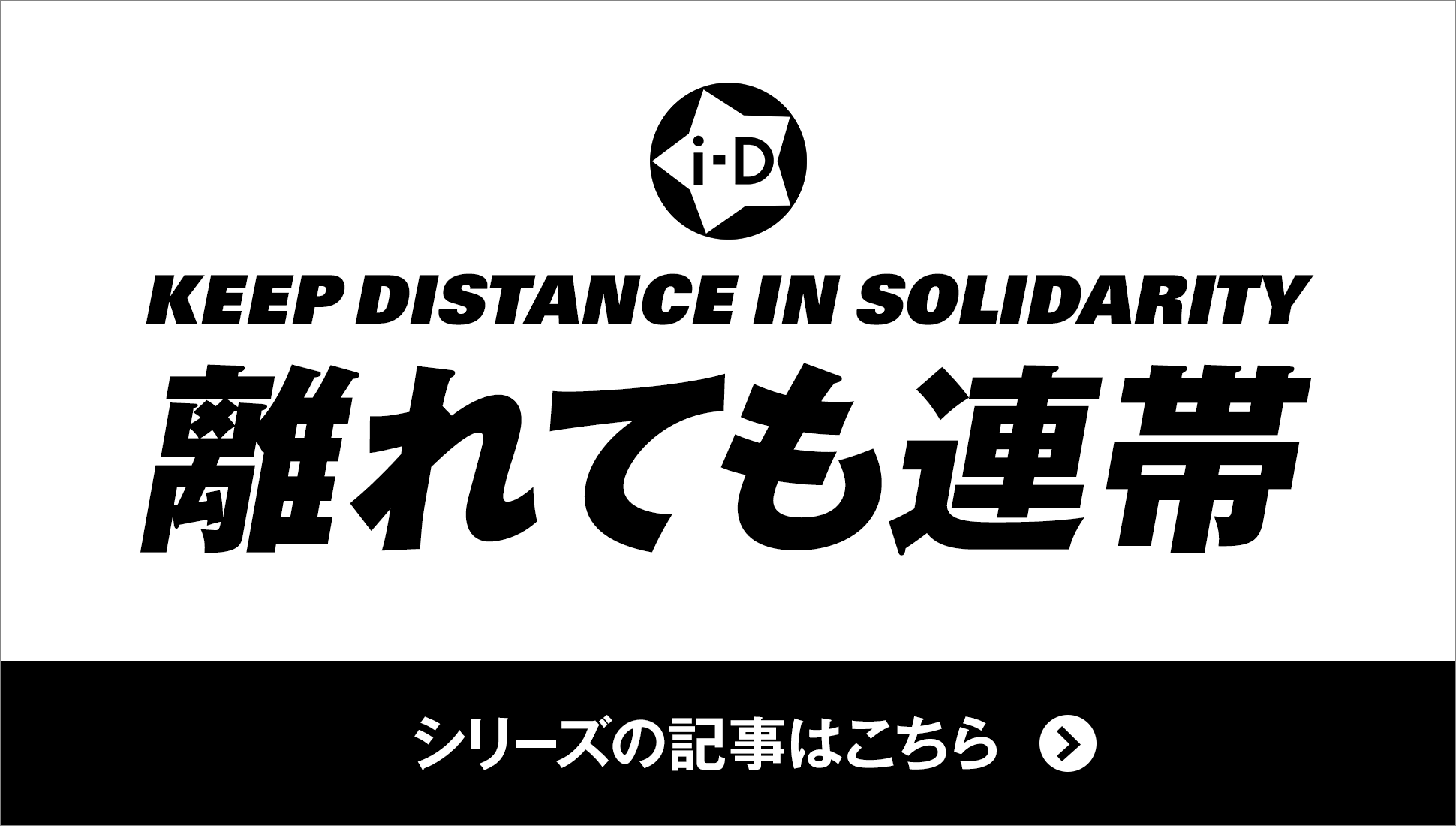木澤佐登志のレット・イット・ディ(プレッション)【来るべきDに向けて】
現代特有の「病」であるメンタルヘルス。それはどこからやってくるのか。気鋭の文筆家・木澤佐登志が、鬱病と資本主義社会の表裏一体の関係を紐解く。
坂本龍一とGotchが中心となり、震災(Disaster)から10年(Decade)という節目にさまざまなDをテーマにした無料フェス「D2021」が、2021年3月13日と14日に日比谷公園で開催される。この連載「来たるべきDに向けて」では、執筆者それぞれが「D」をきっかけとして自身の記憶や所感を紐解き、その可能性を掘り下げていく。
今回はインターネット文化から思想まで多岐にわたる領域で執筆活動を行ない、著作に『ダークウェブ・アンダーグラウンド 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』『ニック・ランドと新反動主義 現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』がある文筆家の木澤佐登志が登場。
ここ数年でメンタルヘルスに対する人びとの関心は一気に高まった。現代に特有のこの「心の病気」は、ミレニアル世代やZ世代にとっても大きな悩みの種であり、欧米のカルチャーメディアでも日々メンタルヘルス関連の記事がアップされ続けている。ではこの「病(やまい)」はどこからやってくるのだろうか。その原因は果たして、その人自身にあるのだろうか。
『資本主義リアリズム』著者で批評家のマーク・フィッシャーが自身の鬱病について記したテクストを手がかりに、鬱病と資本主義との関係性に迫る。
「Depression──鬱」木澤佐登志
2017年にみずから命を絶った批評家マーク・フィッシャーのテクストに、「何の役にも立たない(”Good For Nothing”)」と題した、十代の頃から彼を断続的に苦しめてきた自身の鬱病について書かれたものがある。その中で、彼は次のように書いている。「僕の鬱は、自分は文字通り何の役にも立たないという確信と常に結びついていた。三十歳までの人生のほとんどを、自分は絶対に働けないと信じて過ごしてきた。」
フィッシャーは、常に自分はどこにも居場所がない、求められた人間の役割をこなすことができないと感じていた。フィッシャーは精神病院の中にいたときさえも、自分は本当は鬱病ではないのではないかと感じていた。働く能力がないという事実、この社会のどこにも自分の居場所が存在しないという事実から目を背けるために、鬱病を擬態しているにすぎないのではないのか、と。
最終的に進学教育大学の講師としての仕事に就いたときも、フィッシャーは自分に教職のような仕事が務まるとは、確固として信じることができなかった。
こうした信念、すなわちフィッシャーが抱いていた「何の役にも立たない」という無能感はどこからやってきたのだろうか。それはたとえば、生まれつきの性向なのか、あるいはなんらかの脳器質疾患なのか、それとも精神分析でのみアクセス可能なような奥深いトラウマなのか、等々。
長年にわたって鬱に苦しんできたフィッシャーによれば、どれも少なからず正しくないという。フィッシャーは、イギリスの臨床心理学デイビット・スマイルが提唱した「魔術的自立主義(‘magical voluntarism’ )」という概念に注意を払っている。魔術的自立主義、つまりそれは、自分の力だけが自分を変え、なりたい自分になることができるという信念であり、フィッシャーによれば、現代の資本主義社会の支配的なイデオロギーを構成している。そして、鬱病とはこの「魔術的自立主義」の裏返しにほかならない。
つまりはこうだ。鬱病の原因はいつだって自分にあり、自分の不幸の責任は自分にしかなく、それゆえその苦しみは受けるにふさわしい、と。自分の不幸の責任は自分にしかなく、それゆえにそれに値する。再帰的な悪循環と無能感。ここから、また別の自己責任が招来してくる。貧困、機会の喪失、失業、それらもまた自分自身だけの責任であり、その境遇を受け入れなければならない。そう、ここには「社会」というものが存在しない、イギリスの元首相サッチャーがかつて言ったように──。
フィッシャーは次のように書いている。「僕が自分の精神的苦痛の経験を書くのは、それが何か特別だったり珍しいと思ってるからじゃない。そうじゃなくて、多くの鬱の形は、個人の枠組みや心理学の枠組みではなく、むしろ非個人的かつ政治的な枠組みを通すことで、もっとも理解でき、そして闘うことができるという主張に僕が与しているからだ。」
感情的・心理的な苦痛が、最終的にそれを受ける者からかなり離れたところにある社会的・環境的な力の作用によってもたらされることが多い、と上述のデイビット・スマイルは述べる。従来の精神医学は、鬱の原因を(患者からもっとも近いところにある)脳の神経作用に還元していった。抗うつ薬プロザック・ブーム以降、多くの人々が生産性や仕事のパフォーマンスを上げるために向精神薬を飲み、みずからを「神経化学的自己」へと改造していった。
資本主義社会を律する「(再)生産性への信仰」、クィア理論家のリー・エーデルマンが「再生産的未来主義」と呼んで批判してみせたこのイデオロギーは、「何の役にも立たないこと」にネガティブなスティグマを押し付けていく。こうした社会における鬱病患者治療の役割とは畢竟「何の役にも立たない」人々を、社会という名の生産性の回路に組み込み再配置していく不断の作業に他ならない。しかし、フィッシャーのような人々にとって、その割り当てられた場所は常にどこか居心地が悪く(ここには自分の居場所がない)、割り当てられた仕事や、割り当てられた諸々のアイデンティに対しても、その期待された役割を完全にこなすことがどうしてもできないのである。
彼らは「何の役にも立たない」という内なる声によって自分を責めながらも、どこかで社会の<外部>を幻視しているのだろうか。社会の外へと通じる「出口」(イグジット)を探し求めているのだろうか。
唐突だが、ミシェル・フーコーには、1979年に執筆された「かくも単純な悦び」という甘美なテクストが存在する。同性愛者の自殺についての、戸惑うような一文とともにはじまるこのテクストは、人々が死ぬことを求めて訪れる、東京のラブホテルを思わせる幻想的な迷宮のヴィジョンの描写を以て閉じる。その東京のフランス式シャトー、すなわち「ありうべきもっとも不条理なインテリアに囲まれて、名前のない相手とともに、いっさいの身分(アイデンティティ)から自由になって死ぬ機会を求めて入るような、地理も日付もない場所、そうした場所の可能性が予感されるのだ」(増田一夫訳)。
端的に言えば、そこは社会の絶対的な<外部>であり、あまねくアイデンティティが蒸発してしまうような非−場所なのだ。そこでは「死」が「絶対的に単純な悦び」として、名前のない相手と共有される。
そこでの何週間とも何ヶ月間とも知れぬ不確定かつ緩慢な時間の中で、彼らは待ち続けるだろう。何の役にも立たないものが、何の役にも立たないものそれ自体として肯定されうる、そのような瞬間が、絶対的な自明さと絶対的な単純な悦びを伴って現れるまで──。

「D2021」
日時:2021年3月13日(土)、14日(日)
会場:日比谷公園(日比谷公園アースガーデン“灯”内)
主催:D2021実行委員会
共催:アースガーデン/ピースオンアース
※D2021は「311未来へのつどい ピースオンアース」の関連企画です