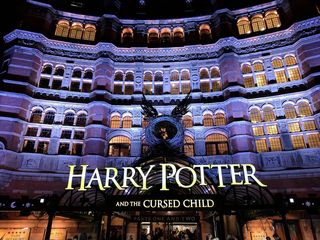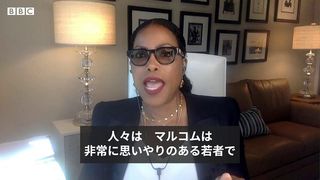政府からも専門家からも独立した「科学顧問」が欲しい
森田:科学顧問の設置という提言を西浦先生は出されていますね。現在の分科会やアドバイザリーボードとはどう違うのですか。
西浦:システムとして政府からも専門家からも独立しているというのが、科学顧問の本来的なあり方だと思います。もちろん、内閣の下にあっていいのですが、総会屋的な根回しの上で会議をするタイプの科学的見解ではありません。少なくとも独立した組織で、できればファウチ所長のように政治とまったく違う意見かもしれないけれども堂々と言うことができ、その身分は政治家や補佐官、審議官の邪魔が入らずに保証されていて、科学顧問の周囲を固めるコミュニケーションのプロがいる、という状況が恐らく理想だと思います。
今、国の専門家から出てくる意見というのはあくまで、特定の省庁がお墨付きを与えた専門家からの意見や審査なんです。それに対して、今の日本でも起こっているように、「もう免疫を持ってるから絶対流行の波は来ない」「もうインフルエンザと一緒だから流行を受け止めよう」といった意見が出るのは健康的なことだと思います。みんなが前に進むためにはいろんな意見があっていい。それが民主主義のコストでしょう。
そのため、専門家の意見と言っても百家争鳴状態になると思いますが、その中でも「科学的に信頼すべきポイントはここで、だからこっちの方向に向かって歩くべきだ」というような助言を言える存在が科学顧問です。有識者会議の上に高名な先生のグループを設置するのとは少し違います(笑)。
新型インフルエンザ2009の総括会議で、(東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授の)押谷仁先生が「高度な専門的知識・経験を要する状況では政治主導は大変危険である」ということを明確に記録に残されています。政治家主導だと、国の議論を誤った方向に導いてしまうことが起こり得るんです。
都道府県知事のリーダーシップが重要だが
西浦:日本の政府そのものは保守的な政党が政権を握っているので、政策自体はそんなに冒険しない。一方、現時点では日本国政府として地域を絞って接触を削減する、休業要請をするといった思い切った手段は取らず、都道府県に任されている状態です。いわば、都道府県知事のリーダーシップに期待が寄せられている状態ですが、政治主導が行き過ぎて科学的評価がおざなりにされがちだったり、バックアップのブレーンがちょっとエキセントリックだったりすると、ユニークな話が出てくることになります。これも民主主義のコストだと考えると、僕たちは今回の流行を通じて、民主主義社会として成熟するプロセスをたどらされているのかもしれません。
コミュニケーション1つとっても、たとえば総理が記者の前に出るときに、総理の横でささやける、ヘルスケアに精通したコミュニケーションのプロがいたらと思います。そういった、専門知を結集できるようなやり方がもう少し何かあるだろうというのは強く感じていることです。