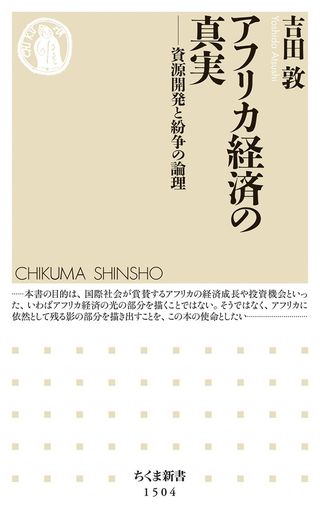専門家の判断と政策判断は違って当然
西浦:今の「Go To」キャンペーンの政策議論もありますけど、政策に関して専門家と政治のそれぞれの本音やズレが明確である、という最近の状況はよくなったかなと思っています。
専門家の有志の会では、基本は「ヒトが動いて流行対策にいいはずがない」ということがベースにあり、少なくともヒトの動きを勧奨することはできない、という議論をしてきました。どうしてもやるんだったら、家族旅行はいいけれど、会社の社員旅行でコンパニオンさんが来るような団体の密な飲み会は避けてほしい、伝播が起こりそうな環境は避けてほしい──など、細かな条件を指定するという話をしたり、状況が悪くなったら2〜3週間先送りした上で判断できるようにしよう、といった話をしていました。
専門家がアドバイスしたことと、有識者会議の分科会を経た上で西村大臣と一緒に尾身茂先生がおっしゃっていることは実はちょっと違います。でも、それは正常なことです。いろいろな要因を総合的に判断して政策決断がされているのだし、GoToに関しては、尾身先生自身から「先延ばしという提案は政治的に採用されなかった」ということを国会でちゃんと言ってもらうことができました。その意味では、GoToで異常に感染者が増え出したときに、「専門家がいいって言った政策だ」というような、いわゆる「専門家スケープゴート」を成り立たせてしまう状況からは進歩しつつあると感じています。
もっといいのは、そこにいる政策決定者が「先延ばししないという判断の責任は自分が取る」と、国民の一部が犠牲を払うことについて、仕方なく是認しているのだということを明確に述べられることです。米国では、トランプ大統領と米国立アレルギー・感染症研究所のアンソニー・ファウチ所長がお互いに批判しながらも一緒の場で会見しています。日本でも、日本のやり方にあった、もっと成熟した形で実現できるんじゃないかと感じています。