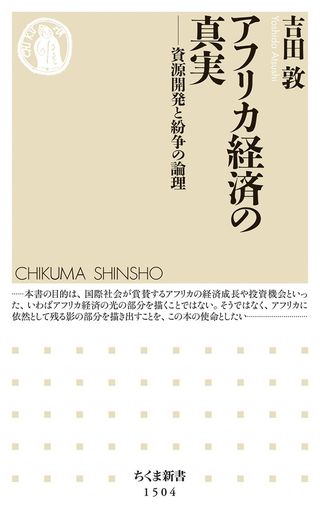森田:私が非常に危惧するのは、このままさらに感染が広がって、かなり強い手段を使わざるを得ない状況になる可能性です。その時には、戦略としては一番まずい「兵力の逐次投入」のようなことになり、国全体として疲弊してしまうのではないかと懸念しています。
しかしそれ以前に、強い手段に踏み切るためには法改正が必要で、その議論が進まないのを歯がゆく思っています。刀を用意をした上で伝家の宝刀にしておくのも1つの方法だと思うんですね。抜くか抜かないかは最後に決めればいい。抜かなきゃならなくなってから刀を作るのでは間に合いません。
「三密」が最も有用なのは感染者が少ない時
西浦:これまでも何度も、政策決定者の立場から感染症対策と社会経済活動というのを両立するということが明確に説明されているんですけれど、一方でその根拠に明示的なものがないことに気付いておくことは極めて重要です。アカデミックに最適解を追求していない、いわば勘に頼っている状態に近いかもしれません。これは、次の波までに何らかの形で解決しておかないといけないことだと思います。
今の制御の考え方は、医療体制の逼迫を避けるという論理で進められていますが、実を言うと、感染を減らすために休業要請が必要なら、もっと小さい山の時点で接触を減らす方が休業期間も短くなるし、流行のピークも小さくなるんです。この点については、増える前の段階から厚生労働省が発表した病床の改善版シナリオで明示的に議論をしてきました。今はもう感染者が増えてしまっているので、病院も、それ以上に保健所も相当厳しい状態です。
本格的にクラスター対策をやっていた時には、数が少ないから感染伝播の連鎖が消えるという確率的な現象を、三密を防ぎながら狙っていました。「感染者数が少ない時に三密対策が特に有用」という考え方は、実は皆さんにあまり知られていませんが、背景の理論に確率的な絶滅というものがあるんです。
三密については、患者が少ない時も増えた時でも三密を避ける効果が同じだと思ってはいけないところに落とし穴があります。なのに、感染者が増えてもモノトーン調に三密の重要性が発表されています。他方、専門家メンバーは三密回避が依然として重要だけれども、話の内容が真新しくないために上手に伝達されないことに悩んでいる状態です。
いずれにしても、今の戦略自体が感染対策と経済を両立させる最適解かというと、少し怪しいです。仮に科学的に正しくないとするならば、なぜこういうやり方をとっているのかという点は、もうちょっと政策策定側が明確にしておかないといけないように思います。