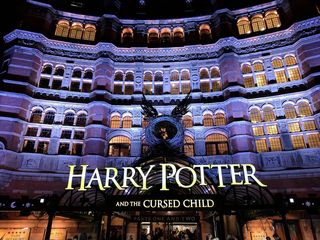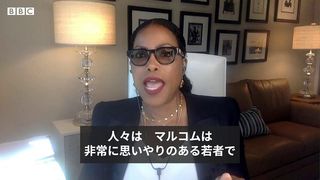森田:リスク評価とリスク管理といった場合、たとえば、感染者が増えているから実効再生産数がこういう数字になるというのは、これは評価の話ですね。その次に、たとえば接触を30%減らすと実効再生産数が1以下になるという予測も評価から出てくる判断です。具体的にどうやって接触を30%減らすかというのはオペレーションだから、管理の話になるという理解でいいでしょうか。また、どこを抑えると30%減になるかということは、評価サイドの研究者が提供できるのでしょうか。
西浦:一部の地方自治体が持っているデータで、どのような属性の人の間で二次感染が起こっているかはある程度、分析ができています。たとえば、職業別で誰が誰に二次感染を起こすという相対的頻度を推定すると、どこを止めるとどれくらい効果があるというのが分かってきています。ただ、自治体の懸念もあって、その情報はなかなか公表することができていません。
また、俗に「夜の街」と呼ばれているところについても、自治体で思い切って検査をして、集団発生の時点で封じ込める試みをしたところがありました。それに対して、ホストクラブなどがとても協力的になるという1つの変化も起きました。協力してもらう代わりに、地下に潜らず、部分営業を安心して続けてもらうためということでやるわけです。
ただ、その後に休業要請をしてばっさりと閉めてしまうと、協力をしていた人の気持ちを反故にするような面もあります。夜間の接待飲食業での伝播を何十%減らせば伝播の多くが止まるって言ったとしても、それを実行するのはなかなか難しい状況にあります。
公衆衛生より営業と行動の自由が重視される日本
森田:海外では、はっきりと禁止して十分な補償もなしというのが一般的だと思います。強制力をもって閉めていますね。行政学をやっていた立場から言うと、公衆衛生では、まだ感染していない人たちを守るために、強制隔離によって感染者との接触を断つというのが一番重要です。でも日本の対応はソフトというか、公衆衛生よりも営業、行動の自由が重視されているように思います。
西浦:おっしゃる通りです。感染症法の基本的な考え方はそこなんです。感染症の流行を制御することによって、感染していない人の感染や死亡を防ぎ、人口全体の利益を最大限にするために一定の行動制限というものを認めるということです。たとえば、感染症法の44条などを利用すれば、自宅待機や就業制限というところまで、ある程度行動を縛って二次感染を防げます。ただ、とくに要請ベースでこの流行に立ち向かっている日本では、それぞれの細部にほころびやずれが出てしまいます。それが、今の状況につながっているんだと思います。