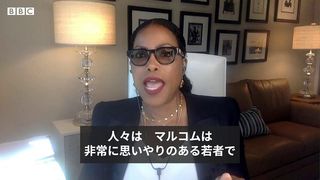西浦:本来、リスク評価とリスク管理は別のものですが、リスク評価者であるべき僕たちがリスク管理にある程度、立ち入ってしまった状態だったんですね。いったん専門家会議が終わるところで、専門家会議の座長、副座長であった脇田(隆字)先生と尾身(茂)先生が皆さんの前で、「前のめりになりました。ごめんなさい」というお話をしたのも、リスク管理に立ち入ったという反省があったからです。
そうした経緯があって、リスク評価や現状分析を専門家が直接皆さんに届ける機会はとても少なくなっています。現状、リスク評価自体は厚労省のアドバイザリーボードという専門家組織に残っていて、リスク管理は厚労省外の内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策分科会(尾身茂分科会長)でやっています。第一波の教訓もあるので、リスク評価と管理の切り分けをしたいという強い意識が専門家の中にあります。
今後のことも考えると、リスク管理や政策の決断に関しては政治家の人にやっていただかないといけないということを、専門家は相当意識しています。結果的に、流行の現状について専門家組織が自由にしゃべらないという状況になっています
実効再生産数はずっと1を超えていた
西浦:実際のところ、緊急事態宣言を解除してから実効再生産数はずっと1を超えていたんです。でも、日本はかなり速いペースで規制が緩和されました。それ自体はもちろん政策判断なので仕方ありませんが、海外では、実効再生産数がたとえば1を超えている時間が一定期間続くとそこでブレーキを踏んで逆戻りをするという対応をとっています。
それに対して、日本では実効再生産数を使った判断が採用されてきませんでした。実効再生産数を活用した指標については私もリスク評価の場でたびたび説明してきましたが、8割接触削減の考えのベースになったSIRモデル(感染症の数理モデル)や実効再生産数がさも悪かのように政治家に扱われた時期が宣言解除後にありました。残念ながら、実効再生産数が積極的に採用されずに規制緩和が進み、ここまで感染者が増えてきたのが実情です。
実効再生産数が、たとえば東京で1.4ですという時には、リスクの高い場所での全接触のうち30~40%の接触を減らすと、実効再生産数が1を割るということにつながります。でも、そうやって言及することは、対策、つまりリスク管理の方の話になってしまうので、専門家がどこまで入り込んでいいのかという葛藤をずっと抱えながらやってきました。
現状では、公には実行再生産数をリアルタイムで説明できていません。だから今、実効再生産数を計算できるダッシュボードの近日公開を目指しています。市町村等が自分のデータを使って最新の実効再生産数が分かるサイトです。