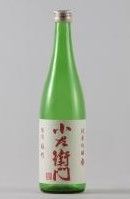岐阜の日本酒【射美(いび)】“日本一小さな蔵元”から生まれる逸品
「射美」は、造り手と地元農家が連携して開発したオリジナルの酒造好適米をはじめ、地元産の原料にこだわった岐阜県の地酒。最近では、定番商品に加えて「無ろ過生原酒」でも日本酒好きを魅了しているという、「射美」の人気の秘密を探ります。
- 更新日:
「射美」は“美酒を射る”志から生まれた酒
Benoist/Shutterstock.com
「射美」は、揖斐川とその支流、根尾川に囲まれた、岐阜県揖斐郡大野町で育まれている、日本酒ファンに話題の地酒。
「射美」という銘柄の名は、地名の「揖斐」と、「美酒を射る」という志からつけられたそうです。
「射美」の製造元、杉原酒造は明治25年(1892年)に創業した100年の歴史をもつ蔵元。現在は従業員が、社長を務める杉原庄司氏と、酒造りを担う5代目慶樹氏の親子2人だけという、自称“日本一小さな酒蔵”。
慶樹氏は、家業を継ぐため、会社員から転身して酒造りを始めたそうです。名酒と称えられている三重県の地酒「而今(じこん)」の造り手とは、ともに学んだ仲だとか。
そんな切磋琢磨のなかで、2009年に誕生した銘柄が「射美」。なかでも最近、高い評価を得ているのが「射美 槽場(ふなば)無ろ過生原酒」です。ろ過や熱処理などをいっさい行わずに出荷するのは、近年の日本酒のトレンドのひとつですが、慶樹氏は、その搾りたての風味に確かな手応えを感じ、「射美」シリーズの中核商品に据えています。
幻の日本酒【而今(じこん)】今を生きる酒
「射美」の酒米は農家とともに開発した専用品種
Purino/Shutterstock.com
「射美」の原料米「揖斐の誉(いびのほまれ)」は、杉原酒造が地元農家とともに開発した、オリジナルの品種です。
もともと、県内でも美濃エリアに位置する揖斐の地は、冷涼な飛騨エリアに比べて夏季の気温が高く、質の高い酒米の栽培には不向きといわれていました。しかし、慶樹氏の「美酒を造るには、よい酒米作りから」との心意気に打たれた地元農家が、品種交配に挑戦。
試行錯誤の末、代表的な酒造好適米「山田錦」と、愛知県で生まれた「若水」の2種類をかけ合わせ、「射美」専用の酒造好適米「揖斐の誉」の開発に成功しました。
現在、地元農家では、所有する田んぼのなかに専用のスペースを確保して、大切に「揖斐の誉」を育てているのだとか。
そんな独自の品種を使い、誕生したのが「射美」。“地元の自然が育てた、地元産の原料米で醸す”という、地酒造りの原点回帰を果たした日本酒なのです。
「射美」は常に向上し続ける酒
ZoranKrstic/Shutterstock.com
「射美」は、「無ろ過生原酒」で注目を集めている銘柄ですが、そのベースとなる味を支えているのは、地酒らしい、地元志向の手間暇かけた酒造りです。
仕込み水には、原料米「揖斐の誉」の栽培に使うものと同じ、蔵の近くを流れる揖斐川の伏流水を使用。発酵を司る酵母には、酒造場にすみついている「蔵つき酵母」を用いています。
原料だけでなく、酒造りの工程にもこだわりがあります。もろみを搾る際、一度に大量に搾るのでなく、「槽(ふね)」と呼ばれる伝統的な容器や、袋吊りといった昔ながらの手法を貫いています。
このように、原料や工程に独自のこだわりを見せるからといって、現状維持をよしとはしていません。「射美」は「常に変わらない味」ではなく「常に変化を求め、上をめざしている」お酒です。
その証のひとつが、原料米である「揖斐の誉」の改良。現在では、品種系統の異なるタイプも開発され、酒造りに活かされています。
いっさい妥協しない、ていねいな酒造りと、常に向上を求める姿勢。
進化を遂げ続ける「射美」に、これからも目が離せません。
「射美」は、蔵元が信頼関係を築いた酒販店で、店頭販売を基本に扱われています。人気の高まりとともに入手が難しくなり、今や“幻の日本酒”とも呼ばれている「射美」ですが、それだけに出会いの喜びも大きいはず。まめに探して、ぜひ手に入れてみてください。
製造元:杉原酒造株式会社
公式サイトはこちら