奈良の日本酒はどう選ぶ? 国際唎酒師が教える選び方のポイント
国際唎酒師の宇津木聡子さんに、奈良の日本酒を選ぶときのポイントを3つ教えてもらいました。宇津木さんの選び方を参考に、自分好みの日本酒を選んでみましょう。
日本酒の歴史をたどるように選んでみる
唎酒師・国際唎酒師、マーケティングコンサルタント
奈良は「日本酒発祥の地」のひとつといわれています。奈良市南東部にある「正暦寺(しょうりゃくじ)」では、当時としては革新的ともいえる「三段仕込み」「諸白(もろはく)造り」「菩提酛(ぼだいもと)造り」の酒造法に加え腐敗を防ぐために「火入れ作業」をおこなうなど、近代の酒造りの基礎となる技術が奈良時代に確立されていたとされ、室町時代の古文書「御酒之日記(ごしゅのにっき)」にも記録されているのです。
また奈良県桜井市には、酒と杉玉の発祥と深いゆかりをもつ大神神社があります。日本酒発祥の地、奈良のお酒を楽しむために、日本酒の歴史と各蔵元やそのお酒のつながりに着目しながら選んでみましょう。
今西酒造『三諸杉 特別純米酒 山乃かみ』
日本酒発祥の地・三輪で造られている日本酒。ササユリの花から採取した酵母を使って仕込まれており、フレッシュでみずみずしい味わいとキレのよさが楽しめる。
>> Amazonで詳細を見るお酒の仕込み方の特色に注目
唎酒師・国際唎酒師、マーケティングコンサルタント
奈良のお酒は「米の旨味や、甘味、酸がありながらも飲み口はすっきり」とされる傾向にあります。しかしながら、お酒をどう仕込むかによって、味わいにはさまざまな特徴が生まれます。
室町時代の奈良で生まれた「菩提もと」はそのひとつで、仕込み水に生米と蒸米を入れて天然の乳酸菌を増やした高酸度の水で酒母を造る伝統的な方法。江戸時代以降、衰退、消滅しますが、1996年から酒蔵や県工業技術センターや正暦寺などが復元に取り組み、1998年に再現に成功しました。
「菩提もと」(別名は「水もと」)で仕込まれたお酒はぜひ一度お試しください。そのほかにも、各蔵元が取り組む仕込みに注目して、味わいの違いを楽しみながら選びましょう。
美吉野醸造『花巴 水酛 純米原酒』
「菩提もと」(水もと)で仕込まれた純米原酒。チーズやヨーグルトのような発酵臭が特徴で、熟成させることで徐々に味が変わる楽しい日本酒。
>> Amazonで詳細を見る水、お米の違いを感じながら楽しむ
唎酒師・国際唎酒師、マーケティングコンサルタント
日本酒の味わいは、使われる水や米の性質によっても違いがあることはよく知られていますが、水の性質の違い、使われている米の種類は、奈良のお酒選びでもひとつのポイントになるといえるでしょう。
奈良には複数の湧き水群が点在し、その代表的なものに吉野郡の湧き水群があります。また、奈良のお酒ならではの味わいを感じたいなら、奈良県のみで栽培されている「露葉風(つゆはかぜ)」という酒米で造られたお酒を試してみてください。
そのほかにも、奈良のお酒にはさまざまな米が使われているので、違いを楽しみながら飲み比べてみましょう。
風の森~露葉風50~純米大吟醸しぼり華 無濾過生原酒720ml
奈良の酒米「露葉風」で造られた無濾過・生原酒です。旨味、甘味、酸味が絶妙のバランスで、開栓後にも、発泡感がおさまってくるごとに味わいの変化が楽しめます。
>> 楽天市場で詳細を見る奈良の日本酒おすすめ10選 国際唎酒師の厳選商品
ここまでで紹介した奈良の日本酒の選び方のポイントをふまえて、国際唎酒師の宇津木聡子さんに選んでもらったおすすめ商品を紹介します。それぞれの特徴をふまえて、自分の好みに合いそうな日本酒を選んでみましょう。

今西清兵衛商店『春鹿 純米 超辛口』
出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 奈良市福智院町 |
|---|---|
| 使用米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | - |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
質の高さを感じる定番
奈良市の中央部にある福智院町にあり、明治17年(1884年)の創業以来奈良酒の伝統を守りながらも進化を続ける酒蔵。「米を磨く・水を磨く・技を磨く・心を磨く」を理念に醸し出される味、コク、香りがありながらもすっきりとしたお酒は、国内外で広く愛されています。
こちらは春鹿の代表銘柄とされるお酒。「超辛口」といいつつもやさしい香りとまろやかさ、おだやかな旨味があり、フィニッシュに心地よいキレが感じられます。いろいろな食事と合わせやすく、冷酒で軽やかに、またお燗でほどよく旨味をふくらませてなど広い温度で楽しめるでしょう。定番の食中酒としてもおすすめです。

中本酒造店『山鶴 純米酒』
出典:楽天市場
| 蔵の所在地 | 生駒市上町 |
|---|---|
| 使用米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール度数 | 15.2度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.7 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
「光る蔵」が醸す食に寄りそうお酒
長い歴史をもつ蔵の多い奈良のなかでも屈指の老舗で、創業は江戸中期の1727年。小さな蔵でありながらも「光る蔵」をめざし、現在は純米酒のみをすべて吟醸規格の精米歩合60%以下と低温発酵で造っています。手造りの伝統を守る一方で、設備や商品管理には最新技術を取り入れているのも特徴。
「旨い料理には山鶴」「山鶴には旨い料理」がコンセプトというだけあって、料理と合わせるのが楽しみになるお酒がそろっています。米を60%まで磨いて醸されたこの純米酒は、軽やかでキレのある印象のなかに旨味とコクもしっかり生きた味わい。
合わせる料理を選ばず冷酒からお燗まで楽しめるので、コストパフォーマンスの高い晩酌のお酒をお探しの方におすすめです。

梅乃宿酒造『アンフィルタード・サケ 山田錦』

出典:楽天市場
| 蔵の所在地 | 葛城市東室 |
|---|---|
| 使用米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度数 | 17度 |
| 日本酒度 | +0.3 |
| 酸度 | 1.9 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
ワインが好きな方にもおすすめ
1893年創業。『梅乃宿』は、蔵の庭にある樹齢300年の梅の古木に飛んでくるうぐいすが、風雅なさえずりを楽しませてくれることにちなんで名づけられました。さまざまなお酒の楽しみ方を提案する蔵元であり、日本酒以外にも日本酒ベースのリキュールなどバラエティに富んだラインナップがあります。
手間をかけて造った純米大吟醸のもろみを強い圧力をかけずにゆっくりとしぼり、濾過(ろか)、火入れをせずにびん詰めしたのがこちらのお酒です。あふれるようなフレッシュ感とフルーティーさが口の中に広がり、あと味はすっきり。やや白ワインのようなおもむきのある味わいは、ふだん日本酒をあまり飲みなれない方におすすめです。

油長酒造『風の森 露葉風 純米大吟醸しぼり華』
出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 御所市 |
|---|---|
| 使用米 | 露葉風 |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度数 | 17度 |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | 2.1 |
| 容量 | 720ml |
時間の経過も楽しめるお酒
江戸時代初期にできた陣屋町の情緒が今も残る「御所(ごぜ)」にある、創業1719年の蔵元です。『風の森』はすべて生酒。自社井戸のミネラル分豊富な葛城山系の伏流水を仕込み水に使い、無濾過、無加水で醸されています。ほんのり残る発泡感、ボリュームのある香味とさわやかな酸味が融合した個性ある味わいで、日本酒ファンにも人気です。
この純米大吟醸は、奈良の酒米「露葉風」で造られており、透明感の中に旨味、甘味、酸が表情豊かにとけこんでいます。開栓後、発泡感があるときはフレッシュに、時間とともに発泡感が消えた状態ではお酒のもつ香味がより深く味わえるでしょう。1本のお酒をじっくり楽しみたいときにおすすめです。

葛城酒造『百楽門 純米大吟醸50』

出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 御所市名柄 |
|---|---|
| 使用米 | 備前雄町 |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度数 | 16.1度 |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸度 | 1.5 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
喉ごしも、旨味も味わえる
創業1887年。葛城山系の伏流水を使い、地元の風土に根ざした酒造りをおこなっています。奈良の酒米「露葉風」「山田錦」「備前雄町」といった米が使われていますが、なかでも雄町の個性を生かした「旨口の喉ごしのよい、旨みある酒」はこの蔵の特徴のひとつとなっています。
そのこだわりが存分に表現されているといえるのがこちらのお酒。おだやかな果実のような香り、口にするとほどよく調和した旨味と酸味がなめらかに広がります。雄町で造られたお酒が好きという方におすすめ。あと味はきりっとキレがあり、飲み飽きず、お料理の中盤からメインにかけてとくに活躍しそうなお酒です。

千代酒造『櫛羅(くじら) 純米 無濾過生原酒』

出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 奈良県御所市大字櫛羅 |
|---|---|
| 使用米 | 櫛羅産山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール度数 | 17度 |
| 日本酒度 | +5~7 |
| 酸度 | 1.8 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
その土地のお米が醸しだす味わい
奈良県南西部の葛城山のふもと、「櫛羅」と呼ばれる地域に位置する酒蔵。日本酒を「米」を原料とした農産加工品ととらえ、日本酒発祥の地である奈良の風土を醸すことをめざした酒造りをしています。
さまざまな米を使って味わいの違いを生かしたラインナップの『篠峯』と、蔵のまわりの自家田で1994年から始めた自家栽培の山田錦のみを使って醸す『櫛羅』のふたつのブランドがあります。
こちらは、櫛羅シリーズの『純米 無濾過生原酒』。山田錦らしいやわらかで繊細な旨味と、無濾過生原酒らしいフレッシュさと力強さを感じながらも重くはない香りや甘味、それをひきしめる酸味が楽しめます。その地ならではのお酒を味わいたい方におすすめです。

久保本家酒造『生酛のどぶ』

出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 宇陀市大宇陀出新 |
|---|---|
| 使用米 | 五百万石、アキツキ |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール度数 | 14度 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | - |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
お燗で味わいひらく、にごり酒
江戸時代から続く歴史ある町並みが広がる大宇陀にある蔵元は、1702年の創業。酒造りを続けて300年以上という歴史があります。造るお酒はすべてが純米酒。とくに、自然の乳酸菌を生かす伝統の仕込み方法である「生もと造り」を日本酒造りの基本として、多くのお酒を造っています。
こちらはめずらしい生もと造りのにごり酒で、乳酸の生きた酸味とコクがありシンプルな辛口とは違う、深いのにかろやかさがある立体的な味わいです。冷酒~常温だと、すっきりさわやか。お燗にすると旨味、酸味、キレが増し、また違ったおいしさが楽しめます。
甘さやもたつきがなく、食事と合わせて自由ににごり酒を楽しみたい方におすすめです。

今西酒造『三諸杉 特別純米酒 山乃かみ』
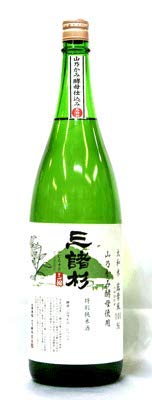
出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 桜井市大字三輪 |
|---|---|
| 使用米 | 露葉風 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | - |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
酒の神様が宿る地ならではのお酒
創業1660年。蔵元がある三輪は日本酒発祥の地とされ、三輪山をご神体に酒の神様として信仰される日本最古の神社「大神神社(おおみわじんじゃ)」があります。「三輪を飲む」をコンセプトに14代目を継ぐ若き蔵元が、ご神体「三輪山」の伏流水、地元でつくられる米を使った酒造りをしています。
奈良の酒米「露葉風」と、2012年に大神神社の神域でササユリの花から分離された奈良独自の「山乃かみ酵母」を使って造られたのがこのお酒。みずみずしく旨味のある味わいと心地よい酸でキレのあるあと味は、冷、常温、ぬる燗などで幅広く楽しめます。味わいはもちろん、奈良、そして三輪ならではのストーリーを感じられるお酒としておすすめです。

美吉野醸造『花巴 水酛 純米原酒』

出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 吉野郡吉野町 |
|---|---|
| 使用米 | 吟のさと |
| 精米歩合 | 70% |
| アルコール度数 | 17度 |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | 4.0 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
旨味と酸のみごとなコラボレーション
千本桜で知られる吉野山の山桜(花)と、広がり(巴)が「花巴」の由来。奈良吉野の豊かな発酵・保存食文化に根ざした酒造りにこだわり、原料米は地域で育まれたものを使っています。また、2017年からはすべてのお酒を「蔵付き酵母(蔵に住みついている酵母)」で醸す「酵母無添加」で造っています。米の旨味と、それに協調するようにあえて抑えない「酸」の立った個性ある味わいが魅力。
「水もと」(菩提もとの別名)で仕込まれたこのお酒は、チーズやヨーグルトのような発酵を感じる香り、甘味・旨味・酸味が一体となったなめらかで味わいがあり、くせのある発酵食品などとも好相性です。食とのペアリングをいろいろ楽しんでみたい方におすすめ。

増田酒造『神韻 純米酒 無濾過生原酒 ブルーラベル』

出典:Amazon
| 蔵の所在地 | 天理市岩屋町 |
|---|---|
| 使用米 | 吟吹雪 |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度数 | 15~16度 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.8 |
| 容量 | 720ml/1,800ml |
さわやかな酸味と旨味のバランスが絶妙
創業は1625年。杜氏の黒瀬氏は、かつてプレミア焼酎『百年の孤独』を手がけた名焼酎杜氏。そのあと、日本酒造りの経験を積み、2009年より増田酒造で製造をほぼひとりで手がけ、代々続く『都姫』に加えて、新しいブランド『神韻』を生み出しました。
いつも杜氏はBGMにジャズを流して酒造りをされているそう。焼酎杜氏経験をもつ杜氏ならではのさまざまなチャレンジや、独自の世界観のあるお酒にファンが注目しています。少量生産ゆえ見つけたときが買いどき。
ブルーのボトルとラベルの印象そのままにすっきりクリアな口あたりのこちらのお酒は、さわやかな酸味と旨味のバランスがとれた味わいで、食中酒としておすすめです。
「奈良の日本酒」のおすすめ商品の比較一覧表
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 奈良の日本酒の売れ筋をチェック
Yahoo!ショッピングでの奈良の日本酒の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
そのほかの日本酒のおすすめはこちら 【関連記事】
和酒コーディネーターのあおい有紀さんに、若い人や日本酒初心者向けの日本酒選びのポイントや初めてでも飲みやすいおすすめの日本酒を教えてもらいました。日本酒は銘柄がものすごくたくさんあるので、初心者は、どの日本酒をえらんだらいいか迷うこともあるでしょう。この記事では、日本酒の基礎知識も紹介している...
日本各地にある地酒には、その土地の風土やつくり手の思いがつまっています。以前はその土地に行かなければ買えなかった地酒も、最近はスーパーなどでも取り扱いが始まったり、ネット通販で遠方のものがかんたんに手に入れられるようになったりと、グッと身近なものになってきました。しかし、地域によってさまざまな...
唎酒師で日本酒ライターの関 友美さんへの取材をもとに、辛口の日本酒の選び方とおすすめ商品6選をご紹介します。辛口の日本酒は、世の中にたくさんありますが、米や米麹などの原料、酒蔵や醸造方法などの違いにより、どれひとつつとして同じ味わいはありません。本当であればひとつ一つ飲み比べられればいいのです...
最近は醸造技術や酵母の進化により、多様な甘口の日本酒が登場しています。とはいってもいざ選ぶとなると、香りをはじめ甘みや酸味の度合いなど、どれを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。そこでこちらの記事では、酒屋の三代目で唎酒師でもある小林健太さんに取材をし、甘口日本酒の選び方とおすすめ商品を教...
京都は日本酒の歴史上、重要な場所であり、日本三大酒神社のなかの2つ(梅宮神社、松尾神社)があります。現在も日本有数の酒どころとして全国2位の日本酒生産量を誇り、日本有数の大きな蔵元も多数存在しています。また、京料理の発展にも大きな役割を果たした名水もたくさん存在しており、食と共に発展してきた多...
国際唎酒師(ききさけし)の宇津木聡子さんにお話をうかがい、兵庫の日本酒の選び方や魅力、おすすめ商品を教えていただきました。兵庫は、昔も今も変わらぬ酒どころ。また、良質な酒米の産地でもあり、数々の銘酒を世に送り出してきました。北は日本海、南は瀬戸内海を望む広い土地をもつ兵庫では、多種多様な味わい...
料理研究家に聞いた、滋賀県の日本酒のおすすめ5選をご紹介します。琵琶湖を中心に豊かな自然が広がり、気候と水に恵まれた滋賀県。米どころでもある県内には、古くからその恵みを活かして酒造りを続けてきた酒蔵が点在し、全国に名を知られた銘酒も少なくありません。この記事では、料理研究家の松本葉子さんに、滋...
国際唎酒師の「ここがポイント」 ロマンあふれる奈良の日本酒
唎酒師・国際唎酒師、マーケティングコンサルタント
奈良には「いにしえ(過ぎ去った遠い過去の日々)」「まほろば(すばらしい場所)」といった言葉がよく使われます。長い歴史をもつ酒蔵が多いのも、日本酒発祥の地であるからこそ。
それぞれの酒蔵を知り、そのお酒を味わうにつけ、ときには日本酒の原点、ときにはそれを新しい形で表現する挑戦を、さまざまな形で感じることができます。
日本酒が生まれた土地だからこそのロマンあふれる奈良のお酒を、じっくりと楽しんでみてください。
※「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。
※商品スペックについて、メーカーや発売元のホームページなどで商品情報を確認できない場合は、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。
※マイナビおすすめナビでは常に情報の更新に努めておりますが、記事は掲載・更新時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。修正の必要に気付かれた場合は、ぜひ、記事の下「お問い合わせはこちら」からお知らせください。(制作協力:結城助助、掲載:マイナビおすすめナビ編集部)
※2020/02/07 コンテンツを追加・修正しました(マイナビおすすめナビ編集部 花島優史 )


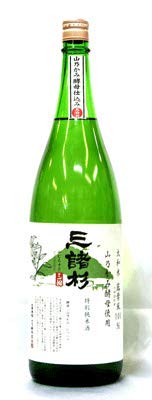
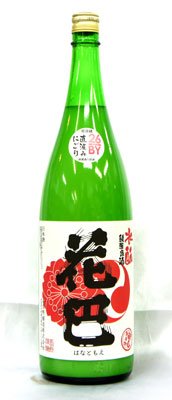





















日本の風土、知恵、歴史が生み出した日本酒の魅力や楽しみ方を、より多くの人に広めるため、訪日外国人へのプライベート日本酒体験、外国人・日本人向け日本酒にまつわるセミナーやイベントの企画を行っている。 外国人のプライベート日本酒体験では、これまでに30か国以上から300人余りをお迎えしている。 日々の生活でも、カンパイは日本酒、スキンケアは日本酒と酒粕で、そして朝晩の甘酒を欠かさない。