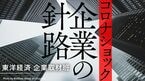塩田:かつては地方分権推進の制度改革の議論が活発でした。地方に競争力をつけるために、大きく仕組みを変えるというデザインやプランをお考えですか。
菅:都会でも地方でも豊かな生活ができるように、政府が環境整備していきますが、そこで大事なのが役所の縦割りの打破です。当たり前の政策が縦割りの壁に阻まれて実現できていないことが多い。
例えば観光で、2013年のビザを要件緩和してインバウンドを増やそうというときに、国土交通省が要望しても、警察と法務省が大反対でした。私はまとめ役として、当時の古屋圭司国家公安委員長、谷垣禎一法相と話しました。すでに安倍総理が施政方針演説で「世界の人たちを引きつける観光立国を推進する」と宣言していました。その方針に沿って、両大臣に政治判断してもらい、それに国土交通大臣と外務大臣に加わってもらって政策決定し、そこからインバウンドは一挙に拡大しました。
塩田:現状を変えて新しい方向に踏み出そうとしても、縦割り構造と省益優先の官僚機構の壁が立ちはだかるケースは、ほかにも多いのでは。
既存のダムを活用した水害対策を打った
菅:縦割りを打破するアイデアは官僚からはなかなか出てきません。例えばダムの活用ですが、きっかけとなったのは、昨年10月に東日本を襲った台風19号です。荒川と多摩川が氾濫しそうになった。もしかすると数百万人が避難することになり、そうなれば経済的にすごい影響が出る。何とかしのぎましたが、ここ数年で水害はひどくなっており、翌年までにできる対策を、秘書官を通じて探ったところ、国交省の担当部局が何十年も「できればいいな」と思ってきたアイデアが出てきました。
新たにダムを造ると、40~50年かかりますが、既存のダムでも水害対策に活用していないものがたくさんありました。ダムは全国に1470ありますが、そのうち水害対策に活用しているのは、国交省が所管する570のダムだけで、残りの900のダムは、例えば経済産業省が電力会社のダムを、農水省は農業用のダムを所管しており、こうした「利水ダム」は水害対策に利用していませんでした。もともとダムは戦前から電力ダムがいちばん大きい。最初に電力会社が造り、その後に昔の建設省(現:国交省)が水害対策用のダムを造った経緯もありました。
この話を聞いて、私は去年の11月から「やるぞ」と各省庁を集め、台風シーズンだけ国交省がすべてのダムを一元的に運用する方向で検討させた。日本はダムの問題で国交省、農水省、経産省が1つになっていなかったわけですが、全国の109の1級水系ごとに運用を一元化する計画を立て、今年6月にようやくまとまりました。これによって、電力会社に被害が発生したら国が補償する仕組みも作りました。
この結果、全国のダム容量のうち、水害対策に使えるのが30%だったのが60%まで増えることになりました。新たにどれくらいのダム容量を水害対策に使えるか、計算すると、群馬県の八ッ場ダム50個分になりました。八ッ場ダムを造るのに50年、5000億円以上かかっていますから、50個分だと、単純計算で25兆円以上が浮く計算になる。