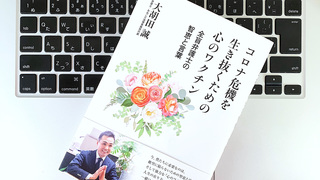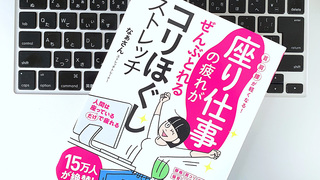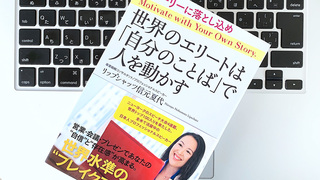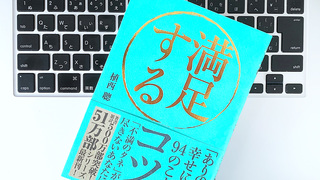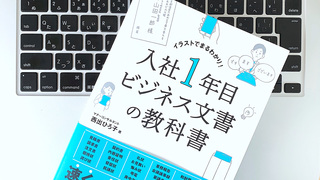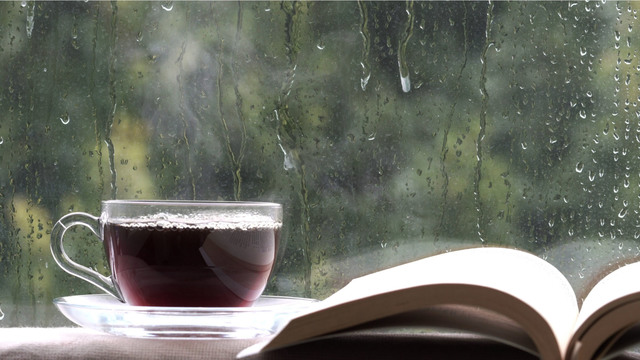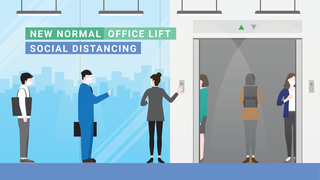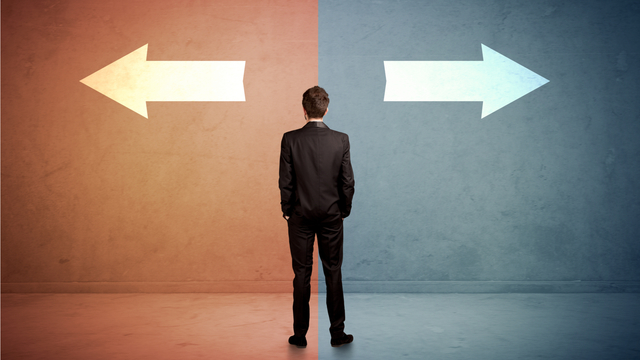『コロナ危機を生き抜くための心のワクチン - 全盲弁護士の智恵と言葉 -』(大胡田 誠 著、ワニブックス)の著者は、42歳になる全盲の弁護士。
2006年に司法試験に合格し、弁護士になって今年で13年目。第一東京弁護士会に所属している、「全盲で司法試験に合格した日本で3番目の弁護士」なのだそうです。
人は人によって傷つけられることもあるけれど、人によって癒されもする。僕は人が人によって癒される力、人が人を癒す力を信じています。
弁護士に相談に来られる人は、人によって傷つけられている人が多い。その重荷を少しでも軽くしてあげて、新たな一歩を踏み出せるようにしてあげるのが、弁護士である私の務めです。
僕は弁護士という仕事を通じて、絶望の中にいる人々の光になりたいと思っています。(「はじめに」より)
そんな思いがあるからこそ、いま気にかかっているのが現在のコロナ危機。
そこで2020年4月15日、コロナ禍によってさまざまな悩みを抱えている人が、少しでも心の重荷を軽くすることができるようにと、無料の電話相談を開設したのだといいます。
電話の向こうから聞こえてくる声はどれも切実で、新型コロナウイルスが人々の生活と心の与えている影響の大きさを日常的に感じているのだとか。
そこで本書では、新型コロナウイルス禍の世界を生き延びるため、私たちがどのように生き、なにをすべきかを著しているわけです。
コロナ禍に関連したさまざまな事例について弁護士としての立場から言及した第2章「仕事の危機を乗り越えるために」のなかから、コロナを理由に仕事を失いそうになったときの2つの対処策を抜き出してみたいと思います。
コロナを理由に退職勧奨されたら
「いまは仕事がない。新型コロナウイルスが収束(終息)したら必ず雇うから、当面の間は我慢してほしい」
もし会社からそう言われたとしたら、どうすべきなのでしょうか?
著者によれば、大切なのは、それが「離職」(会社を辞めること)なのか、それとも休業を命じているのかをはっきり確認すること。
また会社が離職について言及している場合には、「解雇」なのか「退職勧奨」されただけなのか確認することが重要。
解雇とは、雇用主からの一方的な労働契約の解約をさします。
対する退職勧奨は、労使双方の合意による労働契約の解約を目指した「雇用主からの申し込み(雇用主が従業員による申し込みを誘っている)に過ぎないもの。
つまり退職勧奨の場合、退職勧奨に応じる義務は従業員にないということです。したがって、自分から簡単に辞めると言うべきでないのです。
仮にひとりで抗しきれなかったとしたら、その場合は労働組合や弁護士に相談するといいそうです。
また同じように退職勧奨を受けている同僚がいる場合は、連携して断るという方法も。
なお退職勧奨を受け入れる場合、会社が再雇用を約束するのであれば、必ず「具体的な再雇用時の条件について念書」を作成してもらうべき。
単に「業績が回復したら」とか「再雇用に努めます」というような抽象的な文言では、再雇用を拒否されても保護されない可能性があるからです。
加えて、離職している間の生活保障などを交渉してみることも重要なポイント。
具体的には、離職票を作成してもらう際に「自己都合」ではなく、必ず「会社都合」としてもらうことが重要だというのです。
なぜなら自己都合退職としてしまうと、失業手当の支給開始日や支給日数などに違いが出るから。(84ページより)
退職勧奨に応じる義務はない 自分から簡単に辞めると言わないこと 応じる場合には、再雇用を約束する書面の作成を求めること(85ページより)
コロナを理由に派遣切りにあったら
派遣社員については、たとえば派遣期間が1年や半年などと決まっている期間の途中で「新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇する」と言われた場合、契約期間満了までの賃金を派遣元に請求することができるそうです。
有期の(期間の定めがある)派遣労働契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」契約期間中に解雇することはできないから。
ちなみにこの「やむを得ない事由」は、正社員に対する通常の解雇よりも厳格な条件だと解されているといいます。
期間の定めがない雇用契約とは違い、有期雇用契約の期間の定めは、「その期間は原則として雇用を保障する」という趣旨。つまりはよほどのことがない限り、解雇することはできないのです。
解雇するのであれば、「契約期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由」が必要になるということ。
単に「新型コロナウイルスの影響で会社の経営が厳しくなった」「人が入らなくなった」などという理由では、契約期間途中の解雇は認められないわけです。
なお、「雇用期間が契約期間満了で終了する」と言われた場合は、派遣労働契約の更新を求めて派遣元や派遣先と交渉してみるべき。
そうすれば派遣元に対し、雇用安定措置を求めることができるそうです。
いずれにしても、新型コロナウイルスの影響があるというだけで、「派遣切り」が許されていいということにはならないのです。
したがって、雇用調整助成金などの制度を利用しながら、雇用をつなぐように粘り強く交渉していくことが大切だと著者は主張しています。
派遣労働者に対しては、派遣元事業者は「雇用安定措置」を取るべき努力義務や措置義務があるそう。
だからこそ、それらを利用して交渉することが重要な意味を持つということです。(98ページより)
契約期間中に解雇された場合、 期間満了までの賃金を派遣元に請求することができる(100ページより)
現在のような状況下においては、仕事の現場においても理不尽な問題が起こりがち。
だからこそ、電話相談で耳にしたさまざまな悩みと向き合い、答えを提示した本書は役立ってくれるはずです。
あわせて読みたい
Sponsored
Photo: 印南敦史
Source: ワニブックス
印南敦史
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5