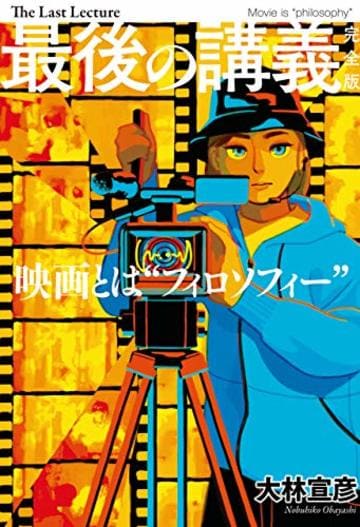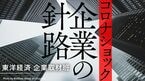大林宣彦「私が120年前の映画に学んだこと」
「最後の講義」で若者に伝えたメッセージ
戦争そのものを描いた人としては、黒澤さんたちの先生にあたる山本嘉次郎さんがいらっしゃいます。
このかたは戦争中に海軍省に命令されて『ハワイ・マレー沖海戦』という戦意高揚映画をつくられました。これは大変立派な芸術映画です。ぼくなんかは子どもの頃にその映画を観ました。
すごい映画でした。ゼロ戦が飛んでいってハワイの真珠湾を攻撃するんだけど、当然、その頃は実写のフィルムで現実の様子を記録することはできません。アメリカの記録映画には実際の映像もありますが、日本が記録として撮っていた映像は少ない。ないと言ったほうが近いくらいだと思います。
それで嘉次郎さんはどうしたか?
のちに『ゴジラ』で特撮の名匠となる円谷英二さんとミニチュアのセットを組んで、真珠湾攻撃を再現されたんです。
本当に見事なものでした。敗戦後にアメリカが真珠湾攻撃の記録映画をつくった際にもその映像が使われているくらいです。
記録映画はすべて現実の映像だと思われているのでしょうが、アメリカの記録映画には嘉次郎さんと円谷英二さんがつくった真珠湾攻撃の場面がかなり使われています。記録映画だと思っていたら、大河内傳次郎さんや藤田進さんといった当時の日本映画のスターたちが出てくるので、ぼくたちはびっくりしたくらいです。
アメリカで記録映画をつくった人たちは『ハワイ・マレー沖海戦』の映像が本当にドキュメンタリーだと思って使ったのではないかともいわれています。
現実よりも特撮がよければ映像を使うのがハリウッド
現実の映像よりも特撮のほうがいいと判断されれば、特撮の映像をドキュメンタリーとして使ってしまうのがハリウッド映画です。
『駅馬車』のジョン・フォード監督は、アメリカという国を愛している人で、自ら望んで海軍に入り、記録映画のカメラマンとして太平洋戦争に参加しました。
そのときに日本軍の攻撃に遭ってケガをして、その後は片方の目に眼帯をかけるようにもなりました。
そのジョン・フォード監督は、日本軍の砲弾が雨あられと飛んでくる中にいて、「これならハリウッドに帰ってつくればいい」と考えました。戦場の真ん中で16ミリのカメラを手持ちで構え、ガタガタ揺れながらフォーカスを合わせられずに記録を続けるよりは、スタジオに戦場を再現して、演出しながら撮ったほうがいいと判断したからです。
そのほうが実際のドキュメンタリー以上にリアルな戦争を再現できると確信できたというのは、映画人としての映画に対する信頼と誇りの表われです。
しかし、そのうちこうした映像に対する見方は変わってきました。戦場で実際に記録した映像は、たとえフォーカスがボケたり画面がグラグラ揺れたりしても、本物だからこその迫力があると考えられるようになったのです。
スタジオの中でクレーンを使って撮ったような映像は、ドキュメンタリーではなく劇映画だと見分けられるようにもなりました。今の人からすれば当たり前のことでも、この時代にはそういう経過があったのです。
戦争中に映画にかかわっていた先輩たちはドキュメンタリーと劇映画を明確に区分しようとする人も少ないくらいでした。