目次
④:戦闘では、自分の攻撃力と敵の守備力を比べる。⑤:攻撃力のほうが高い場合は、敵のカードを倒せる。⑥:敵を倒しても、守備力が敵の攻撃力より低いと自分も倒れる。
はじめに
皆さんこんにちは、しんげんです。
「遊戯王のルールにちょっと詳しくなる記事」シリーズ及び「デッキ紹介記事の書き方」シリーズ、読んで頂いた皆さんありがとうございます。
※過去記事はこちらから!
バンダイ版って?

皆さんは、遊戯王OCGの前身である、所謂「バンダイ版」をご存知でしょうか。
1999年にカードダスで発売されたカードゲームで、当時近所のトイザらスには入荷日に行列が出来ていたのが思い出深いです。
現在ではカードショップのショーケースやストレージで見かけることが出来ますね。
オフ会ではセンターマーカーやプロキシとして使用している場面もたまに見かけます。
さて、この「バンダイ版」、遊戯王OCGの前身だけあり、とても趣深いゲームなのですが、如何せんプレイ人口が少ないです。
ルールを解説しているコンテンツも少なく、また「どのカードを集めればいいのかわからない」という状態でスタートするのは少々ハードルが高いかと思います。
そこで今回は、初心者向けではありますが、バンダイ版の解説を行いたいと思います。
この記事シリーズを読み終えればバンダイ版に超詳しくなれますので、
是非友人同士で手に取って遊んで頂ければ幸いです。
この記事で解説すること
今回の記事では「カードに記載されている情報」「ゲームのルール」を解説します。
どのカードが強いのか、どのようなデッキを組めばいいのかという点に関しては次の記事での解説となります。
バンダイ版は遊戯王OCGとは異なる勝利条件が設定されており、それ故にカードの強弱もルールによって左右されているため、まずはルール(勝利条件)を覚えることが必須になってきます。
カードの見方
さて、バンダイ版のカードを見たことがある方はご存知だとは思いますが、
カードに記載されている情報がOCGとは若干異なります。
モンスターカード

一番の違いは、テキスト欄に「ルール」が記載されていることですね。
カードダスのみでの販売でスターターセット等はなかったので、当然といえば当然でしょうか。
また、カードの中にはルールではなく固有の効果が記載されているモンスターも存在します。
例えば、《-海月-ジェリー・フィッシュ》などはその一枚です。
原作では梶木漁太が使用し、遊戯を苦しめた印象深い(?)カードですね。

雷属性のモンスターには負けない。と記載されています。はて、

属性……?????
考察を始めた当初、ぼくたちは一つの山を二分割して遊んでいたのですが、 《-海月-ジェリー・フィッシュ》 を場に出して「属性どこだよ!!」と笑いあった覚えがあります。
しかし、カードをよく見てみると「属性」も設定されているのがわかります。

カードごとに背景が使いまわされていますよね。
バンダイ版ではこの「背景」が、属性を表していると思われます。

光属性:背景が光っている

闇属性:背景が闇っぽい

地属性:背景が土っぽい

炎属性:背景が炎っぽい
ただし《メタル・ガーディアン》《ガルーザス》のようなカードも同じ背景なので、やっぱり使い回しじゃないか炎属性ではない別の属性の可能性もあります。

雷属性:背景が雷っぽい
ちなみに2019年6月現在、属性を参照するカードは 《-海月-ジェリー・フィッシュ》 のみですので、
「ジェリーフィッシュに負ける」という点でデメリットを持つ唯一の属性となります。

水属性:背景が海っぽい

森属性(?):背景が森
なんでしょうねこれ。森属性?
言われてみると虫とか《きのこマン》とかいるのですが、
《カタパルト・タートル》や《キマイラ》などもこの背景(属性)となっています。
人物カード

皆さんご存知、海馬のカードです。
モンスターカードと違い攻撃力/守備力の記載はありませんが、
特殊能力にて勝敗が決定します。
魔法・罠カード
バンダイ版の「魔法」「罠」の区分に意味はなく、どちらも戦闘中いつでも使うことが出来ます。


「攻撃してきた敵を捕獲し」
雲行きが怪しくなってきましたね。
ゲームの基本ルール
カードに記載されているルールは13種類あります。まずは、基本となる9種類のルールを見ていきましょう。
①:友達と同じ枚数のカードを用意し山札にする。
このゲームでは山札の枚数が定められていません。
そのため、CS・オフ会では事前にデッキ枚数を設定しておくのが基本となっています。
個人的なオススメは25~30枚程度です。
どうしても単調な殴り合いになるので、40枚は普通に飽きます。
逆に少なすぎるとエクゾディアが秒で揃います。
②:自分の山札の上から5枚を引いて、手札にする。
用意した山札をシャッフルするかはルールで設定されていないので、
対戦相手と話し合って決めましょう。
③:手札の中から1枚を選び、同時に出して戦闘開始。
同時にとありますが、一度伏せて場に出し、
魔法・罠を伏せる時間(後述)を設けるとそれっぽくゲームが進みます。
④:戦闘では、自分の攻撃力と敵の守備力を比べる。
⑤:攻撃力のほうが高い場合は、敵のカードを倒せる。
⑥:敵を倒しても、守備力が敵の攻撃力より低いと自分も倒れる。
遊戯王OCGと異なり、お互いの攻撃力と守備力を比較します。
⑦:戦闘終了後、山札からカードを1枚引き手札に加える。
⑧:お互いの山札がなくなるまで毎回これを繰り返す
ドロー出来なくなったら負けではなく、お互いの山札が0枚になった時点でゲーム終了です。
⑨:最後に倒したカードの星の数を合計し、多いほうの勝ち。
最後に、お互いに倒したカードの星(レベル)の数を比較し、多い方の勝ちとなります。
普通に遊ぶ場合は、遊戯王OCGで用いるライフカウンターを使用し、
倒されたモンスターのレベル分ライフを減らしていくとゲームがスムーズに進行します。
ゲームのサブルール
⑩:魔法や罠、装備カードが手札のなかにある場合、場に伏せて置くことができる。
⑪:場に伏せた魔法、罠、装備カードは戦闘中いつでも使うことができる。
⑫:一度使った魔法、罠、装備カードは捨て札になる。
⑬:一方が先に山札がなくなっても、もう一方の山札もなくなるまでゲームは続行される。
サブルールとしてこれらのルールが設定されています。
魔法・罠カードですが、《サイクロン》や《ハーピィの羽根箒》のようなカードは存在しないのでガンガン伏せましょう。
また、ステップの概念は無いので、お互いに発動するカードがないことを確認してから戦闘を行いましょう。
バンダイ版の本質
次回の記事でモンスターについて詳しく取り上げますが、バンダイ版の実戦的なモンスターカードは攻撃力>守備力であることが多いため、戦闘は相打ちが基本となります。
そして、勝敗を決するのは「倒したカードの星の数の合計」であり、言い換えれば「倒されたカードの星の数が少ない方の勝ち」となります。
つまり、「星の少ないモンスターで星の多いモンスターとの相打ちを狙っていく」「相手のデッキタイプから、採用されているモンスターの性質を推測し、有利なカードをぶつけていく」ことがバンダイ版の本質となります。
「あれ?もしかしてちょっと面白いんじゃないか?」と感じてきませんか?
その調子です。
次回予告
基本的なルールは以上になります。
次回は、モンスターの採用基準になる「2600ライン」や「2400ライン」、
「本田シルクハット」などの定番テクニックを解説していきます。お楽しみに!
ところで、記事の途中で触れたように、バンダイ版にもエクゾディアは存在します。

そして、バンダイ版はお互いの山札がなくなるまでゲームは終わりません。
つまり、途中でどちらかがエクゾディアを揃えない限りお互いにデッキを全て引くことになります。
途中で。
どちらかが。
エクゾディアを揃えない限り。
お楽しみに!



















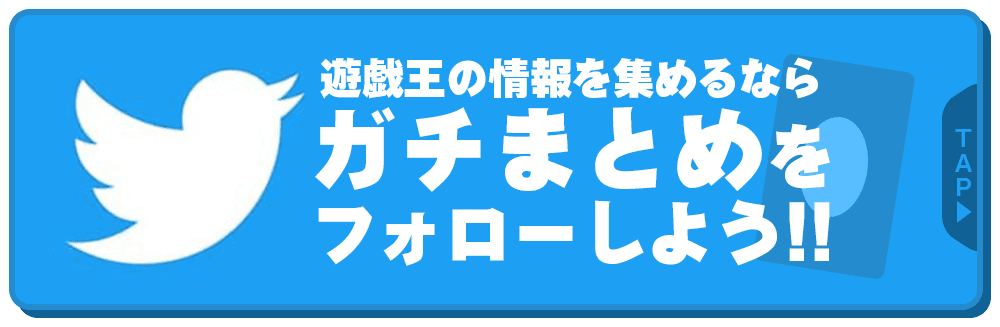
コメント (0)