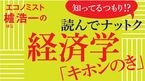コロナ休校でも動じにくい家族の「うまい発想」
非常時にこそ問われる、育児シェアの態勢
石川さんの話を伺って面白いなあと思ったのは、彼が、拡張家族以外にもいろんな形の「シェア」を経験してきたということ。
沖縄での「社会全体で子どもを育てるシェア」、ドイツでの「友人家族との生活シェア」、そして、東京での「意識でつながる家族との生活シェア」です。
もともと夫婦共に長期育休をとって実家近くに戻り、両親や夫婦間でしっかり育児シェアをしたうえで、さらに他人ともいろんな形で育児をシェアして、育児の負担を減らしているのです。
ちなみに、夫が1年&妻が2年という育休期間は、欧州在住の夫婦も多く紹介してきたこの連載でも最長の期間。実は、日本の育休制度はかなり恵まれているのですが(詳細はこちら)、それをちゃんと活用していてすばらしいなあ、日本も変わってきているなあ!と感じました。
コロナによる休校で本領発揮のCift
ところで今、急遽決まったコロナによる休校では、多くの子育て家庭がパニックになっています。いちばん大変なのは小学校低学年などの子の預け先の確保ですが、多くの大人が暮らしている拡張家族Ciftでは、誰かが子どもを見てくれるときもあるため、親の負担は一般家庭よりは少なく済んでいるようです。まさに、こうした緊急時に、本領が発揮されているわけです。
預け先、という点だけではありません。休校の通達と同時に、新しいプロジェクトもスタートしました。
これは「◯◯(お子さんの名前)の学校」というネーミングで、できる人だけが、できる時に、月に一回、メンバーの小学校低学年のお子さんと遊ぶというもの。たとえば、畑作業を教える、お絵描きを教える、はじめの包丁を教えるなどです。
学校が休みになってしまい、子どもの学習面が気になる親は多いですが、こうした仕組みなら親子とも前向きな気持ちで過ごしやすくなります。これも、家族としての人数が多く、多種多様な職業の人が集まるこのコミュニティだからこそできることです。
私が今回の休校パニックで強く思ったのは、もともとの生活で育児シェアの態勢が築けていない家庭は、さらにピンチに追いこまれているかもしれないということ。普段ギリギリでまわしている家庭には、今回のような緊急事態はハードルが高すぎるのです。
ただ、今回のコロナは例外的とはいえ、もともと育児というのは緊急事態が起こりがち。そういう意味でも、ご近所との連携など「自分にあった形の育児シェア」を取り入れていく大事さをあらためて強く感じたのでした。
というわけで、今回学んだつかれない家族になるヒントは……
↓
本当におつかれさまです!!
今後また緊急事態があったときのためにも、
家族内、外部も含めた育児シェア体制をあらためて構築していこう
次回は、別のCiftメンバーの話です。ワンオペ育児を、拡張家族との暮らしによって解決したその暮らしとは?