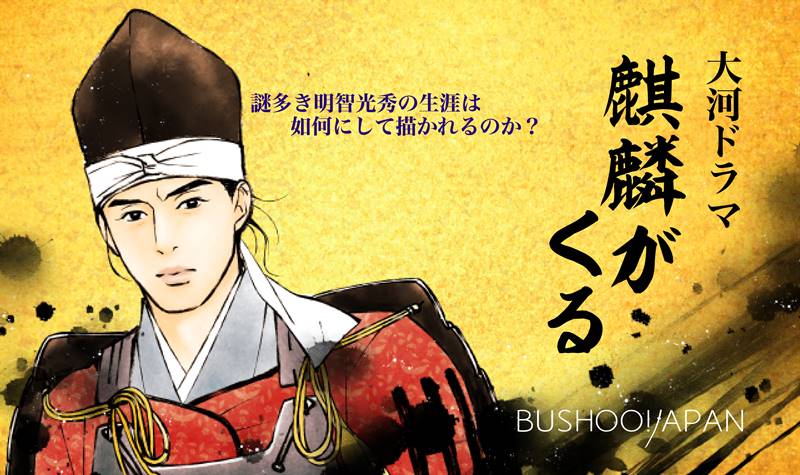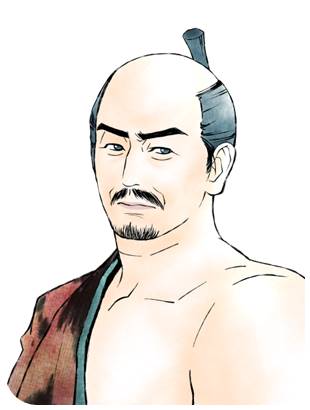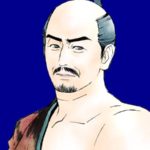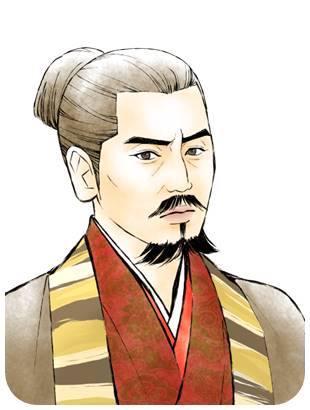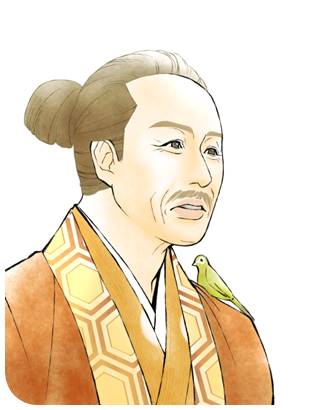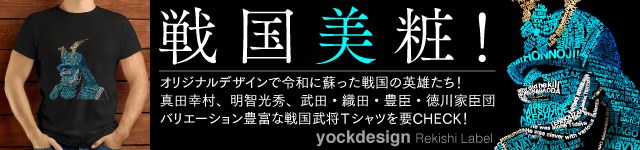◆麒麟がくる第7回 感想あらすじレビュー~視聴率は3/2に発表です
天文17年(1548年)――。
大垣城は、斎藤利政(斎藤道三)が奪還しました。といっても、これは彼が強いだけの話でもありません。
最大の敗因は、清洲城の織田彦五郎が、織田信秀の古渡城を攻めたためでした。
-

-
織田彦五郎(織田信友)――信長&信光に追い込まれた尾張守護代の末路とは
続きを見る
敵を知り己を知れば百戦殆うからず――利政は織田一族の内紛を掴み、攻めたのでしょう。
こうなると、信秀は抜本的な改革を迫られます。
お好きな項目に飛べる目次 [とじる]
お好きな項目に飛べる目次
美濃と手を結ぶ
平手政秀を前にして、織田信秀は目下の勢力を語る。
本作はセリフが細かく、難易度を下げているとは思えます。そういう同盟関係を無視して、主人公がおにぎりやウナギを食べてはしゃいでおりますと、難易度が下がるようで実は上がるわけです。情勢そのものをろくに描かないのであれば、見る側もそこに気づかない。
織田信秀の敵とは?
まことにもって、厄介な状況になりました。同族の敵は、なまじ接触機会もありますし、手の内を知っているだけに面倒なものがあります。こういうときは優先順位をつけなければなりません。
将来、信秀の嫡男・織田信長は「織田包囲網」というもっと厳しい状況に直面します。ここは予習のつもりだと考えておきましょう。
-

-
織田信長49年の生涯まとめ!生誕から本能寺の謎まで史実解説【年表付】
続きを見る
信秀には疑念がある。
「守護代とはいえ、同じ織田の一族。何故、いちいちわしのやることに横槍を入れてくる?」
そう信秀は政秀に問いかけます。答えをわかっている気配はあります。
「はっきり申せば、殿への嫉妬……」
交易の拠点たる、津島、熱田を手にしている。リッチな尾張マネーは信秀にジャブジャブ入ってくる。金もある。力もある。戦も、お強い。
-

-
織田信秀(信長の父)は経済重視の似た者親子!? 道三や義元相手に大暴れ
続きを見る
そのような縁者なぞ、蹴躓いて死んでしまえくらい思うもの――。
政秀よ、これも予習ですか?
身内に優秀なものがいるとなまじ敵対感情が渦巻くものではあります。
信秀は、満足しております。
白雪姫の継母が鏡に一番の美女が誰か問いかけるような、そんな心理が感じられます。
信秀は、次の議題に移ります。
今川義元がもっと手強い。そこは政秀も「まことにもって」と理解を示します。
続けて、息切れが酷くなったと打ち明る信秀。戦のたびに、体の中で、何かが泥のように崩れ落ちてゆく――。
現代医学はさておきまして、漢方ですと【陽】の熱気がこもっている状態です。
そういえば、信秀は瓜を食べておりました。瓜は水分も豊富ですが、漢方医学では【隠】の食材です。つまり、熱気がこもっている時に食べるとよいもの。夏野菜にはこのような役割がある。旬の食材を旬に食べることには、漢方医学的にも意味があります。
そしてここも重要です。
くどいようですが、陰陽に善悪はありません。均衡が崩れることそのものが悪。陽が優勢になりすぎた信秀の、残された日々は短いのです。
彼自身も、その自覚はある。二つの敵であれば、両手でどうにかなる。しかし、三つは手に余る。そう笑い飛ばします。
これも大事なこと。人体の構造を考えると、手足はじめ二つ揃っているものは多いものの、三以上は少ない。【三】という数字には、無限に繋がる最小のものという意味が生じて来ます。
鼎立とは、三本足の鼎の状態を指します。こうなると、なかなか手強いことになります。
そこで、とりあえず三を二にすることを考えたのです。
「そこでじゃ、わしは美濃の蝮と手を結ぼうち思う」
斎藤利政との同盟です。
織田彦五郎と今川義元。この二つと五分に戦うためには、美濃を味方につける他あるまい。そう語るわけです。
なぜ、美濃なのか?
その条件が、ここから明かされてゆきます。
明智荘で十兵衛を待っていたのは
明智荘では、牧と明智光安が囲碁をしておりました。
もう三度目といいつつ、なかなか終わらない様子。
こういうところが細かい。双六ではなく、将棋でもなく、陰陽のような白と黒の囲碁なのです。
光安は、牧殿の整え方は亡き兄上に似ておると感心しております。守りと攻めが一体となっているのです。
牧は、夫にはよく鍛えられたと言います。拙い、拙い。そう言われたのだと。
わしもそうであった、と光安。
小さな何気ない会話のようですが、牧の夫であり、光秀の父のこともわかります。
おなごにはわかるまい、そう見下すような人物ではなかったということです。この要素は、光秀にも引き継がれているのでしょう。攻めと守りが一体になるところも。
それから光安は「先日申した帰蝶様の件」が実に難しいとこぼしております。殿から、それについてどう思うかといきなりご下問があり、光安は答えに窮してしまったとか。
そこで、近習が知らせを持って来ます。
稲葉山城から、十兵衛様が戻ったと知らせがあったとのこと。自宅よりもまずは城に報告するのです。明日昼前には、お帰りになる由――そう聞かされ、安堵感がそこにはあります。
それにしても、囲碁だなんて。
それだけでも面倒な考証が出てくるでしょうに、本当に小さなところまで手を抜かない仕事をしております。今日も盤石ですな。
明智荘に、十兵衛光秀が戻りました。まずは木助、そして牧が出迎えます。
「母上。母上! ただいま帰りました」
「お帰りなさい」
出迎えの場面ですが、台所で食事の支度をしているとわかるところとか。牧の凛とした佇まいとか。お見事です。
ここで、光秀について来た駒が、肩の傷が塞がったことを確認。薬を根気よく塗るよう、指示を出します。
駒を演じる門脇麦さんも語っておりましたが、当時の医学知識は現代と比べると拙いもの。東西問わずそういうものではありますし、それこそ北里柴三郎あたりまで、医学がかえって人を殺すようなこともあったものです。そこは念頭においておくと良さそうです。
-

-
東大とバトルし女性関係も激しかった北里柴三郎~熱血肥後もっこすの78年
続きを見る
牧はこぼします。
「こんなに傷を負っているのなら、教えてくれればいいのに」
便りを遣さない我が子に、そう愚痴を言う。
光秀は逆に心配されるとつっぱねます。母として、遠くにいて何もできないのだから、せめて心配くらいさせてくれと牧は訴えるのでした。
「そういうものですかね」
「そういうものですよ」
そうですね、普通の母子はそうです。
これも予習ですかね。信秀の嫡男・信長くんと、土田御前はこういうあたたかい、普通の交流ができない可能性が高い……きっとあの母子は、母だけでなくて子の側にも問題があるのでしょう。
-

-
ナゾ多き信長の母・土田御前に迫る~信長の死後は?そもそも生まれは?
続きを見る
そう、どでかい問題が。気高い母の心をぶっ壊すような、いろんなことが。
土田御前は、キャストビジュアルの時点で顔が疲れておりますから。
帰蝶の訪問
常がここで、帰蝶様がお戻りになられたと告げに来るのです。
これには光秀も驚きつつ、出迎えます。用件を聞くと、この近くに鶴の群れが来るから、せっかくだから伯母上の顔を見たくて来たと答えるのです。
しかし、光秀は鶴が来るのはもっと遠く、こんなところで寄り道していては城に戻れないと、答える。生真面目です。
帰蝶はうれしそうではあります。いつ戻られたのかと聞いてくる。先程こちらにと答えられると、こう返すのです。
「稲葉山城に戻ったのならば挨拶に参ってもよかろう、素通りとは他人行儀じゃな」
そう拗ねたように言う。ここで光秀は、着いたのは夜分だと答えるのです。
光秀は、女心がわからないとかなんとか言われますけどね。
それの何が悪いのでしょうか?
自分が女心にデレデレするとか、胸キュンキュンしたいからとか、そんな情ではかってどうしますか。それをやりすぎると、セクハラ全開になる。そこはもっと考えねばならないでしょう。
これ以上書くと、嫌味ったらしいので最低限に留めますが。先週の感想が「ほっこりきゅんきゅん」塗れで、甚だ遺憾だとは思いました。内心の自由は誰にでもあります。しかし、こうも高度かつ長尺の歴史物なのですから、そういうことばかり期待しては勿体ない。
そういう話は、2015年で終わりにしたいものです。そんなことばかり言っていると、またあの「俺ら松下村メン!」が来襲しますよ、それでいいんですか……。
ここで、帰蝶と気が合っている駒が、奥の間に来ていることも語られます。
「あがってよいか?」
帰蝶はうれしそうです。蝮の娘ですし、性格も父譲り、これについては後述します。
-

-
帰蝶(濃姫)信長の妻はどんな人だった?『麒麟がくる』で川口春奈さん熱演
続きを見る
けれども、彼女は素直で純粋な女性だということは、考えていきましょう。
あの帰蝶様が本気で鶴が見たいと思うか?
光秀は、叔父上の元へ迎えと促されています。
帰蝶は「あ・し!」と駒に見せる。リスを捕まえようとして木に登り怪我をして、手当てをしてもらった。そなたの薬で、綺麗に治ったのじゃと説明します。
帰蝶はやっぱり素直。でも、そのお礼の言い方が唐突ではある。代役だからどうこう言われておりますが、この飾らないところを川口春奈さんはよく掴んでいると思います。
一方、光安は悩ましい問いかけをします。
◆考えてみよ、光秀よ!
【あの帰蝶様が本気で鶴が見たいと思うか?】
→光秀、素直なのでわかってない。
【城で殿から話はなかったのか?】
→取り込み中だから、近習に挨拶だけして帰って来たとのこと。
どうにもじれったい、そんな光安。光秀は女心だけではなく、ちょっと愛すべき鈍感さがあるのです。
光秀の造形は難解です。
寺では秀才だったとわかりますし、言動の端々から知性はあるのですが、ちょっと抜けているようなところもある。それは生真面目すぎるからなのでしょう。
光安は光秀を手招きし、こう語ります。尾張の織田信秀が殿の元に書を遣し、和議を致したいと申し入れて来たのだと。
もう美濃との戦はせぬ。仲良くしよう。まぁ、そういう話じゃ。そう語り、状況を説明します。
ここで、今川義元が隙あらばと槍を研いでいると語られるのがいいですね。蹴鞠ばかりをしているわけではないのです。義元はまだ一瞬しか出番がないとはいえ、正攻法が強い、英雄の中の英雄らしさは感じます。
『三国志』ならば袁紹あたりかな。途中で負けただけに過小評価されますが、知勇兼備の英雄です。
-

-
今川義元はなぜ海道一の弓取りと呼ばれたか?42年の生涯をスッキリ解説
続きを見る
殿は、和議に同意した。しかし、条件がついて来た。
そう光安は言います。
口約束では心もとない。納得いく証が欲しい。帰蝶様を嫁にくれと。信秀には若い嫡男がいる。その嫁にいただきたい。
その話を告げたところ、帰蝶は即座に口もきいてくれなくなった。帰蝶の伯父としてどう思うか? 利政にそう聞かれたのです。
「どうもこうも、なあ?」
鳥に餌をあげて、アニマルセラピーをする光安。
光秀はいとこであり、幼い頃から親しい間柄。そう叔父上は漏らすのです。
「そなたの館においでになったのも、そういうこともあるのであろう。鶴など言い訳じゃ。そなたの口から、帰蝶様のお気持ちを聞いてみてはくれぬか?」
「はぁ?」
光秀、ものすごく困惑している。
これは光秀本人も理解できない、彼の持つ力。演じる長谷川博己さんも、いろいろ思い悩む、そんな力なのでしょう。
どうしてこんな無理難題をふっかけられるの? そう視聴者も思うでしょうし、今週も「RPGかよ……」というツッコミはあるでしょうけれども。光秀の底力であり、おそろしいところであり、不幸なところかもしれません。
幼い頃から持つ光秀の本質
「さぁ二つが三つになります。お立ち会い!」
駒はお手玉を披露しています。伝吾や子どもたち、そして帰蝶も見ている、そんな芸です。旅芸人一座時代に覚えたんですかね。
そこへ光秀が、浮かない顔でやって来ます。駒になついた子どもたちにも、お手玉を中で教えると誘導されています。
光秀は、帰蝶に告げます。
「帰蝶様、少し話が。お座りください」
「浅ましき話ならここで聞く。おもしろき話なら、座ってもよい」
そう強がる帰蝶に、思わず「ふっ」と笑ってしまう光秀。帰蝶は単刀直入に切り出します。
「叔父上とどういう話をしたのじゃ。私を嫁に行かせる話か」
帰蝶は苦しい胸の内を語ります。一度目は何もわからず、父上の教えに従うた。それで私がどういう目に遭うたか、わかっておろう。
そう語ってしまう。
けれども、考えてみてください。そういう気持ちがあるのならば、どうして父に訴えなかったのか?
帰蝶は、対話すら閉ざしてしまった。今ここで、光秀にその心のうちを打ち明けてしまう。なぜなら……。
※続きは【次のページへ】をclick!