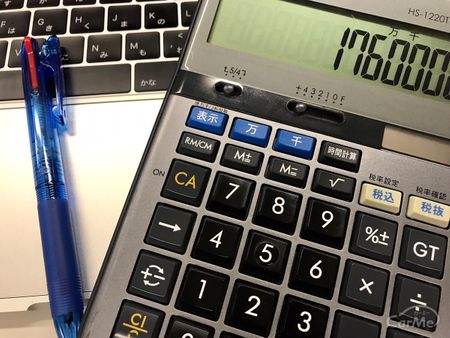除雪車を運転するのに必要な免許は?
10年ぶりの大寒波に見舞われた2018年2月。全国から2mを超える積雪が報告されています。そこで大活躍しているのが、自治体やそこからの依頼を受けた業者の除雪機器(除雪車)です。そのなかには、積もった雪を掻き分けて除雪をするものや、集めた雪を飛ばすものなど、さまざまなタイプがあります。これら除雪車を運転するには、どのような免許を所持していればいいのでしょうか?
- Chapter
- 除雪車を運転するには?
- 各種除雪車に求められる除雪機械運転員資格基準
除雪車を運転するには?

まず公道で除雪作業を行うには、国土交通省が定める「除雪機械運転員資格基準」をクリアしている必要があります。大前提として、除雪車が該当する運転免許を所持していること。さらに除雪機の種類によっては、免許取得に関し運転経験が求められます。また、技能講習(車両による)、除雪講習を受講していること。これらすべてをクリアできなければ、除雪車を使用した除雪作業はできません。
そして、公道・私有地問わず、実際に除雪作業にあたるには、一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)が開催する道路除雪講習を受講する必要もあります。有効期間は5年です。
こちらは公道での除雪作業のみならず、自宅敷地内で使用する小型除雪車やハンドガイド式小型除雪機にも受講が求められます。毎年10月頃に開催されるので、必要な方は、夏頃からJCMA公式サイトをチェックしましょう。
では、各種除雪車に求められる除雪機械運転員資格基準をそれぞれみていきましょう。
各種除雪車に求められる除雪機械運転員資格基準
ひと口に除雪車と言っても、除雪トラック、ロータリー除雪車、除雪グレーダ、除雪ドーザおよびトラクタショベル、小型除雪車などの種類があります。
国土交通省では、それぞれの除雪機械に対して、免許と講習受講義務を課しています。(凍結防止剤散布車も3種類ありますが、本稿では触れません)
6種類の除雪機に必要な除雪機械運転員資格基準を詳しく見て行きましょう。
その①:除雪トラック
除雪トラックとは、車体前方にプラウと呼ばれる樹脂やゴム製の除雪用ディフレクタを装着したトラックです。
この車両を運転するには、大型免許が必要で、大型自動車の運転経験が1年以上求められます。
その②:除雪グレーダ
除雪グレーダとは、ホイールベース内に除雪や水掃きが出来る大型ブレードを装着した車両です。道路工事でも、砂利をならすために活躍している姿を見ることがありますね。
運転するには、大型特殊免許(装輪式)が必要で、装輪式大型特殊自動車の運転経験が2年以上求められます。加えて建設機械施工技士(3種)または技能講習修了も必須です。建設機械施工技士は、建設業法第27条第1項に基づく国家試験です。
その③:除雪ドーザ・除雪トラクタショベル(装輪式)
それぞれ建設機械のブルドーザ・トラクタショベルを、除雪用にアレンジした重機です。免許は大型特殊免許(装輪式)、装輪式大型特殊自動車の運転経験が1年以上必要です。さらに建設機械施工技士(1種)または技能講習修了も必須です。
その④:大型ロータリー除雪車
ロータリー除雪車とは、回転しながら雪を巻き上げ側方に飛ばして除雪を行う機器を搭載した除雪車です。必要な免許は大型特殊免許(装輪式)で、装輪式大型特殊自動車の運転経験が2年以上求められます。
その⑤:小型ロータリ除雪車(小型除雪車)
除雪機能的にはロータリ除雪機ですが、車体サイズはミニマム。私有地の除雪に適したサイズです。必要な免許は小型特殊免許で、普通車または軽自動車の運転経験が2年以上必要です。
ただし小型ロータリ除雪車であっても出力が50ps以上であれば、大型特殊自動車に該当し、上記除雪機械運転員資格基準が求められます。
その⑥:小型除雪機(ハンドガイド式)

小型除雪車には運転席がありますが、それも取り払って小型化した除雪機です。使用者はハンドガイドと呼ばれれるバイクのハンドルに類似した部品を持ち、歩行しながら除雪します。
運転免許は必要ありませんが、小型特殊運転免許相当以上の経験年数が1年以上必要です。