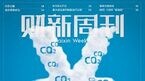「ひきこもり」の9割が外出できるという真実
もっと大変な問題は別のところにある
社会学者の関水徹平さん。家族以外に頼れるところがない「家族の孤立」が、ひきこもり問題や日本社会の息苦しさにつながっているという(写真:不登校新聞)
ひきこもりをめぐる問題とはなんなのか。ひきこもりの研究を続ける社会学者・関水徹平さんに執筆いただいた。関水さんは今号と次号で掲載予定。
ひきこもりの人や経験者は400万人以上
学校では、先生や同級生との人間関係に気をつかうし、いじめも普通にある。仕事も、自分に合う職場に巡り合えるとは限らない。そこでも人間関係はついてまわる。
今の日本社会で生きていたら、学校へ行きづらくなったり、仕事へ行きづらくなったりすることは、いくらでもあると思う。
人よりも繊細だったり、曲げられない主張を持っていたりしたら、なおさらだろう。
内閣府の調査によれば、ひきこもり状態の人は15歳から64歳の年齢層で、推計100万人以上いる。さらに、その3倍ほどの人たちが、過去にひきこもり状態を経験している。
現にひきこもり状態にある人、過去にひきこもった経験のある人は、合わせて400万人以上いるという計算になる。
とはいえ、そのほとんど(9割)は、自宅や部屋に閉じこもっているわけではなくて、趣味の用事やコンビニには出かけるという。
また、過去にひきこもり状態を経験した人たちも、その多くは、家の外とつながるきっかけをつかんでいるようだ。
トピックボードAD
ライフの人気記事