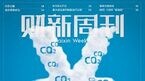日本でiPhoneの売り上げが「不振」に陥ったワケ
新型コロナウイルスがアップルに与える影響
アップルはアメリカ時間1月27日、2020年第1四半期決算(2019年10〜12月)を発表した。iPhone不振で始まった2019年を振り払うような決算だった。
売上高は918億1900万ドルで前年同期比8.9%増、税引き後の1株当たりの利益は4.99ドルで、いずれも過去最高を記録した。低迷していたiPhoneが、新モデルによってペースを取り戻し、売上高は前年同期比で8%増の559億5700万ドル。
またウェアラブル・ホーム・アクセサリー部門は前年同期比37%増の100億100万ドルとなり、Mac、iPadを大きく上回る、製品として第2の売上高を誇る部門へと成長した。サービス部門も引き続き16.9%の高成長を維持し、127億1500万ドルを売り上げた。
ただし、日本での売上高は前年同期比で約10%減となった。もともとiPhone販売比率も高かったはずの日本で、アップルが不振に陥った理由は、総務省による電気通信事業法の改正にあった。
復活を遂げた「iPhone」
ちょうど1年前、2019年1月にアップルは株主に対して「利益警告」を出した。四半期ごとに予測される売上高をガイダンスとして示すが、これを大きく下回る業績が予想されることが原因だった。これを受けてアップルの株価は142ドルまで下落し、アメリカ企業初の時価総額1兆ドルを半年前に記録したのが嘘のような状況に陥った。
しかしその後、アップルは2019年第3四半期(4〜6月)から、回復の兆しを見せた。Mac、iPadのテコ入れと、ウェアラブル、サービス部門の急成長が持続したことが奏功した。そして2019年9月、iPhone 11、iPhone 11 Proシリーズを発売。
iPhone 11 ProではiPhoneとして初めての3つのカメラを備え、バッテリーとディスプレーを強化する順当な機能進化を遂げた。一方iPhone 11にも2つのカメラを用意し、プロセッサーは上位モデルと共通化しながら価格を引き下げ、より買いやすくした。この価格戦略から、iPhone 11の売り上げは好調で、採用されているA13 Bionicチップの増産も報じられた。