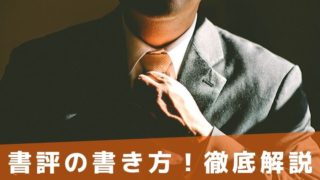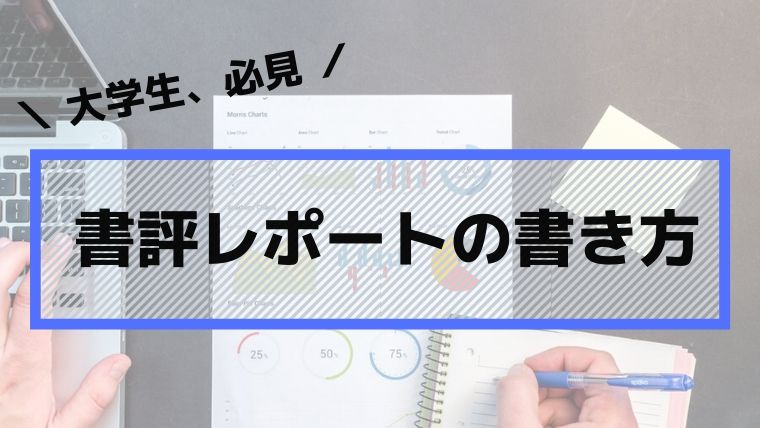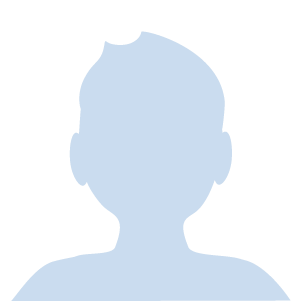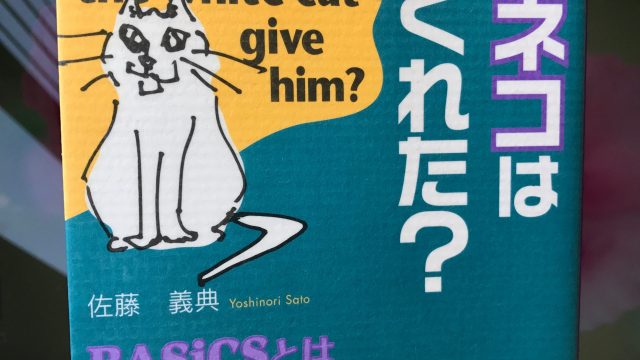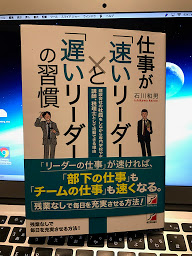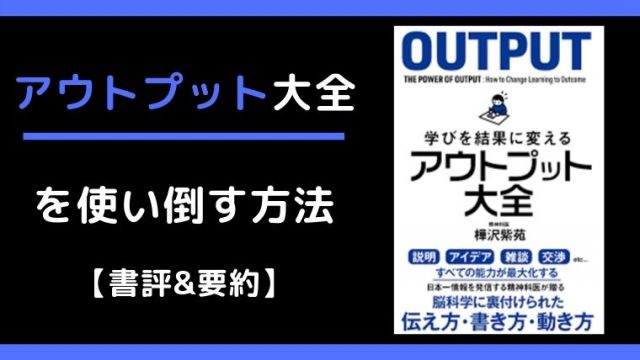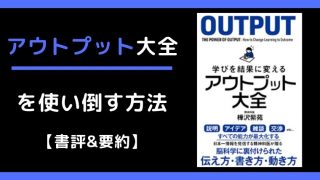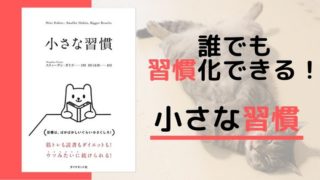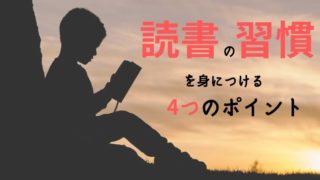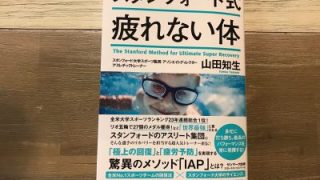書評レポートの書き方を知りたい人
大学で書評の課題が出た人
書評レポートの例を読みたい人
大学などの課題で書評を書く機会があるかと思います。
しかし、普段から書評を書いている人は稀ですし、小学校や中学校などでは「書評レポートの書き方」を学ぶことはありません。
本記事では、今まで書評を170記事以上執筆してきた私が書評レポートの書き方を解説します。
あくまで書き方の解説であり、そのままコピペして利用できるものではありませんのでご注意ください。
この記事の目次 [ひらく]
書評レポートとは
書評レポートと聞いてもピンと来ない人も多いかと思います。
書評レポートを簡単に言うと「読書感想文」です。
もちろん読書感想文とは違い、1冊〜数冊の本を読んだうえで、論評する必要がありますが基本的な考え方は同じです。
本を読んで何を感じ考えたか、それはなぜか
これを論理的に書けば問題ありません。
そんな人も安心してください。構成さえしっかりしていれば、論理的な文章は誰でも書けます。
書評レポートの構成と例
1、導入
2、本の紹介
3、論評
それぞれ詳しく解説していきます。
導入の書き方
導入部分で書くことは以下の4点です。
枕となる言葉(共感)
本の概要や背景の紹介
論評の結論
「その根拠を証明します」
あとは文章に肉付けを行うのみです。
実際に大学生が書いた書評レポートの例を見てみましょう。
サブタイトルとなっている『なぜ社員同士で協力できないのか』という疑問というか嘆きのようなものを感じている人は、近年少なくないのではないだろうか。
本書は全6章で構成されており、第一章ではいくつかの例をあげながら、最近の職場で見られる人間関係の状況について、またそれに伴う問題点について、社員のモチベーションの低下、疲弊、さらには生産性や創造性の低下、品質問題や不正の発生にまで関わる深刻な問題として取り上げられている。
〜一部割愛〜
そして最終章では、「協力の問題は単に個人の問題ではなく、組織の問題であり、社会の問題でもある。」と筆者は強調していた。
筆者が何度も繰り返しているように、人間関係という問題は、短期間で、たった一つの確実な方法で解決させることができるということはないと私も思う。
しかし、個人が改善させる意思を持ち、会社側もそのような環境づくりをしようという行動を起こすことで少しずつ協力関係を築くことができるのではないかと感じた。
引用元:高橋+河合+永田+渡部[2008]『不機嫌な職場』講談社現代新書。
この書評レポートの導入は非常にきれいでオーソドックスです。
自身がない方はこの文章をテンプレートとして、自身の書評する本に置き換えると良いでしょう。
本の紹介と内容の深掘り
書籍の構成にしたがって内容を紹介していきます。
本の紹介部分で書くことは以下の1点です
章ごとの要約
レポートによって指定の文字数が変わると思います。このパートは重要部分ではないので、不要箇所や不要な章は割愛しても問題ありません。
以下、書評レポートにおける本の紹介例です。
第一章では二十代のモチベーションについて書かれている。この年代は経験が浅い分、仕事よりも周り、つまり人間関係や環境によって大きく左右されるのである。
とくに上司との人間関係が築けないのは、若い社員にとって足元が崩れるような思いになると著者も言っている。
これは当然仕事にも影響する。こういったことを防ぐためにもモチベーションの維持・向上が必要だろう。若い社員は上司に褒めてもらうと、より認めてもらいたいという強い意欲が喚起される。これによってモチベーションが上がる。
しかし、褒めてもらうには結果を出さなければならない。そのためには、目標に対する思い入れを強く持つ、つまり目標へのコミットメントが大事だと著者は言っている。
こういったことをすれば、たとえ仕事が上手くいかなくても、自分自身の能力や行ってきたことを見つめなおすことができ、自分自身で良い結果に結びつくような答えを出すことができるのだという。これは仕事だけでなく、生きていく中で何にでも応用できる考え方だと思う。
引用元:菊入みゆき[2004]『会社がイヤになった やる気を取り戻す7つの物語』光文社新書。
論評の書き方
書評レポートを書くにあたり最も大事な部分です。
論評で書く内容は以下の4点です。
本を読んだ上で、自分の意見
その理由
反対意見
自分の意見まとめ
これらを書くうえで下記内容を織り交ぜると、質の高い書評レポートが完成します。
・著者の問題設定やその回答に対して納得できた点
・他と違って「新しい」と感じた点
・足りないと感じた点
・誰でも応用することができるか
・自分の意見や代替案
以下、書評レポートにおける論評例です
本書では、22人もの人が様々な視点から話をしているが、私が印象に残っているものはCV採用というシステムがあるリクルートの話だ。
CV採用とは原則3年(3年の契約延長あり)の有期雇用で、最大の特徴は学歴、前職、年齢、性別など、一般的な企業の採用において重視される要素が一切不問という点である。
話をした人事マネージャーは、企業と個人との新しい関係を提案していきたいと言う。現在、多くの企業が新卒者を採用対象者としている理由は、企業が年齢で人の価値が決まる年功序列の組織であるからだという。
このシステムは、新卒者が絶えず企業に流れているうちは、人材を安定確保し、誰もが定年まで安定した生活を送ることができる。
しかし、需要と供給の調整ができないという致命的な欠陥がある。その結果、多くの非正規雇用を生み、現在の新卒者の売り手市場を生み出したという。ここでも筆者は職能給から職務給への転換を主張している。
企業側だけでなく、年功序列で賃金が年齢とともに上がることは働く側としても楽なのかもしれない。
しかし、今は転職することも珍しいことではないし、労働力が少なくなることで非正規雇用者の力も重要になる。それを考えると、職務給の必要性は明らかである。間違いなく、今、個人も企業も昭和的価値観を捨てるときが来たのだろう。
本書を読んで、自分の中にこれほどまで昭和的価値観が根付いていたのかと驚かされた。一度読んで、自分がいかに昭和的価値観にとらわれているか実感してみると面白いと思う。
引用元:城繁幸[2008]『3年で辞めた若者はどこへ行ったのか-アウトサイダーの時代』ちくま新書。
書評レポートの文字数配分
書評レポートを書く場合には文字数の指定がある場合、ない場合があります。
文章量に規定がない場合は
・導入・紹介:1000字
・論評:2000字
以上の文字配分で書くのが適切です。
文字数の指定がある場合は1:2の比率で論評がメインとなるように書きましょう。
あくまで、論評がメインになってきますので、導入や本の紹介が長くなりすぎないように注意が必要です。
教授が講義の中で触れたポイントを取り上げると評価が上がる
もちろん、目的は教授を持ち上げることではありません。教授が重要と言っている箇所は本当に重要な可能性が高いからです。
書評レポートを書くポイント
最後に書評レポートを書くうえでのポイントをお伝えします。
・本を読んだことがない人でも理解できるように書く
・自分の意見を書きオリジナリティを出す
・書き終えたあとは必ず見直しを行う
・引用する場合は引用元を書く
以上です。
書評の書き方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
社会人やビジネスマン向けの記事ではありますが、考え方やスキル的に参考になる部分もありますので、参考にしてみてください。